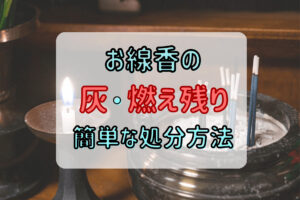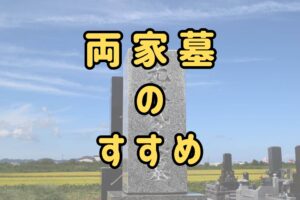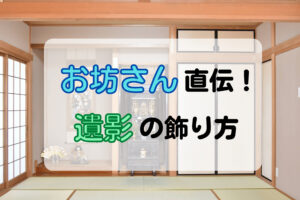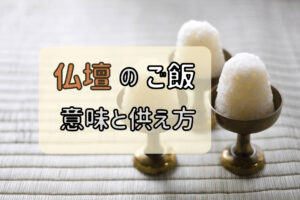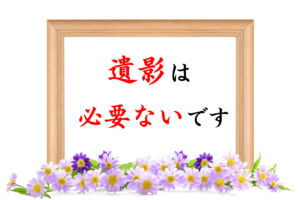- 仏壇を購入する時にはどんな仏具を揃えればいいの?
- いろんな仏具があるけど、それぞれどんな意味があるんだろう?
先日、初めてご家族に不幸があった信者さんから、
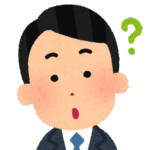
今回初めて仏壇を買うんですけど、仏具は何を買っておけばいいんですか?
という相談を受けました。
多くの人は、仏壇そのものは知っていますが、具体的に『仏壇の中に何を置けばいいのか』ということはあまりご存じではありません。
仏壇の中に置く仏具というのは宗派によって少し違いますが、だいたいは同じものです。
この記事を読むと、
- 新しく仏壇を購入するときに揃える仏具は何か
- 仏壇の中に置く仏具の意味
- 仏具の置く場所
が分かります。
仏壇に置くべき仏具が分かり、それを揃えることで丁寧な供養ができますので最後まで読んでみてください。
※この記事で紹介している仏具は、
- Amazon(アマゾン)
- 楽天市場
- Yahooショッピング
で購入することができます。
詳細については商品画像の右側にある『〇〇で探す』のボタンから確認してみてください。
この記事を書いている僕『未熟僧(みじゅくそう)』は、お坊さん歴25年以上。仏事の疑問を解消するいろんな情報を発信しています。
仏壇を購入するときに揃える仏具
新しく仏壇を購入するときには、いろんなものを買い揃えなくてはいけません。
しかし、多くの人は『仏壇にはどんな仏具が必要なのか』を知りませんので、仏具店に足を運んで、そこの店員さんにいろいろと教えてもらいながら仏具を購入しています。
ただ、仏具店としても商売なので、ちょいちょい【余計なモノ】を乗せてきますが、お客さんはそれを知らずに言われるがまま購入してしまいます。
本記事では、お坊さんの僕が『これくらいは買い揃えておいた方がいいな』と思うものだけを紹介します。
買い揃えておいた方がいい仏具は、
- ご本尊様《仏壇内の最上段(須弥壇)中央》
- 各宗派の祖師の掛軸《仏壇内の最上段左右》
- 位牌《仏壇内の中段》※浄土真宗は不要
- 高坏《仏壇内の中段の両脇》
- 仏飯器《仏壇内の中段》
- 茶湯器《仏壇内の中段》
- 花立て《仏壇内の下段左右》
- 常花《花立てにさす》
- 霊具膳《仏壇内の下段中央》
- 経机《仏壇の手前に置く》
- 四角打敷《経机に敷く》
- 火立て(ローソク立て)《経机に置く》
- お鈴セット《経机に置く》
- 香炉(線香立て)《経机に置く》
- 火消し《経机に置く》
- マッチ消し《経机に置く》
- 線香差し《経机に置く》
- 瓔珞と吊灯籠《仏壇内の天井部》
- 【過去帳】《経机の上に置く》
- 【ワラビ卓】《仏壇内の中段中央》
です。
この中で『19・20』に関しては【あったらいいな】という程度なので、余裕があったら購入してもらえると仏壇としての威厳が増します。
ご本尊様《仏壇内の最上段(須弥壇)中央》
まず、仏壇に絶対になきゃいけないものがあります。
それは、ご本尊様です。
ハッキリ言いますと、ご本尊様がなければ仏壇を買う意味が無いんですよね。
なぜなら、仏壇は『お寺の本堂の代わり』になるものだからです。
お寺の本堂には必ずご本尊様が祀られていますので、同じように仏壇にも【ご本尊様】が必要になります。
ご本尊様は必ず【仏壇内の最上段の中央】に置くようにしてください。ここが仏壇の中で一番の上座になります。
ご本尊様は【木製の仏像】と【仏画の掛軸】のどちらでもかまいません。
とにかく、『仏壇にはご本尊様が必要である』ことだけは絶対に忘れないようにしてください。
仏壇に関する詳しい解説は『仏壇の意味と役割とは?仏壇の準備からお参り方法まで丁寧に解説』の記事に書いていますので読んでみてください。
各宗派の祖師の掛軸《仏壇内の最上段左右》
日本の仏教にはいろんな宗派があることはご存じですよね?
各宗派のお寺では、それぞれの宗派の創始者となるお坊さんの絵を本堂内に飾ることがほとんどです。
これは、仏壇でも同じことなんですよね。
ですから、ご本尊様の両脇には、そのような各宗派の『祖師』となるお坊さんの絵を掛軸にして飾るのです。
この祖師の掛軸を飾っていない人が意外と多いのですが、仏壇の役割を考えたら必要なものです。
せっかくですから、仏壇の購入をきっかけに『あなたの家の宗派』を確認して、ぜひとも祖師の掛軸を飾ってください。
位牌《仏壇内の中段》※浄土真宗は不要
仏壇には『位牌』を置くのが一般的です。
しかし、本来の仏壇は『位牌を置くためのもの』ではありません。
仏壇はお寺の本堂の代わりをするものなので、仏壇はご本尊様に手を合わせて拝むためにあります。仏壇の中は『仏様の世界』を象徴する清らかな空間なので、ご本尊様は仏壇の中に置くんですよね。
では、なぜ位牌を仏壇に置くのでしょう?
位牌というのは、人の魂が宿る【依代(よりしろ)】の役割をしています。そのため、位牌は故人の魂が宿るものは清らかな空間(仏壇)に置きましょう、ということなんです。
ただし、位牌はご本尊様と『同格』のものではなく、仏壇の主役はあくまで【ご本尊様】です。なので、順序としては、位牌はご本尊様の次。
というわけで、位牌はご本尊様の一つ下の段、つまり仏壇の中段に置くようにしてください。
位牌について詳しく知りたいという方は『位牌とは何なの?位牌の意味や必要性をお坊さんが解説します。』の記事を読んでみてください。
ちなみに、浄土真宗は位牌を使わず、代わりに『過去帳』を使いますのでご注意ください。
高坏(たかつき)《仏壇内の中段の両脇》
仏壇には、ご本尊様や亡き家族のために『お供物』を供えます。
お供物は、できるだけ『高坏(たかつき)』に乗せて供えるようにしましょう。
高杯とは、仏様へ供える食べ物などを置くための、脚の高い器のことです。
脚を高くしているのは、私たちの【仏様を敬う姿勢】を表しているからです。
高杯は、必要というほどの仏具じゃないですが、私としては敬意の象徴としてぜひ使ってほしいなと思います。
ちなみに、高杯に供える時には、折った半紙を高杯の上に敷いてからお供物を置くと、さらに丁寧な供え方となります。
仏飯器《仏壇内の中段》
私たち日本人の主食は『米』ですよね?
ですから、日本人は昔からよく仏様や神様に『米』をお供えするんです。
そして、仏壇の場合は、仏様へ美味しく炊いた米を供えるために『仏飯器(ぶっぱんき)』という器を使います。
これも高坏と同じように、脚の高い器です。
仏飯は、毎朝新しいご飯を供えてあげましょうね。
茶湯器《仏壇内の中段》
あなたは、食事をする時にお茶やお水といった『飲み物』を用意していますよね?
仏様にも同じように『飲み物』を用意してあげてください。
仏様の飲み物を入れる器を『茶湯器(ちゃとうき)』といいます。
茶湯器は、高さのある脚が付いた茶卓に湯飲みを置くという形状になっています。
言ってみれば、【仏様専用の湯飲み】ということですね。
毎朝仏飯を供えるのと同じタイミングで、茶湯器に飲み物を注いで供えるようにしてください。
ちなみに、茶湯器という名前ではありますが、僕はお茶よりも【水】を供えた方がいいと思います。
仏様に供える【水】というものにはとても重要な意味があるので、詳しくは『仏壇に【水】を供える意味をお坊さんが詳しく解説します。』の記事を読んでみてください。
花立て《仏壇内の下段》
仏壇にお花を供えるために『花立て(花瓶)』が必要です。
仏具店で販売しているような花立てが正式な形ではありますが、市販の花瓶を使用しても問題はありません。
また、花立ては2つ用意して仏壇内の左右に飾ってもいいですし、1つだけ飾ってもかまいません。
ただし、1つだけ飾る場合は、仏壇に向かって『左側』へ飾るようしてください。
常花《花立てにさす》
仏壇には花を供えます。
しかし、毎日新しい生花を供えるのはかなり大変です。お寺でさえも毎日ちゃんと生花を供えているところは少ないのではないかと思いますよ。
そこで、生花の代わりとして供えるのが『常花(じょうか)』です。
常花というのは金色で作られた『蓮』を模したものをいい、金色の造花みたいなものです。
お盆の時期が近くなるとホームセンターなどで販売されていたりしますが、あなたも一度はみたことがあるんじゃないですか?
常花は金色の蓮なので、これは【仏様の世界に咲く花】を意味しています。
そして、仏様の世界に咲く花は枯れることはありませんので、生花を供えず【作り物】で金色の蓮の花を供えているのです。
霊具膳《仏壇内の下段中央》
仏様へのお供え物は、基本的にはいつも使っている茶碗や皿に盛って供えてあげれば大丈夫です。
しかし、故人の回忌法要やお盆など、ちゃんと『法要』をするときには正式な器を使います。
そのような、正式なお供物用の器セットのことを『霊具膳(りょうぐぜん)』といいます。または『霊供膳』とも表記します。
霊具膳には4つのお碗と1つの皿の合計5つの器を使用します。
その5つとは、
- 『親椀』ご飯を盛る器
- 『汁椀』汁物用の器
- 『平椀』煮物を盛る器
- 『壺椀』和え物を盛る器
- 『高杯』香の物を盛る器
です。
まぁ、これも絶対になきゃダメっていうほどのものではないですが、仏様へ礼を尽くす意味でも購入しておくことが理想的ですね。
経机《仏壇の手前に置く》
仏壇にはいろんな仏具を置くので、必要な物を全部置くことができません。
そこで、『経机(きょうづくえ)』があると便利です。
経机とは、本来であれば名前のとおり『経本を置くための机』なのですが、実際のところは仏具を置くために使っている人も多いですよ。
きっと、仏具を普通の机に置くことに抵抗があるから、わざわざ経机を使っているんだと思います。
それはそれで、仏様を大切に考えている証拠ですものね。
四角打敷《経机に敷く》
経机の上に仏具を置く場合には、『四角打敷(しかくうちしき)』を敷くようにしておきましょう。
これは、『ありがたい仏具なのだから、華やかな布を敷いて、そこへ置きましょう。』という意味で使われる敷物です。
四角打敷には防火性の素材で作られたモノがありますので、ぜひそれを敷いてください。もしかすると、『防火マット』みたいな名前で販売されているかもしれません。
四角打敷の上には、香炉やローソクといった『火を扱うもの』を置くことが多いんです。
もしも、燃えたままの線香や火の着いたローソクが倒れてしまった場合でも、防火用の打敷の上であれば安心ですよ。
特にローソクが倒れたことが原因で火災が起きた事例はたくさんありますので、防火性の素材で作られた四角打敷を強く推奨します。
火立て(ローソク立て)《経机に置く》
仏壇をお参りするときには必ず灯明に火を灯します。
灯明とは、要するに【火の着いたローソク】のことです。
となると、ローソクを立てるためには『火立て(ローソク立て)』が必要となります。
火立ては2つあるなら左右に置いてもいいですし、1つだけなら仏壇に向かって『右側』へ置くようにしてください。
もちろん灯明には、明かりをとること以外にも大事な意味がありますよ。
灯明(ロウソク)の明かりというのは『仏様の教え』を象徴するものなのです。
灯明に関する詳細は『多くの人が知らない【仏壇のロウソク(灯明)に火をつける意味】』の記事で解説していますので、興味のある方は読んでみてください。
また、ロウソクで火を使うことが心配な人は、代わりに《電気ロウソク》を使ってもよいと思いますよ。
お鈴セット《経机に置く》
仏壇をお参りするときには【お鈴(りん)】を「チ〜ン♪」って鳴らしますよね。
お鈴を鳴らして、あなたが心を込めてお参りしていることを仏様へお知らせします。
また、お鈴を鳴らすことで、その場の全体を清める効果があるとされています。
ですから、仏壇をお参りするときには【お鈴】が必要なのです。
また、お鈴というのは、基本的にはお経を読むときに鳴らす仏具ではありますが、それ以外のときでも遠慮なく鳴らしていいですよ。
よく「お鈴はむやみに鳴らすもんじゃない。」と言う人がいますが、そんなことはないんですよね。
その理由については『仏壇にある鐘【お鈴(おりん)】はいつでも鳴らしていいですよ。』の記事で詳しく解説しています。
香炉(線香立て)《経机に置く》
仏壇をお参りするときには【線香】を供えましょう。
仏様は、線香や焼香などを燃やした時に出てくる『香り』を食べる、といわれています。これを【香食(こうじき)】といいます。
つまり、お線香を供えることは、仏様に食事をしていただくことを意味するんですよね。また、お香から出る香りは『その場を清める効果』もあるのです。
お香を供えることは、仏事において基本中の基本なので、必ず供えるようにしてくださいね。
ですから、お線香を供えるために『香炉(線香立て)』は必要です。
お香についてもっと詳しく知りたいという方は『お線香のあげ方やマナーを場面別に詳しく紹介。お焼香の作法も合わせて紹介』を読んでみてください。
火消し《経机に置く》
仏壇のお参りが終わったら、ローソクの火を消さなければなりません。
ローソクやお線香に着いた火は、息を吹きかけて消さないように注意してくださいね。
私たちの息は、さまざまな生き物を食べた口、そして人の悪口・嘘・愚痴などを言っている『不浄な口』から出ています。そんな不浄な口から出る息を、【仏様の教えの象徴】であるローソクの火に向かって吹きかけてはいけません。
ですから、ローソクの火は、
- 手であおぐ
- 専用の【火消し】を使う
という方法で消してください。
僕なんかは手であおいでサッと消してしまいますが、慣れない人がコレをやると、なかなか火が消えません。下手をすると、あおいだ手が火の着いた線香に当たってしまいます。
そこで、あると便利なのがローソク専用の『火消し』です。
使い方は非常に簡単、火消しでローソクの火をカポッと被せるだけ。これは、酸素を無くして火を消すという『窒息消火』の原理を使っているのです。
これであれば、安全に確実に火を消すことができますから、できれば『火消し』を購入しておきましょう。
また、火消しはしっかりとした【取っ手】があるものを選ぶといいですよ。
マッチ消し《経机に置く》
ローソクの火をつけるときに【マッチ】を使う人は多いです。
ライターなんて無い時代は、マッチを使って火を着けるのが一般的でしたからね。その名残りで、年配の方はよくマッチでローソクに火を着けています。
それに、マッチの燃える時の匂いが好きな人もけっこう多いですよ。じつは私もそのうちの一人、あの火薬の燃える匂いが何だか落ち着きます。
言うまでもないのですが、使い終わったマッチをすぐにゴミ箱なんかへ捨ててはダメです。くすぶっていたマッチの火が他のゴミに引火してしまうかもしれません。
使い終わったマッチは、必ず仏壇用の『マッチ消し』に入れておきましょう。
マッチ消しは金属製ですし、酸素が取り込みにくい構造になっているので、マッチの火をしっかりと消してくれます。
線香差し《経机に置く》
先ほども言いましたが、お線香を供えるのは【仏様に食事を召し上がっていただくこと】です。
だから、お線香の扱い方もできれば丁寧にお願いしたいんですよ。
信者さんの家でよく目にするのは、線香を買ってきたまま箱を開けっ放しにして、そこから線香を取り出して供えている光景です。
できれば、お線香を買ってきたら『線香差し』にちゃんと入れておきましょう。
箱から取り出すのって、スーパーで買ってきた惣菜を皿に盛り直さずそのまま食卓に出すようなものです。
少しだけ『手抜き感』が出ちゃうんですよね。あっ、べつにこの場を借りて私の妻に対して文句を言ってるわけじゃないですよ。私たちの普段の食事なら、そんなことは気にしませんが、仏様のモノとなるとね・・・。
仏様の召し上がるものを入れるための仏具ですからちゃんと購入しておきましょう。
瓔珞と吊灯籠《仏壇内の天井部》
お寺の本堂って、何やらジャラジャラと金色のモノが天井から吊られていると思いませんか?
その吊られている金色の仏具は『瓔珞(ようらく)』といいます。
これは、もともとは古代インドの身分の高い人達が身につけていた装身具です。いろんな仏様もこれらの装身具を身につけておられますよ。
それがやがて、お堂を華やかに飾り付けるための仏具としても使われるようになりました。
仏壇は、ご本尊様や亡き家族の位牌を置くための清らかな空間です。
左右に瓔珞を吊るして、仏壇をより華やかに飾ってあげてください。
また、暗い仏壇を明るい光で照らし出してくれる『吊灯籠(つりとうろう)』も瓔珞と合わせて買った方がいいですよ。
仏壇の中は意外と暗いので、吊灯籠を入れることで中を明るく照らしてくれます。もちろん、本物の火は使わない【電飾】ですよ。
もしかすると、瓔珞と吊灯籠がセットで売っているかもしれませんね。
【過去帳】《経机の上に置く》
仏様がたくさんおられる家の場合、全部の位牌を仏壇に置くことができません。
そのような場合は、たくさんある位牌を【先祖代々の位牌】として1つにまとめる、という方法があります。
しかし、そうなると戒名や法名など【各仏様の戒名や法名などの情報】がわからなくなってしまいます。
そこで、それぞれの仏様の情報を記録しておくための『過去帳(かこちょう)』があると便利です。
過去帳があれば、各仏様の命日がすぐにわかるので、月命日のお墓参りを忘れてしまう、なんてことがなくなります。
必要というほどのものではありませんが、多くの人が使っている便利なものではありますよ。
【ワラビ卓】《仏壇内の中段中央》
先ほど紹介した、香炉やローソク立てなどを置く台として『ワラビ卓』というものがあります。
仏飯器や茶湯器を置くこともありますね。
これは、天板と卓の間に三角打敷を挟んで使用する、仏具を置くための『より正式で丁寧な台』です。
これは、仏壇の中段に置くものなのですが、正直なところスペースをとってしまうので、無理に使用することはありません。
仏様のために、できることは全てしてあげたい、という人はぜひ購入してください。
まとめ
仏壇は『お寺の本堂』と同じ役目をするものです。
つまり、本来なら仏壇にはお寺の本堂と同じような仏具を揃えなきゃいけないわけです。
そうはいっても、普通の家庭で本堂にあるような仏具を揃えるなんて無理ですし、そこまでする必要もないでしょう。
仏壇としてしっかりと機能できるくらいの仏具を揃えておくだけでいいと思います。
そのような観点で、今回は【必要な仏具】と【できればある方がいい仏具】を合わせて20個選んでみました。
あなたが仏壇を購入するときの参考にしてみてください。
※仏壇に関する疑問があればこちらの記事を読んでみてください。