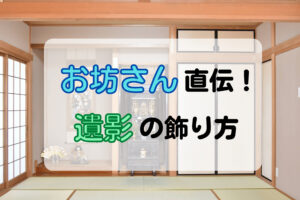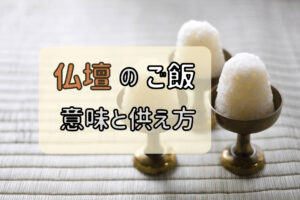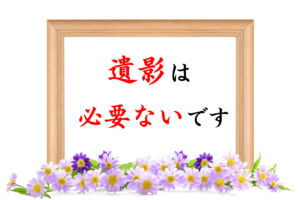- どうして仏壇のロウソクに火をつけるの?
- 仏壇のロウソクの供え方に決まりはあるの?
- 仏壇にはどんなロウソクを供えればいいの?
仏壇をお参りするときは、ロウソクに火をつけて、ロウソクの火で線香に火をつけますよね。
でも、仏壇のロウソクは【線香に火をつけるためのもの】ではないですよ。
毎日のように仏壇に手を合わせていても、ロウソクの意味や取扱い方をちゃんと知っている人は意外と少ないものです。
この記事では、
- 仏壇のロウソクに火をつけることの意味
- ロウソクの火の【つけ方】と【消し方】
- 仏壇で使われるロウソクの種類
- ロウソクの取扱い方
について解説しています。
それぞれの仏具の意味を知ることで質の高いお参りになりますので、興味のある方は最後まで読んでみてください。
この記事を書いている僕『未熟僧(みじゅくそう)』は、お坊さん歴25年以上。仏事の疑問を解消するいろんな情報を発信しています。
仏壇のロウソク(灯明)に火をつける意味
仏壇のロウソクに火をつけると、仏壇内部がほんのりと照らし出されて荘厳な雰囲気になりますよね。
そして、ロウソクの火はお線香に火をつけるときにも使います。
ロウソクに火をつけることは、言ってみれば【仏壇をお参りするときの作法】です。
しかし、『仏壇のロウソクに火をつける意味』を知っている人は少なく、多くの人は何となく【そういうもの】としてロウソクに火をつけています。
仏壇のロウソクの火には、
- 明かりをとるためのもの
- お釈迦様の教え
- 仏様の温もり
- 私たちの煩悩を焼き払ってくれるもの
というように、いくつかの意味があります。
明かりをとるためのもの
まずは、実用的な意味から。
昔のお寺は【学校】の役割をする場所でもありました、いわゆる『寺子屋』です。
寺子屋では、日が落ちてお堂の中が暗くなると、ロウソクの火で明かりをとって勉強をしていました。
ですから、ロウソクの火は【学び】において重要なものだったんですよね。
また、お寺はいろんな法要をする場所です。
法要をするときには、お坊さんが【お経】を読みますが、お堂の中が暗いと経本の文字が見えません。
経本に書いている内容は、さまざまな仏様の教えがギッシリと詰まった非常に『ありがたいもの』なので、読み間違えるわけにはいきません。
ですから、お寺にとって【ロウソクの火】は仏像や経本と同じくらい大切にされているものなんです。
また、仏壇は『お寺の本堂の代わり』をするものです。
なので、ちゃんと見てみると仏壇の中は【お寺の本堂の中】に似せて作られています。
だから、お寺の本堂にあるような仏具を、個人宅の仏壇でも使っているんですよね。
つまり、お寺の本堂で必要なロウソクは、当然ながら仏壇でも必要なものとなります。
【関連記事】:仏壇の意味と役割とは?仏壇の準備からお参り方法まで丁寧に解説
お釈迦様の教え
ロウソクのことを仏教では、『灯明(とうみょう)』といいます。
仏教において、灯明の火は『仏様の教え=正しい道を照らしてくれるもの』の象徴と考えています。
また、灯明には、
- 自灯明(じとうみょう)
- 法灯明(ほうとうみょう)
という2つの灯明があるのです。
これは、仏教を広めた【お釈迦(しゃか)様】が、たくさんいる弟子達に向けておっしゃったものです。
お釈迦様は、自分がいなくなった後でも弟子達が正しい道を進むことができるように、
- 「自分自身を灯明とせよ」=自灯明
- 「法(お釈迦様の教え)を灯明とせよ」=法灯明
とおっしゃいました。
自灯明
まず1つめの『自灯明』ですが、これは字のとおりで【自分自身を灯明とせよ】という意味です。
つまり、
今までお釈迦様からたくさんのことを学んだ【自分自身】をより所にして、自分を強く信じて仏の道を進め。
という意味です。
お釈迦様の教えをちゃんと守って、地道にコツコツと修行をしてきた弟子達に【自分が信じる道】を進むように言ったんですね。
法灯明
次に、もう1つの『法灯明』ですが、こちらは【法を灯明とせよ】という意味です。
仏教では、仏様(お釈迦様)の教えのことを【法】といいます。
なので、【法灯明】は、
お釈迦様が言ったことをよく思い出し、【お釈迦様の教え】をより所として仏の道を進め。
という意味です。
悟りを得るには、偉大な『お釈迦様の教え』をちゃんと理解して、それを実践する必要があります。
まずは、仏教の根本である『お釈迦様の教え』を強く信じることが悟りへの第一歩なんですね。
仏様の温もり
火というものは、【明かりをとる】だけではなくて【暖をとる】ときにも使われます。
暖炉やストーブの火の温もりは、芯まで冷えきった体を暖めてくれます。
仏壇のロウソクにも同じように《温もり》の意味がありますが、仏壇のロウソクの場合は『仏様の優しさと慈愛に満ちた温もり』がその場に広がることを意味します。
私たちがいろんな悩みや不安の中にいるときは【寒さで体が芯まで冷え切った状態】です。
そこで、ロウソクへ火をつけることで『仏様の温もり』が私たちに注がれ、悩みや不安を解決するための暖かいパワーが生まれます。
このように、仏壇のロウソクに火をつけると『仏様の温もり』をいただける、ということなんです。
私たちの煩悩を焼き払ってくれる
あなたは『護摩祈祷(ごまきとう)』をご存じですか?
護摩祈祷とは、簡単に言うと、『仏様が宿った火』のチカラで私たちの願いをかなえてもらうための法要です。
火は仏様の『教え』や『温もり』を象徴するものであり、加えて『火には仏様のチカラが宿る』とも考えられています。
そして、ありがたいことに仏様が宿った火は、私たちの煩悩(=尽きない欲望や執着)を焼き払ってくれます。
ですから、護摩法要では、
- まずは、仏様が宿った火のチカラで、私たちの煩悩を焼き払ってもらう。
- 次に、煩悩がなくなった清らかな心で願う。
- 最後に、清らかな心で願ったことを仏様にかなえてもらう。
ということをやっているんです。
火のチカラは護摩祈祷だけに有効なのではなく、仏壇のロウソクの火にも同じ効果があります。
ですから、仏壇のロウソクに火をつけることは、そのたびに仏様が私たちの煩悩を焼き払ってくれている、ということなんですね。
ロウソクの取扱い方法
ここからは、
- ロウソクの供え方
- ロウソクの火の消し方
- ロウソクを保管する時の注意点
など、仏壇に供えるロウソクの取扱い方法について書いていきます。
特に【火の消し方】には注意が必要なのでチェックしてみてください。
ロウソクの供え方
仏壇のロウソクには【供え方】が一応はあります。
ロウソクを立てるためには『燭台(しょくだい)』という仏具を使います。
これを1つだけ使うのか、それとも対になるように2つ使うのかでロウソクの供え方が少し変わります。
燭台を1つだけ使う場合
まずは、燭台が1つだけある場合。
燭台が1つだけの場合は、お花を供える花瓶も1つだけ使いましょう。
仏壇における基本的なお供えに『三具足(みつぐそく)』というものがあります。
これは、仏壇に向かって、
- 右側に、ロウソクを1つ
- 左側に、お花を1束
- 中央に、香炉(お線香たて)を1つ
という形で供えるやり方です。
つまり、仏壇に向かって【お花(左)・香炉(中)・灯明(右)】という形で横一直線に並べるのです。
仏様へのお供物の中でも特に重要度の高いものだけを3つ厳選したのが三具足です。
言い換えれば、最低限お供えするべき3つのもの、ということになります。
ですから、もしも、ご飯や菓子類など他のお供物がなくても、とりあえず三具足があれば問題はありません。
燭台を2つ使う場合
次に、燭台が2つある場合。
燭台が2つある場合は、お花を供える花瓶も2つ使いましょう。
仏壇における基本的なお供えに、もう1つ『五具足(ごぐそく)』というものがあります。
これは、仏壇に向かって、
- 左右(外側)に、お花をそれぞれ1束ずつ
- 左右(内側)に、ロウソクをそれぞれ1つずつ
- 中央に、香炉(お線香たて)を1つ
の形で供えるのです。
つまり、仏壇に向かって左から順番に【お花・灯明・香炉・灯明・お花】という形にして横一直線に並べるのです。
三具足をさらに丁寧に供えたものが五具足です。仏壇を購入するときには、できるだけこの五具足で買っておきましょう。
ロウソクの火の消し方
あなたは誕生日ケーキのロウソクの火はどうやって消しますか?
きっと、「・・・ハッピーバースデートゥーユー♪」からの「フーッ!」ってカンジですよね?
でも、仏壇のロウソクの場合は「フーッ!」はダメです。
たぶんあなたもご存じでしょうけど、仏様に供えるロウソクや線香の火を消す時には息を吹きかけてはいけません。
私たちの口は、
- いろんな生き物の肉を食べている
- 嘘・愚痴・人の悪口などを発している
など、要するに【汚れている】んです。
そんな汚れた口から出た息を、仏様に向かって吹きかけるようなことはしてはいけません。
逆に言うと、【息さえ吹きかけなければイイ】ってことですね。
仏様に供えるロウソクに関しては、いくつか『火の消し方』がありますので紹介します。
仏壇用の火消し道具を使う
まず、1番確実で安全な火の消し方は【仏壇用の『火消し』道具を使う】です。
ロウソクの火の上から、専用の『火消し』でカポッ♪っと覆うだけなのでとても簡単。
この火消しは、【窒息消火】という方法で火を消すのですが、覆ってから2秒で消せますよ。
しかも道具を使うので、ヤケドをする心配がありません。
この『火消し』はインターネットでも購入できますので、時間のあるときに探してみていください。
手であおぐ
次に、多くの人がやっている火の消し方は『手であおぐ』です。
手だったら何も道具を使わずに火を消せます。
でも、慣れていないと、一生懸命あおいでも【火が揺れるだけ】でなかなか消えてくれません。それに、勢いあまって他の仏具に手をぶつけることもあるんです。
僕はもう慣れているので、ほとんど一発で消せますが、多くの人は何回かあおがなくてはいけません。
手であおぐときのコツは【手首のスナップ】をうまく使って素早くサッとあおぐことです。
また、多くの人は『手のひら』を火に向けてあおぎますが、そうではなく『手の甲』を火に向けるようにしてあおぐといいですよ。
手のひらで風を作るのではなく、手の甲で風を作り出すイメージで、火から2cmくらい横をサッとあおぐ、というカンジですね。
道具なんか使いたくない、できるだけ自分の手で消したい、というのならこのコツを掴むまで何度か練習をしてみてください。
ロウソクの芯を指で素早くつまむ
最後に、もう一つ火の消し方を紹介します。
それは、【ロウソクの芯を指で素早くつまむ】という方法です。
でも、この方法はけっこう怖いですよ、なにしろ火の中に指を突っ込むわけですからね。
僕も勇気を出してやってみたことがありますが、まぁ、たしかに熱くはなかったです。
この方法で消すなら、芯をつまむ場所は、できるだけ【火の下部(根元の部分)】をつまむようにしてください。火は上にいくほど温度が高くなりますので。
そして、怖がらずに「おりゃっ!」って一発で決めてくださいよ、ビビったら逆に熱いですからね。
この方法の欠点は、ちゃんと火は消せるのですが、指にロウがついてしまうことです。
ということで、わざわざヤケドのリスクを負ってまで火を消す必要はないと思うので、僕はこの方法はあまりおすすめできませんが、一応は紹介しておきました。
ロウソクを保管するときの注意点
ロウソクは意外とすぐに使い切ってしまうので、ある程度は【買いだめ】をします。
でも、買いだめをするときには【保管方法】に注意しなければいけません。
できるだけ涼しい場所で保管する
ロウソクは、当たり前ですが【ロウを燃やして】火を出します。
ということは、ロウソクは熱に弱いんです。
だから、真夏などは日射しの当たらないような、できるだけ【涼しい場所】で保管してくださいね。
暑い中で置いておくと、曲がってしまったり、他のロウソクとくっついてしまうんです。
保管するときには、必ず箱の中に入れておき、さらにその箱も仏壇の引出しなどに入れておいてください。
湿気の多いところは避ける
ロウソクは、熱だけではなく【湿気】にも弱いです。
もしも芯の部分が湿ってしまうと、なかなか火がつきません。
また、劣化が進んで古くなったロウソクは湿気が多い場所にあると【カビ】が生えてしまいます。
そこへさらに湿気が加わると余計に劣化を進めてしまい、負の連鎖となってしまうんです。
なので、ロウソクはできるだけで湿気のない場所で保管するようにしてください。
特に梅雨の時期などは、ロウソクを入れる箱の中に乾燥剤を一緒に入れて保管すると効果的です。
ロウソクは【和ロウソク】と【洋ロウソク】がある
仏壇で使用できるロウソクには、
- 和ロウソク
- 洋ロウソク
の2つがあり、材質や使い方に違いがあります。
和ロウソク
まずは、日本で昔から使われている【和ロウソク】です。
ロウソクといえばこの【和ロウソク】をイメージする人も多いでしょうね。
和ロウソクは、本体側面の中央部が少しくぼむようにカーブして、上部に向かって広がっていく形をしているのが特徴です。
この形のことを【碇型(いかりがた)】ともいいます。
原料となっているのは植物油で、芯の部分は【い草】や【こより】が使われています。
植物油が使われていることもあり、油煙が少なくてすむので、
- 仏壇が汚れにくい
- 汚れても拭き取りやすい
というのが便利なんですよね。
また、和ロウソクは形状的にロウが垂れにくいというのも良いところです。
ロウが垂れるとロウソクが変形したまま燃え続けてしまうと最後まで使いきれないことがありますが、ロウが垂れにくければ長く火がついていられるので、ちゃんと使い切ることができます。
でも、和ロウソクというのは職人が作るケースが多いです。職人が作るということは、品質はとても高いのですが生産数が少ないため価格が高くなります。
つまり、和ロウソクは少し高級品なんですよね。
ですから、和ロウソクは法事など『大事な法要』のときに使うくらいでよいと思います。
洋ロウソク
続いては【洋ロウソク】です。
今私たちが仏壇で使っているのは、ほとんどが【洋ロウソク】です。
洋ロウソクは、原料に石油由来のパラフィン・牛脂などを素材とするステアリンが使われ、芯の部分は綿糸で作られています。
形は【真っすぐな棒型】のものが多く、日本だけではなく世界中で使用されています。
単純な形なので機械で大量生産できるので価格が和ロウソクに比べて圧倒的に安いんですよね。
なので、日頃の仏壇のお参りに使うには洋ロウソクにした方がお得なんです。
ただし。
洋ロウソクは石油由来の成分で作られているので、油煙が多くなってしまい、それだけ仏壇も汚れやすくなり、汚れも落ちにくくなるのが残念です。
しかも、和ロウソクに比べてロウが垂れやすい形をしていますので、少し傾くと変形したまま燃えてしまい、意外と最後まで使いきれないこともあるんですよね。
とはいえ、とにかく価格が安いので、毎日仏壇をお参りするには洋ロウソクを使うのが現実的です。
ロウソクの費用が大変だからお参りの回数を減らすなんていうことになってしまうと本末転倒ですからね。
まとめ
ロウソクに火をつけるのは、ただ【明かりをとる】だけではありません。
ロウソクの火は【仏様の教え】や【仏様の温もり】を表し、また火そのものが【私たちの煩悩】を焼き払ってくれる非常に『ありがたいもの』です。
なので、火を消すときには【息を吹いて消す】なんていう仏様に対して失礼なことはせず、専用の【火消し】を使って消すのが最適です。
ロウソクには、和ロウソクと洋ロウソクがありますが、大事な日には和ロウソクを使い、普段の仏壇参りのときには洋ロウソクを使うとよいでしょう。
また、ロウソクを保管するときは『高温多湿を避ける』ということに注意しましょう。
この記事を読んでくれたあなたは、もうすでに『仏壇へロウソクに火をつけて供える意味』をご存じなので、今までよりも『質の高い仏壇のお参り』ができます。
これからは、ロウソクの火に『仏様』を感じながら手を合わせ、より良い仏壇のお参りにしてくださいね。
※ろうそくで火を使うことが不安な人はコチラの記事をご覧ください。