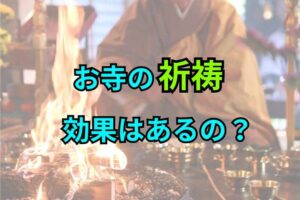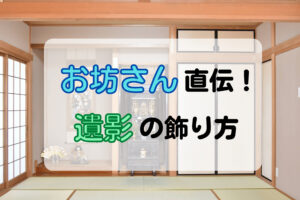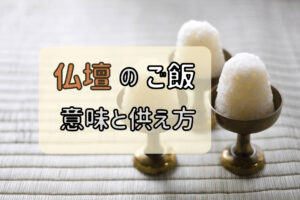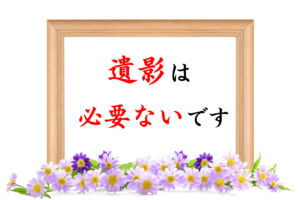- 仏壇の『お鈴』を鳴らすことにはどんな意味があるの?
- 『お鈴』はむやみに鳴らしちゃいけないの?
- 『お鈴』を鳴らし方のコツあるの?
あなたは、棒で叩くと「チ〜ン♪」という音が出る仏具をご存じですよね?
その仏具の名前は、『お鈴(りん)』といいます。
いつも鳴らしているお鈴ですが、
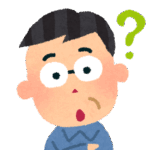
これって、どういうときに鳴らせばいいのかな?
と迷ったことはありませんか?
じつは、お鈴に関しては、
- むやみに鳴らしてはいけない
- いつでも鳴らしてよい
という2つの意見に分かれます。
僕は、お鈴はいつでも鳴らしてよいと考えています。
『お鈴』についてちゃんと理解してもらえれば、僕のこの主張の意味がお分かりいただけるはずです。
この記事を読むと、仏壇の前で堂々と『お鈴』を鳴らせるようになりますので最後まで読んでみてください。
この記事を書いている僕『未熟僧(みじゅくそう)』は、お坊さん歴25年以上。仏事の疑問を解消するいろんな情報を発信しています。
お鈴を鳴らす意味
仏壇をお参りするときに鳴らしている鐘は、一般的に『お鈴(りん)』と呼ばれています。
『お鈴』には一体どんな意味があるのでしょう。
『お鈴』とはどんなもの?
『お鈴』とは、お椀の形をした金属製の鳴り物で、仏壇には欠かせない仏具の一つです。
『お鈴』を打つと「チ〜ン♪」といい音がしますよね。
あれは、真鍮(しんちゅう)と亜鉛を混ぜ合わせた合金で作られていて、音を響かせるにはちょうどいい硬さになっているんですよ。
そして、傷が付きにくくて丈夫なので長期間使用できる仏具です。
また、『お鈴』は、
- お鈴本体
- りん座布団
- りん台
- りん棒
を合わせてワンセットとして使います。
ちなみに、最近では『高台りん』といってワイングラスが短くなったような形状をしている『お鈴』があります。
『高台りん』は、りん座布団やりん台が必要なく、それ一つあれば音が響くようにできているのでとても便利です。
他にも球型のものなど、いろいろなデザインの『お鈴』がありますね。
お鈴は【形の決まり】などはありませんから、あなたのお好みの物を使ってかまいません。
※ちなみに『高台りん』とはこういう形ですので参考にしてみてください。
『お鈴』を鳴らす意味
仏具には【音を出す】ものが多いです。
例えば、
- 除夜の鐘でつく『梵鐘(ぼんしょう)』
- 読経のときに叩く『木魚(もくぎょ)』
- 読経の区切りのときに打つ『けい』
- 本堂の正面入口に吊るしてある『鰐口(わにぐち)』
- 人を集めるために吹く『法螺(ほうら)』
などは有名です。
これらのような音の出る仏具のことを『梵音具(ぼんおんぐ)』といい、『お鈴』も梵音具の一つです。
【梵】という字には、『穢れがなく澄みきった清らかなもの』という意味があります。
梵音具から出る『清らかな音の力』によって、音が届くところは全て清められる、といわれています。
つまり、仏壇の『お鈴』を鳴らすことによって、
- その場所全体を清める
- お参りしている人を清める
- 本尊様やご先祖様にお知らせする
といった意味があるのです。
ご本尊様やご先祖様を前にしているのだから、『お鈴』を鳴らして仏壇やその場を清めましょう、ということですね。
【関連記事】:仏壇の意味と役割とは?仏壇の準備からお参り方法まで丁寧に解説
いつでも『お鈴』を鳴らしていい理由
よく、「お鈴は、お経を読むときに鳴らすものだから、それ以外ではむやみに鳴らしてはいけない。」と言う人がいます。
でも、僕は「それは少し違うのでは?」と思っています。
僕は、『お鈴』はお経を読まないときでも鳴らしてよいと考えています。
『お鈴』は読経の始まりや終わりなど、お経の区切りで鳴らす仏具で、お経を読むときに『お鈴』を鳴らすことで仏様やご先祖様へ供養していることを【お知らせ】しています。
また、『お鈴』の音色に合わせて読経の音程を決める、という場合もあります。
ですから、仏壇の前で『般若心経』などのお経をお唱えするときには、ぜひ『お鈴』を使ってください。
では、お経を読まないときは『お鈴』を鳴らしちゃダメかというと、そんなことはなく、お経を読まないときでも鳴らしてかまいません。
多くのお経は、
- 仏様を称賛する
- 仏様の教えに感謝する
- 仏様のご利益に感謝する
- 仏様に対する信心を誓う
というような内容ですが、僕たちお坊さんは、これらの内容を【読経】という形で声に出して仏様へお伝えしています。
でも、仏様を称賛したり感謝したり信心を誓うことは、読経という方法以外でもお伝えできるんですよね。
例えば、仏壇のご本尊様に手を合わせ「いつもありがとうございます。今日も仏様の教えを守るように心がけます。」と、仏様に対して感謝や決意の言葉を口にすれば、それはお経をお唱えすることと同じだと思うんですよ。
つまり、仏様に対し〔称賛・感謝・信心の誓い〕をお伝えする方法が『お経』か『口語』かという【形の違い】だけなんです。
僕は、仏様に対する日頃の挨拶もお経に等しいものだと思っているので、お経を読まなくたって【仏様への声がけ】があれば同じことなんです。
もっと言うと、声に出さずに【心で仏様へ声がけ】をするだけでもお経をお唱えすることに等しいと思いますよ。
そもそも、『おりん』を鳴らすことには、その場所や人を清める意味があるのですから、お経の有無にかかわらず鳴らしていいはずです。
というわけで、僕は、
- 読経の代わりになることをすればよい
- お鈴は『清める』ために鳴らしている
この2つの理由により、『おりん』を鳴らすのは読経のときだけではなく、いつでも鳴らしてよいと考えています。
『お鈴』の鳴らし方のコツ
いつでも誰でも『お鈴』は鳴らしてかまいません。
せっかく鳴らすのですから、美しく「チ〜ン♪」と音を響かせたいと思いませんか?
ここで、『おりん』の鳴らし方のコツを紹介します。
よく、上の画像のように、りん棒を【上から軽く振り下ろす】ように当てて鳴らす人がいます。
間違いということではありませんが、このやり方だと音の響きが悪くなってしまいます。
お鈴を鳴らすときのコツはこうです。
- りん棒は、親指・人差し指・中指で軽く持つ
- りん棒は、お鈴へ当てる部分を【下】に向けて持つ
- 手首のスナップを使い、お鈴のフチにりん棒を当てる
りん棒というのは『お鈴』へ当てる部分が布で巻かれています。
この布のおかげで優しい音色が響きます。
また、音をキレイに響かせるには、りん棒で『お鈴』のフチを【軽くはじく】ように当てるとよいです。
鳴らす回数については各宗派によって異なりますので、あなたのお付き合いのあるお寺へ聞いてみるとよいでしょう。
『お鈴』の取り扱い方法
『お鈴』は長く使うことのできる仏具ですが、何も手入れをせずにいると色が黒ずんできたり、微妙に音も変わってしまいます。
なので、できれば『お鈴』は定期的に磨いた方がいいですよ。
仏具店では専用の磨き剤や道具などが売っていますので、それを使ってみてください。
また、専用の磨き剤がない場合は、ホームセンターなどでも金属の磨き剤や道具が売っていますので、それを使用して手入れすることも可能です。
しかし、ホームセンターで販売しているものは使用方法をよく確認してください。
研磨剤が粗いものだと、表面を傷つけてしまい、見た目も音も悪くなってしまいますので注意しましょう。
じつは、金属を傷つけることなくピカピカにすることができる『ニューテガール』という金属磨きの液剤ありますので紹介しておきますね。
僕はこれをいつもインターネットで購入しています。
この液剤は、金属を液体に浸すだけで金属本来の輝きが戻るというものです。
ニューテガールの原液を水で薄めて使用をするのですが、商品名のとおり【こする作業】がないので非常にラクなので、女性の方や、簡単に手入れをした方は試してみてください。
次に、お鈴の取り扱いについて大事なのは【落とさない】ことです。
僕は以前、掃除をしているときに誤って『お鈴』を床へ落としてしまいました。
そのせいで、わずかですが【亀裂】が入り、試しに鳴らしてみようと思ったのですが、どのようにりん棒を当ててもビックリするほど音が鳴りません。
いつもなら「チ〜ン♪」と響くところが、わずかでも亀裂が入ると「チッ」という具合に全然音が響きません。
もしも、僕のように落としてしまい亀裂が入ったら完全にアウトですから、手に持つときは十分に注意してくださいね。
まとめ:『お鈴』はいつでも鳴らしていいですよ
仏壇に向かい、お供物を供え、お線香をあげ、『お鈴』を鳴らして、最後に手を合わせる。
仏壇のお参りは、この一連の作法を行えば大丈夫です。
基本的に、『お鈴』を鳴らすときに読経はセットですが、読経をしなくても、心を込めて手を合わせることでその代わりはできています。
また、お鈴を鳴らすことで、その場所や、そこにいる人が清められます。
ですから、お鈴はいつでも鳴らしていいですよ。
※仏壇についてはこちらの記事も読まれています。