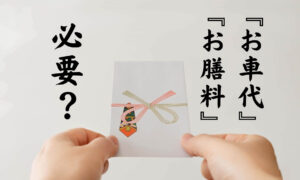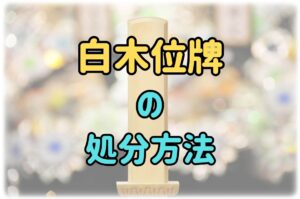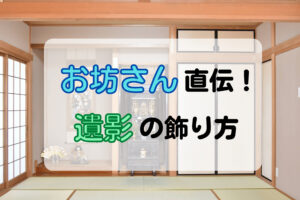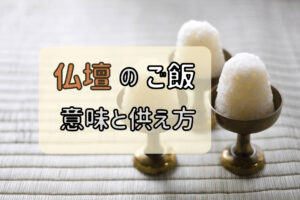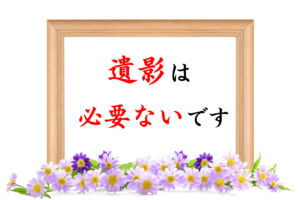ほとんどの家では仏壇に位牌を祀ります。
でも、なぜ位牌を祀るのか不思議に思ったことはありませんか?
そもそも、位牌は必要なものなのでしょうか?
この記事では、多くの人が知っているようでよく知らない『位牌』についてお坊さんの僕が解説しています。
あなたが思っている以上に位牌が素晴らしいものであることが分かりますので、興味のある方は読んでみてください。
この記事を書いている僕『未熟僧(みじゅくそう)』は、お坊さん歴25年以上。仏事の疑問を解消するいろんな情報を発信しています。
位牌とは何なの?
位牌というのは、亡くなった人の、
- 戒名(または法名)
- 亡くなった年月日
- 亡くなったときの年齢
- 生前の名前
が記されている木製の札のことです。
私たちは位牌に向かって手を合わせ、朝夕の挨拶をしたり、いろんな報告をします。
仏具の中でも位牌は特に大切に扱われているもので、昔は『火事になったら、まず位牌を持って逃げろ。』なんて言われていました。
それくらい位牌というものは、とても大切にされ、まるで【故人そのもの】のように扱われます。
位牌の起源
位牌は日本で生まれたものではありません。
位牌の起源とされるものはいくつかの説があります。
まず、仏教発祥の地であるインドには位牌がないので、位牌の起源はインドにはありません。
位牌は、中国の『儒教』が起源だとされる説が有力です。
儒教では、死者の霊の拠り所として【生前の官位】や【名前】を札に書き記すという風習がありました。
インドで始まった仏教が中国へ伝わり、中国から日本へ伝わるときにこの風習が一緒に伝えられた、と考えられます。
これが位牌という形で現在でも残っているわけですね。
位牌の意味:位牌は依代(よりしろ)の役割をするもの
私たちは、位牌に故人の魂が宿ると考え、位牌を【故人を象徴するもの】として扱っています。
しかし、故人の魂がずっと位牌の中にいるわけではありません。
位牌とは、私たちが故人に向けて大事な何かを伝えるとき、また反対に故人が私たちに何か大切なことを伝えたいときに【一時的】に故人の魂が宿る場所なのです。
つまり、位牌は、故人の魂が宿る『依代(よりしろ)』の役割をしているんです。
また、位牌は故人専用の連絡ツールにもなっていて、私たちと故人を繋いでくれているものでもあります。
例えるなら『携帯電話』みたいなもので、私たちが故人に伝えたいことがあるときには、位牌に向かってお伝えすれば、位牌を経由して故人に届くというわけです。
故人はあの世で仏道修行に励んでおられますので、そんな中で愛する家族から連絡があれば嬉しいものです。
なので、私たちがいつも携帯電話で連絡を取り合うように、位牌を通じて故人とコミュニケーションをとりましょう。
ちなみに、法事やお盆供養などの【法要】をしているときや、家族の大事な報告をしているときなどは、故人はちゃんと位牌に宿ってくれています。
位牌の開眼供養をする
新しく位牌を購入したら、お坊さんに依頼して必ず『位牌の開眼(かいげん)供養』をしてもらってください。
購入しただけで何もしなければ、その位牌は【ただの木札】のままであり、開眼供養をすることによって『位牌』としての役割を果たすようになります。
先ほどの携帯電話の例でいうと、携帯電話の端末(機械本体)があるだけではダメで、ちゃんと手続きをしてからでないと通話ができません。
開眼供養とは、この手続きと同じ意味をもつのです。
逆に、昔からある古い位牌を新しいものに作り直すとき、あるいは完全に処分するときには、解約手続きに相当する『閉眼供養(へいげんくよう)』が必要になるのです。
ですから、位牌を新しく作り直したときは、
- 古い位牌の閉眼供養をする
- 新しい位牌の開眼供養をする
- 古い位牌の処分(お炊き上げ)をする
という流れとなります。
位牌は【お墓】の縮小版
あなたは位牌を見て何かに似ていると思いませんか?
じつは、位牌は『お墓』と少し形が似ています。
位牌とお墓はいずれも、土台の部分が2段ほどあって、一番上の部分の表と裏には文字が記されています。
じつは、位牌は【お墓】の縮小版なんです。
人が亡くなると、ご遺骨をお墓へ埋葬し、その後は、お墓に向かって手を合わせ、お供えをして、故人に向けていろんなことをお墓を通じて伝えます。
この【お墓】もまた位牌と同じように『依代』の役割をしているのです。
というか、お墓の方が順番としては先です。
お墓参りは本当であれば【毎日行うもの】なのですが、そんなことは無理ですよね。
そこで【お墓に代わるもの】として位牌を祀るようになったのです。そして、位牌の形も次第に【お墓】に近くなっていきました。
毎日お墓参りに行けなくても、位牌だったら毎日お参りすることができますからね。
位牌はお墓の代わりとして、自宅にいながらあの世の故人と繋がるための大事な仏具なのです。
位牌は必要なのか?
ここまで位牌について解説をしてきましたが、位牌が【必要なもの】なのか疑問ですよね。
位牌は【必要なもの】なのかどうか、これは多くの人が疑問に思うところです。
結論としては、【必要】というわけではないとなります。
まず、位牌というもの自体が《宗教》に付随するものです。宗教は、その教えの内容や、教えにまつわる道具の効果や役割を『信じる』ことで成立します。
ですから、もしも「この木の札に故人の魂が宿るなんて、そんなのとても信じられない。」というのであれば、あなたにとってそれは【ただの木の札】なので必要ではありません。
他にも【必要】とはいえない理由があります。
先ほども言いましたように、位牌は『お墓の縮小版』です。
つまり、もしも家の近くにお墓があって、毎日でもお墓参りができるような環境であれば、位牌が必要というわけではなくなります。
位牌の元であるお墓にお参りできるのであれば、本来はそれが理想的なことなのです。
お墓参りに毎日行けるのであれば位牌がなくても問題はありません。
また、
- お墓はあるけど、家のすぐ近くではない
- 仏教に対する不信感があるわけでもない
- それでも位牌の必要性は感じない
という人もいると思います。
そのような人は、一旦は位牌を作製せず、その代わりに『過去帳(かこちょう)』を購入しておきましょう。
過去帳とは、簡単にいうと『亡くなった人たちの情報が記載された帳簿』のことです。
過去帳には、位牌に記されていることと全く同じ内容が書かれています。
過去帳はただの帳簿なので開眼供養をする必要がありませんし、しかも故人の戒名などの情報がしっかりと記録できる便利なものです。
でも、亡くなった故人を身近に感じていたいという人は、ぜひ位牌を祀っていただきたいなと思います。
位牌はあの世とこの世を繋いでいますので、私たちから故人へ、逆に故人から私たちへ、位牌を通じてお互いにいつでもすぐにメッセージを伝えられます。
そして、位牌は故人の依代なので、故人が家族の様子を見たくなったときには、いつでも見に来ることができるのです。
そういう意味では、位牌はご家族にとってだけではなく、故人にとっても大事なものであるといえるのではないでしょうか?
ですから、お坊さんの僕としては、できるだけ位牌を祀ってもらいたい、位牌を祀らなきゃもったいない、と思っています。
まとめ:位牌は私たちと故人を繋ぐ大事な依代です。
位牌は、亡くなった人が一時的に宿るための【依代】の役割をする大事なものです。
私たちは位牌を通じていつでも故人と繋がることができます。
しかし、もしも「そんなことは信じられない」と思うのであれば、無理に位牌を祀らなくてかまいません。
位牌は【強制】されるものでもありません、そして【必要】というわけでもありません。
位牌は『故人を身近に感じていたい』という人だけが祀ってください。
故人を身近に感じていたいという気持ちがあるのは、あなたが故人のことを大事に思っている証拠です。
あなたのその気持ちは、位牌を通じてしっかりと故人に伝わります。
そして、故人も、そんなあなたのことをしっかりと守り導いてくださいます。
位牌があるおかげで亡きご家族といつでも繋がっていられるのです、こんなにありがたいもはないと僕は思います。
※位牌関連はこちらの記事も読まれています。