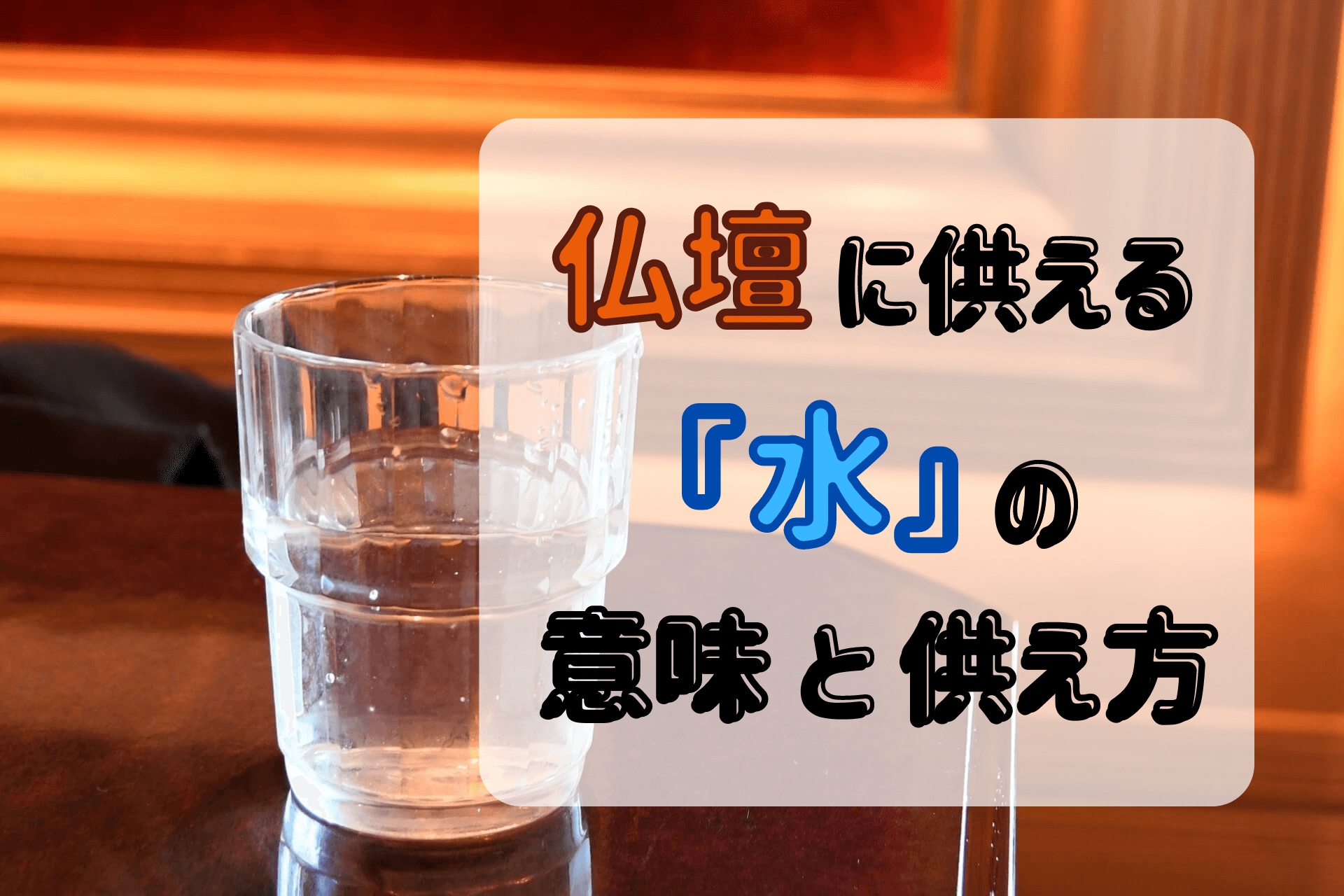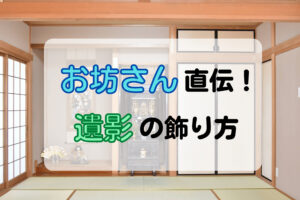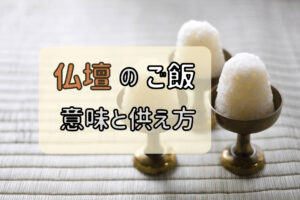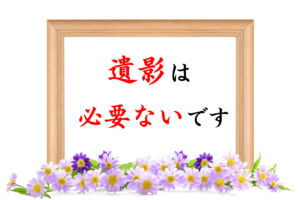- 仏壇へ供えている水にはどういう意味があるんだろう?
- 仏壇にはどうやって水を供えたらいいの?
- お茶やジュースを供えたらダメ?
毎日のように仏壇へお水を供えていても、その意味を知らない人はけっこう多いです。
お水を供えることには、
- ご先祖様や亡き家族など、仏様たちの喉を潤してもらう=感謝の気持ちを示す
- すべての生き物に対して【布施】をする=施しの心を育てる
という意味があり、とても重要な宗教行為をしているのです。
この記事では、
- 仏壇に水を供える意味
- 仏壇への水の供え方
について解説しています。
仏壇参りに対する意識と質が変わりますので、興味のある方は最後まで読んでみてください。
 未熟僧
未熟僧今まで【何となく】水を供えていた人は必見ですよ。
この記事を書いている僕『未熟僧(みじゅくそう)』は、お坊さん歴25年以上。仏事の疑問を解消するいろんな情報を発信しています。
仏壇に水を供える意味
まずは『仏壇に水を供える意味』を解説します。
仏壇に水を供えることには、
- ご先祖様や亡き家族など、仏様たちの喉を潤してもらう=感謝の気持ち
- すべての生き物に対して【布施】をする=施しの心
という2つの意味があります。
これらの意味を分かった上で水を供えると、今までよりもずっと【質の高いお参り】に変わります。
仏様たちの喉を潤してもらい、感謝の気持ちを伝える
まずは、仏壇に水を供える意味の1つめです。
1つめの意味はとても単純で、ご先祖様や亡き家族など、仏様たちの喉を潤してもらうという意味があります。
仏様だって喉が渇くでしょうから、水を飲んでいただこうということです。
でも、ただ喉を潤していただくのではなく、そこには私たちの仏様に対する『感謝の気持ち』が込められており、どちらかといえば、こちらの方が大事です。
仏様はいつも未熟な私たちを見守ってくれて、正しい方へと導き、しかも困ったときには助けてくれるので、きっと多くの負担をかけてしまっているはず。



それでも仏様は汗水を垂らして私たちを救ってくれています。
そんな仏様に、お供物やお水を供えて「いつも本当にありがとうございます。よかったらこれ、どうぞ召し上がってください。」と『感謝の気持ち』をお伝えするわけです。
また、水には物や身体を清めるチカラがあるとされています。
神社やお寺に行くと【手水舎(ちょうずや)】で手や口を洗ってからお参りをしますが、あれは神様や仏様へお参りする前に手や口を水で清めているのです。
ですから、仏壇へ水を供えるときには、毎日お水が飲めること、そして自分の身体も清められることに対する感謝の気持ちも表しましょう。
すべての生き物に対して【布施】をする
次に、仏壇に水を供える2つめの意味を解説します。
私たち人間を含む動物、そして植物というのは生きていくために【水】が必要不可欠ですから、【水】はあらゆる生物にとって『命の源』となるものです。
そんな『命の源』となる水を仏壇に供えることによって、仏様の喉を潤すという目的だけではなく、この世のすべての生き物に対して【布施=施し】をするという意味もあります。
つまり、水を供えることは立派な【布施】ということです。



じつは、仏壇に水を供える主な目的となるのは、この【布施】の部分なのです。
そもそも、仏壇は『お寺の本堂の代わり』ですから、仏壇へ何かを供えるという行為は、お寺の本堂でお供えをすることと同じ意味です。
お寺の本堂で行われることはすべてが『修行』ですから、仏壇に水を供えることも立派な修行の1つの【布施】となります。
そして、布施をする人には仏様の【ご利益】や【チカラ】が注がれますので、仏様のために水を供えることで、あなた自身も得るものがあるということです。
【関連記事】:仏壇の意味と役割とは?仏壇の準備からお参り方法まで丁寧に解説
浄土真宗の場合は水を供えなくてよい
今さらですが、仏壇に水を供えることは【必須】ではないので、そんなに窮屈に考えなくても大丈夫です。
じつは、水というのは『仏壇をお参りするなら、できるだけ供えましょうね』というレベルです。
特に、浄土真宗の門徒(信者)さんの場合は仏壇に水を供えなくてかまいません。
なぜなら、浄土真宗では、
- 人が亡くなったら、すぐに阿弥陀様が極楽浄土へ連れて行ってくれる。
- 極楽浄土では、飢えとか喉の渇きみたいな【苦しみ】というものがまったくない世界である。
- しかも、極楽浄土には『八功徳水(はっくどくすい)』という、清らかな水が常に湧き出ている。
と考えているからです。
極楽浄土にいるご先祖様や亡き家族は、喉も渇かないし清らかな水だってちゃんとある、だから水の心配はしなくてもいい、というわけです。
つまり、浄土真宗の場合は「仏壇に水なんか不要!」という教義なので、無理に水を供える必要はありません。
仏壇にはどうやって水を供えればいいの?
次に、『どうやって水を供えればいいか』について書いていきます。
とはいえ、仏事では『絶対にこうしなきゃダメ!』というものは無いので、これから紹介する内容は【目安】として参考にしてください。
お水を供える場所
まずは、水を供える場所について解説します。
仏壇に水を供える場合、一般的には『仏壇の中段』にお供えします。
しかし、これは『一般的には』ということでしかありませんから、置くスペースがないようでしたら他の場所へ供えてかまいません。
ただし、仏壇の上段には置かない方がいいです。
仏壇の上段は【仏像】や【各宗派の偉いお坊さんの掛軸】を置くための段なので、水を供えるのは中段以下の方が無難です。
お水を入れる器は何を使えばいいの?
仏壇に供えるお水はどのような器を使えばいいのでしょう?
仏様へお水を供えるときには、基本的には【茶湯器(ちゃとうき)】を使います。
名前に【茶】という字がついていますが、べつにこれは《お茶専用の器》というわけではないです。茶湯器にお水を入れて供えたってかまいませんので、仏壇を購入したときに茶湯器を一緒に買っていたなら、ぜひそれにお水を入れて供えてください。
茶湯器がなければ【コップ】や【グラス】を使ってもかまいません。故人が生前に愛用していたコップやグラスがあるなら、それを使ってお水を供えてください。
じつを言うと、仏壇にお水を供える器はべつに何だっていいんですよね。
大事なのは器ではなく、中身にちゃんと【お水】が供えられている、ということです。
【超重要!】お茶やジュースではなく『水』を供えよう
ここまで読んでくれたあなたは、もしかすると、



さっきから【水】のことばかり書いてあるけど、ひょっとして【お茶】とか【ジュース】は供えちゃダメだったの?
と思っているかもしれませんね。
仏様の喉を潤してもらおうと『感謝の気持ち』を伝えるために供えているのですから、お茶でもジュースでもダメではありません。
しかしながら、仏壇には【お茶】を供える人が多いです。
さらには、水とお茶の両方を供えている人もいます。
水とお茶の両方を供える場合、水とお茶は左右どちらに供えればいいのかという質問をよく受けます。
本来は左右で考えるのではなく、『お茶は東側』で『水は西側』に供えるというように方角で考えます。
仏事において東側は上位となる方角なので、より手間のかかるお茶を東側に供えるのです。
しかし、家によって仏壇の向きはさまざまなので、仏壇に向かって『お茶は右側』で『水は左側』と覚えておいてもよいでしょう。
というわけで、仏壇へ供えるのはお茶でもジュースでも大丈夫です。
大丈夫なんですけど・・・僕はできれば『水』だけを供えた方がいいと思っています。
なぜなら、原則として仏様には【澄んだ水】を供えることが望ましいからです。
仏様に供える水のことを『閼伽水(あかみず)』または『功徳水(くどくすい)』といいます。
僕が修行をしていたお寺では、この閼伽水を取るために深夜の2時頃に井戸まで水をくみに行ってました。
なぜそんな時間に水をくみに行くかといいますと、深夜2時頃は一日の中で『最もキレイな水』が取れる時間帯だからです。
余計なものが入っていない透明な水は『仏様の清らかで澄みきった徳』を象徴するんですよね。
だから、お茶やジュースのように『余計なものが入っている』ものは、仏様へのお供えとしては適していません。
ちなみに、僕のいる寺では仏様へ供える水には【ウォーターサーバー】の水を使っています。
水道水でもいいのですが、仏様には可能な限りキレイで安全な水を供えたいのでウォーターサーバーの水を使っているのです。
もちろん、ウォーターサーバーではなく、
- 浄水器を通した水
- 販売されているペットボトルの水
などでもかまいせん。
とにかく、仏様にはできるだけ『きれいな水』を供えるように心がけてください。
※最近では『きれいな水』を簡単に作れる便利なものがありますよ。
水は毎回供えるべき?
先日、法事が終わった後に信者さんから、
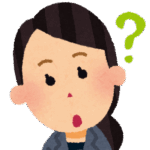
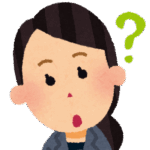
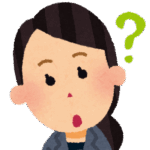
毎日仏壇にお線香をあげているんですけど、やっぱりお水も毎日あげた方がいいですか?
と質問されました。
先ほどもチラッと言いましたが、水を供えることは【仏壇参りの基本】ではありますが【必須】というわけではありませんよ。必須ではないんですけど、できれば毎日(あるいは毎回)お供えしてほしいなと思います。
べつに、「毎回新しいお茶を供えてくれ。」と言っているわけじゃないんです、水でいいんですよ、水で。
水でいいんですから、それくらいの労力は惜しまないでください。
仏壇に供えた水はいつ下げるの?
仏壇に水を供えるということは、どこかのタイミングで今度は水を下げなくてはいけません。
では、供えた水はいつ下げるのがいいのでしょう?
じつは、仏様に供えたものを下げるときの決まりはないのです。
とはいえ、何らかの基準がほしいところですよね?
お坊さんの僕としては、水を下げるタイミングは【供えてから1時間くらい】がいいと思います。
もしも夏に冷えた水を供えたとしたら、それがヌルくなっているのが1時間後くらいです。
もしも冬に温かいお茶を供えたとしたら、それが冷めてしまっているのが1時間後くらいです。
もしも朝食の前に水を供えたとしたら、食事が終わって片付け始めるのが1時間後くらいです。
ということで、水を下げるタイミングには決まりなんてありませんが、【供えてから1時間後くらい】を目安にしてみてください。
まとめ:仏壇の水は【仏様への感謝の気持ち】と【施しの心】で供えよう
仏壇をお参りするたびにお水を取り替えるのはけっこう大変ですよね?
せっかく毎日お水を供えているなら、その意味を知っておきましょう。
仏壇にお水を供えるのは、
- 仏様たちの喉をうるおしてもらう=感謝の気持ち
- すべての生き物に対して【布施】をする=施しの心
という意味があるので、仏壇をお参りするときにはこの2つを意識してください。
そうすれば、今までよりもグッと【質の高いお参り】になりますよ。
これからは、『仏壇に供える水の意味』を意識しながらハイレベルな仏壇参りをしてくださいね。
※仏壇についてコチラの記事も読まれています。