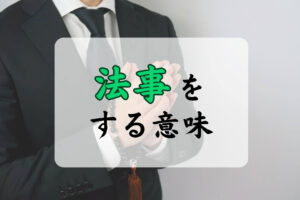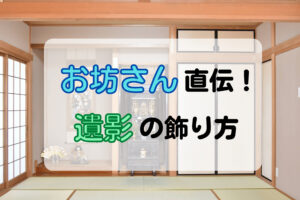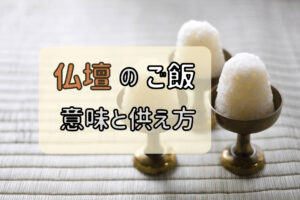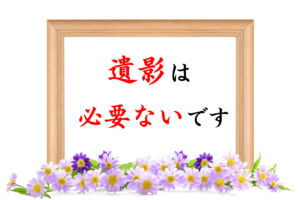- 仏壇の意味と役割
- 仏壇のお参り方法と注意点
あなたは毎日仏壇に手を合わせていますよね。
それは誰に対して手を合わせていますか?ご先祖様ですか?亡きご家族ですか?
じつは、最初に【ご本尊様】に対して手を合わせるべきなのですが、それをご存じでしょうか?
いつも当たり前のように見ている仏壇ですが、「それは知らなかった」ということが意外とあるものです。
この記事を読めば、一通り『仏壇』に関する知識が得られますので、これから仏壇を購入される方は最後まで読んでみてください。
※仏壇に置く仏具についてはコチラをご参考にどうぞ。
この記事を書いている僕『未熟僧(みじゅくそう)』は、お坊さん歴25年以上。仏事の疑問を解消するいろんな情報を発信しています。
仏壇の意味と役割
毎日仏壇に手を合わせている人でも『仏壇にどんな意味があるのか』をご存じでないことが多いです。
仏壇には『お寺の本堂の代わり』という意味があります。
だから、仏壇の中をよく見ると、お寺の本堂内と何となく造りが似ていますよ。
じつは、【仏壇】と【寺の本堂内】は造りが似ていないとダメなんです。
なぜなら、仏壇はお寺へ行かなくても自宅でお参りができるように考えられたものだからです。
仏壇の準備
仏壇を購入するときにはいくつか注意点があります。
ここでは、お仏壇をお祀りする上での『原則』をお伝えします。
仏壇には【各宗派で決められた本尊様】を祀る
まず1つめの注意点です。
仏壇には【各宗派で決められた本尊様】を祀るようにしてください。
一般的に、人が亡くなると【お葬式】を執り行います。
お葬式を『仏式』で執り行った場合、基本的には【お葬式を勤めたお寺の宗派】のやり方で今後の故人の供養をすることになります。
お葬式のときに授けられた『戒名(法名)』も、そのお寺が属する宗派の決まりに従って授けられているんです。
つまり、お葬式以後は【お葬式を勤めたお寺】と同じ宗派の信者になるということなんですよね。
そのため、仏壇は【お葬式を勤めたお寺】の宗派の決まりに従って用意しなくてはなりません。
宗派の決まりに従って仏壇を用意するということは、必ず【各宗派で決められた本尊様】を祀ることになります。
どの宗派が何の仏様なのかは、お寺や仏具店に確認すると教えてもらえます。
たまに、仏壇の中に位牌しか安置していない家がありますが、仏壇には本尊様が必要ですよ。
はっきり言って、本尊様がないと仏壇の意味がありません。
本尊様は【木製】でも【掛け軸】でも、どちらでもかまいませんので必ず購入してください。
また、その他の仏具についても宗派ごとに微妙に違うので、仏具店の人へ宗派を伝えてから購入をした方が無難です。
必ずお坊さんに『仏壇開眼(魂入れ)供養』をしてもらう
次に、もう1つ大事な注意点があります。
仏壇用具一式と本尊様を購入したら、お坊さん(お葬式のときと同じ宗派のお寺)に、必ず『仏壇開眼(ぶつだんかいげん)供養』をしてもらってください。
『仏壇開眼供養』とは、簡単にいうと購入したご本尊様に《仏様としてのチカラ》を宿らせるための供養です。
仏壇開眼供養は忘れないでください。開眼供養をすることでようやく『本尊様』としての役目を果たすようになります。
何もしないと、ただの【木製の仏像】のままですよ。ただの木製の仏像にいくら手を合わせたって何の意味もありませんからね。
また、新しい位牌ができあがっていたら、仏壇と同様に『位牌開眼(いはいかいげん)供養』もしてもらってください。
位牌開眼をすることによって、位牌を通じて今は亡き故人やご先祖様と通じ合うことができるようになります。
ただし、仏壇と同じように、位牌も開眼供養をしていないものに手を合わせたって意味がありませんので、ご注意ください。
仏壇は【お寺の本堂の縮小版】です
仏壇は【お寺の本堂の縮小版】の役割をしています。
ほとんどの宗教には宗教施設があり、信者さんはその宗教施設へ出向いて【信仰の対象】を崇拝し、祈りを捧げます。
仏教の場合は、宗教施設が『寺(本堂など)』であり、信仰の対象は各お寺の『本尊様』です。
本来なら毎日のようにお寺に行って、本堂の前(あるいは本堂内)で本尊様に手を合わせるのが仏教の信仰というものです。
でも、実際のところ、ほとんどの人は毎日お寺に行くことができません。
それで、お寺の本堂の代わりになるものとして『仏壇』ができました。お寺に行けないなら、代わりになるものを各自で作ってしまえということですね。
つまり、仏壇は【お寺の本堂の縮小版】なんです。
そうなると、お寺で本尊様に手を合わせるのと同じように、仏壇にも手を合わせる【信仰の対象】が必要となるので、仏壇には必ず本尊様を安置するんですよね。
ちなみに、宗教を信仰することにおいて【家族の誰かが亡くなっているかどうか】なんてことは関係ありません。
なので、仏壇がお寺の本堂の代わりということであれば、誰も家族が亡くなっていない家に仏壇があっても全く変ではないのです。
とにかく本尊様を中心に考える
仏壇内の主役は本尊様なので、仏壇を取り扱うときには、とにかく【本尊様】を中心に考えるようにしましょう。
仏壇を前にしてまず最初に合掌する相手は、本尊様。
あなたのご先祖様や亡きご家族を導いてくださっているのも、本尊様。
あなたの家全体を守ってくれているのも、本尊様。
お仏壇においては、とにかく【本尊様】を中心にして考えます。
だから、仏壇を購入するときも、まずは『本尊様』から決めていくべきです。
そして、言い方は悪いですが、仏壇を購入するときに『一番お金をかけるべきもの』は本尊様です。お願いします、本尊様だけは奮発してください。
ちなみに、同じ名前の仏様なのに仏像によって顔立ちが全然違うので、本尊様を決めるときは『どんな顔立ちなのか』をよく見てくださいね。
すると、その中に「なんか、この仏像が気になる。」というものがありますので、それを選びましょう。
それが、あなたと本尊様の【仏縁(ぶつえん)】です。
あと、本尊様以外のものに関しては必要以上に費用をかけなくてかまいませんよ。
購入する仏壇は昔からあるような大きなものではなく、コンパクトなもので十分です。
大きな仏壇を購入できるくらいの金額があれば、コンパクトな仏壇なら【かなりの高級品】が買えます。
でも、仏壇はそんなに高級である必要はありませんので、本尊様の方にお金をかけてください。
購入する仏壇は『10万円~30万円』くらいのものが、比較的お手頃な価格ですし、品質も十分に良いですよ。
位牌はどこに置くの?
仏壇には本尊様が必要であり、本尊様が主役であることはお分かりいただけましたよね。
では、【位牌】はどのように扱えばいいのでしょうか?
位牌は『本尊様よりも下になる場所』に安置してください。
大切な家族の位牌なのですが、優先順位としては、やはりご本尊様が【最上位】となります。
そして、仏壇をお参りするときは、まずは本尊様、その次に位牌という順番です。
仏壇に位牌があると、ついつい意識が位牌にだけ向かってしまうかもしれませんが、そうではないのでご注意ください。
少し大げさですが、位牌は『本尊様と同じ空間に置かせていただいている』というイメージでもいいくらいですよ。
では、具体的にはどのあたりに位牌を安置すればいいのでしょうか。
位牌を安置する場所は『ご本尊様がいる段より一つ下の段』が最適で、
- 本尊様が最上段の中央
- 位牌はそのすぐ下の段の中央
がいいと思います。
他の仏具の配置に関しては、それぞれ置きやすい場所でかまいません。
【関連記事】⇒位牌とは何なの?位牌の意味や必要性をお坊さんが解説します。
仏壇のお参り方法と注意点
本尊様の開眼供養が済んだら、それでもう仏壇としての機能はあります。
あとは毎日仏壇にお参りをするだけです。とはいえ、これが一番大変なことなんですけれどもね。
では、簡単に仏壇のお参りの仕方を説明します。
ただし、宗派によってお参り方法が少し違いますので、一般的なものを説明します。
仏壇の前に座り(正座できる人はしてください)、
- 仏壇に向かって合掌(礼でも可)をする
- お供物・お水・お花を供える
- ロウソクに火をつける
- 線香に火をつけて供える
- 数珠を左手に持ち、合掌して頭を深く下げる
- お鈴を鳴らす
- お経をお唱えする(お唱えできる人だけ)
- 再び、合掌して頭を深く下げる
- ロウソクの火を消す
- 合掌(礼でも可)をしてから退く
と、このような手順でお参りしてください。
そして、お参りのときにはいくつか注意点がありますので、頭の隅に置いておいてください。
お仏壇のお参りは、朝と夕方の2回行うのが好ましいです。お寺でも朝と夕にお勤めをしていますよ。
香炉の下には必ず仏壇用の【防火マット】を敷くようにしましょう。まれに火のついた線香が香炉の外に倒れてしまうことがあります。最近では『電気線香』というのもあるので、火災が心配な人は使ってみてください。
仏壇に供えるお花は【トゲのある花】を避けるようにしましょう。本尊様に鋭利なものを向けてはいけません。
仏壇へのお供物は、お刺身などの『生もの』は避けましょう。本尊様もご先祖様も亡きご家族も、あの世では生ものを召し上がりません。
線香に火をつけた後、息を吹いて火を小さくしないでください。手で仰ぐか、線香を立てるように持って、そのまま真下にシュッと下げて消しましょう。仏様へ供えるものに人間の息を吹きかけるのはNGです。
お経をお唱えするときは、お鈴を鳴らします。お唱えしない場合は、鳴らしても鳴らさなくても、どちらでもけっこうです。※これには賛否両論ありますが、別記事の『仏壇にある鐘【お鈴(おりん)】はいつでも鳴らしていいですよ。』に書いたように、僕はお鈴をいつでも鳴らしていいと思います。
ローソクの火を消すときも、息を吹いて消さないでください。
本尊様へのお供物は、お参りが終わったら家族で食べてください。お供物を食べることも立派な供養です。
仏壇の扉は、基本的に『開けたまま』でかまいません。仏壇の本尊様が家の中をちゃんと見られるようにしておきましょう。
しかし、大掃除の時などの場合は一時的に閉めて大丈夫です。仏壇の扉の開閉については『仏壇の扉は開けっ放しでいいの?家族に不幸があった時やお盆の時は閉めておくの?』の記事を読んでみてください。
まとめ : 仏壇はお寺の本堂と同じ!毎日のお参りを心がけよう
仏壇のお参りは、なかなか毎日はできないかもしれません。
何でもそうですが、毎日続けるというのは大変なことです。
そういえば、仏壇のお参りを毎日続けることについて、僕の知り合いのお坊さんが以下のような話をしていました。
なるべく毎日仏壇をお参りするように『意識』をしてみてください。
『意識』をしていると、やがて実際に『行動』に移されていきます。
『行動』を続けると、それはやがて『習慣』になっていきます。
そして、その『習慣』は、いずれその人の『生き方』となります。
私たちは、ご先祖様や亡きご家族の姿を見ることができません。
しかし、毎日仏壇に手を合わせるみなさんの姿を、仏様達はちゃんと見ておられます。
みなさん、どんなときにも感謝の気持ちを忘れない日々を送る、それをまず意識してみてください。
と、こんなカンジだったかと。
本来は毎日お寺をお参りして、本尊様に日々の感謝をお伝えするのですが、それは多くの人にとって現実的なことではありません。
お寺に行くのは無理でしょうから、せめて【仏壇を毎日お参りしよう】と『心がける』ようにしてみてください。
あなたの『心がけ』が、いずれ『仏様に毎日手を合わせる生き方』になり、感謝の心を忘れない豊かな人生になることでしょう。
※仏壇に置く仏具についてはコチラをご参考にどうぞ。