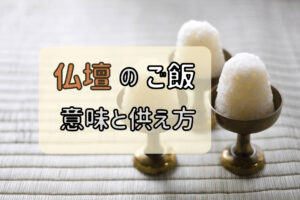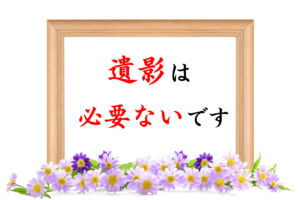- 遺影の飾り方がよく分からない。
- 遺影って、仏壇の中に飾ってもいいの?
- そもそも、遺影は何のためのものなんだろう?
せっかく遺影を飾るなら、正しい場所に正しい方法で飾りたいと思いませんか?
でも、遺影をどこにどうやって飾ればいいのか分からないですよね。
じつは、遺影には【飾る場所】や【飾り方】にコレといった決まりがないのです。
遺影というのは【ただの写真】なので、どこに飾っても問題はないですが、しいて言うなら『仏壇の近く』あるいは『家族が集まる場所』に飾るのがよいと思います。
この記事では、
- 遺影を飾る場所とその理由
- 遺影の飾り方
- 遺影とはどういうものか
について紹介しています。
遺影に対する考え方や取扱い方法が分かりますので最後まで読んでみてください。
 未熟僧
未熟僧遺影を飾るときの簡単な目安をお伝えします。
この記事を書いている僕『未熟僧(みじゅくそう)』は、お坊さん歴25年以上。仏事の疑問を解消するいろんな情報を発信しています。
遺影を仏壇の中に飾ってもいいの?
遺影に関して「仏壇の中に遺影を飾ってもいいですか?」という質問がよくあります。
結論から言いますと、遺影を飾る場所にはコレといった決まりがないので、仏壇の中に遺影を飾ってかまいません。
また、一部では「仏壇に遺影と位牌を飾ると、故人の魂がどちらに宿ればよいか迷ってしまう。」と言う人もいますが、遺影に故人の魂は宿らないので心配無用です。



故人の魂は『魂入れをした位牌』に宿るんです。
でも、じつは、本来であれば遺影は仏壇の中に飾らないんですよね。
なぜなら、仏壇は『お寺の本堂の縮小版』だからです。
お寺の本堂には、その宗派にとって重要なお坊さんの絵や歴代住職の写真は飾ってありますが、それ以外の個人的な遺影はありません。
そもそも、本堂というのは多くの人が仏道修行をするための《道場》なので、そこへ個人的な遺影は置かないんですよね。
ですから、 『お寺の本堂の縮小版』 である仏壇の中には遺影を飾らないのが妥当なんです。
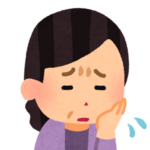
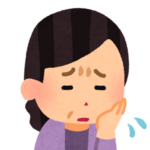
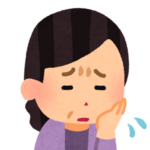
できれば仏壇の中に遺影を飾りたいんだけど・・・。
仏壇の中に遺影を飾りたい場合は、遺影を仏壇の一番下の段で、中央を外した場所に置くのがよいでしょう。
仏壇では上の段ほど上位となっており、ご本尊様は最上段、お供え物は中段、その他は一番下の段に配置します。
そして、どんなに大切な人が映っていても、遺影は【ただの写真】であり仏具ではないので、仏壇の中に遺影を飾るなら一番下の段になります。
また、仏壇の中に遺影を飾るときには中央を外すようにしてください。
仏壇内では中央が上位となるので、遺影を飾るなら中央ではなく左右のどちらかに少し外すようにしましょう。



遺影以外にも《仏壇内に置くもの》は、置き場所がある程度決まっていますよ。
仏具の置き場所については別記事の『仏壇の購入時に揃えるもの20選。それぞれの仏具の意味と置く場所も紹介』で詳しく紹介していますので読んでみてください。
遺影の飾り方
基本的に仏壇の中には遺影を飾りません。
すると「仏壇の中でなければ、どこに飾ればいいの?」という疑問が出てきますよね。
遺影を飾る場所に決まりはありませんが、ある程度の目安はあるので参考にしてみてください。
四十九日忌までは後飾り壇に飾る
お葬式が終わると、四十九日忌を迎えるまでの間、自宅には『後飾り壇』という簡易的な祭壇を設けます。
お葬式で使用した遺影は、遺骨や仏具などと一緒に『後飾り壇』に飾るのが一般的です。
多くの後飾り壇は2~3段になっており、遺影は最上段に飾ることが多いです。
しかし、遺影は【ただの写真】なので、べつに最上段にこだわる必要はなく、仏具などの飾り付けのジャマにならない場所へ飾れば問題ありません。
四十九日忌を過ぎたら後飾り壇を片付けますので、その際に遺影を他の場所に移動させましょう。
遺影のリボンは外してよい
お葬式で使った遺影には、写真の角に【リボン】が付けられます。
このリボンは四十九日忌を過ぎたら外すようにしてください。
遺影に付いているリボンは『遺影リボン』と呼ばれ、お葬式で使う【喪章】と同じ意味があります。
喪章は故人を偲び《喪に服す》気持ちを表すものであり、遺影にもリボンを付けることで故人を偲ぶ意味があるのです。
そして、仏教では喪に服すのは49日間なので、遺影リボンも四十九日忌のタイミングで外します。
しかし、外し忘れているのか遺影リボンをずっと付けている人が多いので、四十九日忌を迎えたらちゃんと外しましょう。



遺影リボンは飾りではないのでご注意ください。
仏壇のそばに飾る
遺影は、仏壇のそばに飾るといいですよ。
遺影はあくまで【ただの写真】ですが、そうはいっても【亡くなった人の写真】ですから『仏様』にちなんだ場所に飾りたいですよね。
そうすると、やはり仏壇のそばが最適で、例えば、
- 仏壇のすぐそばの棚に飾る
- 仏壇の手前にテーブルなどを置いて、そこに飾る
- 仏壇の近くの長押(なげし)の上に飾る
というのがよいかと思います。
ちなみに、遺影は【仏間】に飾ることが多いです。



仏間というのは、その名のとおり仏壇を置くための部屋のことです。
仏間に仏壇を置けば、遺影も仏間に飾ることになります。
したがって、遺影を飾る場所として多いのは【仏間】ということになります。
家族が集まる場所に飾る
最近は仏間のない家が多いですし、さらに仏壇の近くに遺影を飾る場所がないという人もいます。
そのような人は、家族が集まる場所に遺影を飾るといいですよ。
遺影というのは、いつまでも故人のことを忘れず、ずっと故人を近くに感じるために飾ります。



ならば、遺影は家族みんなの目に入る場所に飾るのが理想的です。
本来なら、毎日手を合わせる仏壇の近くに遺影を飾るのですが、もしも仏壇の近くがダメなら他の場所に飾るしかありません。
他の場所で、さらにいつもみんなの目に入る場所となれば、リビングなどの【いつも家族が集まる場所】に飾るのがおすすめです。
家の雰囲気に合わせて遺影を飾る
最近では家の雰囲気に合わせて遺影を飾るという傾向にあります。
今までの遺影といえば、額縁の色が【黒】や【茶色】といったような『古臭い』ものばかりです。
近年の住宅は洋室がメインとなっているので、せっかくの洋室に古臭い遺影なんて飾りたくないですよね。
ですから、いろんな色やデザインの【フォトフレーム】に故人の写真を入れて飾っている家が多く、オシャレな家族写真と並んで自然に遺影が飾られています。
遺影はあくまで【ただの写真】ですから、家の雰囲気に合わせて飾ればOKです。



古臭い額縁ではなく、ちゃんと家の雰囲気に合ったフォトフレームに入れてあげてくださいね。
飾る遺影の大きさは【L判サイズ】がおすすめ
遺影といえば、『四つ切サイズ』と呼ばれる【254mm×305mm】の大きさが一般的です。
でも、この一般的なサイズって、ちょっと大きすぎるんですよね。
昔の家のように広い仏間があれば、長押(なげし)に四つ切サイズの遺影を飾るのもよいと思います。
しかし、今のマンションやコンパクトな家だと、四つ切サイズは威圧感が強すぎるのです。
ですから、お坊さんの僕としてはL判サイズ(89mm×127mm)くらいの小さな遺影を飾ることをおすすめします。
このサイズであれば仏壇の中にも収まりますし、他の場所に飾ってもジャマになりません。
それに、法事のときなどに持ち運んだり、掃除のときに移動させたりするのもラクです。



遺影は家族みんなが見ることができる大きさであれば十分です。
デジタルフォトフレームで飾る
近年ではいろんなものがデジタル化しています。
デジタル化は遺影にも及んでおり、最近では『デジタルフォトフレーム』で故人の写真を飾る人が増えています。
デジタルフォトフレームとは、スマホやデジカメで撮影した写真画像を小型液晶ディスプレイに表示させる『デジタル用の写真立て』のことです。
デジタルフォトフレームなら、複数の画像を順番に流しながら表示できるので、1つの画面でたくさんの【故人との思い出】を見ることができます。
あなたのスマホやデジカメには故人の姿がたくさん撮影されていることでしょう。でも、それらの写真画像を現像することはほとんどないですよね。
だったら、スマホのアルバムに埋もれている故人の写真をデジタルフォトフレームに入れて、ちゃんと日常的に見えるようにしてあげるのもよいと思いませんか?
ちなみに、デジタルフォトフレームについて、お坊さんの僕から1つ切実なお願いがあります。
家にお坊さんが来て法事をするときは、あらかじめ一番良い写真を【固定表示】させてください。
じつは以前、読経の途中で『故人のユーモア溢れる姿』がスライド表示され、それがあまりにも面白く、笑いをこらえながら法要を進めるのが大変でした。
ですから、法事のときだけはユーモア要素のない写真を固定表示しておいてください。
複数人分の遺影がある場合は、向かって【右】を上座にして飾る
あなたの家には複数人分の遺影がありますか?
遺影を飾るときには一応の【飾る順番】があります。
複数人分の遺影を飾る場合は、向かって【右】を上座にしてください。
仏事では、
- 私たちから見て『右』が上座
- 私たちから見て『左』が下座
と考えます。
上座や下座があるということは、大変失礼ながら仏様に優先順位をつけているのです。
仏様の優先順位のつけ方は、生前の地位や性別に関係なく先に亡くなった人から順番に上位になると覚えてください。
夫婦の場合、もしも妻が先に亡くなったら、妻が上位です。
親子の場合、悲しいことに子どもが先に亡くなれば、たとえそれが赤ちゃんでも、子どもの方が上位です。



遺影は、右から左へ【先に亡くなった人の順】で飾ると覚えておきましょう。
とはいえ、これは遺影を飾るときの単なる基準というだけなので、家族のみんなで納得のいくように飾ってかまいません。
遺影を飾る【向き】に決まりはない
遺影を飾るときに【向き】を気にする人はとても多いです。
しかし、遺影の【向き】に決まりはないので気にしなくて大丈夫。
遺影は単なる写真ですから東西南北どの向きでもかまいません、家族みんなが見やすい向きにして飾ってください。
それでも【向き】が気になるという人は、できれば『仏壇の反対側(対面側)には飾らない』ようにしてみてください。
仏壇の反対側に遺影を飾ると、遺影を正面に見たときに仏壇にお尻を向けてしまうからです。



仏事において【仏様にお尻を向けない】というのは基本的な作法なので意識してみてください。
遺影を飾るときのタブー
読者さんの中には『遺影を飾るときのタブー』を知りたい人もおられることでしょう。
べつに遺影を飾るときのタブーというのはないのですが、注意点のようなものは1つあります。
それは、遺影を仏壇の上には置かないということです。
仏壇の天板は平面なので、ついそこへ遺影を置きたくなりますが、天板のすぐ下にはご本尊様がいらっしゃいます。
遺影はあくまで【ただの写真】であり、それをご本尊様の頭上に置くのは好ましくないので、なるべく仏壇の上には遺影を置かないようにしましょう。



遺影だけでなく、仏壇の天板には何も置かないことが望ましいですね。
遺影はいつまで飾るべきか
遺影を飾ったら、次に気になるのが【遺影をいつまで飾ればいいのか】ということです。
遺影を飾る期間については完全にあなたの『自由』です。
例えば『◯◯回忌を迎えるまで飾る』みたいに年回忌で区切る人もいれば、特に区切りをつけない人もいます。



僕は『写真が少し色あせるまで』を基準にしていますよ。
遺影は年数が経過するとだんだんと色あせてきますので、色が少し白みがかってきたら、他の写真に交換するか、あるいは遺影を飾ること自体をヤメるタイミングだと判断します。
写真の処分方法については【一般ゴミ】として処分してかまいませんが、心理的にそれも心苦しいことでしょう。
そのような場合は、写真を封筒などに入れてから、お寺で《お焚き上げ》をしてもらってください。
そのときには必ず1千円~3千円程度の『お焚き上げ料』を納めるようにしましょう。
遺影は他の顔写真に替えてもいい
多くの人は、お葬式のときに使った遺影をその後もずっと飾り続けています。
しかし、べつに遺影は他の顔写真に替えてもいいんです。
お葬式のときは慌ただしくて、少ない時間でたくさんのことを一気に決めなきゃいけないので、じっくりと遺影を選ぶ時間がありません。
それで、仕方なく『とりあえず無難な写真を遺影にする』というケースがあります。
すると、後になって「この写真、やっぱり何だかしっくりこないなぁ・・・。」なんてことになるんですよね。
遺影というのは『生前の故人をよく表す写真』がベストなので、より良い写真が見つかったら交換をしてください。
遺影は『絶対に必要なもの』ではない
これまでは、遺影を飾る場所や方法について書いてきました。
しかし、今さらですが、遺影は『絶対に必要なもの』というわけではないんですよね。
くどいようですが、遺影は【ただの写真】なので、それを飾るかどうかは家族が決めること。
しかも、遺影には仏教的な意味が無いので故人の供養にも関連性は一切ないため、もしも遺影を飾りたくないなら無理に飾らなくてかまいません。
それに、最近では写真をわざわざ現像することも少ないですよね?
あなたのスマホに保存されているたくさんの写真、それをすべて現像なんてしませんよね?
いろんな思い出や人の写真を『画像データ』として残して、思い出したタイミングでたまに見るだけ。
ですから、遺影を飾りたくないなら、パソコンやスマホなどに故人の写真を『画像データ』として保存しておくだけでもよいと思います。
それで、ふと故人のことを思い出したときに画像データを見てあげてください。
【関連記事】:遺影はいらない。遺影を飾りたくないなら処分してもOK
まとめ
遺影というのは【ただの写真】にすぎないので、仏壇の天板に置かないということだけ注意すれば、あとはどのように飾ってもかまいません。
一応の目安としては、遺影は仏具ではないため、仏壇の中でなく【仏壇のそば】か【家族が集まる場所】に飾るとよいでしょう。
そして、昔のように黒縁の額に大きな写真を入れて飾るのではなく、家の雰囲気に合わせて小さな写真(L判サイズ)を明るくカジュアルに飾ってください。
また、遺影というのは写真を取り替えてもかまいませんから、他にもっと良い写真が見つかったら交換してあげましょう。
遺影をどのように取り扱おうとあなたの自由です。
まずは、愛する家族の遺影があなたにとってどういうモノなのかを考えてみて、それから遺影をどこへ飾るのかを決めましょう。
※こちらの記事もよく読まれています。