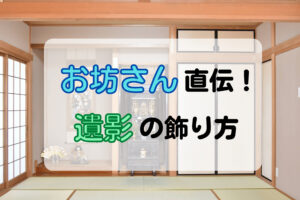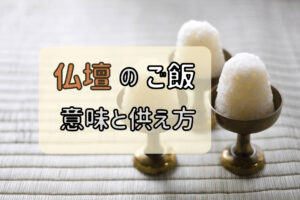- べつに遺影なんて飾らなくてもいいんじゃない?
- 遺影を飾らないと故人は成仏できないの?
- 飾らない遺影はどうすればいいんだろう?
家族が亡くなると『遺影』を飾るのが一般的です。
でも、正直なところ「べつに遺影は飾らなくてもいいんだけどなぁ・・・。」と思っていても、遺影を飾らないと何となく《後ろめたさ》を感じてしまうことでしょう。
先に結論を言いますと、遺影は飾らなくてもいいですよ。
なぜなら、遺影は『ただの写真』にすぎないからです。
ただの写真を飾るかどうかは自由ですし、なんなら処分をしてもかまいません。
この記事では、
- 遺影とはどういうものなのか
- 遺影を飾らない場合はどうすればいいのか
について解説しています。
遺影に対する考え方が分かりますので最後まで読んでみてください。
 未熟僧
未熟僧遺影については簡単に考えて大丈夫ですよ。
この記事を書いている僕『未熟僧(みじゅくそう)』は、お坊さん歴25年以上。仏事の疑問を解消するいろんな情報を発信しています。
遺影は無理に飾らなくてもいい
家族が亡くなると遺影を飾るのが一般的です。
でも、遺影を飾りたくない場合は、遺影を飾らなくてもいいですし、なんなら処分をしたってかまいません。
遺影は『ただの写真』にすぎない
多くの人は『家族が亡くなったら遺影を飾るのが当たり前』だと思っています。
しかし、遺影は《必ず飾るべき》というほど大事なものではありません。
遺影はただの『写真』なので、遺影を飾るかどうかは自由に決めてOKです。
とはいえ、遺影を飾らないと、
- 「もしかして故人が怒るんじゃないかな?」
- 「ちゃんと供養できるのかな?」
と不安になりますよね?
大丈夫ですよ、遺影がなくても故人は怒りませんし、供養にもまったく影響はありません。
また、遺影に向かって手を合わせる人もいますが、そんなことをする必要はないですよ。遺影はただの『写真』ですから、『手を合わせる』ものではなく『見る』ものです。



手を合わせなきゃいけないのは【位牌】です。
位牌は必要なものですが、遺影はあまり重要ではないということを覚えておいてくださいね。
【関連記事】:位牌とは何なの?位牌の意味や必要性をお坊さんが解説します。
遺影を飾る風習は比較的最近のもの
多くの家で当たり前のように飾られている遺影。
あまり知られていませんが、じつは遺影を飾る風習は比較的最近のものなんです。
遺影を飾るようになったのは明治期以降ですから、だいたい今から150年前くらいです。
それ以前には遺影というのはなかったのですが、遺影に似たようなものはありました。
遺影の元になっているのは、江戸時代の『死絵』や『葬儀絵巻』だという説があります。『死絵』というのは役者などの有名人が亡くなったときに冥福を祈る意味で書かれた浮世絵で、『葬儀絵巻』は記録として葬儀の様子を絵に描いたものです。
この頃はまだ【絵】ですが、明治期に入った頃に有名人の生涯を写真集に残すようになり、これが故人の姿を【写真】に残すキッカケとなりました。
その後は、日清日露戦争で亡くなった人の写真を遺影として使うようになり、その風習が全国に広がって現在の『遺影』として残っています。
また、遺影を飾るのは日本独特の風習なのです。
欧米人は『生きている人』の写真を飾りますが、『亡くなった人』の写真は飾りません。
私たち日本人は、よく遺影に向かって話しかけますが、欧米人にとってはこれに違和感を覚えるそうです。すでに《亡くなった人》で、しかも《写真》に向かって話しかける日本人は【頭がどうかしている】ように映るみたいですよ。
ということで、遺影を飾る風習は比較的最近のものですし、日本だけで広がったものですから、ずっと昔に遠くのインドで誕生した仏教とは何の関係もないんですよね。



ですから、遺影を飾ろうと処分しようと完全にあなたの自由です。
遺影を飾るのはよくない?
以前に信者さんから、



遺影を飾るのは縁起が悪いからあまりよくないって聞いたんですけど、本当ですか?
という質問をされことがあります。
なぜ【遺影を飾る=縁起が悪い】という発想になるのか、僕にはイマイチ分からないんですよね。亡くなった人が写っているから、何となく他の《霊》を呼び寄せてしまう気がするのでしょうか?
何度も言いますが、遺影は『ただの写真』ですから、縁起の良い悪いなんて関係ないです。



縁起なんて気にせず遺影を飾るかどうか決めてください。
ちなみに、縁起とは関係ありませんが、『遺影を仏壇の上に置く』のはよくないです。
仏壇の天板は平面なので遺影を置くにはちょうどいいんですが、仏壇の上には物を置いちゃいけません。
なぜなら、仏壇の中にいらっしゃる『ご本尊様』の頭上に物を置くことになるので、それが仏様に対してとても失礼にあたるんです。
遺影を飾るかどうかは自由ですが、飾るなら仏壇の上以外の場所へ飾るようにしましょう。
飾らない遺影はどうすればいいの?
家族と話し合って『遺影は飾らない』ことに決まった場合、飾らない遺影はどうすればいいのでしょうか?
飾らない遺影は、
- とりあえずどこかに保管しておく
- 処分をする
のどちらかです。
本当にどちらでもいいので、あなたの自由でかまいませんが、あえてどちらかを選ぶなら『とりあえずどこかに保管しておく』ことをおすすめします。
とりあえずどこかに保管しておく
遺影の保管場所は本当にどこでもいいので、置いてもジャマにならないような所にとりあえず保管しておくのがおすすめです。
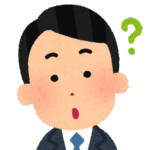
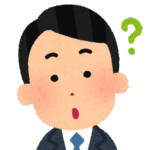
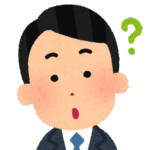
えっ?飾らないなら保管なんてしなくてもいいんじゃないの?



今後もしも【法事】をするなら遺影はあった方がいいですよ。
法事をするときには故人の【遺影】を飾ることがほとんどです。
遺影があった方が「この人の供養をしていますよ。」ということが分かりやすく、遺影を見ている方が生前の故人のことを思い出しやすくなります。
また、お坊さんによっては「寺で法事をするときは遺影を持って来てください。」という人もいるので、そのようなときに遺影がなかったら少し面倒なことになります。
その他にも、遺影がなかったら親戚から文句を言われるかもしれません。
多くの人は《家族が亡くなったら遺影を飾るのが当然》だと思っていますので、あなたの親戚の中に『うるさくて面倒くさい親戚』がいる場合は注意した方がいいですよ。
きっと「遺影がないなんて故人がかわいそうだよ。」みたいなカンジで言われることでしょう。
なので、遺影はとりあえず保管しておく方が無難です。
処分をする



やっぱり遺影はいらないから、もう処分したいんだよね。



そうですか・・・。じゃあ処分の方法を紹介しますね。
遺影はいらないから処分したいという人もいることでしょう。
ここからは遺影の処分方法について紹介していきます。
遺影の処分方法は、
- 自分で処分する
- お寺や神社で処分してもらう
のどちらかです。
自分で処分する
クドいようですが、遺影はただの『写真』なので自分で処分するというのが基本です。
自分で処分というのは【可燃ゴミ】として出すことです。
他の人に写真が見えないよう、半紙などに包んでビニールに入れて出すようにしましょう。
あるいは、【自分で燃やす】というのも方法の1つです。
自分で燃やす場合は、庭で燃やすか、家の中なら十分に注意して灰皿の上で燃やすといいでしょう。



くれぐれも火の扱いには注意してくださいね。
お寺や神社で処分してもらう
遺影がただの写真とはいえ、自分で処分することに抵抗がある人もいるでしょう。
そんなときは、お寺や神社で処分してもらうというのも1つの方法です。
お寺や神社なら、ちゃんと供養をしてから処分してくれますから、何となく安心できますよね。
ただし、処分を依頼するということは『お金』が必要になると思っておいてください。
処分費用は【5千円】もあれば大丈夫でしょう。
でも、遺影の処分をしないお寺や神社もありますので、ちゃんと事前に確認をしてから持って行くようにしてください。
まとめ:遺影はただの写真。飾らなくてもいいし、処分をしてもいい。
一般的に、家族が亡くなったら故人の『遺影』を飾りますが、最近では「遺影を飾りたくない。」という人が増えました。
遺影は無理に飾らなくていいですし、必要ないなら処分をしてもかまいません。
なぜなら、遺影は『ただの写真』だからです。
また、ただの写真である以上、遺影を飾る・飾らないというのは故人の供養と何の関係もないので、遺影を飾るのかどうかは『あなたの自由』です。
しかし、故人の回忌法要をするときなどに遺影が必要となる場合がありますので、とりあえず処分はせずに保管をしておく方が無難です。
どうしても処分をしたい場合は、自分でゴミに出すか、費用をかけてお寺や神社に処分してもらってください。
最近では写真を撮っても、それを現像する人は減っており、みんなスマホやPCに画像を保存します。
故人の顔を忘れないように、そして故人をいつも近くに感じるための遺影ですから、その目的が果たせるのであれば【現像された写真】にこだわる必要はないのかもしれませんね。
※こちらの記事もよく読まれています。