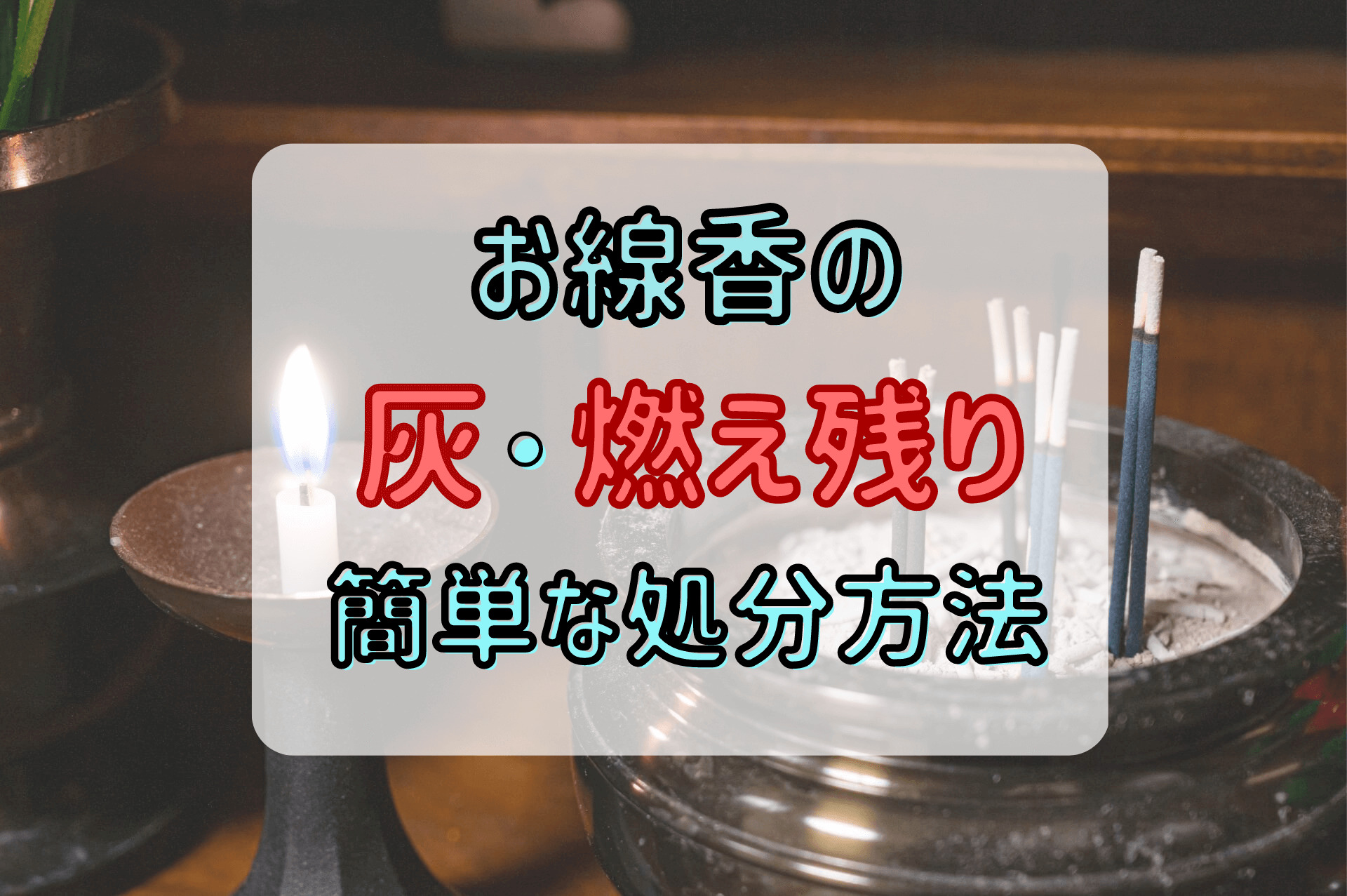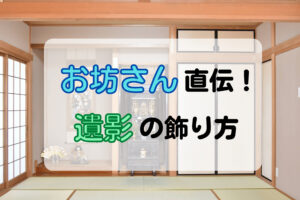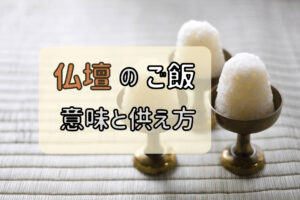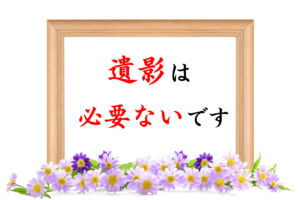- 仏壇に供えたお線香の【灰】や【燃え残り】はどうやって処分すればいいの?
- 香炉の中はどのように掃除するの?
- なぜ、お線香が燃え残っちゃうの?
仏壇に毎日お線香を供えていると、香炉(線香立て)の中に【灰】や【燃え残り】が溜まっていきます。
それを見て、
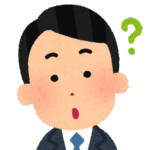
これはどうやって処分すればいいんだろう?
と悩んでしまう人が多いです。
お線香の【灰】や【燃え残り】の処分方法は意外と簡単です。
まずは本記事で紹介している方法で香炉の掃除をして、あとはお線香の灰や燃え残りを『可燃ゴミ』に出すだけです。
この記事では、
- 香炉(=お線香立て)の掃除の方法
- お線香の【灰】や【燃え残り】を可燃ゴミとして捨ててもよい理由
- 供えたお線香が燃え残ってしまう理由
について書いています。
お線香の【灰】や【燃え残り】の処分に関する悩みが解消できますので最後まで読んでみてください。



何度かやればすぐに慣れちゃいますよ♪
※↓これがあると香炉の掃除がラクです。
この記事を書いている僕『未熟僧(みじゅくそう)』は、お坊さん歴25年以上。仏事の疑問を解消するいろんな情報を発信しています。
【4ステップ】お線香の灰や燃え残りの処分方法(捨て方)
毎日お線香を供えていると、香炉の中にたくさんの【灰】や【燃え残り】があるはずです。
そして、それらの【灰】や【燃え残り】の処分で困っている人は多いのですが、じつは、処分の方法に決まりはないので自由に処分してかまいません。
とはいえ、自由と言われても困ると思いますので、これから紹介する方法で香炉の掃除をしてみてください。
その後は、必要なくなった【灰】や【燃え残ったお線香】を『可燃ゴミ』に出しましょう。
《ステップ1》お線香の灰や燃え残りを処分するための事前準備
香炉の【灰】や【燃え残ったお線香】を処分するときは、ちょっとだけ掃除するのではなく、どうせなら香炉の中の灰をすべてキレイに清掃しましょう。
まずは、事前の準備です。
香炉の中の【灰】や【燃え残ったお線香】をキレイにするために、
- 作業場所(屋外、または物が少ない部屋)
- 新聞紙または45ℓくらいのゴミ袋を2枚
- 灰ふるい専用の【ふるい】、または市販の【網目の細かい金属製のザル】
- 大さじのスプーン
- 小さなビニール袋(コンビニの袋など)
- 濡らした雑巾
- 濡らしたキレイな布
- マスク
これらの準備をしてください。
最初に《作業場所》を決めます。
作業をするときは『屋外で風のない場所』があれば理想的ですが、そのような場所がないときは『部屋の中』で行いましょう。部屋の中でやる場合は、作業中に舞い上がった灰が周囲の物に付いてしまうので、できるだけ物が少ない部屋での作業をおすすめします。
作業をする場所が決まったら、そこへ新聞紙または【45ℓくらいのゴミ袋】を2枚を用意しましょう。要するに、灰を落としても大丈夫な【敷き物】があればいいので、それを用意してください。
次に、灰ふるい専用の【ふるい】か、または市販の【網目の細かい金属製のザル】を用意してください。ザルの大きさは、直径で《20cm~30cm》くらいが理想的です。
あとは、灰をすくうために、プラスチック製でも金属製でもかまわないので【大さじのスプーン】と、灰の中に残った《線香の燃え残り》などを捨てるための小さなビニール袋を用意しておきましょう。
それと、大事なのが【濡らした雑巾】と【濡らしたキレイな布】ですね。香炉のフチなど《灰がついたところを拭く》ためのキレイな布と、後で《周囲を掃除する》ための雑巾が必要なのです。
そして、空気中に舞った灰を吸い込んでしまわないよう、できるだけ【マスク】を着けておきましょう。
以上で事前準備はOKです。
《ステップ2》香炉の中のモノをすべて出して、ふるいにかける
事前の準備が終わったら、まずは『香炉の中のモノを全部すくい出す作業』をします。
最初に、作業スペースに【新聞紙】あるいは【45ℓくらいのゴミ袋2枚】を広げて敷いてください。
次に、敷いた新聞紙やゴミ袋の上で、香炉の中のモノをスプーンですくい、【灰ならし専用のふるい】や【網目の細かい金属性のザル】の上に落とし、よくふるってください。
この『スプーンですくう⇒ふるう』の作業を地道に繰り返してください。
そして、ふるいやザルに残った【ゴミ】とか【燃え残りのお線香】は、【小さなビニール袋】に入れておいてください。



何度も灰をふるうのが面倒な人は、便利なものがあるので使ってみてください。
《ステップ3》ふるいにかけ終わった灰を必要な量だけ香炉へ戻す
次に、ふるいにかけ終わったキレイな灰は、スプーンですくって香炉へ戻します。
灰は必要な量だけ香炉へ戻しておけば大丈夫ですから、余った灰は他のビニール袋に入れて取っておくか、後述する方法で捨ててしまいましょう。
香炉の中に入れる灰の量は、香炉の【3分の2】程度まで入れておけば大丈夫です。
キレイな灰を香炉へ戻したら、周りに何もないことを確認した上で、香炉をトントン叩いて、灰を平らにならしてください。
このときに空気中に舞った灰が香炉のフチなどに付いてるはずなので、それを濡らしたキレイな布でふき取ってください。
他の場所にも灰が飛んでいたら、濡らしたキレイな布、または場所によっては濡らした雑巾でそれらもしっかりとふき取りましょう。



これで香炉の中の清掃は終わりなので、もう仏壇に戻してOKです。
ちなみに、灰を戻す前に《香炉の中の水洗い》をしてもいいのですが、しっかり乾かしておかないと、灰を戻したときに【灰が香炉に付着したまま固まる】ので注意が必要です。
ですから、普段の掃除のときには水洗いをせず、年に1回くらいのペースで水洗いをしましょう。
以上の方法でキレイに香炉と灰を掃除したら、次の日からまた心を込めて線香をあげてください。
※線香のあげ方について疑問がある方は、別記事の『お線香のあげ方やマナーを場面別に詳しく紹介。お焼香の作法も合わせて紹介』を読んでみてください。
《ステップ4》お線香の灰や燃え残りは【可燃ゴミ】に出して捨てる
最後に、お線香の灰や燃え残りの処分方法について書いていきます。
余分な灰や、ふるいにかけて残ったお線香は『可燃ゴミ』に出してかまいません。
大丈夫ですよ、言い方は悪いですが、灰や燃え残ったお線香は『ただのゴミ』ですから。
じつは、お線香というのは『仏様の食べ物』なんです。
正確には、お線香などを燃やしたときに出るお香の『香り』が仏様の食べ物なんですよね。
ですから、【お線香を燃やした後の灰】や【燃え残ったお線香】というのは、言ってみれば仏様の食べ残しみたいなものです。
あなたは、お腹いっぱいで食べ残したモノは、生ゴミとして【可燃ゴミ】の日に出しますよね?同じ【食べ残し】なのですから、他の可燃ゴミと一緒にビニール袋に包んで捨てちゃえばいいのです、そんなに難しく考えなくて大丈夫。
ただし、他の可燃ゴミと違って灰は舞ってしまうので、灰を捨てるときは水分を含ませて固めるといいですよ。
そして、灰の処分方法は他にもあります。
一軒家に住んでいて【庭】がある場合は、灰を庭にまくというのも1つの方法です。
灰には《カリウム》という物質が多く含まれています。
カリウムは、
- 植物が育つための重要な成分で、適量をまけば植物の根が強く育つ
- 灰はアルカリ性なので、雨などで酸性が強くなった土にまくことで、その周辺の土を本来の弱酸性に戻してくれる
という性質があります。
ですから、灰を庭にまくことで【灰の処分ができる】だけではなく【庭の植物の栄養分にもなる】ので一石二鳥です。
ただし、1か所にドバッと大量の灰をまいてはいけません。



灰は風が吹くと舞ってしまうので、ご近所に迷惑です。
そして、大量の灰を1か所にまいてしまうと、その周辺の土が【アルカリ性が強い状態】になり、それはそれで植物に悪影響が出てしまうのです。
ですから、庭に灰をまく場合は【土と少量の灰をかき混ぜる】というカンジで処分をしてください。また、土の性質を急激に変化させないためにも、この作業は1回でまとめて行わずに、日を空けてこまめに回数を分けて行うようにましょう。
そのためにも、日頃から香炉の中に灰を溜め過ぎないことが大事なんですよね。
以上のように、お線香の灰や燃え残ったお線香の処分方法というのは意外に簡単です。
じつは、仏様に関するモノで『特別に扱うべきもの』はそんなに無く、ほとんどのものは普通のゴミとして処分してイイんです。



みなさん仏事に対する考え方が真面目すぎます。
仏様を大切に考えるのは非常に良いことなのですが、あまり作法とかを気にしすぎると面倒になってしまいます。
取り扱いを気にしなくちゃいけないのは、ご本尊様などの《仏像》または《位牌》といった『魂入れ』をしているものだけです。
それ以外の仏具に関しては、取り扱いがちょっとくらい雑でもかまいませんよ。
香炉の中にある灰は、繰り返し使えます
今さらですが、念のためにお伝えしておきます。
お線香を供えたときに出た灰などの『香炉の中にある灰』は繰り返し使えます。
たまに、香炉の中に灰が溜まってくると、
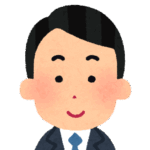
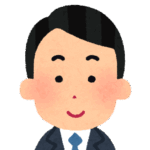
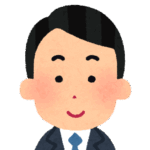
もう灰がいっぱいだから捨てなきゃね。
と言って、灰を全部ごっそりと捨てて『新品の灰』を香炉の中に入れて使う人がいます。べつに新しい灰を使うことは何の問題もありませんし、むしろ仏様をとても大事にしている証拠なので素晴らしいことです。



僕としては、少しもったいないかなぁと思います。
灰はちゃんと手入れすれば何度でも繰り返し使えるんですよね。それに、灰を繰り返し使うことは『仏様に対して失礼』にはならないので大丈夫です。
というわけで、『香炉の灰の種類を変えたい』という場合を除けば、わざわざ新品の灰を買う必要はありません。
お線香が燃え残ってしまう原因は、湿気と酸素不足
お線香って、灰だけではなく【燃え残り】の処理もけっこう面倒なんですよね。
お線香が燃え残ってしまう原因は、
- お線香自体に湿気がある
- 灰の中で、燃えるために必要な酸素が不足する
ということです。
たまに、お線香を供えても途中で火が消えてしまうことがありますよね?
それって、ほとんどの場合はお線香に湿気がある(濡れている)のです。
古いお線香、あるいは湿気が多い場所にずっと保管されていたお線香にはこのような現象が起きやすいです。
ですから、お線香はできるだけ湿気を避けて保管しましょう。
また、お線香が【灰の中】で燃え残ってしまうことがありますよね?
【灰の中】で燃え残ってしまうかどうかは『灰の状態』で決まります。
香炉の中の灰は《平面のものを押し当ててならす》という方法もあるのですが、この場合は灰を押し固めすぎないように注意してください。
灰をグイグイ押し込みすぎると、灰がギュッと固められ、灰の中にある酸素が外へ押し出されてしまいます。それでお線香を供えたときに『灰の中のお線香』の部分だけが酸素不足で燃え残ってしまうんです。
それが繰り返されて灰の中は燃え残りのお線香でいっぱいになり、さらに酸素の居場所がなくなるという負のループとなります。
ですから、お線香の燃え残りがどうしても気になって嫌だという場合は、『わら灰』を使うといいですよ。



わら灰とは、その名のとおり『わら』を燃やした灰のことです。
わら灰であれば、空気が入る【すき間】が多いため、灰の中にも十分な酸素を確保できるので燃え残りはなくなります。
しかし、わら灰はギュッと押し固めてもまだ柔らかいので『お線香が立てにくい』という欠点がありますね。
お線香が燃えた後の灰を使うか、わら灰を購入して使うか、これは【好みの問題】なので、あなたの好きな方を選んでください。
お線香の灰や燃え残りを【お寺】に持って行くのはヤメて!
仏様に関するものは自分で処分しづらいかもしれません。
どうしても自分で処分できないという場合は、お寺で処分してもらえることもあります。
例えば、
- 遺影(亡くなった人の写真)
- 仏画
- 切れた数珠
- 書写した写経用紙
- お守り
などは、僕のいるお寺にも持ってくる人が多いですね。
この辺のモノはたしかに自分で処分はしづらいでしょうから、これらはお寺で預かって『お焚き上げ』という形で焼却処分をしています。
しかし、お線香の灰や燃え残りについては、お寺に持って来られても困るんですよね。



ごめんなさい、ハッキリ言って迷惑です。
もちろん処分することはできるんですよ、寺の可燃ゴミと一緒にしちゃえばいいだけですから。
ただ、お線香の灰や燃え残りは可燃ゴミで出していいものなので、お寺としては「えっ、それは普通にゴミで出してくれよ。」って思うんです。
先ほども言いましたが、お線香の灰や燃え残りというのは【仏様の食べ残し】みたいなものです。
ですから、それをお寺へ持って行くことは『食べ残しをお寺で処分してもらう』ことと同じです。
あなただって、



これ、ウチの家族の食べ残しなんだけど、あなたの家で処分しといてくんない?
って言われたら、



はぁ~っ!?何でウチが処分しなきゃいけないの?
って思いますよね?
お寺で処分してもらった方がいいのは、お坊さんに供養や祈祷をしてもらったものだけです。
お坊さんに供養や祈祷をしてもらったモノは、いわゆる【魂入れ】をしています。そして、【魂入れ】をしたものを処分するときには、ちゃんと【魂抜き】をする必要があるんです。
ですから、購入時に【魂入れ】したものは、処分する際にはお寺に持って行き、お坊さんに預けた方がいいのです。
しかし、それ以外は【一般ゴミ】として処分しても大丈夫です。
まとめ:お線香の灰や燃え残りは【可燃ゴミ】として処分しても大丈夫です!
仏壇に毎日お線香を供えていると、香炉に灰や燃え残ったお線香がたまっていきます。
それらは定期的に【香炉の中の清掃】をして、灰を適量だけ香炉へ戻してあげてください。
そして、【余分な灰】や【燃え残ったお線香】は普通に『可燃ゴミ』として処分してかまいません。
灰や燃え残ったお線香は《仏様の食べ残し》なので、、私たちが残った食べ物を【可燃ゴミ】として処分するのと同じで、お線香も決められた曜日に可燃ゴミとして捨てましょう。
あとは、灰はそのまま捨てると空気中を舞ってしまいますから、
- 必ずビニール袋に入れる
- 場合によっては水分を含ませて固める
というくらいのマナーは必要ですが、他には何もすることなんてありません。
仏様に関わる多くの物が【一般ごみと一緒に処分してよいもの】なので、今後はお線香に関わるものは、すべて一般の可燃ゴミに出して処分しましょう。
※仏壇のお線香についてはこちらの記事も読まれています。