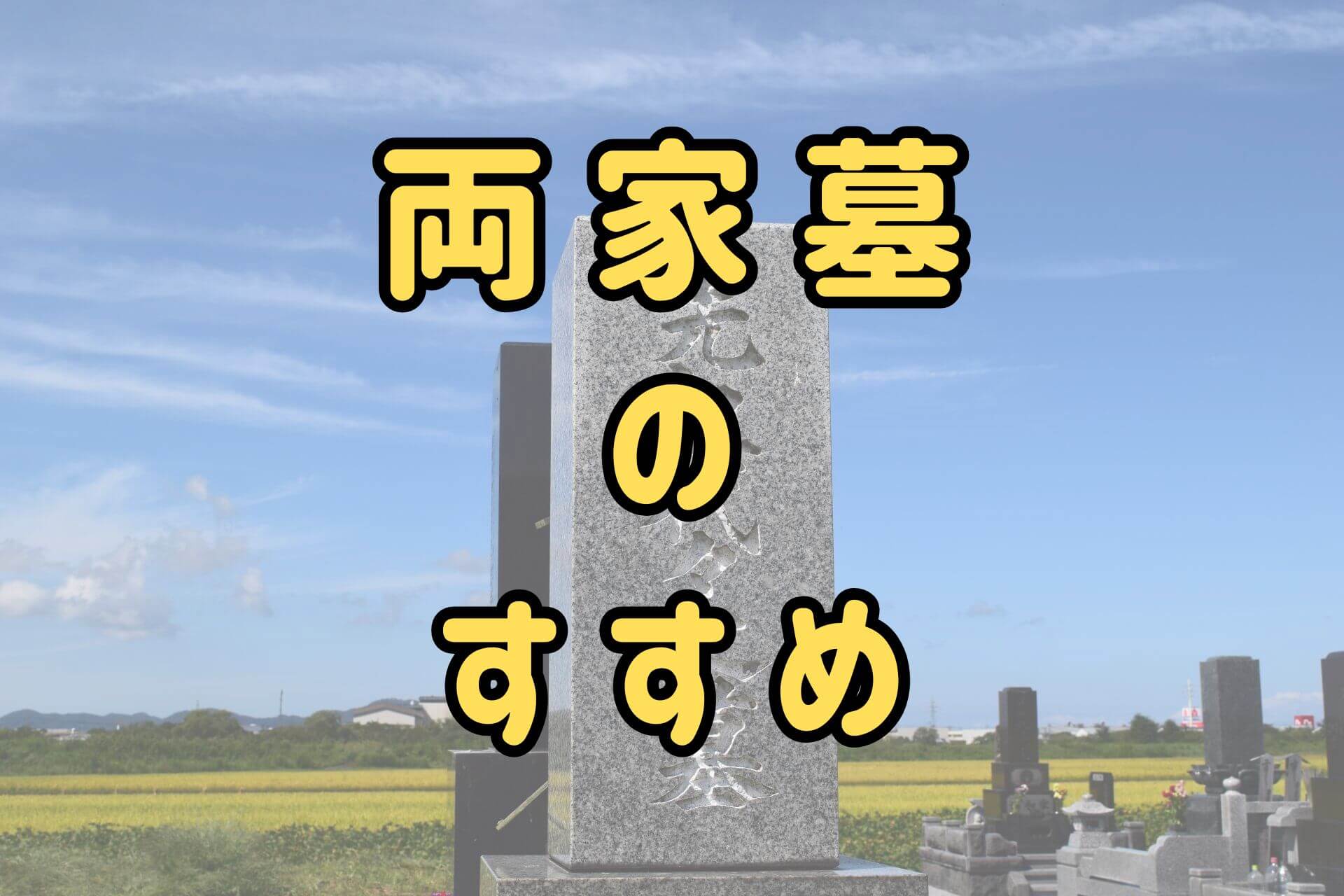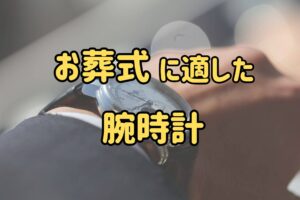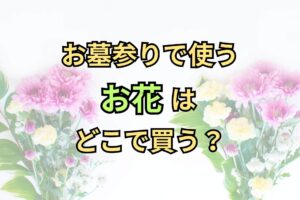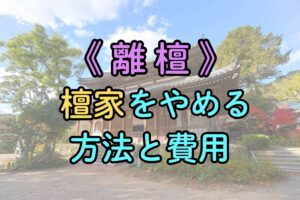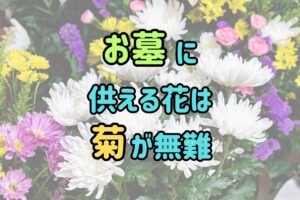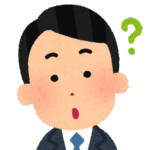
自分の家のお墓に【妻の実家の仏様(遺骨)】を一緒に納骨したいですが大丈夫ですか?



それは大丈夫です。これを機に、あなた家のお墓を『両家墓』にしてみてはどうでしょう?
最近では『両家墓』を建てる人が増えてきました。
両家墓とは、姓が違う2つの家のお墓を1つに統合したお墓のことです。
両家墓は多くの人が抱えているさまざまな『お墓に関する問題』を解決してくれます。
お坊さんの僕としては両家墓を建てることに賛成ですし、『おすすめのお墓の形式』でもあります。
しかし、両家墓にはメリットだけでなく、やはりデメリットもあります。
この記事では、【両家墓のメリットとデメリット】について、僕のお坊さんとしての経験をもとに書いています。
両家墓を建てたことを後悔しないために最後まで読んでみてください。
この記事を書いている僕『未熟僧(みじゅくそう)』は、お坊さん歴25年以上。仏事の疑問を解消するいろんな情報を発信しています。
『両家墓』はおすすめのお墓の形式
日本は『少子高齢化』がどんどん進んでいます。
少子高齢化の問題は、そのまま『お墓の継承者の問題』にもなっているんですよね。
さらには、お葬式や法事などもしないという人まで増えて、いわゆる『仏教離れ』も急速に進んでいます。
そのような状況もあってか、お墓の継承者がおらず【無縁墓】となってしまうお墓が増えています。



せっかく建てたお墓なのに【無縁墓】にしたくないですよね。
無縁墓にしないためには、『両家墓(りょうけばか)』を建てるという方法があります。
両家墓というのは、『姓が違う2つの家のお墓を1つ統合したお墓』のことで、夫婦どちらかの実家のお墓に継承者がいない場合に建てられます。
お墓というものは、誰かがお参りをしてナンボです。誰も継承者がいないのであれば、近い将来には【無縁墓】となってしまいます。
もちろん、お墓じまいをして遺骨を【永代供養墓】へ納骨するという選択肢もありますが、それはあくまでも最終手段。
とりあえず、家族はダメでも、親族などで他に継承できる人がいないか探してみましょう。もしも継承できる人がいれば、その人がお墓を守ってくれるのが理想です。
とはいえ、その人だって、すでに自分のお墓を持っているかもしれません。複数のお墓を管理するのはかなり大変なので、継承を断られる可能性も十分にあります。
そこで、自分の家のお墓と妻側のお墓を一緒にしてしまう、という発想が生まれたんですね。
自分の家のお墓に統合してしまえば、管理もできるし、お墓参りも1ヶ所で済みます。
両家墓は、お墓の管理の負担を増やすことなく、なおかつ無縁仏を出さなくていいという素晴らしいお墓の形式だと思います。
奥様の家のお墓に継承者がいない場合は、まず『両家墓』を先に考えてみてください。
両家墓は新しく建てなくても大丈夫
あなたは「両家墓を建てる」と聞いて【新しいお墓を建てなきゃいけない】と思っていませんか?
べつに両家墓は新しく建てなくても大丈夫ですよ。
もしも今、すでにあなたの家のお墓があるのなら、墓石の正面の彫刻(文字)を変えてしまうだけでいいんですよ。
変えてしまうというか、正確には、墓石の正面を一度全部削ってしまい、改めて文字を彫り直すということです。
全部削った墓石の正面には、
- あなたと奥様の実家の両家の苗字を並べて彫る
- 両家の苗字ではなく『先祖代々之墓』とだけ彫る
のどちらかを選べばいいでしょう。
そして、墓石の左右の側面のスペースに余裕があれば、そこへ新しく入った仏様達の戒名などを彫刻します。
もちろん、墓石の側面ではなく、別に設けられた『墓誌』の方へ彫刻しても大丈夫です。
これで、両家の仏様が入ったお墓であることがわかるようになります。
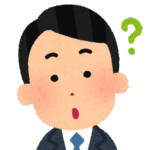
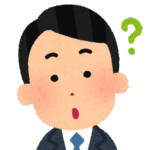
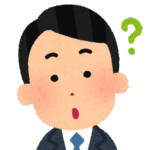
正面の彫り直しをせずに、今のままで両家墓として使えないんですか?



可能ですが、できれば彫り直してほしいですね。
たしかに、お墓の正面を全部削って、そこへ新たな文字を彫るには、それなりの費用が必要です。
しかし、お墓を新しく建てる費用に比べれば、その10分の1以下の金額で足りるでしょう。
だったら、ちゃんと両家の仏様を敬うという意味でも、墓石の正面を彫り直すべきだと思いますよ。
ちなみに、もしも、あなたが『彫り直し』ではなく『新しく建てる』というつもりなら、ぜひそのようにしてください。
それが一番理想的で、両家の仏様に対して【最高の供養】ができますから。
【関連記事】:お墓の意味や役割とは何?お墓参りでお墓はパワースポットに育つ?
両家墓を建てるメリット
僕が両家墓をおすすめするということは、それなりにメリットがたくさんあるからです。
ここでは、僕が「これは大事なメリットだな」と思うものを紹介していきます。
無縁墓にせず両家の仏様をお参り(供養)できる
両家墓の大きなメリットの1つは、お墓を【無縁墓】にせずに済み、なおかつ両家の仏様をお参り(供養)できるということです。
じつは、【無縁墓】が無くなることは寺側にも大きなメリットがあるんですよね。
寺にとって一番困るのは『誰もお参りに来ない無縁墓ができてしまうこと』です。
寺にとって【無縁墓】は、
- 誰にも管理されないので雑草が生え放題で迷惑
- 誰もその家の仏様の供養をしない
- 墓地の管理料が徴収できず1円の収入にもならない
- 貴重な墓地の1つを占領されてしまう
という、かなり困った存在なのです。
しかし、誰も来ないからといって、寺が勝手に墓じまいをしてしまうわけにもいきません。
実際は法的に墓じまいすることもできますが、それにも一定の費用と期間が必要です。
ですから、無縁墓にせず遺骨を引き取ってくれる人がいると、寺側としては本当にありがたいんです。
墓地が1つだけなので経済的にラク
複数のお墓を1つに統合するということは、『お墓の管理にかかる費用』も1つにできるということです。
お墓の管理にかかる費用は、
- 墓地の年間管理料
- お墓参りのときの費用
- 行事ごとの供養料や寄付
などです。
これらを1か所だけにできるというのは、経済的に大きな負担軽減になります。
墓地の年間管理料
お寺や霊園などにお墓がある限り『墓地の年間管理費』が必要です。
年間の管理費は、そのお寺や霊園によって設定価格がまったく違いますし、その他にも、
- 墓地の大きさ
- 墓地の場所
によって変わります。
僕の知っている限り、年間管理費の金額は【1,500円~32,000円】とかなりの差があります。
管理費が安い墓地だといいのですが、高い墓地を複数管理していると、それだけで数万円の出費です、しかもそれが毎年です。
お墓を1つに統合することは、それだけで年間の出費を確実に抑えることができます。
お墓参りの費用
お墓を複数管理していると、それぞれのお墓にお墓参りをすることになります。
これはけっこう大変なことですよ。
それぞれのお墓が近くにあるならいいですが、離れた場所にあったらいちいち移動するだけでも一苦労です。
それに、お墓へ行くまでの交通費などがそれぞれに必要となりますよね。
それだけではありませんよ。
お墓参りに行くときは【お花】を持って行きますが、それだって、それぞれのお墓ごとに必要です。
さらに厳密に言えば【お線香】だって必要だし、【お供物】も供えますよね。
このように、お墓の数だけ『お墓参りの費用』が必要です。
これがお墓を1か所にできれば、ずいぶんとお墓参りの費用が減らせるはずです。
行事ごとの供養料や寄付
お寺にある墓地を複数管理するのは本当にやめた方がいいですよ。



お坊さんの僕が言うんだから間違いない。
まず、お寺にお墓がある場合、お盆などの行事のたびに『供養料』を納めなくてはいけません。
日本のお寺でお盆供養をしていないところなんて無いでしょう。当然ながらお盆は毎年あるので、そのたびに【数千円~数万円】を納めるわけです。
複数の墓地を管理していれば、その数の分だけ負担が増えるので大変です。
さらに、です。
お寺の墓地の大きなデメリットの1つである『寄付を要求される』という可能性があります。
お寺の仏具などは金額がいちいち高いんですね。
ましてや、本堂の建て替え事業となれば『億単位のお金』が必要になります。
そうなると寺の財産だけでは到底まかなえないので、信者のみなさんに寄付を募ります。
寺が募る寄付というのは、【1人あたり数千円】というわけにはいきません。どんなに少なくても、【数万円〜数百万円】という金額になってしまいます。
もしも、複数の寺の墓地を管理していて、同じ時期に寄付を要求されたらどうします?
だから、お寺の墓地を複数管理するのはヤメて、できるだけ早く1つのお墓に統合しましょう。
そうすれば、行事の供養料や寄付を1か所分に減らせますから。
墓地が1つだけなのでお墓参りがラク
お墓を1つに統合するメリットには、単純に『お墓参りがラクになる』ということもあります。
1か所だけ行けばいいのですから、先ほど言ったような【費用の面】だけではなく、
- 体力的な面
- 時間的な面
でもラクができます。
何時間もかけて複数か所のお墓参りをするなんて疲れちゃいますよね?
それが両家墓なら1か所ですべての仏様を供養できるんですから、かなり体力的な負担を減らせると思いますよ。
それよりも大事なのは、時間の節約ができるということ。
時間はすべての人に平等に与えられています。だから、時間は有効に活用しなきゃダメです。
複数か所のお墓をお参りすることがダメだと言っているわけではありませんよ。
余計な時間を省略できれば、その方があなたの人生をより豊かにできますよ、と言いたいのです。
僕は、両家墓にした方が『あなたの人生にとってプラスになることが多い』と思っています。
両家墓を建てるデメリット
両家墓にはメリットだけではなく、デメリットもあります。
このデメリットの部分をちゃんと理解してから両家墓を建てないと、後になって面倒な事態を招きます。
ここからは、僕が今まで見てきた『両家墓のデメリット』を紹介します。
家紋の問題
日本の場合は、家ごとに『家紋』があります。
昔のお墓には、正面に家紋が彫られていることが多いんですね。
ところが、両家墓となると、あなたの家の家紋と奥様の実家の家紋のどちらを彫ればいいのかという問題が生じます。
両家ともに家紋を彫ればいいのでしょうか?
僕はまだ両家の家紋が彫られているお墓を見たことがありません。きっと、両家の家紋を彫る【スペースの問題】と【見た目の違和感】が原因なのでしょうね。
なので、両家墓を建てるなら家紋は彫らなくていいと思いますよ。
両家墓は家紋のような目立つ彫刻はあまりしない方が無難です。
あなたの親戚の中に両家墓に対して理解のない人が見たら、もしかしたらイヤミの1つくらい言われるかもしれません。それに、最近ではお墓に家紋を入れる人の方が珍しいです。
余計なトラブルも避けられますし、家紋を彫るのだってお金が必要ですから、両家墓に家紋は無しでいいんじゃないでしょうか?
俗名の彫刻に注意が必要
両家墓の場合は、戒名などを彫刻するときに少し注意が必要です。
墓石の左右の面には納骨されている人の『戒名』や『俗名(生前の名前)』が彫刻されます。
それで、問題は『俗名(生前の名前)』の彫り方です。
普通なら、俗名を彫刻するときは、苗字は彫らずに名前だけを彫ります。
なぜなら、苗字は墓石の正面に『◯◯家之墓』と彫ってあり、わざわざ側面にもう一度苗字を彫る必要がないからです。
しかし、両家墓となると話が変わります。
名前だけを彫ると、それがどちらの家の人なのか分からなくなります。
ということで、両家墓の場合は俗名をフルネームで彫刻する必要があるんですね。
これをちゃんと石材店に伝えておかないと、全員分の彫刻が名前だけになってしまい、後代の人たちが見たら『誰がどちらの家の人なのか分からない』という事態を招いてしまいます。
ちなみに、苗字も彫るということは、それだけ【字数】が増えますので、場合によっては彫刻の代金が少しだけ上がるかもしれません。
このように、俗名の彫刻にいちいち注意しなきゃいけないのは両家墓のデメリットです。
離婚をすると面倒
最後に両家墓の最大のデメリットを紹介します。
それは、『離婚』をすると面倒ということです。
特に、両家墓を建てた土地も墓石も完全に新規購入だった場合はモメます。
両家墓を建てた後に、事情があって離婚をした場合、まずは【離婚後は、建てた両家墓を夫側と妻側のどちらが使うのか】という問題が出ます。
離婚後はどちらか一方がお墓を出なくてはいけないですからね。
そして、出た側は新たにお墓の準備をしなくてはいけないので、それなりに大きな労力と金銭的な負担が発生します。そのため、どちらがお墓を出るのかを決めるときが一番モメるわけです。
そして、そのままお墓を使う側もやるべきことがあります。
まず、墓石に刻まれた文字は全面的に彫り直しますよね。正面の両家の名前だったり、左右の側面の各仏様の戒名や生前の名前とかです。
後は、納骨されているすべての遺骨を取り出して、両家で分けていかなくてはいけません。
お墓から遺骨を取り出すときの作業費用、墓石の彫刻のやり直しの作業費用、これらでも10万円は超えてしまうでしょう。
念のため、両家墓は離婚をしたら大変だということを覚えておきましょう。
まとめ:両家墓はおすすめです。
少子高齢化の進む日本。じわじわと進む仏教離れ。
そのような状況下では、お墓を継承者する人が減っていくのは当然のことです。
そうなると、自分の家のお墓に【妻の実家の仏様】を一緒に納骨するという、いわゆる『両家墓』を選択するケースが増えていきます。
僕は両家墓をおすすめしています。
お墓は、誰かがお参りをしてこそ存在意義があるので、継承者がおらず誰もお参りしないような【無縁墓】になってしまっては、その家の仏様に対して失礼です。
だったら、複数の家のお墓を1つにできるのであれば、その方が無縁墓になってしまうよりもずっとイイと思います。
ただし、両家墓にはメリットだけではなく、それなりにデメリットがあることも事実です。
お墓はずっと守っていくものですから、メリットとデメリットの部分もちゃんと理解した上で、みんなが納得してから両家墓を建ててくださいね。
※こちらの記事もご参考にどうぞ。