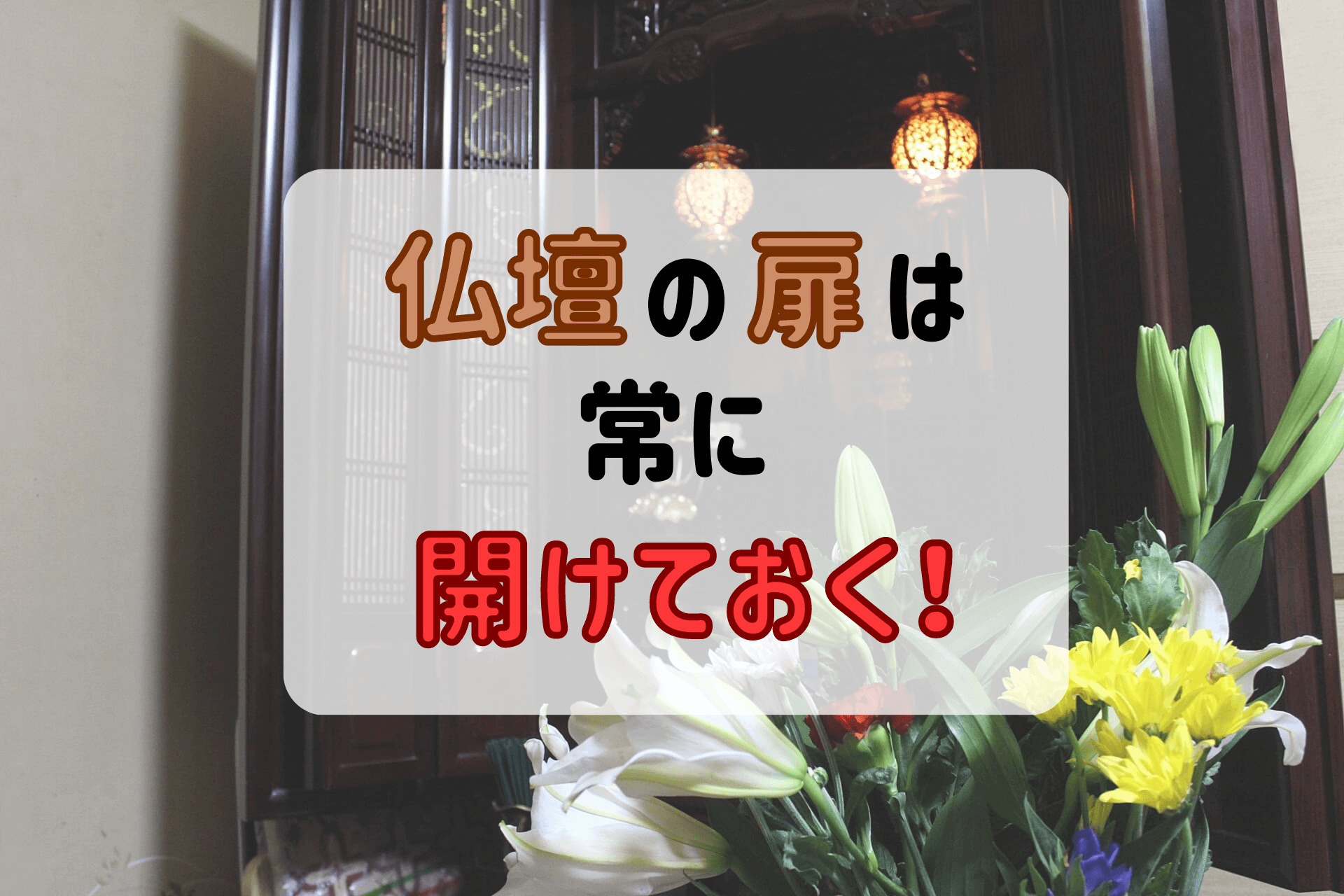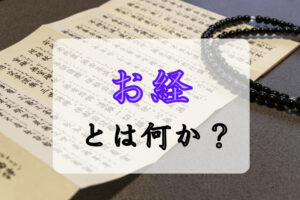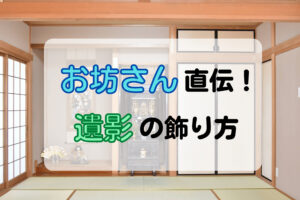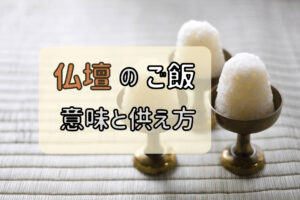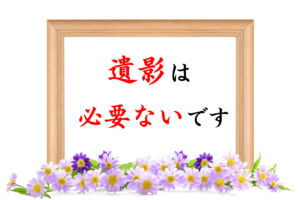- 仏壇の扉はずっと開けっ放しで大丈夫なのかな?
- 『家族に不幸があったときは仏壇の扉を閉めておく』と聞いたけど本当なの?
あなたは仏壇の扉を【ずっと開けておく】か、あるいは【夜は閉めておく】かで迷ったことはありませんか?
扉がある以上は、開閉をするということですから、そのタイミングを知りたいですよね。
結論から言いますと、仏壇の扉はずっと開けっ放しでかまいません。
仏壇の中の《ご本尊様》がいつでも家の中を見渡せるようにすることが大事なので、仏壇の扉はずっと開けっ放しにしておく方がいいのです。
この記事では、
- 仏壇の扉をずっと開けっ放しにしてよい理由
- どのような場合に仏壇の扉を閉めるのか
- 仏壇の扉が二重になっている理由
について詳しく解説しています。
もう『仏壇の扉の開閉』について悩まなくなりますので最後まで読んでみてください。
 未熟僧
未熟僧よくある質問なので参考になると思いますよ。
この記事を書いている僕『未熟僧(みじゅくそう)』は、お坊さん歴25年以上。仏事の疑問を解消するいろんな情報を発信しています。
仏壇の扉は開けておくの?それとも閉めるの?



仏壇の扉って、ずっと開けておいてもいいんですか?
これ、ホントによくある質問です。
この質問をする人は、きっといろんな人の意見を聞いてしまい、どうすればいいのか迷っている状態なのでしょう。
さらには、同じ宗派や地域でも住職の考え方によって意見が違うので、なおさら分かりづらいです。
仏壇の扉の開閉については、だいたい、
- 『ずっと開けておく』派
- 『夜間だけは閉めておく』派
の2つに分かれます。
じつは、仏壇の扉の開閉については『正解』がないので、どちらも間違いではないんですよね。
そして、僕は仏壇の扉はずっと【開けっ放し】でいいという考えです。
なぜなら、仏壇の扉を開けるのは『ご本尊様から家の中が見渡せるようにするため』だからです。
仏壇の中には必ず《ご本尊様》を安置します。ご存じでない方も多いのですが、ご本尊様がいないと『仏壇の役割』を果たしていません。



ご本尊様がいない場合は必ず購入をしてくださいね。
仏壇の中におられるご本尊様は、いつもあなたの家全体を見守ってくれています。
それなのに、扉を閉めたらご本尊様から何も見えなくなっちゃいますよね。だから仏壇の扉は開けっ放しでいいんです。
しかし、「夜は扉を閉めるべき」という人もいます。
「夜は扉を閉めるべき」という人の中には、『仏壇の扉の開閉』と『家の戸締り』を同じように考えている人もいます。
しかし、【家の扉】と【仏壇の扉】はまったくの別物として考えた方がいいと思います。
ご本尊様は昼夜を問わず見守ってくれているので、家族みんなが安心して眠れるように、夜も仏壇の扉を開けるべきです。
一方で家の扉は、家族みんなが安心して眠れるように、しっかりと戸締りと施錠をするべきです。



家の戸締りは必要、仏壇の戸締りは不要です。
また、「夜は仏壇の扉を閉めておかないと【飼い猫】が中に入ってしまうかもしれない。」と言う人もいます。
たしかに猫は狭い場所を好む生き物ですから、家族みんなが寝ている間に仏壇の中に入ってしまう可能性はあります。
あるいは、猫だけではなく【ネズミ】や【虫】なども入る可能性があります。
もしも、夜間に【飼い猫】【ネズミ】【虫】が仏壇の中に入ることがどうしても気になるのであれば、扉を閉めてもいいと思います。
仏壇の扉の開閉には『正解』がありませんから、心穏やかに過ごせる方を選択していいんです。
とはいえ、【飼い猫】は昼夜を問わず狭い場所に入りますし、それは【ネズミ】や【虫】だって同じなので、それならずっと開けっ放しでいいのではないでしょうか?
【関連記事】:仏壇の意味と役割とは?仏壇の準備からお参り方法まで丁寧に解説
仏壇の扉はなぜ二重なのか
あなたの家の仏壇は【扉が二重】になっていませんか?
二重の扉のうち、
- 外側の扉は『雨戸』
- 内側の扉は『障子』
といいます、私たちが住む家と同じ呼び方ですね。
それで、僕がずっと「仏壇の扉は開けておいてください」と言っているのは、この『雨戸』と『障子』の両方を開けてくださいという意味です。
でも、なぜ仏壇に扉が2つあるのか不思議ですよね?
仏壇に扉が2つある理由は、仏壇は『お寺の本堂』の代わりだからです。じつは、仏壇の中は『お寺の本堂の中』に似せて造られているんです。
お寺の本堂には雨戸と障子扉があって、昼間は信者さんたちが参拝に来ますから、両方の扉を開けたり、あるいは雨戸だけを開けていたりします。
そして、夜になると両方の扉を閉めて施錠をしています。



ちょっと待って!仏壇はお寺の本堂の代わりでしょ?
だったら、お寺の本堂と同じように、仏壇の扉も毎日ちゃんと開け閉めするべきなんじゃないの?



おっしゃることは分かりますが、それでも仏壇の扉は開けておいてください。
お寺としては夜間も本堂を解放しておきたいのですが、現実には盗難やイタズラがあります。
それで、本来であれば本堂は24時間365日解放されているべきですが、やむを得ず夜間だけは扉を閉めているわけです。
つまり、お寺の本堂の扉は【防犯上の理由】で閉めているだけなんです。
でも、仏壇は違います。
仏壇は家の外に出しているわけでもないし、扉を閉めて防犯対策を施す必要もないわけですから、扉は常に開けておいて大丈夫なのです。
扉の開閉についてよくある質問
仏壇の扉の開閉についての質問は、
- 家族に不幸があったとき
- お盆のとき
に受けることが多いです。
では、それぞれの場合で、扉を開けておくのか、それとも閉めるのか、順番に説明していきます。
家族に不幸があったときは仏壇の扉を閉めるの?
もしも家族に不幸があったときは、普段どおり仏壇の扉を開けておくようにしてください。
この前、信者さんとお葬式の打ち合わせをしているときに、



49日忌が来るまでは仏壇の扉を閉めておくんですよね?
と質問されました。
それを聞いて、僕は「えっ、誰がそんなことを言ったの?」って思いました。
仏壇を購入したばかりで【魂入れ】をしていないという場合は扉を閉じておいていいですが、すでに【魂入れ】が終わっている仏壇なら開けておくべきです。
「49日忌までは仏壇の扉を閉めるべき。」と言う人は、たぶん仏壇と神棚がごっちゃになっているのでしょう。
神道の場合は、家族に不幸があると、神様に故人の姿を見せないように神棚を白い紙で隠します。
これを『神棚封じ』といいます。
でも、仏壇は49日忌までの間もずっと扉を開けておくようにしてください。
じつは、故人はあの世に行くまでの間、少し『不安定な状態』で家にいらっしゃいます。
亡くなった人は【49日忌に『仏様の世界(あの世)』へ行くまでの間は霊魂としてこの世に残っている】と言われています。
つまり、故人の霊魂はまだ仏様の世界には行っておらず、でも故人の身体は火葬をしてもう無くなっている、という中途半端で不安定な状態なんですよね。



そんな不安定な状態の故人を守ってくださるのが仏壇のご本尊様です。
だから、ご本尊様から故人の霊魂が見えるように、仏壇の扉は閉めちゃダメ。
ということで、家族に不幸があったときこそ仏壇の扉は開けておくようにしてください。
お盆のときは仏壇の扉を閉めるべき?
お盆期間中に関しては、仏壇の扉は開けても閉めてもどちらでもいいですよ。
お盆になると、故人はあの世から家に帰って来ます。
お盆期間中は、位牌を仏壇から出して精霊棚(しょうりょうだな)という【ご先祖様や故人のために別に設けた席】に置きます。
お盆期間中は位牌を仏壇から出してあげないと、ご先祖様や故人が家にいてもゆっくりできない可哀想な状態になってしまうんですよね。
なので、お盆期間中だけは位牌を少しでも仏壇から切り離してあげるという意味で、扉を閉じるのはアリです。
一方で、やはり仏壇のご本尊様には家の中を見守ってもらいたいから扉は開ける、というのもアリなんですよね。
ですから、お盆期間中に関しては扉を開けても閉めてもどちらでもいいので、あなたの自由にして問題ありません。
※お盆期間中に位牌を仏壇から出す理由については『お盆の意味や由来。お盆の供養と風習についても詳しく解説』の記事を読んでみてください。
大掃除の時だけは閉める
じつは、僕が「仏壇の扉を閉めてくださいね。」とお願いしている唯一の場面があります。
それは、年末の大掃除のときです。
さすがにですね、大量のホコリが舞う部屋の中で「仏壇の扉は開けておいてください。」とは言えません。
年末の大掃除のときだけは扉を閉めて、大掃除が終わったら再び扉を開けて、ピカピカになった家をご本尊様に見せてあげてください。
また、大掃除のときに仏壇を動かすこともあるでしょう。
たまに「仏壇を動かす場合はお坊さんお経を読んでもらわなきゃいけないのですか?」と質問されますが、少し移動させる程度なら何もしなくてかまいません。
ただし、引越しなどで仏壇を【屋外へ出す】場合は供養をしてもらいましょう。
仏壇の移動や設置場所については別記事の『仏壇を移動するなら供養が必要?引越し等で仏壇を動かすときの注意点と置き場所』を参考にしてみてください。
まとめ:仏壇の扉はずっと開けておきましょう
仏壇の中には【ご本尊様】がおられて、あなたの家全体を見守ってくださっています。
だから、仏壇の扉はずっと【開けて】おいてください。
せっかくご本尊様が見守ってくれているので、それをわざわざ遮断する必要はありません。
家族に不幸があったときも、お盆のときも、仏壇の扉は開けっ放しでかまいません。
扉を閉じるのは、大掃除の時みたいに【部屋中がホコリだらけになる】ようなときくらいです。
もしかすると、知人や親戚からのいろんなご意見があるかもしれませんが、それらは無視してOKです。
とにかく常に【開けて】おいて大丈夫!
仏壇の扉は常に開けておき、いつもあなたの顔をご本尊様にお見せしてください。
※一通り仏具を揃えておきたい方はコチラの記事をご参考にどうぞ。