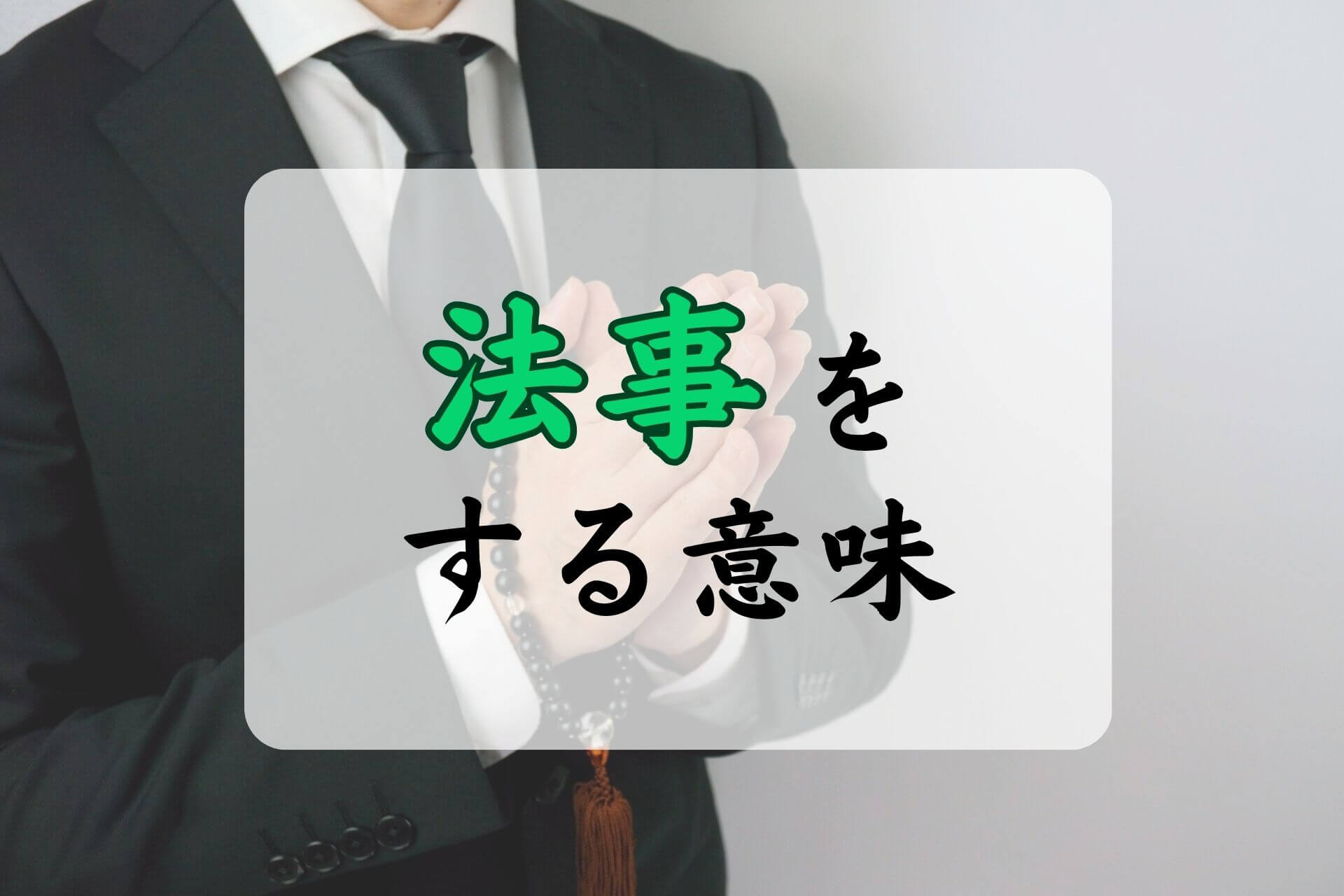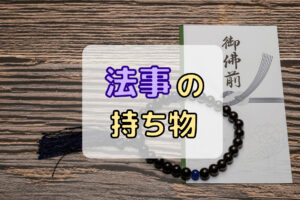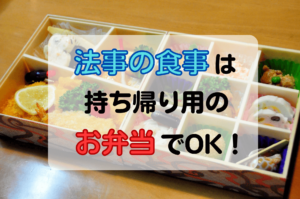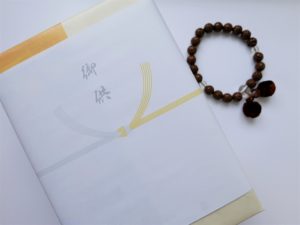- 法事はしなきゃいけないものなの?
- 法事にはどのような意味があるの?
- 法事の注意点を知りたい。
多くの人は『お葬式』と聞けば【亡くなった人を偲んでお別れをする儀式】とすぐに連想できます。
しかし、それが『法事』となればどうでしょうか?
お葬式とは違って、法事では何をしているのかがイマイチ分からないですよね。
そして、何をしてるのかが分からないので「別に法事なんてしなくてもいいんじゃないの?」という心理になります。
じつは、法事をすると、故人はもちろん、あなたにとってもメリットがあるんです。
この記事は、法事に関する根本的なところを解説していますので最後まで読んでみてください。
 未熟僧
未熟僧法事をしようか迷っている方は参考になりますよ。
この記事を書いている僕『未熟僧(みじゅくそう)』は、お坊さん歴25年以上。仏事の疑問を解消するいろんな情報を発信しています。
法事をする必要性と意味
本記事をお読みいただくにあたり、まずは【法要】と【法事】の違いについて簡単に説明します。
まず【法要】とは、故人の供養のためにお坊さんが読経や作法をして、参列者は手に数珠を持ってお焼香をするといった『儀式の部分』のことをいいます。
一方で【法事】とは、法要だけではなく、法要後の会食などを含めた『法要に関わる全体』のことをいいます。
この記事でも、法要と法事の2つの表現をしておりますので、それぞれの意味を踏まえた上でお読みください。
法事を執り行うのには2つの目的があります。
その2つの目的とは、
- あの世で修行中の故人に、感謝と応援のメッセージを伝えるため
- 私たちが仏様からの『チカラ』や『ご利益』をいただくため
です。
つまり、法事は故人はもちろん私たちのためにも執り行っているのです。
法事(回忌法要)と十三の仏様
法事の説明をするには、まずは仏教で重要視されている13の仏様について触れておかなければなりません。
日本では昔から『十三仏(じゅうさんぶつ)信仰』という、13の仏様に重きをおいた考え方があります。
これは、【亡くなった人は、初七日から33回忌まで13の仏様に守られて、たくさんのお導き(教え)を授かる】というものです。
そして、故人を守ってくださる仏様は年回忌ごとに決まった順で移り変わっていくといわれています。
13の仏様と年回忌の関係性は、以下のとおりです。
- 初七日⇒不動明王(ふどうみょうおう)
- 二七日⇒釈迦如来(しゃかにょらい)
- 三七日⇒文殊菩薩(もんじゅぼさつ)
- 四七日⇒普賢菩薩(ふげんぼさつ)
- 五七日⇒地蔵菩薩(じぞうぼさつ)
- 六七日⇒弥勒菩薩(みろくぼさつ)
- 七七日⇒薬師如来(やくしにょらい)
- 百か日⇒観音菩薩(かんのんぼさつ)
- 一周忌⇒勢至菩薩(せいしぼさつ)
- 三回忌⇒阿弥陀如来(あみだにょらい)
- 七回忌⇒阿閦如来(あしゅくにょらい)
- 十三・十七・二十三・二十七回忌⇒大日如来(だいにちにょらい)
- 三十三回忌⇒虚空蔵菩薩(こくうぞうぼさつ)
亡くなった人は、あの世(仏様の世界)に行かれてから仏様の弟子として修行を続けるそうです。
となると、修行をするときにいろいろと教えてくれる『先生』みたいな存在が必要で、それが13の仏様たちです。
そして、その13の仏様たちは、それぞれ持っておられるチカラやご利益が違います。要するに、13の仏様それぞれに《得意分野》があるんですよね。
亡くなった人は、それぞれの仏様に導かれ、たくさんのことを学びます。
修行中の故人に応援と感謝のメッセージを送るため
亡くなった人は、あの世でいろんな修行を続けておられます。
そして、一定期間の修行が終わる頃には、真の意味での『悟りを開く』ことができるそうです。
【修行】と聞くと、苦しいことに耐えながら一生懸命に努力を続けている姿、というのをイメージされるかと思います。しかし、それは【今私たちのいる世界】で修行をする場合です。
あの世での修行は、苦しみよりも【楽しみ】の方が断然多いらしいですよ。煩悩(ぼんのう)に染まった私たちには理解できないようなことも、あの世ではすぐに習得できてしまうのです。
そうすると、今まで想像すらできなかったような『宇宙全体の真理』が理解できるようになり、全てのことが新発見で新鮮に感じるので、修行がとても楽しくなります。
しかし、いくら楽しい修行とはいえ、疲れてしまって修行の意欲が落ちることもあるそうです。
そこで、定期的に法要を執り行って、「あの世の修行を頑張ってくださいね。私たちのことは心配しなくても大丈夫ですよ。いつも見守ってくれてありがとうございます。」と、修行中の故人に応援と感謝のメッセージをお伝えしているわけです。
故人は、法事を通じて、家族や親戚から応援と感謝のメッセージを受け取っています。きっと、それが故人にとっては【さらなる修行への励み】になるんですよね。
ですから、定期的に法要を行い、その度に心を込めてエールを送ってあげれば、故人はとても喜ぶと思いますよ。
私たちが仏様からチカラやご利益をいただくため
法事は故人のためだけに行うものではありません。
じつは、法事を行うことで私たちが仏様から『チカラ』や『ご利益』をいただく機会にもなっているんです。
法事を行うことは、仏教における《善行(ぜんぎょう)=良い行い》をすることになります。
私たちが善行(=法事などの供養)をすることによって、まずは故人に向けて仏様のチカラやご利益がたくさん注がれます。法事をした場合は、先ほどの十三仏の一覧のとおり、それぞれの年回忌の仏様から故人に向けて注がれるわけです。
このとき、故人は仏様のチカラやご利益のうち【7分の1】だけを受け取って、あとの【7分の6】は私たちの元へ返礼のように戻すのだそうです。
ちなみに、このことを『地蔵菩薩本願功徳経・第七章利益存亡品』というお経の中では【七分獲一(しちぶんぎゃくいつ)】という言葉で記されています。
また、仏様のチカラやご利益は善行(法事)をした私たちにも注がれるといわれています。
ですから、故人を偲んで供養するために法事を行なっているのですが、いつの間にか私たちの方がたくさん【いただきもの】をしているのですね。
せっかく【人】に生まれたのなら法事をしませんか?
仏教を広められたお釈迦(しゃか)様は、私たちが生死を繰り返している世界は『六道(ろくどう・りくどう)』と呼ばれる【六つの世界】で構成されているとおっしゃいました。
六つの世界とは、
- 【天】苦しみがとても少ない自由な世界
- 【人】いろんな苦しみや楽しみがある世界
- 【修羅】争いごとが絶えない世界
- 【畜生】本能のままに生きてしまう世界
- 【餓鬼】常に飢えや喉の渇きがある世界
- 【地獄】全ての苦しみを受け続ける世界
のことです。
地獄(じごく)、餓鬼(がき)、畜生(ちくしょう)、修羅(しゅら)の4つの世界は、苦しみや欲望に満ちあふれた世界とされています。
つまり、自分のことだけを考える、あるいは、自分のことだけで精一杯という世界です。そのため、これらの世界には【他者を思いやる気持ち】や【受けた恩に対する感謝の気持ち】というものがありません。
逆に、願うことが次々と叶い、ほとんど苦しみの無い【天(てん)】の世界ですが、ずっと欲望が満たされて苦しみがほとんど無い状況が続くと、それはそれで【思いやり】や【感謝】といった気持ちが少しずつ消えていってしまいます。
では、私たち人間が生きている【人(にん)】の世界はどうでしょうか。
私たちは、生きている中でさまざまな楽しみがありますが、一方でいろんな苦しみにも耐え抜いていかねばなりません。しかし、いろんな苦しみを経験するからこそ【他者を思いやる気持ち】や【受けた恩に対する感謝の気持ち】が芽生えるのだと思います。
そして、私たちの思いやりや感謝の気持ちというものは、生きている人だけではなく、既に亡くなった人にも向けられます。法事や先祖供養は、既に亡くなった人たちに対するそのような気持ちがあるからこそできるのです。
つまり、亡き人を供養するという行為は、私たち『人間』にしかできないですよね。
私たち人間にしかできないことなのであれば、それをするのが務めというか、それをしないと【もったいない】のではないかなと思いますよ。
縁があって【人】の世界に生を受けたのです、せっかくですから法事をしませんか?
【関連記事】:法事の当日までに施主が準備するべきことを詳しく紹介します。
法事が【三】と【七】を繰り返す理由
13仏のところでも紹介しましたように、法事は、一周忌の後、
三回忌、七回忌、十三回忌、十七回忌、二十三回忌、二十七回忌、三十三回忌・・・
と続いていきます。
あなたもお気付きかと思いますが、法事における年回忌の数は【三】と【七】を繰り返しています。
じつは、法事において【三】と【七】はとても重要な数なのです。
【三】のもつ意味
まず、【三】の説明をします。
私たち人間は、【富・貧】【強い・弱い】【勝つ・負ける】【美しい・醜い】【得をする・損をする】などのように、物事を『二極分化』して考えることがあります。
この二極分化、つまり【2つのどちらか】という考え方は、仏教において『極端に偏った物事のとらえ方』であり、悟りを妨げる考え方とされています。
お釈迦様は、
「2つのうちのどちらか一方ではなく、どちらでもない【真ん中】を見なさい。どちらにも偏らない3つ目の道(=真ん中)が悟りへの道なのだ。」
とおっしゃいました。
【三】のつく年回忌で法事を行うのは、【2つのうちのどれか】という考え方から、【真ん中を見る】という考え方が1つ加わった状態《2+1=3》になりますように、つまり、『故人が早く悟りを開きますように』という願いが込められているのです。
【三】にちなんだ年回忌で法事を行い故人の供養をすると、故人はさらに悟りへと近づいていく、ということなんですね。
【七】のもつ意味
続いて、【七】についての説明です。
先ほど、私たちが生死を繰り返している世界は【6つの世界(=六道)】で構成されている、ということを説明しました。
六道の世界とは【苦しみを味わう世界】であるともいえます。
仏教は『苦しみからの解放』を目指す教えですから、それはつまり、【六道の先にあるもう1つの世界】を目指す教えなのです。
そして、【六道の先のもう1つの世界】こそが、さまざまな仏様のおられる悟りの世界なのです。
ですから、【七】のつく年回忌で法事を行うことには、早く故人が【苦しみの世界(六道)】の先の【もう1つの世界(悟りの世界)】、つまり、《6+1=7つ目の世界》に到達しますように、との願いが込められているのです。
法事の注意点
法事をする上で多くの人が誤解をしていることがありますので、ここからは『法事の注意点』を紹介します。
法事は【親戚や知人が集まるためのもの】ではない
法事をする意味は何かという問いに対して、
「法事は故人のために行うものではありません。親戚や知人など【故人と縁のあった人】が集まり、そこでみんなが故人の話をすることによって、遺族の悲しみが少しずつ和らいでいく、これが法事をすることの意味です。」
というような意見があります。
本当にそうでしょうか?
それはつまり、一応は『故人の供養』と銘打ってはいるけれど、親戚や知人が集まることの方が重要で、それが法事なのだ、ということですよね。
それだと、もしも親戚や知人が誰も参列できないとしたら、法事をする意味はないということになります。
そもそも、故人を供養するために執り行っている【法要】そのものをする必要がなく、親戚や知人が集まれば、それで十分だという解釈ができます。
それって何だかオカシくないですか?
確かに、法要をしても『間違いなく故人を供養できた』という目に見える証拠はありません。
そのせいで、法要をすることに意味を感じず、今いる人たちの方に目を向けて法事の意味を考えているのでしょう。
そして、遺族の悲しみを少しずつ和らげることが、法事をする意味の1つになっているのも間違いありません。
それでも、法事は親戚や知人が集まることがメインではありません。
ちゃんと法要を行うことで『これで故人はあの世で仏様に守られて、充実した安らかな日々を過ごせるんだな』と安心できるからこそ、遺族の悲しみが少しずつ和らぐのです。
まずは法要をするという大前提(目的)があって、親戚や知人が集まることで法事をする目的がさらに追加される、という順番だと思います。
1人でも法事はできる
最近では法事の参列者数が減少傾向にあり、【家族のみ】で法事をするという家が増えています。
ですから、ときどき【参列者は施主1人だけ】で法事をすることもありますよ。
しかし、法事をする上で、参列者の【人数】が多くても少なくても、法要内ですることは全く同じです。そこに1人だけいても100人いても内容は全く変わりません。
ただ、参列者の人数が多いと、その分お焼香に時間がかかってしまいますから、法要全体の時間は長くなりますけどね。でも、違うのはそれだけです。
ですから、法事をする際に参列者が少なくても全く気にすることはありません。
逆を言えば、たとえ1人でも法事はできますので、もしもあなたが「人数が少ないから法事をしても意味ないよね。」と思っていても、それは法事をしない理由にはならないのでご注意ください。
ちなみに、法事に人数が関係ないということは、【お布施】の金額も変わらないので、その点も注意してくださいね。
【関連記事】:法事は身内だけでやりたい!親戚を呼ばないで法事をするときの注意点
法事はいつまで続けるの?
法事はいつまで続けるものなのか、というのは多くの人が疑問に思うところです。
お坊さんの立場としてお答えすると、『本来はずっと続けるものなので、いつまでという期限はありません。』となってしまいます。
でも、現実にはそんなの無理ですよね。わかってます、一応お伝えしておきたかっただけですから。
法事を続ける目安となるのは、33回忌(=亡くなった日から32年経過)までです。
一般的には、33回忌の法要をもって『弔い上げ(とむらいあげ)』といい、それ以降は法事をしなくても問題はないとされています。
誤解しないでくださいね、法事をしなくても問題はないだけであって、法事をストップさせるということではないですよ。
33回忌が最後の法事だという人がとても多いのですが、そうではありませんので注意してください。
33回忌を迎える頃には【あの世での故人の修行が一段落する】とされていますので、それまでのような【故人の修行を応援する目的】で行う法事は必要なくなる、ということです。
故人は、自分自身を向上させるための修行が一段落すると、次に私たちを守り導くことに専念されます。
したがって、33回忌以降の法事は【故人が私たちを守り導いてくれていることへの報恩感謝】という目的で行うので、先祖供養に近い意味合いとなってくるわけですね。
そのため、33回忌以降は法要の目的が変わるだけで、その後も37・43・47・50・100回忌と法事は続いていくのです。
私たちが今ここに存在できるのは、両親や両祖父母、そしてたくさんのご先祖様がいて、絶やすことなく生命を繋いでくれたからです。
ご先祖様達に直接会ってお礼は言えませんが、法事をすることで報恩感謝の気持ちを伝えることができます。その気持ちは伝え続けるべきなので、供養に期限というものはありません。
とはいえ、実際のところ、ほとんどの人は33回忌で打ち切りますし、そもそも33回忌まで続ける人が少なくなってきました。
法事をするには、いろんな準備をしなくちゃいけませんし、費用だってそれなりに必要なので大変ですよね。
できれば、頑張って33回忌まで法事をしてほしいのがお坊さんとしての僕の本音ですが、現実的に考えれば、無理のない範囲で供養を続けていただくのがいいかと思います。
法事を永く続けてくれる信者さんに対しては、お寺側だって感謝しているものです。
なので、もしもあなたが、【法事にかかる費用】のことで悩んでおられるのなら、お寺に相談をしてみてください。多くのお寺は、施主の事情を考えてそれなりに対応してくれるはずですから。
【関連記事】:法事の当日までに施主が準備するべきことを詳しく紹介します。
まとめ : 法事は大変ですが、できるだけ続けましょう
法事は、あの世で仏道修行に励んでおられる故人を応援するために行います。
そして、法事をすることにより、故人はもちろん私たちにも仏様のチカラやご利益が注がれます。
参列人数は少なくてもかまいませんので、節目となる【33回忌】まで法事を続けてみてください。
もちろん、「法事を絶対にやってください」とは言いません、大変なことだと知っていますから。
でも、法事をしなかったことを後々まで悔やむ人もいて、それがずっと心に引っかかっているようでした。
なので、もしも法事を行うかどうか【迷った】のなら、ちゃんと法事をした方が無難ですよ。
きっと故人も、法事をしてくれたあなたを見て感謝していると思いますよ。
※法事で施主をする人に読まれている記事はこちらです。