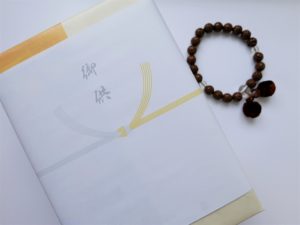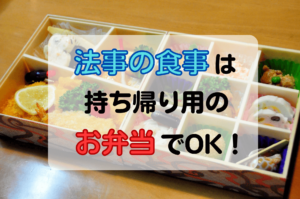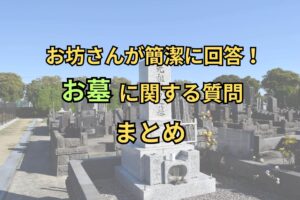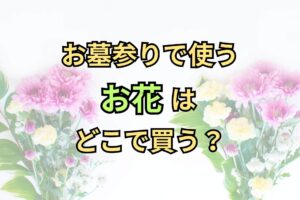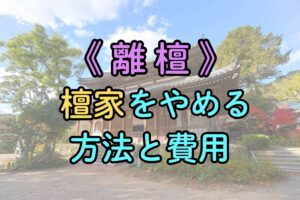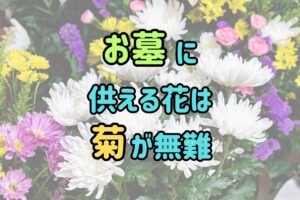- お墓参りって、いつ行くのがいいんだろう?
- お墓参りをする時間に決まりはあるのかな?
- お墓参りに行ってはいけない日はあるの?
仏事というのは《決まりごと》や《マナー》が多くて困りますよね。
そのせいか、お墓参りをする日や時間など『お墓参りにいつ行けばいいのか』を気にする人も多いです。
結論を言うと、お墓参りはいつ行ってもいいですよ。
お墓参りをする日や時間には決まりがないので、基本的には『あなたの気が向いたとき』でかまいません。
しかし、そうはいっても何らかの【基準】みたいなものが知りたいですよね?
この記事では、そんなあなたに向けて、
- お墓参りにはいつ行けばいいのか
- お墓参りをする時間
について解説しています。
お墓参りのタイミングに関する疑問が解消されますので最後まで読んでみてください。
この記事を書いている僕『未熟僧(みじゅくそう)』は、お坊さん歴25年以上。仏事の疑問を解消するいろんな情報を発信しています。
お墓参りにはいつ行くべき?
「お墓参りにはいつ行けばいいんだろう?」と疑問に思っている人は多いです。
ご先祖様や亡き家族のことを大切に思っている人ほど『お墓参り』のことで悩んでしまいます。
お墓参りのタイミングについては何の決まりもないので、お墓参りはいつ行ってもいいですよ。
お墓参りは仏教的な宗教行為です。しかし、その仏教では【お墓参りのタイミング】に関する決まりがありません。
だから、基本的には『あなたの気が向いたとき』にお墓参りをして大丈夫。
ただし、決まりではないですが、多くの人がお墓参りをする時期や時間というのがありますので、それらに従ってお墓参りに行くとよいでしょう。
お墓参りをする時期
お墓参りにはいつ行ってもかまいませんが、何らかの【基準】を知っておきたいですよね。
お墓参りをする時期というのは大体決まっており、多くの人は、
- 祥月命日
- 月命日
- お盆
- お彼岸
- 年末年始
- 家庭でのイベントがあったとき
にお墓参りをしています。
祥月命日
まずは、大事な家族の亡くなった日にはお墓参りをした方がいいと思います。
要するに、故人の『祥月命日(しょうつきめいにち)』のお墓参りです。祥月命日というのは、1年に1度の『△△月●●日』という故人の命日のことです。
祥月命日を迎えるたびに「あぁ、亡くなってから〇〇年経ったんだなぁ。」と振り返って、故人の冥福を祈って感謝をし、少しずつ故人の死を受け入れていきます。
ところで、あなたは家族の『誕生日祝い』をやっていますか?
多くの家庭では、1年に1度の誕生日を家族みんなでお祝いしますよね。
できれば【故人の祥月命日】も家族の誕生日と同じくらい大切に考えてあげてください。
誕生日というのは、
- 無事に1年を過ごせたことを喜ぶ
- 自分を育ててくれた親へ改めて感謝をする
という日です。
祥月命日は、
- 家族が無事に過ごしていることを報告する
- あの世からいつも見守ってくれていることに改めて感謝をする
という日です。
どちらも、『感謝をする日』という大事な共通点があります。
1年に1度の祥月命日は、改めて故人に感謝をする家族にとっても重要な日ですから、ぜひ家族みんなでお墓参りをしてもらいたいと思います。
月命日
1年に1度の命日のことを祥月命日といいますが、『●●日』というように【毎月ある命日】のことを『月命日(つきめいにち)』といいます。
ですから、月命日というのは【1年間で11回】あるわけですね。
月命日というのは、じつは祥月命日ほど重要ではありません、なにしろ毎月ありますので。
また誕生日の例を出しますけど、毎月誕生日のお祝いなんてしないじゃないですか、それと同じことです。
だから、「最近お墓参りに行ってないなぁ。」と思ったら、月命日にお墓参りをするといいでしょう。
お盆
1年に1度というのが祥月命日の他にもう1つあります。
それは、『お盆』です。
お盆の期間というのは一般的に、
- 【7月盆】:7月13日~7月16日
- 【8月盆】:8月13日~8月16日
のどちらかとなっています。
お盆になると《あの世にいるご先祖様や亡き家族がこの世に一時的に帰ってくる》と言われています。
ですから、あの世から帰って来るお盆期間の初日(13日)にお墓参りをして、お墓までご先祖様達や亡き家族をお迎えに行くわけです。
そして、自宅に帰ってこられた方々を供養してお盆期間を一緒に過ごします。
お盆期間の最終日(16日)になると、またお墓参りをして、今度はお墓でお見送りをします。
お盆については『【意外と知らない?】お盆の意味と過ごし方をお坊さんが詳しく解説』の記事で詳しく解説していますので読んでみてください。
お彼岸
お墓参りをするタイミングと聞いて、『お彼岸』を思い浮かべる人もいるでしょう。
お彼岸の期間というのは、『春分の日』と『秋分の日』を中日とする前後3日間を含めた合計1週間のことをいいます。
したがって、お彼岸の期間はだいたい、
- 【春彼岸】3月18日~3月24日(中日は21日)
- 【秋彼岸】9月20日~9月26日(中日は23日)
のどちらかとなっています。
お彼岸のお墓参りというのは、普段のお墓参りとは目的が違うんですよね。
命日やお盆にお墓参りをする主な目的は、簡単に言うと【亡くなった人達の供養(=故人を偲び感謝の気持ちを伝えること)】です。
一方で、お彼岸のお墓参りは【お墓参りをする人自身の修行】のためにしています。
本来、お墓参りの目的は【亡くなった人達の供養】と【自分の修行】という両面を兼ね備えており、お彼岸に関しては【自分の修行】の方が主になるんですよね。
お彼岸のことは、『彼岸にお墓参りをする理由。彼岸の意味と過ごし方をお坊さんが解説』の記事で詳しく解説していますので、よかったら読んでみてください。
ですから、お彼岸は【自分自身のためのお墓参り】なので、あなたのタイミングですればよく、誰にも強制されるものではありません。
年末年始
僕がいる寺では、1年の締めくくりとして年末にお墓参りをする人が多いです。
そして、そのような人はちゃんと年始にもお墓参りに来られますよ。
お墓参りを大事に考えており、なおかつ比較的お墓の近くに住んでいる場合は『年末年始』にお墓参りをするのもよいでしょう。
私たちはお世話になった人や親しい知人へ【お歳暮】を贈って歳末のご挨拶をしますよね。
それで、新年を迎えたら【年賀状】を送って年始の挨拶をします。
それと同じように、ご先祖様や亡き家族に対しても年末年始の挨拶をするのが礼儀ではないでしょうか?
家庭でのイベントがあったとき
お墓というのは『この世とあの世を結ぶもの』であり、私たちはご先祖様や亡き家族とお墓を介して通じ合うことができます。
お墓に関する詳細は、別記事の『お墓の意味や役割とは何?お墓参りでお墓はパワースポットに育つ?』を読んでみてください。
ですから、あなた自身のことや家族のことなど『家庭でのイベントがあったとき』にはお墓参りをするといいですよ。
ご先祖様や亡き家族だって、お墓参りであなたの家族のことを知らせてもらえると嬉しいのではないでしょうか?
ただ、あなたが「今のところ特に伝えるようなこともないな・・・。」と思っているのであれば無理にお墓参りをしなくてもいいですよ。
お墓参りに行ってはいけない日はある?
ここまで【お墓参りにいつ行けばいいのか】について解説してきました。
では、反対に【お墓参りに行ってはいけない日】というのはあるのでしょうか?
結論としては、お墓参りの日や時間には決まりがないので、そのため『お墓参りに行ってはいけない日』というのもありません。
ただし、『お墓参りに適さない日』はありますし、一部の地域では『お墓参りに行ってはいけない日』というのがあったりします。
雨が降っている日
お墓参りにはいつ行ってもかまいませんが、それはあくまで『天候の良いとき』の話です。
天候の良いときがあれば、当然ながら『天候の悪い日』もあります。
日本という国は、1年の約34%は『雨』だそうで、それはつまり3日に1度のペースで雨の日に当たるということです。
それくらい高確率で雨が降るなら、あなたがお墓参りをする予定の日に雨が降ることだって十分にあり得ます。
ほんの少しの雨ならお墓参りはできますが、僕は雨の日には無理をしてお墓参りに行かない方がよいと思いますよ。
理由は簡単で、危険が多いからです。
最近の墓石のほとんどは『御影石(みかげいし)』という硬い石が使われており、表面はピカピカに磨かれています。
そのせいで、墓石に水がついていると、まぁよく滑るんですよね。
うかつに墓石のどこかへ手をつくとズルッと滑って、下手をすれば体勢が崩れてケガをしてしまいます。
それに、雨のときは【傘】をさしたままでお墓参りすることになりますが、傘を片手に持っているとお墓参りがやりにくいんですよね。
お線香へ火をつけるときは両手を使いますから、さしている傘を【肩と首で挟んで】無理な体勢で火をつけます。そんなときに風が吹くと、傘がクルッと回ってしまい、結果的に雨に濡れてしまうんですよね。
ですから、雨の日というのは、あまりお墓参りには適していないんです。
とはいえ、べつに『雨が降っていたらお墓参りをしてはいけない』というわけじゃありません。
「雨が降ってるけど、それでもお墓参りに行きたい。」と思うなら、十分に気をつけてお参りをしてください。
一方で、もしも「今日は月命日なんだよな、どうしようかなぁ。」くらいの気持ちだったら、無理をしないで翌月にお参りすればいいと思いますよ。
【関連記事】:雨が降っていてもお墓参りをしていいの?雨の日のお墓参りの注意点。
猛暑日など気温の高い日
お墓の多くは屋外にあります。
すると、夏の猛暑日などは非常に気温が高い中でお墓参りをすることになります。
最近の夏の暑さは異常ですから、場合によっては体調を崩してしまうこともあるんですよね。
ですから、猛暑日(気温35℃以上)の日には無理をしてお墓参りに行く必要はありません。
急に体調が悪くなって倒れてしまうと大変ですし、しかも倒れるときに墓石に体を打ちつけると大ケガをします。
さらに、強烈な日差しを受けると墓石がメチャクチャ熱くなるんですよね。
熱くなった墓石へうかつに手をつくとヤケドをする可能性があります、実際に僕はヤケドをしました。
ですから、お盆や祥月命日など【重要度の高いお墓参り】なら考えなくてはいけませんが、そうでなければ気温の高い日には無理してお墓参りをしない方が無難です。
【関連記事】:夏のお墓参りの注意点。暑さ対策(水分補給や服装)が特に重要!
『友引』の日
お葬式をするときには【友引】の日を避けます。
これは、【友引】という字が『故人があの世まで友人を引きつれてしまう』と解釈できるため縁起が悪いとされているからです。
それで、「お墓参りも友引を避けた方がいいのでは?」と思う人が意外と多いんですよね。
しかし、お墓参りは【友引】の日に行っても問題ありません。
故人はすでに仏様の世界で安らかにお過ごしになっていますので、今さら誰も引きつれることはしません。
というか、そもそも『友人をあの世まで連れて行く』なんてことはないですよ。
ですから、友引でも赤口でも大安でも、そんなことはまったく気にせず【あなたのタイミング】でお墓参りをしてください。
『仏滅』の日
お墓参りをするにあたり、友引だけではなく【仏滅】を気にする人もいます。
【友引】や【仏滅】というのは、中国発祥の考え方である『六曜』の1つです。
六曜とは、ものすごく簡単に言えば『その日の吉凶を占うもの』です。
そして、ここが大事なのですが、六曜と仏教は何の関係もないんですよね。
本来であれば、友引にお葬式をしてもいいですし、もちろんお墓参りについても何も気にすることはありません。
お墓参りをしたい日が友引でも仏滅でも、そんなことは一切無視して【あなたのタイミング】でお墓参りをしてください。
毎月『29日』
一部の地域では『毎月【29日】はお墓参りに行ってはいけない』と言われています。
これは『29』という数が『二重に苦がある』という語呂合わせができてしまうからです。
特に《12月29日》は1年を締めくくる最後の29日なので、この日のお墓参りは厳禁とされています。
しかし、29日がダメだという仏教的な根拠が一切ないので、これは完全な【デマ】ということで無視をしてかまいません。
もちろん、ご先祖様や亡き家族そしてあなたにも『二重の苦』どころか『1ミリの苦』もありませんので安心してください。
逆に、29日にお墓参りをすれば『29(フク)=福』が舞い込んで来るんじゃないですか?
お墓参りをする時間は16時までが目安
冒頭でも言いましたように、お墓参りは基本的に『あなたの気が向いたとき』に行ってかまいません。
しかし、お墓参りをする【時間】には少し注意をしてください。
お墓参りは、可能であれば午前中に行く
僕が信者さんからたまに質問されるのが、「お墓参りに適した時間はありますか?」というものです。
お墓参りは、可能であれば午前中に行くといいですよ。
これは『午後に行ってはダメ』ということではなく、あくまで午前中が望ましいというだけの話です。
というのも、あの世では『午前中に食事をする』という決まりがあるそうなので、お供えをするのは午前中の方がいいとされています。
あなたは、お墓参りのときに『お線香』を供えますよね?
じつは、お香を燃やしたときに出る【香り】というのは、あの世での『食べ物』になります。
つまり、お墓参りなどでお線香を供えることは、ご先祖様や亡き家族に【食事をしてもらうこと】なんです。
だから、あの世の食事に間に合うよう、午前中にお墓参りをしてお線香を供えるのが理想的なんですよね。
【関連記事】:お線香のあげ方やマナーを場面別に詳しく紹介。お焼香の作法も合わせて紹介
お墓参りは16時までに!夜に行くのはヤメておきましょう
午前中にお墓参りができればいいですが、それができない場合だってありますよね。
午前中はいろいろと忙しいですから、午後にお墓参りに行くという人の方が多いかもしれませんね。
しかし、午後とはいっても、お墓参りは16時までにすませるようにしてください。
理由は、
- 季節によっては、16時以降は暗くて周囲がよく見えないから
- 寺院や霊園の多くは17時に閉まるため、慌ただしくなるから
です。
墓地というのは、意外と狭いですし、当然ながら周りは硬い石だらけです。
そこへさらに【暗さ】が加わると、控えめに言ってとても危険です。高確率で何かにつまずいて、暗いのでうまく手をつくこともできず大きなケガをしますよ。
それに、周囲が暗い中で他の誰かがあなたの姿を見たらビックリするでしょう。夜の墓地にうっすらと人影が見えるんですよ、それって結構怖くないですか?
お墓参りというのは「お墓参りをしよう」という気持ちが重要であって、仏教的な決まりごともありませんから、基本的にいつ行ってもかまいません。
しかし、夜に行くのはデメリットしかありませんから、よほどの理由がない限りヤメておきましょう。
ついで参りは良くない?
お墓参りに行くときは、
- お墓参りだけをしに行く
- 他の用事のついでにお墓参りをしに行く
という2パターンがあります。
一般的に、他の用事のついでにお墓参りすることを『ついで参り』といい、好ましくないこととされています。
これは、『大事なお墓参りを何かの【ついで】にすることは、ご先祖様や亡き家族に失礼である』という理由ですね。
つまり、『お墓参りは他の用事よりも優先させるべきこと』ということです。
でも、僕はこの【ついで参りは良くない】という考え方に疑問を感じます。
たしかに、お墓参りはご先祖様や亡き家族へのご挨拶なので、とても重要な意味を持っています。
しかし、大事なのは、ちゃんと《お墓参りをしに行くこと》であり、その優先順位ではありません。
ですから、僕はべつにお墓参りを最優先にしなくてもよいと思っています。
しかも、お墓参りをする予定はなかったけど、近くを通った【ついで】にお墓参りをした、というケースもあります。
この場合、本来はする予定ではなかったお墓参りをしに行ったわけですから、むしろ良いことです。
お墓参りは、【予定したお墓参り】でも【ついで参り】でも、どちらでもいいので行けるときに行きましょう。
【関連記事】:ついで参りの何がダメなの?他の用事と一緒にお墓参りをしてもOK。
お墓参りは1人で行ってはいけないの?
お墓参りは、家族などの複数人で行く場合もあれば、1人だけで行く場合もあります。
じつは、昔から『お墓参りには1人で行ってはいけない』と言われています。
これには【単なる迷信】の部分と【安全上の理由】の部分があります。
1人でお墓参りに行くと【悪い霊に取り憑かれる】とか【何らかの霊を連れてきてしまう】と言われているんですが、これらは完全な『迷信』なのでご安心を。
一方で、1人で行くと、もしも何らかの事故や事件があったときに対処できないという可能性があります。
特に、女性が1人で行く場合は、安全上のリスクが少しだけ高くなってしまいます。
そのため、安全上の理由により1人で行ってはいけないというのは理屈が通っています。
とはいえ、先ほども言いましたように、雨の日を避けたり、16時までにお墓参りを終わらせておけばそのリスクは大幅に減らせます。
ですから、『雨が降らない日の16時まで』ということに気をつけていれば、1人でもお墓参りをして大丈夫です。
【関連記事】:お墓参りに1人で行くのは良くない?その理由と真実をお坊さんが解説
まとめ:お墓参りにはいつ行ってもいい。
多くの人がお墓参りをしているタイミングとしては、
- 祥月命日
- 月命日
- お盆
- お彼岸
- 年末年始
- 家庭でのイベントがあったとき
です。
しかし、お墓参りには【いつ行かなきゃダメ】というような決まりはありません。
ですから、基本的には『あなたの気が向いたとき』に、つまりお墓参りにはいつ行ってもいいんです。
ただ、あまり遅い時間になると、いくつかの問題や危険があるので、できれば16時までに行くように心がけてください。
お墓参りは、「お墓参りをしよう。」という気持ちが何よりも大事です。
お墓参りに行こうと思ったら、そのときが【お墓参りのベストタイミング】です。
ついで参りでもかまいませんし、1人で行ってもかまいませんので、ぜひご先祖様や亡き家族に挨拶をしてあげてください。
※お墓参りへ行く前にコチラの記事もぜひご覧ください。