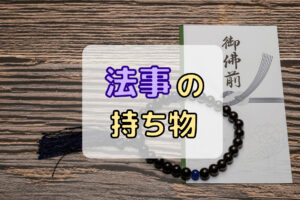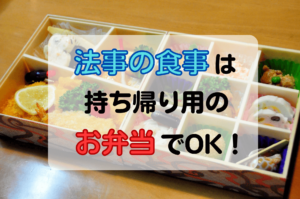- 法事に持って行く『お供物』にはどんなものを選べばいいのかな?
- 物ではなく現金(=【御供物料】)じゃダメ?
- 持って行った『お供物』をいつ渡せばいいんだろう?
あなたは、【法事に持って行くもの】と聞いてどんなものを思い浮かべますか?
まず、『御仏前』ですよね、あとは『数珠』も必要です。他にも持って行くものがありますよね?
そう、『お供物』です。
でも、『お供物』として何を持って行けばいいのか分かりませんよね?
決まり事の多い仏事ですから、きっと何か【マナー】みたいなものがありそうですもんね。
結論を言うと、法事に持って行く『お供物』で迷ったら、【菓子折り】にしておけば無難ですよ。
『菓子折り』は、施主と参列者ともに扱いやすいお供物なので1番いいです。
今後はもう【法事の『お供物』選び】で悩まなくてすみますので最後まで読んでみてください。
この記事を書いている僕『未熟僧(みじゅくそう)』は、お坊さん歴25年以上。仏事の疑問を解消するいろんな情報を発信しています。
法事に持って行く『お供物』はどんなものを選べばいいの?
法事に持って行く『お供物』にどんなものを選べばいいのか分からないですよね。
故人が好きだったモノを供えればいいのか、それともあくまで仏事のマナーに沿ったモノだけを供えるべきなのか、考えれば考えるほど迷ってしまうことでしょう。
まずは、持って行く『お供物』を選ぶときの考え方について説明します。
故人が好きだったもの
あなたは誰のために『お供物』を供えるのですか?きっと【故人】のためですよね?
ならば、『お供物』には【故人が好きだったもの】を選んであげてください。
和菓子が好きだったなら和菓子を、洋菓子が好きだったなら洋菓子を供えてあげましょう。もしも具体的な商品名が分かっているのなら、それを供えてあげるのがベスト。
でも【故人の好きだったもの】が分からない場合もありますよね。
まさか、故人の家族に「故人は何が好きでしたか?」なんて今さら聞けないですよね。しかも、いかにも【故人の好きな供物を持って行きまっせ〜!】っていう雰囲気がして何だかイヤラシイ。
なので、故人の好きなものが分からない場合は、あなたが『故人のために供えてあげたいと思うもの』をお供えしてあげてください。
もしかすると、それが大ハズレかもしれません、最悪の場合【故人が嫌いだったもの】の可能性もあります。
しかし、例えそうであっても、故人の方は笑って「ありがとうね。」と言ってくれますから安心してください。
なんだかんだ言って、結局は『供える人の気持ちが大事』ってことですね。
生もの・肉魚類はダメ
あなたは、
- 焼肉
- 刺身
- 焼き鳥
- 豚肉の生姜焼き
はお好きですか?
えっ、大好きですか?僕もです♪
もしかすると、それは故人も大好きだったんじゃないですか?
先ほども言いましたが、お供物には『故人が好きだったもの』を供えてよいのですが、生もの、肉魚類はダメなので注意してくださいね。
理由は簡単で、仏教では動物を殺すことを認めないからです。
焼き肉、刺身、焼き鳥、豚肉の生姜焼き、どれも間違いなく動物を殺してます。
これは仏教の立場からすれば、「自分の命を保つために、生きてる動物を殺して食べるなんて言語道断だ!」ってことなんですよ。
そんな《タブー》ともいえる【生もの・肉魚類】を、仏様のもとにいらっしゃる故人に供えてはダメなんです。
『お供物』として供えるもの5選
どこからか「いろいろと考えて選ぶのも大変だし、何か【おすすめの供物】みたいものはないの?」っていう声が聞こえました。
そうですよね、『お供物』の選び方を知っていても「本当にこれで大丈夫かな?」と心配になりますよね。
ということで、『お供物』として供えられている代表的なものを5つ紹介しますので参考にしてください。
【菓子折り】が無難。※これが一番ラク♪
法事に持って行く『お供物』で僕が1番おすすめしているものがあります。
それは『菓子折り』です。
菓子折りであれば、まぁ間違いはないでしょう。
まず、『お供物』を持って行く側にとって、菓子折りは【持ち運びがしやすい】というのがいいです。
菓子折りなら、重さは大したことないし、紙袋に入っていれば手で持ちやすいんですよね。
それに、和菓子と洋菓子のどちらでもよくて、とにかく商品の種類が豊富ですから他の人とカブりません。
菓子折りを買うときには、なるべく【賞味期限の長いもの】を選んでください。
法事が終わった後に、施主は供えられた『お供物』を食べなくてはいけません。だって、せっかく参列者が供えてくれた『お供物』をそのまま捨てるわけにもいきませんからね。
たくさんの『お供物』を食べることになるので、賞味期限の長い方が喜ばれます。
あと、これは非常に地味なことなんですけど、菓子折りの中身が1つ1つ小分けになっているものの方がいいと思いますよ。
その方が少しずつ食べられるので、施主側としても取り扱いがラクなんですよね。
さらに、菓子折りであれば、賞味期限を確認した後に箱を重ねておけるので、さほど場所を取られずにすみ、食べ終わった後も、箱は簡単に潰して処分できますよね。
菓子折りは、参列者にとっても施主にとっても【ラクで良い】のです。
ですから、法事に持って行く『お供物』で悩んだら、菓子折りにするのがおすすめですよ。
昔ながらの定番【果物】
僕は『お供物』には【菓子折り】をおすすめします。
でも、『お供物』といえば【果物の盛合わせ】が昔からの定番なんですよね。
果物を供える理由は、季節ごとに獲れる旬な果物が【うまい】からです。
【うまい】の語源となった言葉は『甘い』なのですが、昔は、果物が熟してとても甘くなることを『うまい』と言っていました。
私たち人間は【甘いもの】を食べると、気持ちが満たされて心地よくなります。この【気持ちが満たされて心地よくなる】というのは『心が安らかな状態』です。
そして、『心が安らかな状態』の究極が《悟りを開いた状態》なんですよね。
ですから、故人に甘い果物をお供えして、より『心安らかな状態』になってもらい、悟りに近づいてもらうのです。
要するに、果物を供えるのは故人に早く悟りを開いてもらうためなんですよね。
ただ、果物というのは早く食べないと腐ってしまいます。しかも【盛合わせ】なので数が多くて、腐る前に食べきることは意外と大変です。
だから僕はあまり『果物の盛合わせ』をおすすめしていません。
お線香
法事の『お供物』と聞いて、「あぁ、お線香を持って行くんでしょ?」と思ったあなたは『仏事の通』でいらっしゃいますね。
なぜなら、仏様への『お供物』として本来供えるものは【お香】だからです。
仏教では、お香から出る【香り】は『仏様の食べ物』だと考えています。
だから、お葬式や法事のときには必ず『お焼香』をするんですよね。
ただし、お線香にはいろんな匂いがあるのですが、人によってお線香の匂いに好き嫌いがあります。
なので、施主にとって【嫌いなニオイ】のお線香を持って行ってしまうリスクがあるんですよね。
仮に施主の嫌いなニオイだったとしても、施主はおそらく「せっかく供えてもらったんだから。」ということで一度くらいはその線香に火をつけることでしょう。
でも、やっぱり嫌いなニオイなんですよね。嫌いなニオイの中にずっといるのは、まぁまぁのダメージを負います。
お線香は匂いがしばらく残るので、それが嫌いなニオイだった場合、いくら仏様へのお供えだとしてもけっこうな苦痛なんです。
となると、きっとあなたの知らない所で、施主は「あぁ◯◯さん、ごめんな。これは使えないよ。」と申し訳なく思いながらそのお線香を捨てることでしょう。
本来の意味からすれば【お線香】はベストですけど、実際のところを考えると、さほどおすすめできるものではありません。
【関連記事】:お香(こう)を供える意味とは?焼香の作法や線香の供え方も紹介します
人によっては【生花】が好まれる
仏様への『お供物』としてもう1つ代表的なものが【生花】です。
生花を供えて、故人を供養する場所を色鮮やかな花々で飾りつけてあげるのです。
その他にも、生花を供える私たちの「目標を達成するためにツラい事にも耐え忍びます!」という決意を象徴します。
参列者が生花を持ち寄り、さまざまな生花が祭壇を彩ります。
でも、僕が個人的に1番おすすめできない『お供物』が、この【生花】なんですよね。
なぜなら、供えるときには場所をとるし、後の処理も面倒なので、ヘタをすると《迷惑なお供物》になってしまうからです。
お供物に生花を持って行くなら、
- 故人はお花が好きだった
- 施主もお花が好きである
この2つが絶対条件だと思います。
ということで、『お供物』として持って行くもので、人によっては【生花】もアリです。
施主も参列者も、本音は【現金=『御供物料』】が1番ありがたい
最後は、より実用的なものを紹介します。
僕だったら『お供物』として1番嬉しいものはダントツで【現金=御供物料】ですね。
なんだかんだ言って、1番嬉しいのはコレだと思うんですけど、あなたは違いますか?
だって、現金の方が圧倒的に使い勝手がいいし、ジャマにもならないし、腐ることもないんですよ?
みんな口に出しては言わないだけで、本音は「現金だとありがたい」と思っていることでしょう。
日本人は『お金』に対してネガティブなイメージが強すぎるんですよね。
お金の話をすることを嫌がりますし、物を贈るときにもお金だと【手抜きをしている】みたいな印象を抱く人もいます。
中には、まるでお金のことを【悪いもの】みたいな言い方をする人だっている。
でも、僕は『お供物』として現金を持って行くのは、施主のことをよく考えた【気遣い】だと思いますけどね。
法事の『お供物』というのは、故人のことを考えるのはもちろんですが、それを受け取る施主のことも考えなきゃいけません。
というか、『お供物』に関しては《7:3》で施主のことを優先に考えてあげてください。
施主のことを考えたら、『お供物』には現金が1番なんです。
でも、現金を否定する人も多いので、今のところはまだ【おすすめ】とは言えないのです。
まぁ、近いうちに『お供物』として【御供物料】を包むのが主流になると確信はしていますけどね。
お供物の値段の相場はいくら?
『お供物』として用意するものが決まったら、それを購入しなくてはいけません。
とはいえ、その『お供物』はどのくらいの価格のものを購入すればいいのか迷うことでしょう。
『お供物』だけに限らず、何かを購入するときには必ず【相場】を確認しましょう。
僕が20年以上見てきたかぎり、『お供物』の相場は【3千円~7千円】程度です。
先ほど紹介した、菓子折り、果物盛合せ、お線香、生花においてこの金額が該当します。
これ以下だと【少ない感】がありますし、これ以上だと逆に【多すぎる感】があるんですよね。
ですから、この《3千円~7千円》くらいのところが【ちょうどイイ価格帯】です。
ただ、もしも【御供物料】を包む場合は、5千円、もしくは1万円のどちらかがいいですよ。
本来であれば、『お供物』は事前に用意して持って行くものであり、そこを省略しているわけですから、ちょっと多めに包むのがマナーでしょう。
だから、最低でも5千円、できれば1万円。
そして、使う紙幣もなるべくなら【新札の5千円札】あるいは【新札の1万円札】に越したことはありません。
お供物はどのタイミングで渡すの?
持って行った『お供物』は、どのタイミングで渡せばいいのでしょう?
法事のときは、施主が先に現地にいるはずです。
ですから、あなたが到着したら施主が出迎えてくれるでしょう。
『お供物』は、施主に会って挨拶をするときに渡すようにしてください。
「この度はお招きを頂き、ありがとうございます。」と施主に挨拶をして、そのときに『お供物』を渡すのです。
もしも紙袋などに入っていたら、そこから中身をちゃんと出して渡してください。
でも、もしかすると、あなたが現地に到着したときに、たまたま施主がいないかもしれません。
そんなときは、仕方ありませんから、あなたが自分で『お供物』を祭壇に置いてしまって・・・はダメですよ。
勝手に置いちゃいけませんし、他の親族に渡すのも微妙ですから、ちゃんと施主に直接渡すようにしてください。
また、『お供物』を渡すときには【御仏前】も一緒に渡しましょう。
ちなみに、【御仏前】にもいろいろマナーがありますので注意してくださいね。
【関連記事】:不祝儀袋【御香典(御香奠)・御霊前・御仏前】の意味、書き方、お札の入れ方を詳しく解説。
最近では『お供物』を持って行かないケースも多い
最後に、この記事をひっくり返すような内容についても触れておきます。
じつは、最近では法事に『お供物』を持って行かないというケースが増えています。
これも時代の流れでしょうか、最近では施主と参列者の間で、「お互いにとって大変だから、もう『お供物』を持ち寄るのはヤメておきましょう。」という暗黙のルールができているんです。
僕がいる寺で法事をする方々も『お供物』を持って来るのは施主だけですよ。
今でも『お供物』を持ち寄っているのは【自宅での法事】のときだけですね。
それ以外の場所だと、昔よく見た【お供物の山】を見かけなくなりました。
仏事はどんどん『簡略化』の一途をたどっていますが、『お供物』に関しても簡略化されています。
僕は、べつに簡略化がダメだとは思いませんし、それが【時代の変化】だと受け入れています。
でも、昔ながらの慣習を守っている人もたくさんいるんですよね。
あなたが参列する予定の法事が、もしも『お供物』を持ち寄るケースなら、ぜひこの記事を参考にしてみてください。
まとめ:法事で供える『お供物』には【菓子折り】が無難です
法事のときには『お供物』を持って行くこともあります。
法事ではいろんなものをお供えしていいと思いますが、持って行く『お供物』としては、【菓子折り】が無難です。
菓子折りなら、持って行く側は持ち運びがラクですし、受け取る側の施主としても後の取り扱いがラクなんです。
ですから、お供物選びで迷ったときには【菓子折り】です。
持って行った『お供物』を渡すタイミングについては、最初に施主へ挨拶をするときに渡すとよいでしょう。
ただ、最近では「お互いに気を使って大変だからヤメましょう。」ということで、参列者が『お供物』を持って行かないというケースも増えています。
しかし、これは地域の慣習によって違うため、地域ごとのやり方に沿ってください。
いずれにしても、故人の供養のために心を込めてお供えをするようにしてくださいね。
※法事に参列する前に読んでみてください。