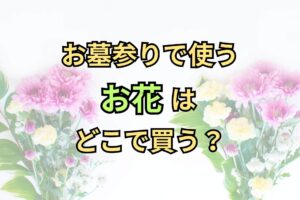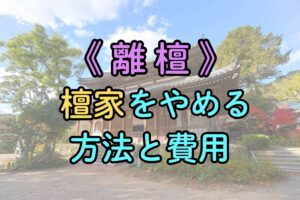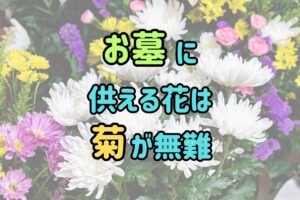- 彼岸の意味
- 彼岸にお墓参りをする理由
- 彼岸の過ごし方
『彼岸』は春と秋の年2回あり、この期間には多くの人がお墓参りをします。
でも、彼岸にお墓参りをする意味を知っている人は少ないです。
じつは、彼岸のお墓参りには、命日やお盆のお墓参りとは違う意味があります。
この記事では、『彼岸にお墓参りをする理由』について詳しく解説しています。
彼岸のお墓参りに対する向き合い方が変わりますので最後まで読んでみてください。
この記事を書いている僕『未熟僧(みじゅくそう)』は、お坊さん歴25年以上。仏事の疑問を解消するいろんな情報を発信しています。
彼岸の意味
多くの人は『彼岸』と聞くと【お墓参りをしに行く期間】という認識です。
もちろんそれは間違いではありませんが、せっかくなので、もう少し深く『彼岸の意味』を知ってほしいなと思います。
まずは、『彼岸』の基本的なところから説明します。
彼岸とは何?
仏事では当然のように使っている【彼岸】という言葉ですが、それにはどんな意味があるのでしょう?
【彼岸】という言葉は、仏教の『到彼岸』という言葉が由来となっており、これは《悟りの世界に到達すること》を意味するものです。
仏教では、あらゆる苦しみから解放され、絶対的な安らぎを得ること、要するに『悟りの境地に到ること』を目指しています。
しかし、現実の私たちは、いつも何らかの苦しみにさらされ、それに耐え続ける日々。
そのような私たちがいる《苦しみや迷いに満ちた世界》のことを【此岸(しがん)】といいます。
反対に、あらゆる苦しみから解放され絶対的な安らぎのある世界、つまり仏様たちがいる世界のことを【彼岸(ひがん)】といいます。
もう少し詳しく説明すると、《悟りの世界》の前に流れている大きな川をはさんで、まだ悟りを得られていない私たちがいるのは、此方(こちら)側の岸なので【此岸】です。
一方で、悟りをひらいた仏様たちがいるのは大きな川をはさんだ向こう側、つまり彼方(あちら)側の岸なので【彼岸】ということです。
彼岸へ渡るには、お釈迦様のように悟りをひらく必要があり、そのためにはいろいろな仏道修行を続けていかなければなりません。
ですから、春と秋の彼岸は『到彼岸』を目指して努力(=修行)をする期間なんですよね。
【暑さ寒さも彼岸まで】の意味
『暑さ寒さも彼岸まで』という言葉があります。
この言葉は一般的に『夏の暑さ、冬の寒さは、お彼岸の時期を過ぎれば緩和される』という意味で使われます。つまり、《気候の移り変わり》のことを指しています。
でも、これを仏教的に解釈すると少し意味が違うんです。
【暑い】とか【寒い】という感覚は、私たちが肌で感じる『苦しみ』の1つです。
肌で感じる苦しみも含めた『あらゆる苦しみ』は彼岸に渡る前までのものであり、修行をして彼岸に渡れば無くなります。
つまり、仏教的な解釈での『暑さ寒さも彼岸まで』というのは【悟りへの道すじ】を意味する言葉なんです。
なので、私たちが彼岸にしているお墓参りは《私たち自身が悟りを得るための修行》なんですよね。
彼岸の期間はいつからいつまで?
彼岸は1年に2回、春と秋に1週間ずつあります。
では、それぞれの彼岸の期間はいつからいつまでなのでしょう?
彼岸の期間は、
- 【春彼岸】:春分の日と、その前後3日間を合わせた計7日間
- 【秋彼岸】:秋分の日と、その前後3日間を合わせた計7日間
です。
彼岸の期間というのは、【〇月〇〇日~〇月▲▲日】みたいに決まった日にちで固定されているのではなく、あくまで『春分の日』と『秋分の日』を基準にして決めています。
そのため、その年によっては『春分の日』と『秋分の日』の日にちが変わってしまうことがあるのです。
彼岸の日にちは、その都度インターネットなどでちゃんと確認をしておくといいですよ。
なぜお彼岸にお墓参りをするのか
あなたは、3月の『春分の日』と9月の『秋分の日』をご存知ですよね?
どちらも休日ですし、しかも気候が良い時期なので、どこかへ出かけたくなりますよね。
でも、『春分の日』と『秋分の日』には、ぜひとも【お墓参り】をしてほしいと思います。
なぜなら、『春分の日』と『秋分の日』というのは【彼岸の中日】であり、最もお墓参りに適した日だからです。
彼岸の時期は『昼と夜の時間がほぼ半分』になるのですが、【彼岸の中日】はさらにその真ん中なので、昼と夜の時間が『ちょうど半分』になります。
じつは、この『ちょうど半分』というのが重要であり、彼岸にお墓参りをする理由にもなっているんです。
【中道】という教えに即した時期だから
仏教を世に広めたお釈迦様は『中道(ちゅうどう)』という教えを説かれました。
中道というのは、【両極端にかたよらない】考え方や判断をすることが大切である、という教えです。
【両極端にかたよる】というのは、欲望のままに日々を過ごしたり、逆に、禁欲によって自分を押さえ込み過ぎる、ということです。
あとは、「これしかないのだ!」と、自分にとっての正解をひたすら探し続けて、他の大事なものに目を向けられないことも極端にかたよった状態になります。
そんな《自分で自分を苦しめている人たち》に対して、お釈迦様は、
どちらか一方へ極端にかたよるのではなく、ちょうど良いバランスになるような『真ん中の道』を進みなさい。
と教えてくださったのです。
それで、中道の教えにしたがって『昼と夜の時間が同じになる時期に修行をするとよい』と考えられるようになりました。
じつは、お墓参りというのは日々の『先祖供養』であり、供養することは修行の1つなので、お墓参りをすることは私たちにとって【仏道修行】なんですよね。
それで、昼と夜の時間が半分になる『彼岸』が修行に適しているので、お墓参りをするようになったというわけです。
この世と極楽浄土が最短距離でつながる時期だから
彼岸の時期に、昼と夜の時間がちょうど半分になるということは、つまり、太陽が『真東から昇って、真西に沈んでいく』ということです。
今度は『真西に沈んでいく』というのがキーワードです。
あなたは【阿弥陀如来(あみだにょらい)】という仏様をご存じですか?
阿弥陀様は、たくさんいらっしゃる仏様たちの中でもトップレベルの実力を持つ仏様です。
阿弥陀様がいらっしゃる場所は【西方極楽浄土(さいほうごくらくじょうど)】と呼ばれ、その名のとおり西の方向にある清らかな世界です。
彼岸の時期は、太陽が真西に沈むので、この時期に修行をすれば、西にある極楽浄土への道を、迷うことなくまっすぐに最短距離で進むことができるという考え方が生まれました。
それで、太陽が真西に沈む時期(彼岸)に修行の効果が最もあらわれるから、みんなお墓参りをしましょう、ということになったのです。
【関連記事】:お墓参りをする意味とは?お墓参りのやり方と注意点も詳しく解説
彼岸はどうやって過ごせばいいの?
『彼岸』は年に2回ある重要な期間です。
では、『彼岸』のときには普段と違ったお墓参りのやり方があるのでしょうか?
彼岸のお墓参りのやり方については、普段と同じで大丈夫です。服装も、お花も、お線香も、普段どおりでかまいません。
春彼岸と秋彼岸は何が違うの?
彼岸には『春彼岸』と『秋彼岸』の年2回がありますが、春と秋では何か違いがあるのでしょうか?
じつは、春彼岸と秋彼岸で違いはないです。春も秋も同じようにお墓参りをして、同じようにあなた自身の修行をしてください。
じゃあ、なぜ年に2回も『彼岸』があるのでしょうか?
それは、単純に『昼と夜の時間がちょうど半分になる日』が1年に2回あるからです。
修行に最適な時期が1年に2回あるんだから、ちゃんと2回とも修行(=お墓参り)をやりましょう、ということですね。
まとめ : 彼岸の意味を理解してお墓参りをしましょう。
彼岸のお墓参りは《私たち自身の修行をすること》が目的です。
本来であれば彼岸の一週間は毎日お墓参りをするべきですが、それは現実的ではありません。
ですから、せめてお墓参りの効果が最大化される【彼岸の中日】にお墓参りをしてみてください。
彼岸にお墓参りをして、自分自身をさらに成長させていきましょう!
※お墓参りへ行く前にコチラの記事も読んでみてください。