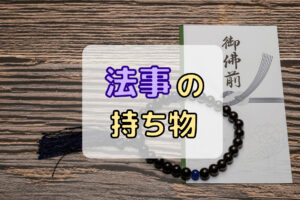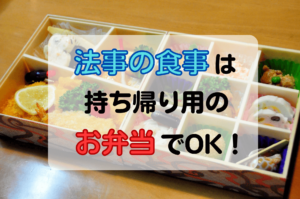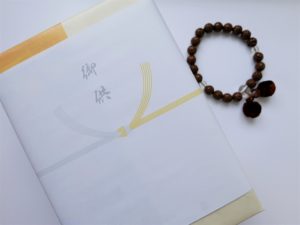法事の場所をどこにしようかと悩んでいませんか?
故人が住み慣れた【自宅】がいいのか、それとも家のお墓がある【お寺】がいいのか。
施主をする場合は、まずこの【法事の場所】を決めるところから始まります。
お坊さんの僕としては、法事をするなら【お寺】がいいと思いますよ。
この記事では、
- 自宅よりもお寺での法事をおすすめする理由
- 自宅で法事をする【メリット】と【デメリット】
- お寺で法事をする【メリット】と【デメリット】
について解説しています。
なお、この記事ではあなたの家のお墓が【お寺】にあるという前提で書いていますのでご注意ください。
お墓がお寺ではなく【霊園】などにある場合は、【お寺】の部分を【霊園】に置き換えて読んでいただければ大体は大丈夫です。
この記事を書いている僕『未熟僧(みじゅくそう)』は、お坊さん歴25年以上。仏事の疑問を解消するいろんな情報を発信しています。
法事をするなら自宅よりも【お寺】がおすすめ
法事をしようと思ったとき、多くの人はまず【場所をどこにするか】で悩んでしまいます。
一般的な選択肢としては、【自宅】または【寺】のどちらかになることが多いでしょう。
場所が違うと供養の方法も変わるのかというと、そんなことはなく、場所どこでも『全く同じ方法』で供養します。
では、どちらを選ぶのがよいのでしょう。
僕はお坊さんになって20年以上です、今までいろんな場所で法事をお勤めしてきました。
その経験をふまえた上で僕は、お寺(本堂)での法事がおすすめです。
決して僕がお坊さんだから移動の手間を省きたくて言っているのではないですよ。
法事の場所に【お寺】を選ぶと、施主と寺、そして仏様(故人)にとってメリットが大きいからです。
あくまで、お寺で法事をする方が【メリットが大きい】ということであって、自宅がダメというわけではありませんので、その点はご了承ください。
それぞれにメリットとデメリットがありますので、順番に説明していきます。
自宅での法事
昔は、自宅で法事をすることが多かったです。
各家のお仏壇の前でお勤めをし、法要後は施主とその家族や親戚のみなさんと一緒にお茶菓子を頂きながら、いろんな話をしていたものです。
ちなみに、自宅での法事の場合、家の中を見渡すと信者さんの普段の生活が何となく分かってしまいます。
じつは、自宅での法事というのは、お坊さんにとって【信者さんに関する情報】を得る絶好のチャンスなんです。
本当に申し訳ないですが、家の中に入った時点からチラチラと見させていただいてます。でも、決して他言しませんからご安心くださいね。
それでは、まず自宅で法事をするメリットとデメリットを紹介していきます。
自宅で法事をするメリット
自宅で法事をするメリットは、
- 自宅なので気が楽
- 移動をしなくてもよい
- お坊さんの読経や説法が聞こえやすい
- お坊さんにいろいろ質問しやすい
- 普段着でも法要が可能
といったところでしょう。
自宅なので気が楽
まず、自宅であれば家中の勝手が全てわかるので、施主や家族にとっては気が楽でイイですよね。
また、仏様(故人)にとっても住み慣れた我が家での法要を喜んでおられるかもしれません。
移動をしなくてもよい
自宅であれば、当然ながら移動をしなくてもよいので、法要開始時間に遅刻することもありませんし、荷物をたくさん持って行くこともありません。
荷物がないということは、忘れ物をするなんてこともないですよね。
もし法要中に数珠を忘れたことに気づいても、すぐに部屋へ取りに行けますもんね。
お坊さんの読経や説法が聞こえやすい
自宅の場合、お坊さんとの距離が近いので、お経や説法が聞きやすくなります。
小さな声で話すお坊さんの場合、広い場所だと話がほとんど聞こえませんが、自宅ならちゃんと聞こえます。
しかし、たまに説法をしないお坊さんがおります。
せっかくの法事なのに、ただお経を聞いてるだけじゃ物足りないですよね?
ですから、説法をしてもらえるように予めあなたから誘導してあげましょう。
お坊さんにいろいろ質問しやすい
そして、すぐそこにお坊さんがいますので、いろいろと話をしているうちに、いろいろと質問をしやすい雰囲気になります。
普段なかなか聞けないようなことを質問できる良いチャンスなので、疑問に思うことをドンドン質問してしまいましょう。
普段着でも法要が可能
これは賛否両論あるでしょうけど、参列者が家族だけというケースなら、服装も【普段着】でよいと僕は思います。
しかし、親戚などを招いて法事をするときは、原則として喪服を着用するようにしてください。
もしも、喪服を持っていないという人は、購入しておくことをおすすめします。
喪服については、『喪服を持っていない時はどう対処する?喪服の意味と必要性を解説します』の記事で詳しく解説していますので読んでみてください。
自宅で法事をするデメリット
次に、デメリットを紹介していきます。
考えられるデメリットは、
- 参列者やお坊さん用に駐車スペースを確保する必要がある ※これが意外と大変です
- 家中の片付けや掃除など、法事ができるように部屋の準備をしなければならない
- 参列者へのお茶とお菓子を用意しておかなければならない
- 夏の場合、参列者が多いと部屋が暑い
- 法事後の食事を家でする場合、料理や飲み物は業者のものでも良いが、食器類などは用意する必要がある
- 全て終わった後、部屋を元のカタチに戻したり掃除するなど、後片付けが大変
以上のようなことが挙げられます。
駐車スペースの確保が必要
参列者の全員があなたの自宅まで電車・バス・タクシーを利用して来るというわけではありません。参列者の中には自動車で来る人だっています。
特にお坊さんは自動車で来ることが多いでしょう。
お坊さんとしては、荷物が大きいので、お寺のすぐ近くでもない限り自動車で移動したいものなのです。
そのため、自宅の駐車場だけでは足りず、他の場所にも駐車できるように事前の手配が必要になるケースもあります。
駐車スペースとして近隣のお宅の場所(土地)を借りた場合は、そのお礼も必要なので、それだけでも負担が増えてしまいます。
家中の片付けと清掃をして、法事の準備が必要
自宅に人を招くからには、家の中が【散らかりっばなし】というわけにはいきません。
法要をする部屋はもちろん、玄関・通路・トイレ・リビング・台所、家中を片付けて法事の準備をしなくてはなりません。
おそらく、年末の大掃除並みの労力が必要になるかと思います。
参列者へのお茶やお菓子を用意しなければならない
あなたの自宅に参列者の人たちが到着したら、お茶やお菓子を出してあげるのがマナーです。
これを参列者みんなに振る舞うのですから、法事が始まる前からやる事がたくさんです。
また、そのお茶やお菓子ですが、どんな物をどのくらい買っておくのかなど、いろいろと考えるべきことが増えます。
夏は部屋が暑くなりがち
夏に自宅で法事をする場合は要注意です。
少人数であれば問題ありませんが、人数が10人を超えると部屋の中がかなり暑くなってしまいます。
もちろん、部屋の広さにもよりますが、一般的な間取りの部屋に10人以上が集まると、クーラーを作動させても暑いです。
クーラーだけでは足りない場合、扇風機を併用するなどして対策をするといいでしょう。
ただし、扇風機の風がローソクや燃やした線香に当たらないよう注意が必要です。
自宅で食事をする場合、準備が必要
法事の後にそのまま自宅で食事を振る舞う場合、料理は仕出料理業者に発注したり出前をとることが多いですが、食器類は施主側が用意しておかなければなりません。
食器類の他には、簡単なおつまみ・飲み物などが必要ですし、醤油などの調味料もあった方が良いと思います。
そして、みんなで食事をしているときに起きやすい【飲み物の入ったグラスを倒す】という事故があることも覚悟しておきましょう。
全て終わった後も、家中の片付けが大変
無事に法事が終わりホッとひと息をついたら、まだやるべきことが残っています。
移動した家具類をいつもの配置に戻したり、みんなが使って汚したトイレや玄関を清掃したり、部屋や廊下の掃除機かけ、台所に溢れている使用した食器類を洗う、などなど。
このように、自宅での法事はデメリットもたくさんあります。
やはり、すべての準備や後片付けを自分でするが大変というところが最大のデメリットです。
自分の家なので気楽なところがある反面で、人を招く上でいろいろ気をつかうことも多いのが【自宅での法事】というものです。
お寺(本堂)での法事
僕が断然おすすめするのは【お寺での法事】です。
というか、お墓がお寺にある人は『お寺で法事をするべき』だとさえ思います。
お寺で法事をするメリット
お寺で法事をするメリットは、
- 供養をするには最も適した場所である
- 広い駐車場がある
- 法要をする場所の準備をしなくてよい
- 本堂は広いので大人数でも大丈夫
- 法要後すぐにお墓参りができる
- 法要後の食事をする場所がある
- じつは、お寺側としてもありがたい
というところです。
供養をするには最も適した場所
お寺での法事をすすめる1番の理由は、本堂が『あらゆる法要の基本となる場所』だからです。
お寺の本堂には、お寺全体と信者さんを守ってくださる仏様(=ご本尊様)がおられます。
仏教の基本として、お葬式・法事・祈祷といったあらゆる法要は、お寺のご本尊様の前で行います。
なぜなら、ご本尊様がお寺の中心的な存在であり、そのご本尊様の前で法要をすることで、最も良いカタチで故人の供養ができ、さらには施主や参列者にもいろんなご利益があるからです。
あなたは最高のカタチで故人を供養したいと思いませんか?
広い駐車場がある
僕が今まで見てきた限り、法事に参列する人の多くは自動車で来ます。
ですから、自宅の法事だと駐車場スペースの確保はけっこう大変なんです。
しかし、お寺には広い駐車場があります。
広い駐車場があるというのは、参列する側の人たちにとっても安心なので、施主と参列者の双方にとってメリットになります。
法要をする場所の準備をしなくていい
お寺で法事をする場合は、施主が法要場所の片付けや掃除などの準備をする必要がありませんし、お茶やお菓子の用意もお寺がしてくれます。
事前に依頼をしておけば、生花だってお寺で用意をしてくれますよ。
つまり、法事に必要最低限のモノさえ持って行けば、あとはお寺側でいろんな準備をしてくれるのです。
もちろん、法要後の後片付けだってお寺の人がやってくれます。
これは施主にとって大きなメリットだと思います、かなりの負担軽減になるのではないでしょうか?
本堂は広いので大人数でも大丈夫
自宅での法事の場合、大人数だと法要をしている部屋の中に全員が入りきらず、一部の人は隣の部屋などに座るということが多いです。
しかし、だいたいのお寺の本堂であれば100人程度は収容できると思います。
十分に広いので、参列者全員がゆったりと座ることができ、法要の様子もよく見渡せます。
法要後すぐにお墓参りができる
法要が終わった後は、お塔婆などを持ってみんなでお墓参りをします。
お寺にお墓がある人は、そのまますぐにお墓参りができますよ。
自宅で法事をした場合は、わざわざお墓まで行かなくてはならないですよね。
お塔婆・お花・お線香・お供物を持って移動するのは意外と面倒です。
なので、法要場所のすぐ近くにお墓があるというのはとても楽だと思いますよ。
法要後の食事をする場所がある
法要とお墓参りが終わると、最後に参列者全員で食事をします。
お寺であればだいたい食事ができるような場所があるので、当日はわざわざ他の場所へ移動することなく、すぐに食事が始められます。
ただし、食事場所の確保や料理の注文については、事前にお寺へ依頼する必要がありますので、なるべく早めに連絡をしておきましょう。
じつは、お寺側としてもありがたい
では、お寺で法事をするメリットの最後の部分です。
正直に言うと、お寺としても本堂で法事をしてもらう方がありがたいです。
自宅での法事の場合、法要の時間だけでなく移動の時間も必要です。
お寺からすぐ近くの家であればイイですが、車で数十分の距離ということもあります。
しかし、お寺に来ていただけると、移動がない分だけ時間のやりくりをしやすくなり、同じ日に他の家の法事もお勤めできるのです。
法事を行うのは、どうしても土日祝日に集中してしまいます。
できるだけ各家の希望の日にお勤めをしたいので、お寺としては、移動の時間を削減できてより多くの法事ができる『お寺での法事』の方がありがたいのです。
お寺で法事をするデメリット
お寺での法事をオススメしていますが、残念ながらデメリットもあります。
- 遅刻する ※コレがとても多いです
- 忘れ物をする ※位牌だけは忘れないで!
- 冷暖房を完備していないお寺も多い
- お寺側のミス
- 他の家の法事がある
デメリットなんてあまり無いかと思っていましたが、よく考えてみると意外と出てきましたね。
ここは正直に書いていこうと思います。
遅刻する
お寺の場所によっては、周りの住宅に隠れてしまって、なかなか見つけられないということもあります。
親戚などにとっては普段あまり馴染みのないお寺なので、場所が分からなくなってしまうんですね。
特に自動車だと、道路状況によっては一度通り過ぎてしまうとなかなか戻って来られないケースがあります。
また、電車の遅延や道路の渋滞などで、法要開始時間に間に合わないという人はとても多いです。
もしも施主が遅刻してしまうと、法要そのものが始められません。
お寺で法事をする最大のデメリットは【遅刻のリスク】という点だと思います。
忘れ物をする
お寺での法事で遅刻に次いで多いのが、忘れ物です。
法事に持参する物はたくさんあります。
位牌、遺影、供物、線香、お布施、返礼品、お花、花切りバサミ、ライター、などなど。
そうすると、忘れ物をしてしまう人がどうしても出てきます。
人間なので忘れ物をするのはかまいません、しかし『位牌』だけは忘れないようにしてください。
位牌は故人が宿る場所です、位牌を忘れると肝心の故人がいない所で法要することになります。
【関連記事】:位牌とは何なの?位牌の意味や必要性をお坊さんが解説します。
冷暖房を完備していないお寺も多い
基本的な考え方として、お寺の本堂は仏教信者が集まって修行する【道場】です。
つまり、本堂内の造りは、そこにいるための【快適さ】ということはほとんど考慮されていません。
最近のお寺の本堂は冷暖房が完備されているところも増えていますが、まだ設備が整っていないお寺もたくさんあります。
そのようなお寺で法要をすると、夏は暑く、冬は寒いといった、まさに修行のような時間をすごすことになります。
お寺側のミス
前もってお花の発注をお寺に依頼しておけば、当日はお寺側でお花を用意してくれています。
ただ、お寺の発注ミスによりお花が用意されていないこともあります。
ですから、念のために法事当日の3日前くらいにお寺へ電話しておいて、持ち物の再確認と、発注の再確認をしておくとよいでしょう。
他の家の法事がある
お寺では同じ日に他の家の法事も行なっています。
もし同じ日に別の家の法事があった場合、その家の法要中は静かにしておくなど、他者にも気を使わなければなりません。
まとめ : 法事の場所を自宅かお寺で迷ったら、お寺を選ぶべし!
法事は故人を定期的に供養する大切な仏事です。
大切な仏事ですから、なるべく長く続けてもらいたいのです。
でも、毎回大変な思いをしてしまうと長くは続けられません。長く続けるには法事1回の負担をできるだけ減ら必要があります。
施主の負担を軽減させるためにも【お寺】での法事をおすすめします。
荷物を運んだりするのは大変かもしれませんが、自宅での大きなデメリットを考えれば、お寺の方がずっと楽ですよ。
また、お寺での法事は、【故人の供養に最適な場所】であり【施主の負担も減らせる】ことはもちろん、【お寺側にとってもありがたい】という、理想的な条件が揃っています。
なので、最後にもう一度言います。
法事をする場所は、【お寺】がおすすめです。
※法事の施主をするならこちらの記事も読んでみてください。