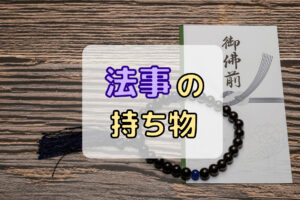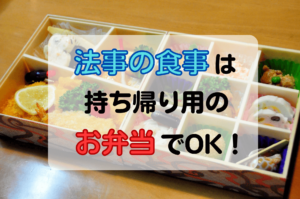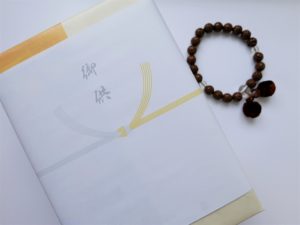正座をしていると、足がしびれて感覚が無くなり、膝の痛みが出て、最終的には立てなくなりますよね。
正座が得意な人はいいですが、正座が苦手な人にとってはまるで【拷問】です。
そんな【拷問】を強いられる場面の1つが『法事』で、法要中の30分〜1時間くらいは正座をしていることになります。
しかし、僕は法事のときに正座なんかしなくてもイイと思っています。
特に【自宅の法事】の場合は、正座なんかしないで座椅子を使えばいいんですよ。
この記事では、
- 正座の意味
- 正座をしなくてもいい理由
- 足がしびれにくい正座の方法
について紹介しています。
正座が苦手なあなたの助けになる内容だと思いますので最後まで読んでみてください。
※こちらの記事も読まれています
この記事を書いている僕『未熟僧(みじゅくそう)』は、お坊さん歴25年以上。仏事の疑問を解消するいろんな情報を発信しています。
法事では無理に正座をしなくてよい
僕はお坊さんを20年以上していますが、今までに何度も、
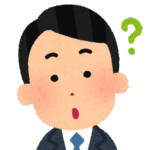
お坊さんて、正座しても足がしびれないんですよね?やっぱり何かコツがあるんですか?
と質問されました。
皆さん少し誤解をしているようですが、お坊さんも正座をするとちゃんと足がしびれます。
しっかりと足はしびれているんですが、長年の経験で【しびれ始める時間】や【うまくゴマかす方法】を知っているため、何ともないように見せられるんです。
何ともないように見せることが上手なのは【正座が得意なお坊さん】で、下手なのが【正座が苦手なお坊さん】だと思います。
そして、僕は【正座が苦手なお坊さん】なので、基本的にしびれ始める時間が早いし、うまくゴマかすのも下手です。
そんな僕は「なぜ法要のときには正座をしなくちゃいけないの?」といろいろと考えてみた結果『正座なんかしなくてもイイ』という結論にいたりました。
僕は一応『お坊さん』なので、正座をヤメることは難しい立場ですが、あなたは気にせずヤメちゃっても大丈夫です。
正座をする意味
では、まず根本的なところから。
一般的に、法事のときに正座をするのは【ごく当たり前のこと】みたいになってますが、「そもそも、正座をして何の意味があるの?」と思いませんか?
僕は思っていましたよ。
だって、正座をすると足が痛くなって、まったく法要に集中できないんですから。
でも、法要で正座をすることにはちゃんと意味がありました。
正座というのは、目の前にいる相手に対して、
- 敬意があること
- 敵意がないこと
を表すための座り方なんです。
正座をしているとすぐには立ち上がれません。つまり、正座というのは【目の前の相手を攻撃するには不向きな座り方】なんです。
だから、この座り方をすることで、
「私は、あなたに対する敵意なんて一切ありません。
その証拠に、ほら見て、私はこんな座り方をしてるんですよ?
私は、あなたに敬意や親愛の気持ちしかないんです。」
と相手に伝えているのです。
そして、それが【目の前に相手がいるときの座り方】つまり『正座』として定着した、ということです。
これを仏様に対しても同じように、【敵意が無い】ことはもちろんですが、【敬意】を表すために正座をするわけですね。
仏様には敬意を表すべきなので、そういう理由で正座の方がイイと言われたらお坊さんの僕としては文句を言えません。
正座をしなくてもよい理由
正座をすることには重要な意味がありますが、それでも僕は『正座をするべき』とは思いません。
まず、正座はすべての人ができるものではありません。
例えば、足の不自由な人に対して「正座をしてください」とは言わないですよね?
身体的な理由で正座ができない人はみんな【仏様への敬意がない】ということでしょうか?そんなことないはずです。
僕は、仏様への敬意を表す方法は、べつに『正座以外のやり方』でもイイと思うんですよね。
敬意を表すには【頭を下げる】や【手を合わせる】など他の方法もあるので、仏様に敬意を表す方法は人それぞれ《自由》でいいと思います。
もし、寝転がって鼻をほじることが敬意を表すことだったら、誰のことも気にせずソレをすればイイんです。
僕はそれを見ても怒りませんよ、でも事前に『その人にとって【寝転がりの鼻ほじほじ】が敬意の表れ』であることは教えておいてくださいね。
この例は極端でしたが、要するに正座に固執することはないですよと言いたいのです。
正座をする人、正座をしない人、それぞれが選択した【敬意を表す方法】をやればイイです、そこに強制はありません。
もう1つ。
これは僕の経験から思うことですが、正座をすると、法要の途中から、僕も含めてみなさんの意識が【足のしびれ】の方に行ってしまいがちです。
あなたは法要の途中でこう思ったことありませんか?



あ〜ヤバイな、お焼香のときにちゃんと立てるかな。転んじゃったらどうしよう。
って。
こうなると、もはや【故人の供養】よりも【足のしびれ】のことを考えている状態です。
法事は、故人を供養するために行うものですから、法要の間は故人のことだけを考えてほしいのです。
それを妨げるものは、たとえ正座であっても排除してかまいません。【座り方】なんかより【故人を供養する気持ち】の方が大切なのですから。
ということで、僕は、『法事のときでも正座はしなくてよい』という結論にいたりました。
【しびれにくい正座の方法】と【しびれの対処法】



他の人が正座をしていたら自分だけしないわけにもいかないよ・・・。
まぁそうですよね。では、そんなあなたに【しびれにくい正座の方法】を紹介します。
とはいえ、同じ座り方をしても人によって《しびれの度合い》は違います。
これから紹介する方法は、あなたにとって【しびれにくくなる】かもしれませんし、逆に【しびれやすくなる】かもしれませんので、その点はご了承ください。
しびれにくい正座の方法
20年以上お坊さんをしてきた僕の【しびれにくい正座の方法】は以下のとおり。
- 両足の親指を平行にしてつける、あるいは、ほんの少しだけ重ねる(僕は、親指をしっかり重ねるとつってしまうんです)
- かかとは少し開く(開きすぎるとヒザへの負担が増えるので注意)
- お尻の肉はかかとにしっかり乗せる(両かかとで肛門を開くイメージ)
- 上半身の重心を2〜3分おきに前後左右にズラしていく(他の人にバレないように少しずつズラす)
- 「まだ大丈夫」と自分に暗示をかける(これが意外と効く)
ここで1つあなたへアドバイスですが、正座をするなら厚くて柔らかい座布団を使わない方がイイですよ。
じつは、これを言っているお坊さんは意外と多いんです。
何故でしょうかね?僕にも分かりませんが、柔らかすぎると足の広範囲を圧迫するのかもしれません。
なので、ぜいたくを言わせていただくと、使いこんだペラペラの座布団が理想的です。
床に直接座るよりも痛みがなく、なおかつ圧迫も少ないので、正座をするときにはペラペラの座布団が最適です。
完全に足がしびれてしまったときの対処法
法事で仕方なく正座をすることになったあなた。
そして、もうとっくに足の限界を迎えて、足の感覚が無くなっており、すぐに立ち上がることは不可能になってしまいました。
そんなときは、こうしてみてください。
- お尻をグッと上げて上半身を前に倒して、足の血流を少しずつ戻す。
- 足がピリピリしてきたら血流が戻ってきた証拠。そのまま数十秒間その姿勢をキープする。
- 足首が曲げられるくらいまで回復したら、つま先立ちで正座をする(ここまでくれば、ほぼ立ち上がれます)。
- 立ち上がるときは、しっかりと手をついて【ゆっくりと】立つ。
足がしびれたら、なるべく早い段階で血流を戻すのがポイントです。
しかし、それでも足がしびれたら、とにかく【ゆっくり】と動くようにしてください。
僕は足がしびれて転んでしまう人を何人か見てきました。本当に危険なので、急に立ったり、無理に歩こうとしないでくださいね。
あと、最後にもう1つ大事なことがあります。
もしも足がしびれたら、恥ずかしがらずに「足がしびれたので少し待ってください。」と伝えましょう。
無理に立とうとして転ぶ方が恥ずかしい思いをしますし、ケガでもしたら法事が台無しになります。
座椅子に座る
法事では無理に正座をしなくたっていいんですよ。
正座ができないと思ったら、座椅子に座っていればいいんです。
最近のお寺は、法事の参列者のためにイスを用意しているところが増えています。ちなみに、僕のいる寺も本堂内はすべて【イス席】です。
他のお寺でも、昔みたいに正座なんかさせていませんよ。
お寺でさえイスの使用がOKなのですから、自宅で法事をするときだってもちろん座椅子に座って大丈夫。
テーブルで使うような高さのイスだと、正座をしている他の参列者を上から見下ろすような形になりますから、もしも座敷用の脚の短いイスがあったら、それを使うのが一番イイですよ。
【関連記事】:【自宅の法事に最適!】正座ができない人におすすめの座椅子3選
まとめ: 法事でも正座をしなくていい
法事をするときは、無理に正座をしなくていいですよ。
座椅子があるなら遠慮なく使いましょう。
それでも正座せざるを得ない場合は、
- 両足の親指を平行にしてつける、あるいは、ほんの少しだけ重ねる(僕は、親指をしっかり重ねるとつってしまうんです)
- かかとは少し開く(開きすぎるとヒザへの負担が増えるので注意)
- お尻の肉はかかとにしっかり乗せる(両かかとで肛門を開くイメージ)
- 上半身の重心を2〜3分おきに前後左右にズラしていく(他の人にバレないように少しずつズラす)
- 「まだ大丈夫」と自分に暗示をかける(これが意外と効く)
という方法で座ってみてください。
それでも足がしびれたら、
- お尻をグッと上げて上半身を前に倒して、足の血流を少しずつ戻す。
- 足がピリピリしてきたら血流が戻ってきた証拠。そのまま数十秒間その姿勢をキープする。
- 足首が曲げられるくらいまで回復したら、つま先立ちで正座をする(ここまでくれば、ほぼ立ち上がれます)。
- 立ち上がるときは、しっかりと手をついて【ゆっくりと】立つ。
という方法で乗り切ってください。
高齢化が進んでいることもあり、足が悪くて正座できない人が増えています。
そのため、近年ではお寺でも正座をさせずにイスに座ってもらうようにしています。
おそらく、今後の法事では【正座をする】という慣習は無くなっていくでしょう。
ですから、法事のときでも正座はしなくてイイですよ。
※法事に参列するときはこちらの記事を読んでみてください。