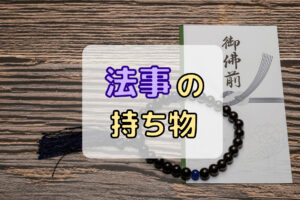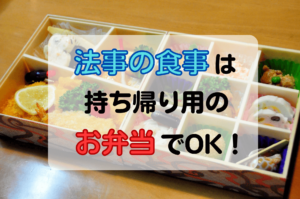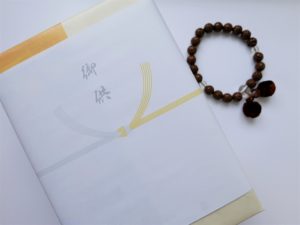- あれっ?今年は年回忌にあたる仏様が2人いるのか!
- 複数の仏様の法事を【一回】にまとめられないかな?
- 複数の仏様を同時に供養するときは、どんなことに注意すればいいの?
法事をしようと思ったら、じつは他にも年回忌に該当する仏様がいた、というのはよくある話。
僕がいる寺でも、
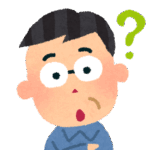
今年は父の◯回忌と母の◯回忌が重なるんですけど、ちゃんと別々に法事をした方がいいですよね?
という質問はとても多いです。
一年のうちに何回も法事をするのはけっこう大変ですから、複数の仏様を1回にまとめて供養をするというのでも大丈夫ですよ。
複数の仏様を同時に供養することを、『併修(へいしゅう)』といって、ごく普通に行われることなので何の問題もありません。
この記事を読めば、
- 併修の意味
- 併修の注意点
が分かります。
もう何も迷うことなく安心して複数の仏様の供養ができるようになりますので最後まで読んでみてください。



詳しく解説しているので参考になると思いますよ。
この記事を書いている僕『未熟僧(みじゅくそう)』は、お坊さん歴25年以上。仏事の疑問を解消するいろんな情報を発信しています。
法事で複数の仏様を同時に供養したい
あなたの家には仏様(亡くなった家族)が何人いますか?
古くから代々続いている家ほど仏様の数も多いはずです。
そうなると、同じ年に複数の仏様の年回忌が重なるということもあるでしょう。
そのような場合は、ちゃんと『それぞれ個別に供養をする』というのが正解です。
とはいえ、一年に何回も法事をするなんて大変だし、正直なところ面倒くさいですよね?
本来なら個別に法事をするものではありますが、実際のところは、複数の仏様を同時に供養するというのが現実的な対応です。
というか、これは多くのお寺や霊園でも普通に行われていることなので安心してください。
この【複数の仏様を同時に供養する】ことを『併修(へいしゅう)』といいます。



複数の仏様を併せて供養を修めるから『併修』というわけですね。
最近では身内だけで法事を行うケースも増えましたが、少し前までは親戚を数十人招くというのは普通でした。
そうすると、法事をするというのは、施主はもちろん参列する側も大変なんですよね。
まず、施主としては、事前にいろんな準備をしなくてはならず、法要当日は気を遣いっぱなしで、費用だって結構かかります。
本音としては、身内だけで費用を抑えて気楽に法事をしたいけれど、親戚同士の付き合いがある以上そういうわけにもいかない。
一方で、法事に招かれた側も「ちょっと面倒くさいなぁ。」と思いながらも、親戚同士の付き合いがあるので、わざわざ仕事を休んで法事に出て、おまけに【御仏前】まで用意します。
このように、法事というのは施主と参列者の両方にとって大変で、まぁまぁ疲れるイベントなんですよね。
なのに、それが年に何回もあったら・・・。
というわけで、大変なことは1回で済ませてしまった方がいいですし、それに対して文句を言う人もいないでしょう。
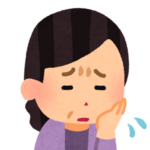
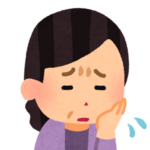
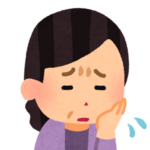
でも、自分たちの都合で法事を1回にまとめちゃったら仏様に失礼じゃないかしら?



それは大丈夫ですよ、仏様を供養したいという気持ちがあることが重要なんです。
あなたには『年回忌にあたる仏様達みんなを供養したい』という気持ちがあるわけですよね?
その気持ちがあれば、【仏様ごとに単独で供養】じゃなくて【まとめて1回で供養】でもかまいませんよ。
もちろん、まとめて供養したからといって【それぞれの供養が手抜きになる】なんてこともないです。
そのへんは私たちお坊さんにお任せください。単独だろうが併修だろうが、お坊さんはそれぞれの仏様の供養はしっかりと行います。
というわけで、複数の仏様の年回忌が重なってしまう場合は、遠慮せずに『併修』を選んでくださいね。
【関連記事】:法事をする必要性と意味。法事の注意点も合わせて解説します。
じつは他にも【来年に年回忌を迎える仏様】がいる
年回忌にあたる仏様が【同じ年】に複数いる場合は併修をすればOKです。
では、【違う年】に年回忌を迎える仏様と併修することは可能なのでしょうか?
例えば、
今年は父の13回忌にあたり、来年は母の7回忌にあたる。
2年連続で法事をするのではなく、今年の父の法事のときに、できれば母も一緒に供養をしたい。
みたいなパターンです。
結論を言うと、原則として、同じ年に年回忌を迎える仏様なら併修はOK、違う年の仏様はNG、となります。
ですから、例に挙げたような【わずか1年違い】のケースでも、年が違えば併修をしません。



え〜っ!じゃあ来年もまた法事をやらなきゃいけないの⁉︎それは大変だなぁ・・・。



まぁ、そうですよね。じつは、僕がいる寺では年が違っても一緒に供養しちゃってますよ。
回忌を迎える年が違うなら『原則』としては分けて供養をします。
ただ、そうは言っても法事が続くと施主も親戚も大変です。そうすると、施主も親戚もみんな【仕方ないから】法事をする(参列をする)、みたいな気持ちになってしまうんですよね。
それじゃ、後に供養される仏様があまりに可哀想です、というかメチャクチャ失礼です。だったら、少し年が違うくらいであれば一緒に供養してあげた方がダンゼンいいと思います。
というわけで、僕がいる寺の場合は、年回忌を迎える年が違う仏様同士でも、施主の要望があれば併修をしています。
ただし、一応の基準があって、
- 1年違いならOK。
- 2年以上違うならNG。
- 33回忌以降の仏様の併修は年数不問でOK。
としています。
とはいえ、これは僕がいる寺の基準であり、あなたとお付き合いのあるお寺がどのように考えているかは分かりません。
ですから、併修をしたいときには、
- 併修が可能なのか
- どのくらいの年の違いであれば可能なのか
を必ずお寺に確認をしてください。
ちなみに、もしも【法事をするのを忘れていた】という仏様がいた場合は、年が違うことなどは気にせず、遅れてでもかまわないので併修をしてあげてください。
年が違うという問題の以前に【遅れたから何もしない】という方がよほど仏様に対して失礼ですから。
【関連記事】:法事をするのを忘れた!遅れて法事をしてもいいの?
併修をするときの注意点
併修をしても問題ないことは理解していただけたと思います。
とはいえ、併修はあくまで【特別措置】のような供養方法です。
なので、併修をする場合には、いくつかの注意点があります。
併修の注意点とは、
- 親戚には併修で執り行う旨を通知しておく
- お寺や霊園に併修が可能であるかを確認する
- 年回忌にあたる仏様だけを併修にする
- 三回忌まではなるべく併修にしない
- 一番早く命日を迎える仏様を基準にして法事の日程を決める
- 仏様が複数になれば納めるお布施は多くなる
- 併修にする仏様全員分の塔婆を建てる
です。
意外と注意点が多くて面倒に感じてしまうかもしれませんね。でも、何回も法事をすることに比べればずっとラクですよ。
逆に言えば、これらの注意点さえ守れば堂々と併修ができるということです。
親戚には併修で執り行う旨を通知しておく
法事をするときは、基本的に親戚も招きます。
なので、親戚へ出す法事の案内の中で【併修で執り行う旨】を通知するという方が無難です。
世の中には【本来のやり方】にものすごくこだわる人がいますが、そのような人があなたの親戚にもいたら厄介です。
当日になってから併修であることを伝えたら、やれ「どうして別々に供養しないんだ!」とか、やれ「事前に知らせるのが普通だろ!」みたいなことを言う人がいるんですよね。
だから、後になって文句を言われないように、「父の◯回忌と母の◯回忌を同日に行います」のように先に通知しておきましょう。
お寺や霊園に併修が可能であるかを確認する
先ほど、法事に関して【本来のやり方】にこだわる人がいると言いましたが、それってお坊さんにも多いんですよね。(お坊さんこそ【本来のやり方】にこだわるべきなのかもしれませんが。)
お坊さんによって考え方が違うので、『併修を認めないお坊さん』もいます。
だから、併修にしたいなら、事前に併修が可能であるかを確認することが必要です。
ほとんどの場合は併修での法事を了承してもらえますが、、ときどき「供養を一回にまとめるなんて、そんなの仏様に対して失礼だ!」とお坊さんが併修を断るケースもあるんですよ。
たしかに、法事っていうのは【仏様の供養】を第一に考えるべきです。だから、施主や参列者の都合で併修にするのは、【自分達の都合】を第一に考えてるように見えるかもしれません。
でも、年に何回も法事をしなきゃいけないと思ったら、おっくうになって【供養をしようという気持ち】が萎えちゃうんですよね。



そうなると仏様の供養をヤメてしまう危険性があります。
つまり、仏様の供養を第一に考えるなら『施主や参列者の都合』に配慮することも必要なわけです。
もちろん「施主の要求をすべて受け入れるべき」というわけではないけど、あまりに【本来のやり方】にこだわるお坊さんは、時代の流れに合わせてもっと『柔軟』に考えた方がイイですね。
だから、もしも併修を認めないようなお坊さんがいるお寺なら、いっそのこと霊園にお墓を移した方がいいと思います。霊園なら、併修はもちろんのこと、いろんな希望を受け入れてくれる柔軟性があります。
一方で、併修さえも認めないようなお坊さんがいるお寺なんて、きっと近いうちにツブれますよ。時代の変化に対応できないようなお寺に明るい未来なんてありません。
そういう意味では、あえて併修を持ちかけてみて、それでどう対応してくれるかで、そのお寺の質が判断できるともいえますね。
年回忌にあたる仏様だけを併修にする
併修をするなら、「◯◯さんの7回忌と、▲▲さんの17回忌が同じ年だ」というように、年回忌にあたる仏様だけを併修にするようにしましょう。
でも、
- 父の13回忌と母の7回忌を一緒に行いたい。
- しかし、じつは母の7回忌にあたるのは来年である。
みたいに、【年回忌にあたらない仏様も一緒に供養したい】というケースがあります。
この場合、母の実際の7回忌には一年早いので、本来であれば併修の対象にはしません。
ここで、お坊さんによって考え方が違います。
併修そのものはOKでも、それが【年回忌に該当しない仏様も併修】となると、
- ちゃんと年回忌にあたる仏様だけを併修にするべき
- 少しくらいなら年が違ってもかまわないから併修にすればいい
というように分かれてしまいます。
このへんは『併修そのものを認めない』というお坊さんとは違って、柔軟な考え方をした上でのお坊さんごとの【こだわりの部分】になります。
僕としては、やはり【施主と参列者の都合】を優先して、1年くらいのズレなら併修にしたらいいと思いますね。
なので、原則として年回忌にあたる仏様だけを併修にするようにして、年回忌に該当しない仏様も併修したいときは、事前にお寺に確認をしておきましょう。
三回忌まではなるべく併修にしない
併修をするときによく言われるのが、三回忌まではなるべく併修にしないというものです。
これは『亡くなってからあまり年数が経っていないのだから、ちゃんと単独で供養するべきだ。』という故人に対する敬意を示した考え方です。
また、三回忌は【どんな者でも必ず救ってくれる】ことで有名な『阿弥陀如来(あみだにょらい)』様とご縁の深い年回忌で、三回忌からは阿弥陀如来様が故人の面倒をみてくださいます。
だから、阿弥陀如来様に故人をお任せするまではしっかりと個別に供養してあげようということなのです。
とはいえ、「三回忌までは絶対に単独で供養をしなきゃダメだ!」というほどではありません。
やはり、【施主と参列者の都合】を優先させた方がいいですから、『三回忌まではなるべく併修にしない』くらいの意識でOKですよ。
一番早く命日を迎える仏様を基準にして法事の日程を決める
法事をするためには、まず日程を決めなきゃいけません。
法事の日程を決めるときには【故人の命日を過ぎないようにする】というのが基本です。
これをふまえた上で、法事は一般的に、
- 故人のちょうど命日
- 命日の直前の土日祝日
に行うことが多いです。
併修をしたい多くの人が『複数の仏様を供養する場合は、誰の命日を基準にして日程を決めればいいのか。』ということで悩んでしまいますが、併修の日程の決め方は簡単です。
併修の場合は【一番早く命日を迎える仏様】を基準にして法事の日程を決めるといいですよ。
例えば、命日が《3月》《6月》《12月》の3人の仏様を供養する場合は、《3月》が命日の仏様を基準にして日程を組んでください。
じつは、年回忌供養には故人を導いてくれる仏様へ挨拶をするという意味があるんです。
故人を導いてくれる仏様へご挨拶をしなきゃいけないのに、まさか遅れるわけにはいきませんよね。
だから、誰1人として遅れることのないように、一番早く命日を迎える仏様に合わせて日程を決める、ということです。



仏様への挨拶が早いぶんには問題ありません。
また、法事の日程を決めるときには【友引】や【仏滅】などは無視しても大丈夫です。
その理由については『法事の日取りは友引や仏滅でもいいの?法事には六曜を考えるべき?』の記事で詳しく解説していますので、興味のある人は読んでみてください。
仏様が複数になれば納めるお布施は多くなる
法事をすれば、供養をしてくれたお坊さんへ【お布施】を渡します。
そうなると、



供養する仏様の数が増えたら、お布施の金額も増えるのかな?
と誰もが思うはず。
ご想像のとおり、併修をする場合は納めるお布施が多くなると思ってください。
例えば、
- 仏様1人だけの供養料⇒5万円
- 仏様2人分の供養料合計⇒6万円〜8万円
みたいに、仏様の数が増えるほど供養料合計も増えていくと思った方がいいですよ。
場合によっては単純に、仏様が2人なら2倍、3人なら3倍になるかもしれません。
本来なら単独で供養すべきところを施主側の都合で一回にまとめるわけですから、お布施が仏様の数だけ2倍3倍となっても基本的には仕方ないことなんですよね。
とはいえ、お経や説法を2倍も3倍もやるかというと、そんなことはありません。なので、『団体割引』じゃないですけど、併修の場合は一人あたりのお布施が少し安くなるのが普通です。
でも、お布施に関してはお寺や霊園によってまったく違うので、申し訳ありませんがハッキリしたことは言えません。
併修にする仏様全員の塔婆を建てる
法事をするときには、一般的には『塔婆(とうば)』を建てます。



浄土真宗の場合は建てません。
塔婆は、故人の供養において重要な意味があるんです。しかも、塔婆を建てると、故人だけではなく建てた人自身にも大きなメリットがあるんですよ。塔婆に関する詳細は『塔婆(卒塔婆)って何なの?塔婆の意味と必要性を説明します』の記事をご覧ください。
ですから、お坊さんの立場としては、法事をするなら塔婆を建てることを強くおすすめしています。
そうなると、併修の場合、塔婆はどのように建てるのがいいのでしょうか。
併修の場合は、併修にする仏様全員分の塔婆を建てることが望ましいですね。併修する仏様が2名なら2名分の塔婆、3名なら3名分の塔婆を建てる、ということです。
最低でも施主はそれぞれの仏様の塔婆を建ててくださいね。
まとめ:単独でも併修でも、ちゃんと故人の供養をすることに意味がある
同じ年に複数の仏様の年回忌が重なってしまうのはよくあることです。
家が永く続くほど仏様の数も増えますから、年回忌が重なるのは自然な現象といえます。
そんなときは『併修(へいしゅう)』という方法で、複数の仏様を同時に供養してあげるのがいいです。
ただし、併修をする場合には
- 親戚には併修で執り行う旨を通知しておく
- お寺や霊園に併修が可能であるかを確認する
- 年回忌にあたる仏様だけを併修にする
- 三回忌まではなるべく併修にしない
- 一番早く命日を迎える仏様を基準にして法事の日程を決める
- 仏様が複数になれば納めるお布施は多くなる
- 併修にする仏様全員分の塔婆を建てる
という点に注意しましょう。
法事はそれぞれの仏様の命日に合わせて『単独』で行うのが基本です。
しかし、1年のうちに何回も法事をするのは大変ですから、複数の仏様を1回にまとめても大丈夫ですよ。
これは多くの人がやっていることで、供養の面でも特に問題はありません。
とにかく、単独でも併修でも『ちゃんと仏様を供養する』という気持ちを大切にしましょう。
※法事で施主をする人は、こちらの記事をご参考にどうぞ。