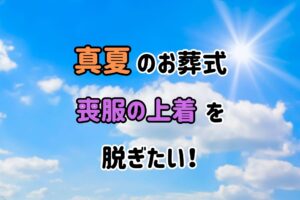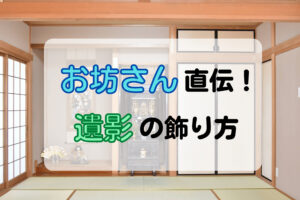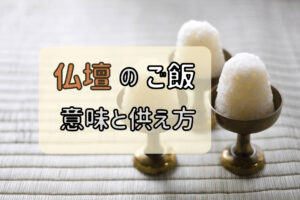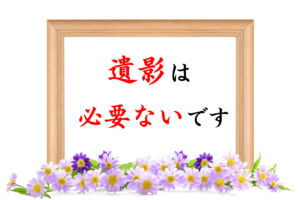- 『位牌分け』って何なの?あまり良くないことなの?
- どうやって『位牌分け』をすればいいんだろう?
- 『位牌分け』にかかる費用はどのくらい?
お葬式の後によく受ける質問の中の1つに『位牌分け』に関することがあります。
『位牌分け』とは同じ故人の位牌を複数作ることをいいます。
位牌分けの手順そのものはさほど難しいことはありません。
この記事では、位牌分けに関する考え方や手順、そして費用について解説しています。
迷うことなくスムーズに位牌分けができますので最後まで読んでみてください。
この記事を書いている僕『未熟僧(みじゅくそう)』は、お坊さん歴25年以上。仏事の疑問を解消するいろんな情報を発信しています。
位牌分けとは何?どんな意味があるの?
まずは『位牌分け』について説明します。
『位牌分け』とは何?
人が亡くなると、故人の戒名などが記された『位牌』を1つだけ作りますよね。
しかし、故人の位牌を1つだけではなく、複数作ることがあり、これを『位牌分け』といいます。
では、どんなときに『位牌分け』をするのでしょうか?
基本的に位牌を守っていくのは1人で、その人を『祭祀承継者(さいししょうけいしゃ)』といいます。
この『祭祀承継者』は、位牌だけでなく【お墓】や【仏壇】も1人で守っていく立場なんですよね。
なので、亡くなった人に子供が複数人いて、長男が『祭祀承継者』となった場合、他の兄弟姉妹は位牌などを守ることはしません。
しかし、他の兄弟姉妹にとっても故人は自分の親ですから、「自分の家にも親の位牌を置きたい」と思うことだって当然あるんですよね。
そこで、祭祀承継者以外の人のために、故人の位牌を複数作りそれぞれの家で安置する『位牌分け』という方法が生まれました。
位牌分けをすることで、祭祀承継者以外の人でも自宅で故人の位牌に手を合わせることができるようになったのです。
位牌分けをしても大丈夫なの?
『位牌分け』は、地域によっては『当たり前の慣習』になっています。
しかし、そのような地域以外の人にとっては、「同じ人の位牌を何個も作って大丈夫なの?」と心配になりますよね。
ご安心ください、位牌分けをすることは何の問題もないですから。
あなたは『分骨(ぶんこつ)』をご存じでしょうか?
分骨とは、字のごとく【故人の遺骨を分けること】なのですが、位牌分けもこれと似たようなものです。
分骨に関しては『故人の体をバラバラにしてしまうようなもの』という理由で、あまり良くないことだと言う人もいます。
しかし、分骨は昔から行われている立派な供養方法の1つです。そもそも仏教を広めたお釈迦様の遺骨だって、弟子達によって分けられていたんですからね。
それに、遺骨を分けることは法的にも全く問題ありません。
だから、2つとない故人の遺骨を分けることでも、みんな普通にやっているのです。
となれば、分骨と同じように、位牌を複数作る『位牌分け』という方法があっても何も問題はないわけです。
しかも位牌は、遺骨と違っていくつでも分けることができます。
ですから、位牌分けをすること自体はまったく問題ありません。
また、兄弟姉妹で信仰する宗派が違っても位牌分けは可能ですよ。仏教のどの宗派にも【位牌分けに関する決まり】なんてありませんので。
位牌分けをする理由
位牌分けをすることは特に問題はありません。
でも、位牌分けをする前に改めて【なぜ位牌分けをしたいのか】を考えた方がいいと思います。
位牌分けをするのは、
- いつでも故人を身近に感じ、手を合わせたい。
- 自宅から祭祀承継者の家またはお墓までが遠い。
といった理由が多いです。
お坊さんの立場としては、『いつでも故人を身近に感じ、手を合わせたい』という理由を大切にしてもらいたいです。
祭祀承継者だけに任せるのではなく「ぜひとも自分も故人のために手を合わせたい」と思うからこそ位牌分けをするんです。
ただ何となく「一応は兄弟姉妹みんなが位牌を持っておいた方がいいよね。」みたいな理由で位牌分けをするのはヤメましょう。
位牌分けをするからには、毎日ちゃんと位牌に手を合わせることは必須条件です。これができないのなら、位牌分けなんかしちゃいけません。
位牌は『故人の魂が宿るもの』であり『故人へ直接メッセージを伝えられるもの』です。
位牌分けをしたら、それぞれの位牌に故人の魂が宿り、それぞれの位牌から故人に向けていろんなメッセージを届けることができるんです。
だから、位牌を置くからには『毎日ちゃんと手を合わせる』ことをサボってはいけません。
決して『ただの慣習』とか『親戚に対する体裁』みたいな理由で位牌分けをしないでくださいね。
【関連記事】:位牌とは何なの?位牌の意味や必要性をお坊さんが解説します。
分けた位牌を【夫側の仏壇】に安置するときは要注意
どんなに『故人を想う気持ち』があるとしても、位牌分けをするときには注意すべきことがあります。
これは、主に『女性』の注意点です。
現在の日本では、結婚をした女性のほとんどは【夫側(嫁ぎ先)の姓】を名乗ります。
そして、もしも夫が『祭祀承継者』であれば、仏壇と位牌を守る立場にあるわけです。
そこへ、妻が【位牌分けをした自分の親の位牌】を勝手に夫側の仏壇に安置するとトラブルになるかもしれません。
もちろん、結婚をしたんですから、夫側の仏壇に妻の親の位牌を安置することは問題ありませんよ。
でも、【勝手に】というのはマズイかもしれません。
もともとは【夫側の家の仏壇】なので、そこへ妻側の仏様の位牌を置くなら、ちゃんと了承を得ておいた方が無難です。
夫や義父母はもちろんのこと、夫側の【口やかましい親戚】の了承くらいは得ておいた方が後々のトラブルがなくなります。
どこの家にも『面倒くさい親戚』ってのはいるもんです。とりあえず、面倒くさい人からカタをつけてしまいましょう。
それが終われば、後はもう堂々と夫側の仏壇に位牌を安置してあげてください。
未婚者には位牌分けをしない?
位牌分けには僕がイマイチ納得できない《謎のルール》があるんですよね。
それは、『未婚者には位牌分けをしない』というルールです。
既婚者でも未婚者でも【故人の子供】には違いないのに、なぜ未婚者には位牌分けをしないのでしょう?
どうやらですね、位牌というものは『代々にわたり大事に守り続けていくもの』であり、未婚者だと後を継いで位牌を守る人がいないからダメだ、という理由らしいです。
・・・何やねんそれ!?
位牌というのは『代々にわたり守り続けること』が大事なのではありません。
先ほど説明したような【位牌を祀ることの意味】を理解をして、故人を偲び心を込めて手を合わせることが一番大事なわけですから、既婚とか未婚とかは一切関係ないんです。
位牌は『故人を偲んで心を込めて手を合わせたい』という人に分けるべき。そして、それは一人だけである必要はまったくない。
故人だって、位牌を通じて自分の子供全員からのメッセージを受け取りたいと思うはずですよ。
べつに未婚で位牌を継ぐ人がいなくたっていいじゃないですか。故人のことを大切に思って手を合わせる人がいるのなら、そこに位牌があるのは当たり前のこと。
『位牌を受け継ぐこと』を重視するなんて、まったくの無意味です。
ということで、ちゃんと未婚者にも位牌を分けるべきです。
位牌分けをするタイミング
兄弟姉妹で話し合って、位牌分けをすることが決まりました。
では、その位牌分けはいつやればいいのでしょうか?
位牌分けをするタイミングとしては『49日忌』がいいですよ。
49日忌であれば、位牌を作製するまでの日数にも余裕がありますので、どんな位牌を作るかをじっくりと考えることができます。
それと、後ほど解説しますが、位牌を作ったら必ずお坊さんに供養をしてもらう必要があります。
そして、多くの場合、新しく作った位牌は49日忌法要のときに一緒に供養をしてもらいます。
もちろん、49日忌以外のときに位牌分けをしてもかまいません。
でも、位牌分けのために再度お坊さんを呼ばなきゃいけませんし、位牌を受け取るために兄弟姉妹がもう一度集まる必要があるので面倒ではあります。
位牌分けの手順
ここからは、位牌分けの手順について解説していきます。
位牌分けをする手順は、
- 位牌を必要な数(兄弟姉妹の人数分など)だけ作製する
- お付き合いのあるお坊さんに依頼して、全部の位牌に『位牌開眼供養(かいげんくよう)』をしてもらう。
- それぞれの自宅に持ち帰り、毎日ちゃんと手を合わせる。
この3つだけです。
位牌を必要な数(兄弟姉妹の人数分など)だけ作製する
まずは、仏具店に依頼して、必要な数だけ位牌を作製します。
依頼する仏具店は、あなたのお住いの最寄にある仏具店でもいいですし、あるいは、葬儀社から仏具店を紹介してもらうこともできます。
仏具店には、位牌だけではなく仏壇や数珠などあらゆる仏具が販売されているので見学してみてください。
また、最近ではインターネットでも位牌作製の注文ができるようになりましたので、忙しくて時間がない場合は利用してみましょう。
位牌を作製するときには、故人の、
- 戒名(法名)
- 故人の氏名
- 死亡年月日
- 故人の年齢
- 宗派
を仏具店に伝えておきます。
あとは、位牌の材質・サイズ・書体などを決めれば2~3週間くらいで出来上がります。
位牌作製にかかる費用については、2万円~5万円(税込)くらいが一般的です。
位牌を作るときは、事前にインターネットでいろんな位牌を見ておいて、どんなものをつくるのかを先にイメージしておくといいですよ。
お坊さんに依頼して、全部の位牌に『位牌開眼供養(かいげんくよう)』をしてもらう
位牌が出来上がったら、次はお坊さんに依頼して、全部の位牌に『位牌開眼供養(かいげんくよう)』をしてもらいます。
日頃からお付き合いのあるお寺があれば、そこのお寺のお坊さんに全部の位牌へ『位牌開眼供養』をしてもらいましょう。
お付き合いのあるお寺がなければ、葬儀社に頼めばお寺を紹介してくれますよ。
念のため言いますが、この『位牌開眼供養』は必ず行なってくださいね。
位牌を購入しただけでは意味がないんです。
位牌開眼供養をすることで【故人の魂が宿る】状態となり、あなたのメッセージが故人に届くようになります。
『位牌開眼供養』のときにお坊さんへ納める費用(お布施)は位牌1つにつき【3千円~1万円】くらいが相場でしょう。
ちなみに、開眼供養をする位牌の数が多いときは、例えは悪いですが『セット割引』みたいなカンジで少し安くなることが多いですよ。
とはいえ、費用についてはお寺によって全然違いますので、依頼するお坊さんに必ず確認をしてください。
それぞれの自宅に持ち帰り、毎日ちゃんと手を合わせる
位牌開眼供養が無事に終わったら、兄弟姉妹みんなでそれぞれ1つずつ位牌を自宅に持ち帰ります。
自宅に持ち帰り、仏壇があれば仏壇内に安置してください。仏壇がなければ、【位牌を祀るためのスペース】を作って、そこへ安置しましょう。
その後は、毎日、位牌に手を合わせるようにしてください。先ほども言いましたが、位牌分けをする以上は必ずこれをやってください。
位牌や仏像などは、ただの仏具ではなく仏様が宿ることができる『特別な仏具』です。
だからこそ、必ずお坊さんに開眼供養をしてもらうんです。
位牌を作ったら仏壇も必要なのか?
位牌分けをする人の中には【自宅に仏壇が無い】という人もいるでしょう。
位牌といえば『仏壇の中にあるもの』というイメージがありますよね?
では、位牌を安置するためには仏壇がなければいけないのでしょうか?
結論としては、仏壇が必要というほどではないですが、位牌を安置する場所としては仏壇が無難です。
仏壇の中には必ず『本尊様』がおられ、仏壇の中だけでなく家全体を守ってくださいます。
仏壇はご本尊様に守られた清らかな空間なので、位牌はできるだけ仏壇内に安置するのが理想的なんです。
それに、仏壇は【家族の誰かが亡くなってから購入する】というものではありません。誰も家族が亡くなっていなくても家に仏壇があってかまわないんです。
仏壇に関する詳しいことは、『仏壇の意味と役割とは?仏壇の準備からお参り方法まで丁寧に解説』の記事をご覧ください。
とはいえ、仏壇はそれなりに高価なものですし、置く場所だって確保しなくてはいけません。なので、仏壇があれば【理想的】ですが【必要】とまではいえません。
仏壇がなければ、【位牌を祀るためのスペース】を作って、そこへ祀りましょう。ちょっとした【座卓】や【テーブル】のようなものでもいいので『位牌を置く専用のスペース』を作ってください。
とにかく、位牌をそこら辺に置いてしまうのではなく、専用のスペースを設けて位牌を大切に扱うということを心掛けていれば、無理に仏壇を購入する必要はないと思います。
まとめ:位牌分けをするからには、毎日ちゃんと位牌に手を合わせましょう。
亡くなった人の位牌を複数作ることを『位牌分け』といいます。
位牌分けは、
- 位牌を必要な数(兄弟姉妹の人数分など)だけ作製する
- お付き合いのあるお坊さんに依頼して、全部の位牌に『位牌開眼供養(かいげんくよう)』をしてもらう。
- それぞれの自宅に持ち帰り、毎日ちゃんと手を合わせる。
ということをすればOKです。
ただし、位牌分けをしたからには、その後は兄弟姉妹みんなが毎日ちゃんと位牌に手を合わせるべきです。
ただ単に『位牌分けをした』というのでは何の意味もありません。
位牌には故人の魂が宿り、あなたと故人を結ぶ役割をしており、位牌を通じてあの世の故人にいろんなメッセージをお伝えするわけです。
なのに、それを何もせずに【ただ置いている】だけなら、位牌分け自体をすべきではないです。
位牌分けをする意味を理解した上で、兄弟姉妹のみなさんで位牌を作っていただきたいなと思います。
※位牌についてはこちらの記事も読んでみてください。