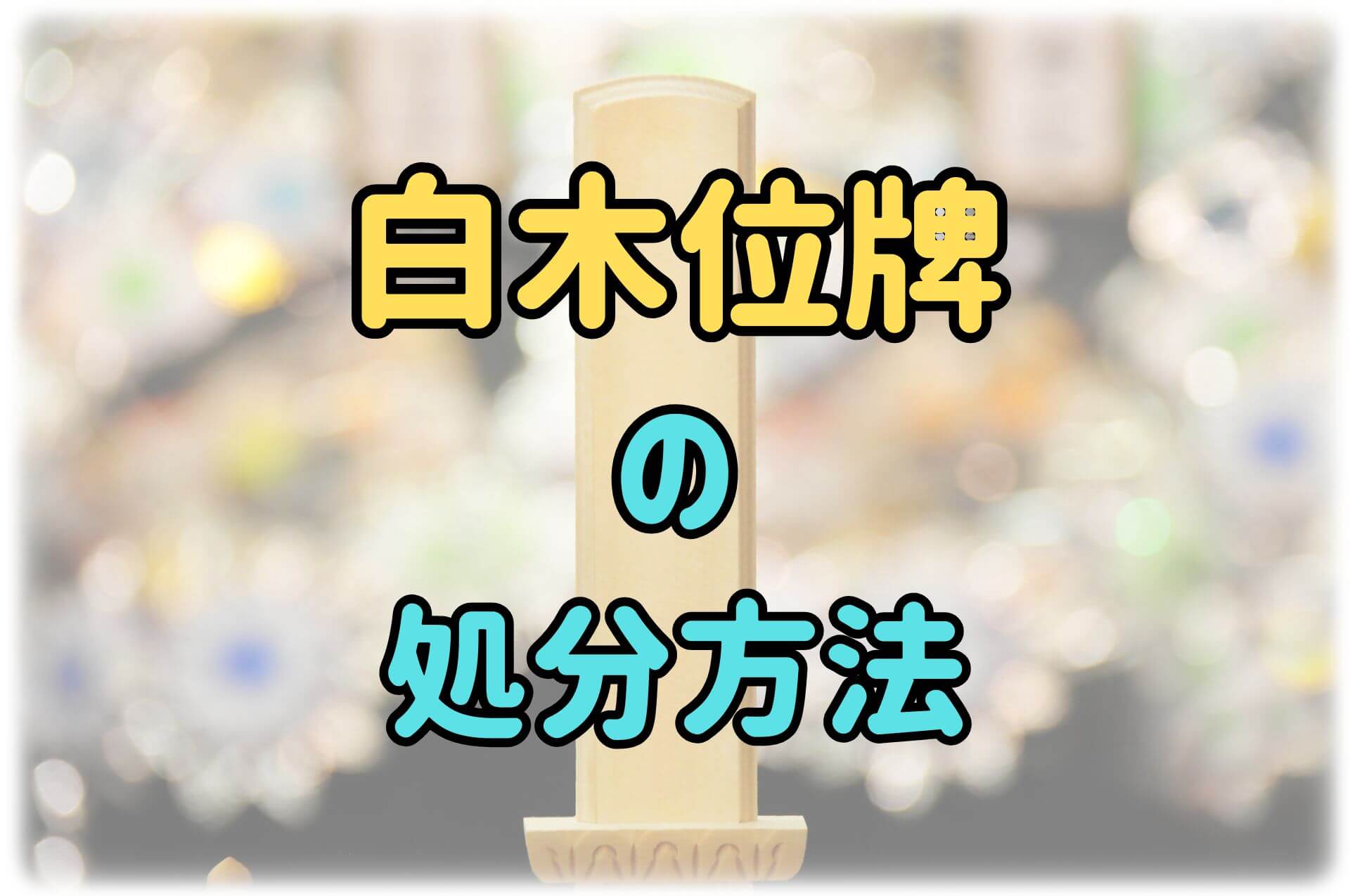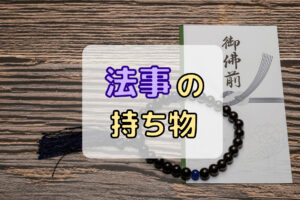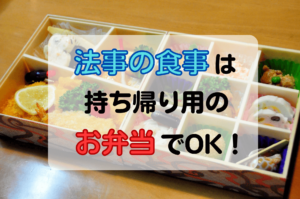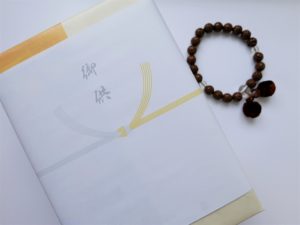- 白木位牌って何なの?
- 白木位牌の処分の方法を知りたい。
- 白木位牌の処分にかかる費用はどのくらい?
お葬式のときに祭壇中央に置かれている位牌を『白木位牌(しらきいはい)』といいます。
白木位牌はあくまでも一時的に使用する【仮の位牌】として扱い、いずれは処分する位牌です。
でも、処分をするといっても、その方法がわからないですよね?
結論を言うと、白木位牌の処分はお坊さんに任せるのが一番です。
この記事を読むと、
- 白木位牌(内位牌・野位牌)の意味
- 白木位牌の処分方法
- 白木位牌の処分にかかる費用
がわかります。
白木位牌を【適切な方法】で処分できるようになりますので最後まで読んでみてください。
 未熟僧
未熟僧白木位牌の処分は簡単なのでご安心ください。
この記事を書いている僕『未熟僧(みじゅくそう)』は、お坊さん歴25年以上。仏事の疑問を解消するいろんな情報を発信しています。
『白木位牌』って何?
お葬式のときには祭壇の中央に白木位牌が置いてありますよね?
白木位牌を使用するときに、
- 内位牌(うちいはい)
- 野位牌(のいはい)
の2つの白木位牌を使用する地域は多いでしょう。
もしかすると、
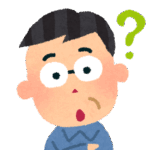
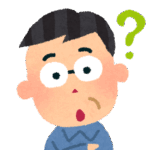
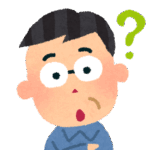
えっ、ウチのお葬式のときには白木位牌が1つだったけど?
という人がいるかもしれませんが、そのようなケースも多々ありますのでご安心ください。



同じ地域でも住職さんの考え方によって【お葬式で使用するもの】が違うんです。
もしも、お葬式で位牌が1つだけの場合、その位牌は『内位牌』です。
一般的に、お葬式で『白木位牌』と呼ばれているのは『内位牌』のことが多いです。
内位牌には、
- 戒名(または法名)
- 亡くなった年月日
- 俗名(故人の生前の名前)
- 年齢
といった故人の情報を筆で直接書き入れます。
内位牌は故人の遺影と一緒に祭壇の中央へ置かれます。
『内位牌』は四十九日忌までの【仮の位牌】
お葬式のときに使用した内位牌は、その後もずっと仏壇に安置するものではありません。
じつは、内位牌は49日間だけの『仮の位牌』として安置するものなんです。
内位牌が『仮の位牌』ということは、いずれは【本来の位牌】が必要となるわけです。
この【本来の位牌】のことを『本位牌(ほんいはい)』といいますが、どうやって内位牌から本位牌へ移行すればよいのでしょうか?
本位牌への移行は、お坊さんに依頼をしましょう。
四十九日忌法要のときにお坊さんへ依頼をしておけば、
- 内位牌の閉眼供養(魂抜き)
- 本位牌に開眼供養(魂入れ)
をしてくれますよ。
これによって、内位牌は【位牌としての役割】を終えて、本位牌が今後ずっとその役割を担います。
【関連記事】:位牌とは何なの?位牌の意味や必要性をお坊さんが解説します。
布の袋を被っている『野位牌(のいはい)』
白木位牌には、内位牌の他にも布の袋を被った位牌があります。
布の袋を被った白木位牌は『野位牌(のいはい)』といい、布の袋のことを【薄絹】や【わんぷ】と呼んだりします。
野位牌とは、墓地へ置きっぱなしにしておく位牌です。
昔は、お葬式が終わると、故人を納めた棺桶を火葬場や墓地へ運びました。



いわゆる『野辺送り(のべおくり)』と呼ばれるものです。
昔は土葬だったのでお葬式当日に埋葬を行うのが一般的でしたが、まだ墓石が建っていなかったり、墓石が建っていたとしても、そこには故人の戒名などの彫刻ができていません。
ですから、誰を埋葬したのかが見た目ではわからなくなります。
そこで、その場所に誰が埋葬されているのか分かるように野位牌を置いたのです。
つまり、「〇〇さんはココに埋葬されてますよ。」という【目印】の役割をしているのが『野位牌』というわけですね。
白木位牌の処分方法
開眼供養をした本位牌を安置するようになれば、もう白木位牌(内位牌)は位牌としての役目を終えることになります。
では、役目を終えた内位牌はどうやって処分すればいいのでしょう?
内位牌は、お坊さんに【お焚き上げ】をしてもらう
本位牌を作ったら内位牌は必要なくなるので、お坊さんに頼んで【お焚き上げ】をしてもらいましょう。
お焚き上げというのは簡単に言うと《焼却処分》のことですが、白木位牌を何もせずにいきなり燃やしてしまうのではありません。
お坊さんは、位牌を焼却する前に『閉眼供養(へいげんくよう)』という供養をします。



閉眼供養とは、要するに位牌を【ただの木の札】に戻す供養です。
内位牌の処分は、まず閉眼供養を行なって白木位牌を《ただの木の札》に戻し、それから焼却処分という方法がベストです。
位牌は、故人の魂が宿るための『依代(よりしろ)』ですから、お坊さんに閉眼供養とお焚き上げをしてもらうことが大事です。
とにかく、内位牌を【何もしないまま】で勝手に処分しないように注意しましょう。
野位牌の処分方法
野位牌は内位牌とは扱い方が異なります。
野位牌は、お墓が建てられたり墓石に故人の情報が彫刻された時点で必要なくなるので、不要となった時点で野位牌を閉眼供養するのが本来のやり方です。
しかし、野位牌は自然に朽ちるまでそのまま墓地に安置しておくことが多いです。
とはいえ、ボロボロになった野位牌をいつまでもお墓に置きたくない場合は、49日忌を過ぎたら撤去して問題はありません。
49日忌じゃちょっと早いと思うなら、1周忌くらいを目安にしてください。
野位牌を処分するタイミングについては地域の風習や住職の考え方によって違いますので、迷ったときはお寺や霊園に確認をしてみてください。



ちなみに、僕のいる寺では、野位牌を置いておくのは『新盆供養が終わるまで』としています。
閉眼供養が終わった位牌は可燃物として処分できる?
閉眼供養が終わった位牌は、厳密に言うと【ただの木の札】なので、一般の可燃物として処分できるという理屈になります。
そして、『廃棄物処理法』の観点から見ても位牌を可燃ゴミとして出すことに問題はありません。
ですから、閉眼供養が終わった位牌は、
- 自宅で焼却する※周囲に十分注意する
- 自治体が許すのであれば、決められた曜日に【可燃物】として出す
という処分をしてかまいません。
しかし、理屈ではそうかもしれませんが、実際にそんなことはできませんよね?
僕も今まで【可燃ゴミと一緒に位牌が置かれている】というのは見たことがありませんから、やはり位牌の処分はお坊さんに依頼するのがいいと思います。
白木位牌を処分するときの費用
白木位牌の処分をお坊さんにお願いするには費用がかかります。
お坊さんに納める費用は、
- 閉眼供養料
- お焚き上げ料
の2つです。
とはいえ、それぞれに袋を分ける必要はなく、両方を合わせて【お布施】と書いた袋に包んで納めれば問題ありません。
白木位牌の処分にあたり、お坊さんへ納めるお布施は、閉眼供養料とお焚き上げ料を含めて、
- 【白木位牌をお寺へ持って行く場合】:5千円~1万円
- 【お坊さんに自宅まで来てもらう場合】:1万円~3万円
くらいが相場です。
費用の面を考えても、基本的に白木位牌はお寺へ持って行って処分をお願いするようにしましょう。
まとめ:白木位牌の処分はお坊さん(お寺)にすべて任せてしまいましょう
仏具はどのように扱っていいものか、正直なところよくわからないですよね?
そんなときは、日頃からお付き合いのあるお寺、あるいはあなたの家の近くにあるお寺に聞いてみてください。
ほとんどのお寺では仏具の取り扱い方について説明してくれますし、もちろん、白木位牌の処分の方法も教えてくれます。
なんなら、そのお寺で【閉眼供養】と【お焚き上げ】をお願いしてしまいましょう。
もちろん費用は必要となりますが、仏具の処分をお寺に任せてばしまえば誰にも文句は言われることもなく、あなたもその方が安心でしょう。
『餅は餅屋』という言葉がありますが、『仏具はお寺』ということですね。
白木位牌もそうですが、【仏具の処分】はお坊さん(お寺)にすべて任せてしまうのが一番ですよ。
※法事の施主をするときはコチラの記事をご参考にどうぞ。