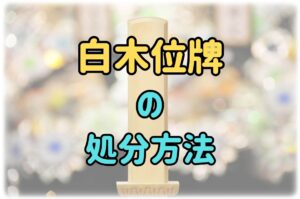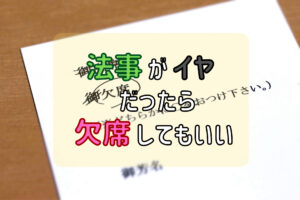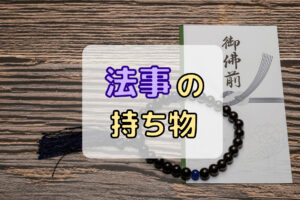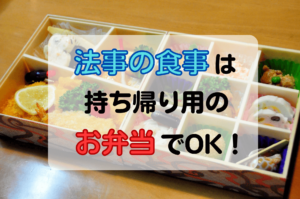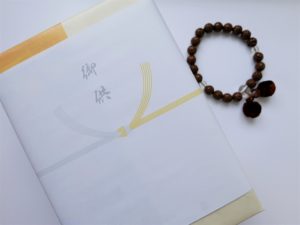- 法事の食事を無しにしたい。
- 法事の食事は必ずしないといけないものなの?
- 食事をしない場合はどうすればいいの?
法事のときには、参列者みんなで故人の話などをしながら食事(お斎)をします。
でも、施主となる人は食事の準備(手配など)をするのが大変なので、いっそのこと法事の食事を省略したいですよね。
とはいえ、省略したいと思っても「本当に食事なしでも大丈夫かな?」と心配になることでしょう。
結論を言いますと、法事の食事はしなくても問題ないので、あなたの自由にしてかまいません。
施主は他にもすべきことが山積みなんですから、省略できるものはドンドン削っていきましょう。
この記事は、法事の食事について【お坊さん側の意見】もふまえて書いていますので参考にしてみてください。
この記事を書いている僕『未熟僧(みじゅくそう)』は、お坊さん歴25年以上。仏事の疑問を解消するいろんな情報を発信しています。
お斎とは何?
法要の後に参列者に食事をふるまってもてなすことを『お斎(とき)』といいます。
お斎という言葉の由来は、仏教の『斎食(さいじき)』です。
斎食とは、修行をしている僧侶たちが食事をすることをいい、食事の時間になると僧侶たちが決められた場所に集まって『斎食儀』という作法をしてから食事をします。
このように、『斎食』というのは【僧侶の食事】をさす言葉なのですが、それがいつの間にか法事の食事に対しても使われるようになりました。
また、『斎食』は本来、【大地の恵み】や【仏様】に感謝をして食事をいただくことという意味なんですよね。
つまり、お斎(法事の食事)というのは、
- 大地の恵み
- 生前に故人から受けたご恩
に対して感謝をしながら食事をするという趣旨でなければなりません。
その趣旨をふまえた上で、次に、法事に来てくれた『参列者』や『お坊さん』へ感謝の気持ちを表すという意味が付加されます。
したがって、お斎(法事の食事)というのは【ただの会食】ではないわけです。
お斎(法事の食事)は必ずしないといけないの?
法事をするときには必ず『お斎』をしないといけないのでしょうか?
冒頭でも言いましたが、お斎(法事の食事)はしなくても問題ないです。
法事の目的は、故人を供養するために【法要を執り行うこと】であって【食事をすること】ではありません。
法要を執り行うことが最優先で、そこへ『お斎』という食事の場が付随しているだけです。
厳密に言うと、『法事』というのは《法要とお斎を合わせたもの》のことですが、法事の主な目的はあくまで【法要】です。
ですから、一番重要な『法要』をちゃんとしていれば、それ以外のものをするかどうかは、あなたが自由に決めてかまいません。
【関連記事】:法事をする必要性と意味。法事の注意点も合わせて解説します。
お斎をしない場合
お斎をするかどうかは、あなたの自由です。
となると、たぶんあなたは、
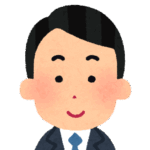
そうなのか、じゃあ、お斎は無しにしよう!
と思うことでしょう。
しかし、お斎をしないと決めたら、その代わりにいろいろと【やるべきこと】があります。
お斎はあくまで二次的なものではありますが、『ただ省略していいもの』というわけでもないのです。
事前に参列者へ食事がないことを通知する
お斎をしないという人は今でこそだいぶ増えてきましたが、それでもまだ「法事のときには食事をするものでしょ。」という考えの人は多いです。
なので、そのつもりで参列した人は、当日になってお斎がないと知ったら「えっ?食事しないの?」と思うことでしょう。
ですから、参列者には前もって【お斎をしない】ことを通知しておいた方がいいですよ。
しかも、あなた側の都合で食事を省くのですから、それなりに参列者にも納得のいくようにしなくてはいけません。
そこで、法事の案内をするときに【お香典は辞退させていただきます】と伝えるようにしておきましょう。
要するに、「食事はしないので、その代わり『お香典』とか『御仏前』は用意しなくていいですからね。」と伝えるのです。
法事に参列するときに包む『お香典』や『御仏前』には【自分の食事代は自分で負担させていただきます】という意味もあるんですよね。
それを予めご遠慮いただくことで参列者の負担を減らし、お斎を省くことに納得してもらうのです。
持ち帰り用の折詰弁当を渡す
事前に参列者へ、【食事をしないこと】と【お香典や御仏前は必要ないこと】を伝えればそれで大丈夫・・・とはいかないんです。
食事をしないとはいえ、参列者に対して何らかの形で【感謝の気持ちを表す】ことはしなくてはなりません。
そこで、参列者には返礼品と一緒に持ち帰り用の【折詰弁当】を渡すという人が多いです。
僕は、この【折詰弁当を渡す】というのは良い方法だなと思います。
なぜなら、お斎というのは、人によっては『面倒くさいもの』にもなるからです。
例えば、もしも親戚の中に『どうしても苦手な人』がいる場合、お斎があると、その人と法要だけでなく食事まで共にしなくてはなりません。
少しの時間なんだから我慢すればいいのですが、そう簡単に割り切れないのが人間の心理です。
どうしても苦手な人がいると、せっかくのお斎が【苦痛な時間】となってしまうかもしれません。
また、お斎には『参列者の時間をさらに拘束してしまう』という側面もあります。
お斎は、食事が始まってから終わるまで【1~2時間】程度はかかるので、参列者の中には「早く帰りたいなぁ。」と思う人もいます。
それに、法事の食事は参列者だけではなくお坊さんの時間も拘束してしまうのです。
お坊さんとしても、お斎に出ている時間があれば【別の家の法事ができる】ので、正直なところお斎に出るのは時間効率が悪いのです。
とはいえ、せっかくお斎の席に招かれたのですから、ありがたく出席させていただいています。
このように、お斎は施主側だけでなく参列者やお坊さんにとってもそれなりに大変なものなんですよね。
しかし、そんなお斎の《デメリット》を持ち帰り用の折詰弁当が解決してくれます。
折詰弁当を渡すことで、
- 食事の代わりの役割をする
- 参列者やお坊さんの拘束時間を減らす
- お斎の目的である『感謝の気持ち』を表す
ことができます。
折詰弁当は、ちゃんと『お斎』の要素を取り入れながら拘束時間も削減できる優れたものなのです。
【関連記事】:法事で食事をしない時は、持ち帰り用のお弁当を渡すのがベスト!
少し高級な返礼品だけを渡すのも可
僕は、お斎の代わりに折詰弁当を渡すことを推奨しますが、折詰弁当にもやはり《デメリット》があります。
それは、
- 弁当なので消費期限が短い
- 電車などに乗る時に【弁当の匂い】がする
- 荷物になる
ということです。
このようなデメリットがあるので、折詰弁当ではなく『少し高級な返礼品だけを渡す』という人もいます。
お斎がなく折詰弁当も渡さない代わりに、一般的な返礼品ではなく『少し高級な返礼品』を渡すのです。
お斎や折詰弁当のような『食べ物』ではなく、『食べ物以外のもの』を渡すことで参列者に感謝の気持ちを表しているわけです。
ただし、食べ物ではない返礼品ということは、厳密に言えば【お斎の代わり】ではなくなります。
なぜなら、お斎は【斎食】が由来なので、最低でも食事に関するものでなければならないからです。
とはいえ、人によっては『少し高級な返礼品』の方が嬉しいかもしれませんので、食べ物にこだわらなくてもいいかもしれませんね。
返礼品の種類は本当にたくさんありますので、なるべく【かさばらないもの】や【軽いもの】を選ぶとよいでしょう。
ちなみに、ここ5年くらいで急増している返礼品は、『カタログギフト』です。
返礼品って、何にしようかといろいろ考えるのがけっこう面倒ですが、カタログギフトなら相手が品目を自由に選択できますし、持ち帰るときにもコンパクトで非常に便利。
何より、カタログギフトなら【施主の負担】を減らせるので、返礼品を何にするか迷ってしまったら、思い切って『カタログギフト』にしてしまうのもアリですよ。
というか、返礼品だけを渡すのであれば、僕はむしろ【カタログギフト一択】くらいに思っています。
参考までに、カタログギフトの価格帯としては、5,000円程度のモノがよく選ばれています。
※業界トップクラスの品揃えのカタログギフトはこちら
カタログギフトのハーモニック〈公式サイト〉お坊さんには【お膳料】を包む
お斎をしない場合、お坊さんに対しては何をするべきでしょうか?
この場合はいくつか選択肢があります。
僕の今までの経験では、
- 【お膳料】を包む
- 参列者と同じ返礼品を渡す
- 何も無し(=お布施だけを渡す)
のどれかです。
そして、お斎がない場合、圧倒的に多いのが【お膳料】を包むことです。
ですから、あなたも法事でお斎をしないのであれば、お坊さんへ5,000円〜10,000円程度の【お膳料】を渡せば大丈夫です。
返礼品については数年前まではよくいただきましたが、最近ではその回数が減ってきています。
また、返礼品をいただく時は、先ほども言いましたように『カタログギフト』が多くなってきています。
最後に、じつは意外と多いのが、お斎がない場合はお坊さんに『お布施だけを渡す』というケースです。
つまり、折詰弁当も返礼品も無しということです。
あっ、勘違いしないでほしのですが、僕はべつに「お布施の他にも何かくれ」と言っているのではありませんよ。
お坊さんには『お布施』だけを渡せば、もうそれで十分な感謝の気持ちの表れになっていますよ、と言いたいのです。
まとめ:お斎はしなくても問題ない
お斎は、参列者やお坊さんへの感謝の気持ちを表し、おもてなしをするために食事をふるまう席です。
昔は、法事をすればほとんどの場合はお斎がありましたが、近年では【お斎をしない】という人が増えてきています。
これは別に、参列者やお坊さんへの感謝の気持ちがないというわけではありません。
食事の席をもうけることは、場合によっては【参列者やお坊さんの時間をさらに拘束してしまう】ことにもなります。
食事をふるまうことだけが『感謝の気持ちを表す方法』ではありません。
感謝の気持ちを表すのであれば、【折詰弁当】や【返礼品】という形でも問題はありません。
事前に【法事の食事がないこと】を通知しておき、食事に代わるものをきちんと用意していればお斎はしなくても問題ないです。
法事が毎回大変なものだと法事そのものをしたくなくなりますので、施主はもう少しラクをしてもいいと思いますよ。
できるだけラクをして、その代わりに《法事を続ける》ということを心がけてほしいと思います。
※業界トップクラスの品揃えのカタログギフトはこちら
カタログギフトのハーモニック〈公式サイト〉