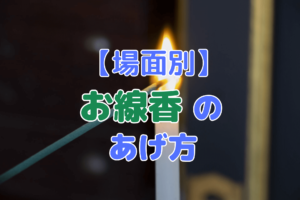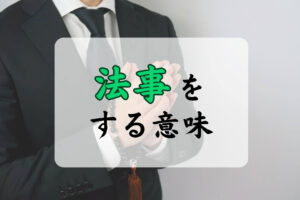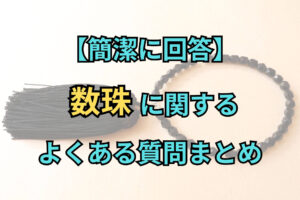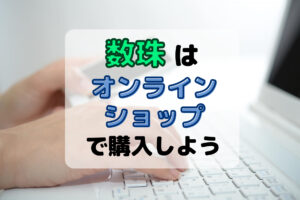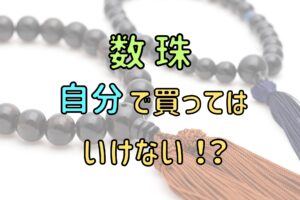- 数珠って何のために持つの?
- 数珠の使い方(持ち方)が分からない。
- お葬式や法事に参列するときに、べつに数珠がなくてもいいんじゃないの?
あなたが、お葬式や法事に参列するときに必ず持っていくモノは何ですか?
『御香典』や『御仏前』の他にもまだありますよね?
そうです、『数珠(じゅず)』です。
数珠は仏事に欠かせないものですが、じつは残念なことに『仏事で持って行くのを忘れてしまう物』の第1位なのです。
数珠を持つことにはとても大事な意味がありますので、お葬式や法事のときには必ず持って行くようにしましょう。
この記事では、
- 数珠を持つことの意味
- 数珠はどのように使う(持つ)のか
- 数珠の必要性
について詳しく書いています。
数珠の重要性や使い方が分かり、大事にしようという気持ちになりますので最後まで読んでみてください。
この記事を書いている僕『未熟僧(みじゅくそう)』は、お坊さん歴25年以上。仏事の疑問を解消するいろんな情報を発信しています。
数珠とは何か?
多くの人が一度は手にしたことがある『数珠(じゅず)』。
お坊さん以外で、数珠の意味や正しい使い方をちゃんと知っている人はあまりいません。
でも、せっかく数珠を持つのなら、数珠がどういうもので、どう使うのかを知っておきましょう。
数珠は【回数】をカウントする道具
『数珠』には別の呼び方があって、『念珠(ねんじゅ)』ともいいます。
『念珠』は、【念仏】の回数をかぞえるための【珠】という意味です。
仏様の名前をお唱えすることを『念仏(ねんぶつ)』といいますが、念仏に没頭すると、自分が何回お唱えしたのか分からなくなってしまうんですよね。
そこで、念珠を使って【1回お唱えしたら指で珠を1つズラす】という方法で数を正確にカウントするのです。
なので、要するに数珠は【回数】をカウントする道具なんですね。
もちろん、僕もお経を読みながら回数をカウントするときには念珠を1つずつズラしています。
数珠の作法としてそのような決まりがあるので、もしも今度お葬式や法事などに参列する機会があれば、こっそりとお坊さんの左手に注目してみてください。※宗派によってはしないかもしれません。
珠の数が【108個】ある
数珠には他にも意味があります。
数珠には本来、珠の数が《108個》あるのですが、これは私たちの煩悩(ぼんのう)の数に合わせています。
煩悩とは、私たちの中にある『さまざまな苦しみの根源となるもの』のことをいい、仏教では、とにかくこの煩悩を取り除くことの重要性を説いています。
したがって、数珠を持つことで『自分の中にある108個の煩悩を消していくぞ!』という精進(しょうじん)の心を表しているのです。
お寺で大晦日に行われる『除夜の鐘』も、鐘を打つ回数は108回と決まっていますが、これも同じ理由です。
また、ずっと数珠を持ち続けることによる効果もあります。
数珠を持ち続けて日々の精進につとめた結果、数珠に仏様のチカラが宿り、数珠を持つ人を守り清めてくれるともいわれます。
お坊さんの僕としては、数珠を持つ意味はこれが最も重要な部分だと思っています。
【108個】は、あくまで《正式な数》というだけ
数珠の玉の数が108個と聞くと、
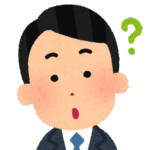
えっ?自分の持ってる数珠は、どう見たって珠が108個も無いけど、これじゃ意味がないの?
と思う人もいるかもしれませんが、心配しなくて大丈夫。
珠が108個ある数珠は、『本式念珠(または本連念珠)』とよばれる、僕たちお坊さんが使うような正式な数珠です。
下の画像のような数珠が本式念珠です。


もちろん、お坊さんではない人でも本式念珠を使っても大丈夫ですし、珠が108個ある数珠を持つのが本来なので、より丁寧でもあります。
しかし、もっと簡単な、珠の数が【54個】や【22個】または【18個】というような『略式念珠(または片手念珠)』とよばれる数珠を使っても全く問題ありませんよ。
略式念珠というのはこういう数珠です。


略式念珠とは、本式念珠を『簡略化』して、なおかつ数珠に宿る仏様のチカラを『集約化』したものです。なので、略式と本式のどちらでも数珠を持つ意味はまったく同じです。
また、多くの略式念珠はどの宗派でも対応できる作りになっているため、ほとんどの人は略式念珠を1つ持っていれば十分です。
ちなみに、1つの数珠を他の人と貸し借りして使うはやめましょう。
先ほども言いましたが、数珠というのは使う人の精進の末に仏様のチカラが宿り、数珠の持ち主を守り清めます。
数珠を借りるのは、自分以外の人が築き上げた《仏様のチカラ》を横取りするようなものです。
貸し借りが絶対にダメというわけではないですが、好ましいことではないので、ちゃんと【自分専用の数珠】を購入して使うのがベストです。
数珠は【1,500円以上】のものを選べばある程度品質のよいものが買えますので、どんな数珠を買えばいいのか迷ったら、以下の記事を参考にしてみてください。
数珠の使い方(持ち方)
数珠の基本的な使い方(持ち方)について説明をします。
数珠の使い方は宗派によって違いますので、基本的には自分の家の宗派のやり方に従ってください。
とりあえず、この記事では一般的な使い方を説明します。
数珠を使うときは、原則として、
- 数珠を手に持って移動するときは、【左手】で持つ。
- お経をお唱えしたり、仏様にお参りするとき、または故人を偲んで供養するときは、【数珠を左手にかけ、そこへ右手を添える】ようにして手を合わせる
ということを覚えておいてください。
次に、左手へのかけ方について詳しく説明します。
まず、本式念珠(珠が108個)の場合は、『浄明玉』という小さな玉がある方の親玉(大きな珠)が上にくるようにして、それを【左腕】にかけます。
数珠の房は、腕の内側と外側のどちらに垂らしてもかまいません。
そして、略式念珠の場合は、房が小指の下に垂れるようにして、左手の【親指と人差し指の間】にかけます。
僕はさっきから、数珠は【左】ということを強調していますが、それには理由があります。
じつは、仏教では左手が私たち人間を象徴する方の手なのです。
数珠には仏様のチカラが宿るため、左手に数珠を持つことによって、数珠に宿った仏様のチカラで私たちを清めてもらうわけです。
ただし、略式念珠では両手の親指と人差し指の間にかける場合もありますので、基本的な数珠の持ち方を押さえつつ、その場に応じて変えてかまいません。
ここで1つ、数珠の取り扱いの注意点があります。
数珠は神聖なものなので雑に扱わないでください。
お葬式や法事で使い終わったら、帰宅するまでは喪服のポケットやバッグに入れておきましょう。
ときどき食事の席などで数珠をテーブルの上に置きっぱなしだったり、椅子の上に置いている人までいます。
でも、それは数珠を汚したり紛失する原因になるので使い終わった数珠はすぐにしまっておきましょう。
そして、帰宅したら、できるだけ早く、
- 数珠袋に入れておく
- 木箱に入れておく
などしてから、直射日光の当たらない場所で保管をしてください。
数珠は『必要』というわけではない
今さらですが、じつは、お葬式や法事のときに数珠が【必要】というわけではありません。
数珠というのは《仏式》の供養を行うときに使うものであり、キリスト教やイスラム教など他の宗教で使うことはありません。
自分の信仰する宗教が仏教ではないのなら無理に数珠を買う必要はないです。
では、仏教を信仰する人は数珠を持つ必要があるのでしょうか?
じつは、「必要か?」と聞かれると、答えは【NO】です。
数珠を持つのは、数珠に宿っている仏様のチカラで自身を清める、ということです。
お葬式の場合であれば、故人に対する【敬意】と【感謝】を表すために数珠を持ち、自身を清めて、それからお焼香をします。
ですから、意地悪を言うようですが、故人に対する敬意と感謝の気持ちがあまり無ければ、べつに数珠なんて持たなくてもいいんですよね。
とはいえ、特に信仰する宗教がなく、なおかつ数珠を持っておこうかどうか《迷っている》としたら、数珠を持っておいた方が無難です。
社会人になればお葬式に参列する機会はありますから、ちゃんと数珠を持っておけば、いざというときでも慌てなくてすむので安心じゃないですか?
「自分は数珠を持たないぞ!」という強い信念があるなら話は別ですが、そうでなければ【社会人のマナー】として数珠を持っておくことをおすすめします。
【関連記事】:数珠を買うにはどこへ行けばいいのか。数珠の購入場所を詳しく紹介
まとめ : 数珠の意味と使い方を知っておきましょう
お葬式や法事のときには数珠を使います。
数珠は【回数をカウントする道具】でもありますが、数珠に宿った仏様のチカラによって【自分の身を清める】という重要な意味があります。
そして、略式念珠の使い方については、房が小指の下に垂れるようにして、左手の【親指と人差し指の間】にかけるようにしてください。
数珠は必要というものではありませんが、特別なこだわりがなければ『社会人のマナー』として1つは持っておいた方がよいと思います。
※数珠に関するいろんな質問をこちらの記事で回答しています。