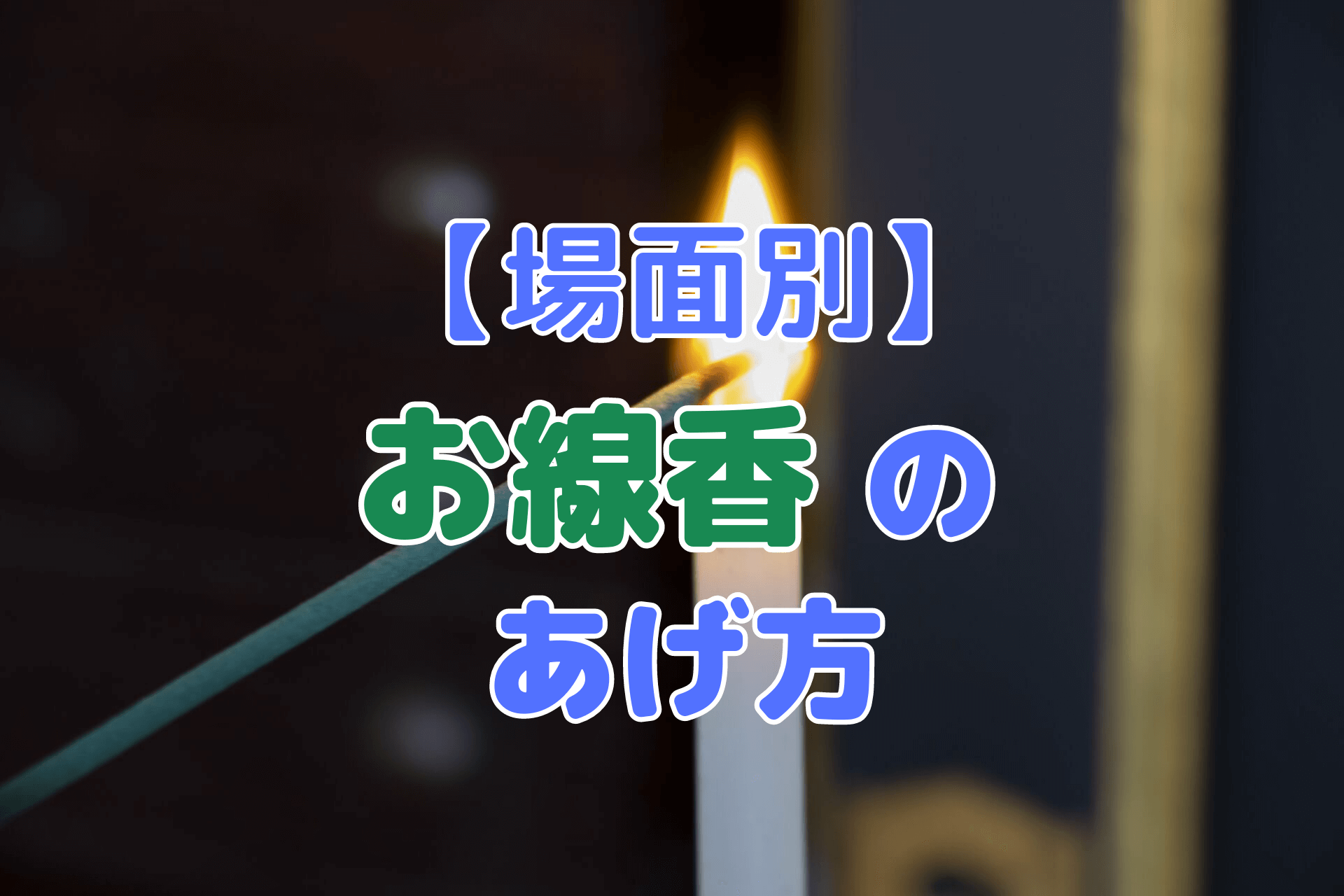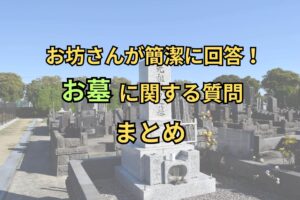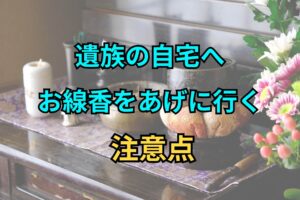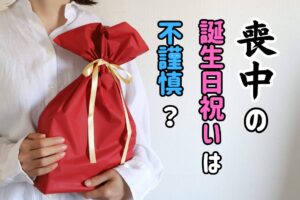- お線香をあげる意味って何だろう?
- お線香のあげ方やマナーを知りたい。
- 恥をかかないようにお焼香の作法も確認しておきたい。
お線香をあげる場面といえば、
- お仏壇参り
- お墓参り
- 法事
- お葬式
などです。
あなたも今までにこのような場面でお線香をあげたと思いますが、そのときに、
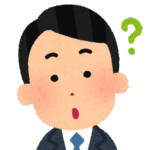
このやり方でいいのかな?
と心配になりませんでしたか?
じつは、お線香のあげ方やマナーは【場面】によって少しだけ変わりますので注意しましょう。
この記事では、『お線香のあげ方』について場面別に詳しく紹介しています。
どんな場面でも自信をもってお線香をあげられるようになりますので最後まで読んでみてください。
この記事を書いている僕『未熟僧(みじゅくそう)』は、お坊さん歴25年以上。仏事の疑問を解消するいろんな情報を発信しています。
お線香をあげる意味
お線香を燃やすと、周辺によい香りが広がります。
お線香は原材料となる木の種類によって香りが違いますし、ものによっては意図的に香りを加えていたりもします。
そんなお線香から出てくる【香り】ですが、じつは非常に重要な意味があるんです。
お線香から出る【香り】は仏様の食べ物
仏教では、お線香を燃やしたときに出る【香り】が仏様の食べ物になるとされています。
これを『香食(こうじき)』といいます。
厳密に言うと、お線香だけではなく、お焼香などのあらゆる【お香】の香りが対象です。
つまり、焼香をしたり、お墓や仏壇へお線香を供えることは、亡くなった人や仏様に、お食事をしてもらうという意味があるのです。
ですから、お墓や仏壇でお線香を供えている所を【香炉(こうろ)】といいますが、この部分は亡くなった人や仏様の『お口』と同じと考えていいでしょう。
香炉は線香の燃え残った灰ですぐに汚れてしまうので、こまめに掃除をしてください。
これは、私たちが日頃している【歯みがき】みたいなカンジですね。
【香り】でニオイ消し
あなたもご存じのように、仏教の発祥地であるインドは暑い国です。
それは、お釈迦様のいらした時代も同じでした。
ですから、お釈迦様は、陽射しの強い屋外よりも【日陰のある涼しい場所】とか【雨風をしのげる部屋の中】で教えを説いたのです。
でも、部屋の中に人が集まると、どうしてもニオイがこもってしまいます。そして、たぶんそれは、体臭というか、良いニオイではなかったはず。
しかも当時はクーラーの効いた部屋なんてありませんから、なおさらのこと。
そこで、お香をたいてその場のニオイをごまかしたのです。要するに、当時のお香というのは【芳香剤】の代わりだったんですね。
【香り】は清めるためのもの
僕たちお坊さんは、法要を始める前に『塗香(ずこう)』というお香を体に塗ります。(※宗派によっては塗らないかもしれません。)
これは、お香を身体に塗ることで、自分の身体を清めているんです。
じつは、お香には清めるチカラがあると考えられています。
仏様の前でお経を読んだり、いろんな作法をするにあたり、まずはお坊さんが自分自身を清めなければなりません。
他にも、仏具や経本をお香の香りに触れさせて清め、法要のある日は、前もって本堂でお香を焚いて本堂全体を先に清めておきます。
また、お香の香りは空間やモノだけではなく私たちの【心】も清めてくれます。
あなたも、お香の匂いを嗅ぐと何となく気持ちが落ち着いたり、心が洗われるような気になりませんか?
それは、お香の匂いや煙が、少し時間がたつとスッと消えて無くなるように、私たちの穢れを洗い落とし、身も心も清めているからです。
【場面別】お線香のあげ方とマナー
お線香のあげ方は、場面によって少しだけ違います。
お線香をあげるのは、
この4つの場面が多いので順番に紹介していきます。
【※注意】:お線香のあげ方に絶対的な決まりはないので、少しくらい間違えても大丈夫です。ただし、どの場面においても『お線香の火を口で吹き消さない』という点には注意をしてください。
お仏壇参りの場合
お線香をあげる機会が一番多いのは、自宅の【お仏壇参り】のときです。
お仏壇参りには一応の作法がありますので、作法と合わせてお線香のあげ方を紹介します。
お仏壇参りでのお線香のあげ方は以下のとおり。
- 仏壇に向かって一礼をしてから、お花・お水・お供物を供える。
- ロウソクに火をつける。
- 改めて仏壇の前で姿勢を整える。
- 左手に数珠を持ち、合掌をする。
- お線香を手に取って(本数は後述します)火をつける。
- 空いている方の手で仰ぎ、お線香の火を消す。
- お線香を、香炉の中央または左奥から立てる。
- もう一度、合掌をする。
- お鈴を鳴らし、お経をお唱えする(お唱えできる人だけ)。
- ロウソクの火を消す。
- 一礼をして仏壇の前から退く。
多くの人がやっていますが、仏壇の前に着いていきなりロウソクの火をつけ始めてはいけません。まずは一礼、それから仏壇参りの準備をして、最後にお仏壇参りという流れです。
続いて、もう少しツッコんだ話をします。
毎日のように仏壇へお線香をあげていると、いろんな疑問が出てきませんか?
例えば、
- お線香の本数に決まりはあるのか
- お線香をあげるときは『立てる』のか『寝かせる』のか
- 長いお線香の場合は、折ってもいいのか
などです。
これらは実際に僕が受けた質問なので、この機会に解説します。
お線香の本数に決まりはあるのか
お線香については『お線香は何本あげればよいのか?』という質問が1番多いです。
この質問の答えは、『本数に決まりはない』となります。
ただし、本来なら『本数に決まりはない』のですが、実際のところは宗派によって本数がある程度決まっています。
各宗派の本数は以下のとおりです。
- 【浄土宗】1~2本
- 【浄土真宗(本願寺派)】1本
- 【浄土真宗(大谷派)】1本
- 【天台宗】3本
- 【真言宗】3本
- 【臨済宗】1本
- 【曹洞宗】1本
- 【日蓮宗】1本
日頃のお仏壇参りのときには、あなたの家が属している宗派の決まりに従ってお線香をあげてください。
お線香をあげるときは『立てる』のか『寝かせる』のか
仏壇へお線香をあげるときには、お線香を『立てる』のか『寝かせる』のか、という疑問も出てきます。
お線香を立てるか寝かせるかについては、これはどちらでもかまいません。
とはいえ、これも宗派によって違ったり、お線香を供える『香炉』の大きさや形状によっても変わります。
私たちがよく目にする香炉の縁が丸いタイプはお線香を『立てる』ことがほとんどですし、浄土真宗の場合はお線香を寝かせるのが基本です。
他にも、ときどき聞かれるのは、



3本のお線香を立てる場合、それぞれ1本ずつ離して立てるのですか?それとも3本を一つにまとめて立てるのですか?
ということです。
複数のお線香を【離す】か【まとめる】かというのは、これもどちらでもかまいません。
ただ、お線香をあげる人が他にもいる場合は、まとめてあげた方が後の人のジャマにならないので親切です。
ちなみに、縁が丸い香炉であったとしても、大きめの香炉であればお線香を横に寝かせても全く問題ありません。
もしかすると、あなたの家にある香炉は《長方形》でしょうか?香炉が長方形の場合はお線香を寝かせるようにしてください。
長方形の香炉は【お線香を寝かせる】ことを前提に作られており、深さがあまりないため、お線香を立てること自体が難しいです。
長いお線香の場合は、折ってもいいのか
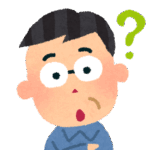
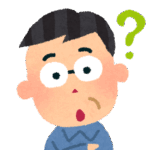
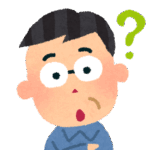
香炉が少し小さいから、お線香を折ってもいいでしょうか?
じつは、つい最近もこのような質問されましたが、お線香が長い場合は折って供えても大丈夫です。
香炉が小さいと、お線香を立てた後に燃えた灰が香炉の外に落ちてしまうことがあります。
また、最悪の場合、火のついたお線香そのものが香炉の外に倒れてしまい、それが原因で火災が発生するケースもあります。
ですから、お線香は折ってから立ててもいいですし、折ったお線香を寝かせてもいいですよ。
先ほども言いましたが、お香の【香り】は仏様の食べ物なので、仏様が食べやすいように【小分けにした】というふうに考えましょう。
ちなみに、浄土真宗ではお線香を『二つに折って横に寝かせる』という決まりがあります。
また、他の宗派でもそうだと思いますが、お香を供えるときには香炉の中の灰に溝を作り、その溝へ粉末のお香を流し込み、最後にお香の左端に火をつけるのです。
まぁまぁ面倒くさい作業なのですが、僕の修行時代は毎回こうやってお香を供えていました。
お墓でも仏壇でもそうですが、お線香を横に寝かせて供えるのは、このような【本来のお香の供え方】が元になっているからです。
お墓参りの場合
お仏壇参りの次にお線香をあげる機会が多いのは、お墓参りです。
お墓参りでのお線香のあげ方を、お墓参りの作法と合わせて紹介すると以下のとおり。
- 墓地へ入る前に一礼する。
- 墓地全体の掃除をする。
- お水を供える。
- お花を供える。
- お供物を供える。
- ロウソクに火をつけて供える(必須ではない)。
- お線香に火をつけ、お参りする人数に合わせてお線香を分ける。
- 1人ずつ、お線香を【火のついている方を左側】にして香炉に供える。
- 左手に数珠を持ち、お墓の前で合掌をする。
- お参りが終わったら、後かたづけをする。
- 最後に墓地の前で一礼してから、その場を離れる。
お墓参りの場合は、お線香の【量】に注意をしてください。
お墓にあげるお線香は1束か2束で十分です。たまに、1人につき1束必要だと思っている人もいますが、それだと量が多すぎて香皿に収まりません。
しかも、大量のお線香があると、お線香から火が出やすくなり、その熱で石製の香炉を割ってしまうことがあるんですよね。
お墓参り用のお線香は、数十本のお線香が1束にまとまっているので、それをお参りをしている人数で均等に分ければOK。
ちなみに、お仏壇のときとは違って【宗派ごとの本数の決まり】を気にする必要もありませんので、もしも1束持って行ったのなら、それを全部供えてください。
また、お墓参りでお線香をあげるときには、もう1つ注意点があります。
それは、お線香の【向き】です。
お線香を寝かせて供える場合は、お線香の火がついている方を【自分からみて左側】にするという作法があります。
これは、右側が仏様を象徴するため、左からお線香を燃やすことで【悟りに近づく】様子を表しているんです。
とはいえ、これは作法というほどではありませんので、覚えていたらやってみてください。
法事の場合
お線香は法事の最中にも使います。
基本的に、法事の場合は『お焼香』を使うのですが、法事をする場所が【施主の自宅】や【お墓の前】の場合はお線香を使います。
法事でのお線香のあげ方は、施主の自宅なら『お仏壇参りの場合』と同じで、お墓の前なら『お墓参りの場合』と同じです。
法事の場所が【施主の自宅】である場合
まずは、法事の場所が【施主の自宅】である場合から紹介します。
- 施主がお線香をあげ始めたら、少し正座を崩して血流を復活させる。
- 自分の番が来たら、仏壇の前まで行き、施主とお坊さんに一礼。
- 仏壇の方を向いて合掌をする。
- お線香を1本だけ手に取り、ロウソクで火をつける。
- 線香についた火を、空いている手で仰ぎ消す。
- 香炉の左奥へお線香を立てる。
- お鈴を鳴らし、左手に数珠を持って合掌する。
- もう一度、施主とお坊さんに一礼する。
- 自席に戻る。
ポイントは、お線香を《香炉の左奥》に立てるというところです。
お線香を香炉の中央に立ててしまうと、後の人がお線香を立てるときのジャマになります。そして、人間の90%は『右利き』なので、後の人がお線香を立てやすいように右側を空けておくわけです。
つまり、これは仏教的な作法ではなく他の人に対する【配慮】ですね。
また、お線香を1本だけ立てるのも、他の人がお線香をあげやすいという理由だけでなく【煙の量を減らす】ことが目的なので、これも他の人に対する【配慮】です。
さらに言うと、お線香はなるべく【垂直に立てる】ように意識してください。傾けて立てると、燃えた灰が香炉の外に落ちてしまい、香炉の周辺が灰だらけになります。
灰だらけになった所を掃除するのは施主ですから、これは施主に対する【配慮】です。
法事の場所が【お墓の前】である場合
続いて、法事の場所が【お墓の前】である場合を紹介します。
法事を【お墓の前】で行う場合は、
- 法要の途中で、火のついたお線香が参列者に配られる。
- 配られたお線香を持って、自分の順番を待つ。
- 自分の順番が来たら、お墓の前まで行き、施主とお坊さんに一礼。
- お墓の香炉にお線香を供える。
- 左手に数珠を持ち、お墓の前で合掌をする。
- もう一度、施主とお坊さんに一礼。
- 元の場所に戻る。
という流れになります。
ここでポイントとなるのは、お線香を寝かせて供えるときの【向き】です。
先ほども言いましたように、本来ならお線香は火がついている方を【左側】にして供えた方がいいです。
しかし、もしも施主が【右側】に供えた場合は施主に合わせてください。
原則として、お線香のあげ方に絶対的な決まりはないので、施主に恥をかかせないよう臨機応変に合わせてあげましょう。
それに、施主と反対向きにお線香をあげると、供えられたお線香の両端から燃えてしまい、やたらと煙が出ます。
また、自分の後にもお線香をあげる人がいる場合は、少し早めにお参りをするのがいいと思います。
火のついたお線香は、順番待ちをしている間もどんどん燃えていきます。すると、順番が後の人たちはお線香が短くなり、燃えた灰で服が汚れますし、線香を持っている手も熱いんですよね。
心を込めてじっくりと手を合わせることは大事ですが、法事など多くの人がお線香をあげるときには、後の人に対する配慮も大事です。
お葬式の場合
お線香は、お葬式でも供えます。
ただし、お葬式でお線香をあげるのは『式の始まる前』です。
お葬式の場合、式が始まるまでは祭壇の前でお線香をあげられるようになっています。
ですから、式場について受付などを済ませたら、まずは祭壇前でお線香をあげてください。
このときには、
- まずは喪主に挨拶をし、お悔やみの旨を伝える。
- 祭壇前に移動し、故人に向かって一礼をする。
- お線香を1本だけ手に取り、火をつける。
- 空いている手でお線香の火を消し、香炉の左奥に供える。
- 左手に数珠を持ち、合掌をする。
- もう一度、故人に向かって一礼をする。
- 余裕があれば、故人の顔を見てあげる。
という流れでお線香をあげましょう。
注意点としては、喪主と話し込み過ぎないということです。
家族を亡くした喪主に対して、いろんな言葉をかけてあげたいのは分かりますが、他にも参列者がいることをお忘れなく。
お線香の種類と使い分け
お線香には一応の使い分けがあります。
お線香には大きく分けて、
- 仏壇に供える『匂い線香』
- お墓に供える『杉線香』
の2種類があるんです。
仏壇に供える『匂い線香』
仏壇に供えるお線香としてよく使われるのは『匂い線香』といいます。
『匂い線香』は、【タブの木の皮】の粉末をもとにして、そこにいろんな香料や香木を混ぜ合わせて作っています。
ですから、混ぜ合わせる香料や香木の種類、または配合する比率によって香りがまったく違いますので、お好みの香りのお線香を選んでください。
ただし、香りというのは人それぞれに好き嫌いがあります。しかも、お線香に火をつけると、しばらくは家中に香りが残ります。
ですから、あなただけではなく家族にとっても「これはいい香りだね。」と思えるお線香を供えるようにしましょう。
また、最近では【煙】の量がとても少ないお線香も販売されていますので、どうしても煙が苦手な人は、ほとんど煙の出ないお線香を使ってみてください。
お墓に供える『杉線香』
お墓に供えるお線香としてよく使われるのは『杉線香』といいます。
『杉線香』は、その名のとおり【杉の葉】を原料として作られています。
『杉線香』は、杉独特の香りがして、燃やしたときの【煙】の量が多めで、価格が安いのが特徴です。そして、お墓参り用として販売されるときには、数十本のお線香が1束にまとめられています。
お墓参りをする際には、1~2束あれば十分ですから、それをお参りの人たちで分けて供えてください。
ちなみに、お墓参りでも『匂い線香』を使ってかまいませんよ。
でも、お墓には多めにお線香を供えますから、お墓参りのときは価格の安い『杉線香』を供えることをおすすめします。
【お焼香】の作法と回数
最後に、『お焼香』の作法についても紹介します。
お葬式では必ず『焼香』をしますので、予習や復習のつもりで読んでみてください。
お焼香の作法
お焼香の作法は、
- まずは喪主から焼香が始まり、遺族、親族、一般弔問客という順番で焼香が行われる。
- 自分の順番が近づいたら席を立ち、焼香の最後列に加わる。この時に数珠を忘れないように注意。
- 自分の順番が来たら、少しだけ焼香台の方へ歩み出て、まずは遺族に向かって一礼をする。
- 次に、祭壇に向かって深く頭を下げる。
- 焼香台の手前まで進み、親指・人差し指・中指の三本の指で抹香(まっこう)を少量つまむ。
- 頭を少し下げ、つまんだ抹香を額の高さまで持ち上げる。※これを『押しいただく』といいます。
- 抹香をゆっくりと静かに香炉へ落とし、数珠を左手(または左腕)にかけて合掌をする。
- 合掌が終わったら、そのまま1、2歩ほど後ろへ下がり、再び遺族に礼をする。
- 自席へ戻る。
と、このようなカンジでやれば大丈夫です。
お焼香の回数
僕がよく聞かれる質問に、
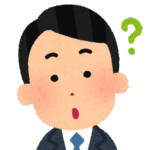
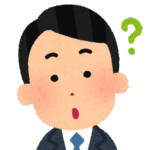
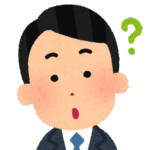
お焼香は何回すればいいのですか?
というものがあります。
じつは、お焼香というのは本来、回数に決まりはないです。
回数に決まりはないはずなのですが、【◯◯宗では◯回】で【△△宗では△回】といったように、いつの間にか宗派ごとの回数の違いが出てきてしまいました。
これは、先ほど紹介したお線香の本数と同じです。
ですから、一応は宗派のやり方に合わせるために、その法要がどの宗派で執り行われるのかを確認した方が無難です。
ちなみに、主な宗派での焼香の回数は以下のようなカンジです。
- 【浄土宗】1~3回
- 【浄土真宗(本願寺派)】1回
- 【浄土真宗(大谷派)】2回
- 【天台宗】3回
- 【真言宗】3回
- 【臨済宗】1回
- 【曹洞宗】2回
- 【日蓮宗】1回~3回
ただし、お葬式のときは焼香の回数は状況に応じて変えることが多いので注意してください。
お葬式の場合は、参列者の人数が多ければ1人あたりの焼香の回数を制限することがあるんです。
ですから、あなたが【施主】や【喪主】となる場合は、お坊さん(あるいは葬儀社の担当者)に焼香の回数を事前に確認しておいた方がよいでしょう。
他の参列者は【あなたの焼香のやり方】を見て、それをそのまま真似します。お葬式でも法事でも、焼香の作法の基準となるのは【最初の人=施主または喪主】なのです。
なので、あなたが喪主や施主となる場合は、ちゃんと焼香の作法や回数を事前に確認しておきましょう。
逆に、あなたが参列者の立場なら《前の人のマネ》をすればOKです。
そのときには、ちゃんと前の人の【焼香の回数】を見ておいてください。油断をして見逃すと他の人に迷惑をかけてしまうかもしれません。
特に、お葬式のときは前の人の回数をちゃんと見ておいてくださいね。
お葬式では、決められた時間内に全員の焼香が終わらなければいけないので、参列者が多い場合は【焼香は心をこめて1回だけ】ということがあります。
みんなが1回の焼香をしている中、もしあなたが3回の焼香をしたら、後の人はあなたと同じように3回してしまうでしょう。
それが連鎖していくと、時間内に全員が焼香をできなくなるという悲劇がおこります。
ですから、参列者として焼香をするときには、しっかりと前の人のやり方を見ていてください。
ちなみに、お焼香をするときに【数珠】を忘れる人がとても多いので注意してください。
数珠を持つことには大事な意味がありますので、数珠はちゃんと《自分だけの数珠》を買ってください。
ちなみに、他の家族の数珠を借りる人がいますが、それはヤメましょう。
その理由は『数珠とは何か?数珠を持つ意味と使い方(持ち方)を説明します。』の記事で詳しく解説していますので読んでみてください。
まとめ
お線香をあげる場面には、
- お仏壇参り
- お墓参り
- 法事
- お葬式
があります。
それぞれの場面でお線香のあげ方は少しずつ違いますが、絶対的な決まりはありませんので、多少は間違えても大丈夫です。
作法やマナーは大事ですが、何よりも、大切な亡き家族やご先祖様に感謝と敬意を大事にしてお線香をあげてほしいと思います。
※お線香を供えた後に読んでみてください。