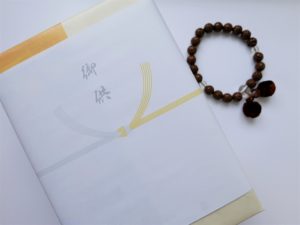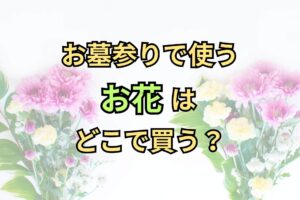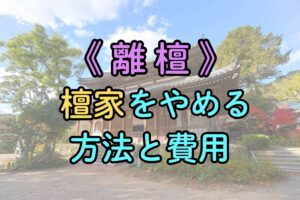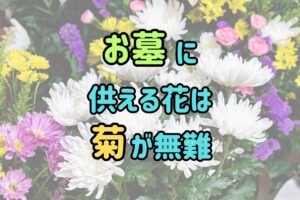- なぜお墓に赤い文字が彫られているの?
- 赤い文字にするのは仏教の決まりごと?
- 赤い文字はずっとそのままにしておくもの?
あなたは、お墓に【一部だけ赤い文字で彫られている】のを見て不思議に思ったことはありませんか?
他の文字は赤くないのに、なぜ一部分だけが赤いのでしょう?
お墓に彫られた赤い文字というのは、『存命中の人の名前』の部分なのです。
墓石には【お墓を建てた人の名前】や【亡くなった人の名前や戒名】などを彫りますが、そこに『存命中』の人の名前があれば、そこだけを赤い文字にするんですよね。
この記事では『お墓に赤い文字を彫る理由』についてお坊さんの僕が解説していますので、興味のある方は最後まで読んでみてください。
この記事を書いている僕『未熟僧(みじゅくそう)』は、お坊さん歴25年以上。仏事の疑問を解消するいろんな情報を発信しています。
お墓のどこに赤い文字が彫られている?
墓石にはいろんな所に文字が彫られています。
1番目立つのは、お墓の正面にある『◯◯家之墓』という文字です。
そして、裏面にも文字が彫られており、そちらは少し小さな文字で『◯◯年吉日建之』と『施主〇〇〇〇』と彫っています。
墓石には、お墓が建てられた日、その家の仏様に関する情報が彫られています。
そんな中で、いくつか【赤い文字】になっている部分があります。
思い出してみてください、【赤い文字】が彫られていた場所はどこでしたか?
とりあえず墓石の正面ではなかったですよね?墓石の正面には【赤い文字】を使わずに、
- 『◯◯家之墓』
- 『◯◯家先祖代々之墓』
- 『先祖代々之墓』
などと彫ってあるはずです。
では、墓石のどこに【赤い文字】を彫るかというと、
- 墓石の裏面
- 墓石の左右の側面
- 墓誌
です。
これらの場所の『戒名の一部』や『名前』の部分が【赤い文字】で彫られているはずです。
お墓に赤い文字が彫られている理由
墓石には『戒名の一部』や『名前』の部分だけを【赤い文字】で彫ることがあります。
なぜ、その部分だけに、しかも【赤い文字】で彫られているのでしょうか?
生前戒名の名前の部分が赤い
墓石の【赤い文字】の部分は誰かの『名前』です。
赤い文字を彫っている場所には条件があります。
それは、
- 墓石に『生前戒名』が彫ってある
- 赤い文字になるのは『名前』の部分だけ
ということです。
本来なら、【赤い文字】を彫るのはこの2つの条件を満たす場合だけなんです。
まず『生前戒名』というのは、その名のとおり【存命中(生前)に授かった戒名】のことです。
戒名というのは、ほとんどの場合、お葬式のときに【亡くなった人】に対して授けられます。これは、亡くなった人に『仏弟子』となってもらうために戒名を授けるのです。
一方で、生前戒名は【生きている人】に対して、先に戒名だけを決めます。
というか、戒名というのは本来【生きている人】に授けるものなんですが、戒名の詳細については割愛します。
基本的に、戒名の中には『戒名を授けられた人の名前の1文字』が入っていることが多いです。
そして、お墓にはその《名前の1文字》の部分だけを【赤い文字】で彫っているというわけです。
名前の部分だけを赤く彫ることによって、戒名は生前に決まっていても、まだ仏弟子になっていないことを表しています。
あと、《生前戒名》のそばには《戒名を授与された人のフルネーム》を一緒に彫るのですが、その名前の部分も【赤い文字】になっています。
以上のように、その家で『生前戒名』を授かっている人がいれば、お墓に【赤い文字】が彫られることが多いです。
しかし、実際のところは、『生前戒名』を授かっていないのに【赤い文字】が彫られているケースもよくあります。
『存命中の人の名前』が赤い文字で彫られている
墓石に赤い文字が彫られるのは、本来なら《生前戒名》が彫られている場合だけです。
しかし、実際のところは、生前戒名がなくても、お墓の建立者名など『存命中の人の名前』の部分にも赤い文字が彫られているのです。
考えてみると、《生前戒名》の『名前』の部分というのは、存命中の人の名前の部分ということになるんですよね。
それで、この『存命中の人の名前』というところだけがピックアップされて、同じく『存命中の人の名前』であるお墓の建立者名の部分も赤くするという習慣が定着しました。
墓石に『存命中の人の名前』を彫るのは、【生前戒名の名前】の部分と、裏面にある【お墓の建立者の名前】の部分です。
だから、お墓の建立者の名前が【赤い文字】で彫られているお墓が多いんです。
なぜ『赤色』なのか
存命中の人の名前の部分を【赤い文字】で彫ることはお分かりいただけたと思います。
でも、なぜ『赤色』なんでしょうね?他の色でも良さそうなもんですよね。
その理由は簡単で、人間の血液が『赤色』だからです。
存命中の人ということは【体に血が通っている状態】なので、それを意味するために『赤色』で彫るわけです。
赤い文字で彫られていた名前の人が亡くなったらどうするの?
墓石に【赤い文字】で彫られていた人が亡くなってしまったらどうするのでしょうか?
その場合は、赤色を抜いて、他の彫刻と同じ状態にするのです。
しかし、『赤色を抜く』といっても、どうやって色を抜くのでしょう?
じつは、墓石を【赤い文字】で彫るといっても、彫った文字の上から赤いペンキで塗っているだけなんですよね。
なので、石材店なら簡単にペンキの色を落とせます。
その人のお骨を納骨する場合は、前もって石材店へ頼んでおけば赤色が消えた状態で納骨ができますので、ちゃんと手配をしておきましょう。
『存命中の人』の名前は必ず赤色にしなきゃダメなの?
この記事では、ここまで『存命中の人の名前』は【赤い文字】で彫ると説明してきました。
でも、
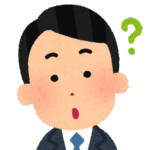
存命中の人の名前は必ず赤色にしなきゃだめなの?
とか、
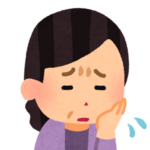
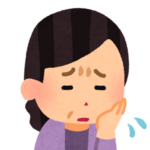
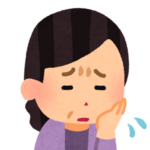
赤色を入れると目立つし、その意味が【血の色】っていうのも何だか嫌だわ。
という人もいることでしょう。
大丈夫ですよ、べつに名前を必ず赤色にするという決まりはないですから。
赤い文字にしたくなければ何もしなくてもいいんです。そもそも、存命中の人の名前を【赤い文字】で彫るのは仏教的な作法でも何でもありませんから。
これはもう完全に日本独特の【慣習】なので、無視をしちゃってもOKです。
では、なぜ赤い文字を彫るようになったのでしょうか?
お墓の左右の側面には、その家で亡くなった人の名前や戒名を彫ります。
しかし、同じ墓石に、存命中の人の生前戒名や名前が彫ってあると、どれが亡くなった人の戒名や名前なのか、パッと見で区別ができなくなります。
そこで、存命中の人の名前に赤色を入れることで、亡くなった人と区別しやすくしただけなんです。
というわけで、存命中の人の名前の部分に【赤い文字】を入れなくても全く問題はありません。
というか、赤色を入れるときも抜くときも【費用】がかかっちゃいますから、最初から【赤い文字】なんて入れない方がいいと僕は思います。
まとめ:お墓に彫られている赤い文字は『存命中の人の名前』です。
お墓には一部だけ赤い文字が彫られていることあります。
お墓に彫られている赤い文字は『存命中の人の名前』を意味します。
本来であれば、『生前戒名』を墓石に彫刻した場合に、その人がまだ正式に仏弟子となっていないことを表すために、名前の部分だけを赤くします。
それがいつの間にか、生前戒名の有無に関係なく【お墓の建立者名】の部分にも赤い色を入れるようになりました。
しかし、これはただの慣習であって仏教における決まりごとではないんですよね。
ですから、赤い文字を入れることが【必要】というわけではありませんので、あなたの自由にして大丈夫ですよ。
※お墓についてはこちらの記事も読まれています。