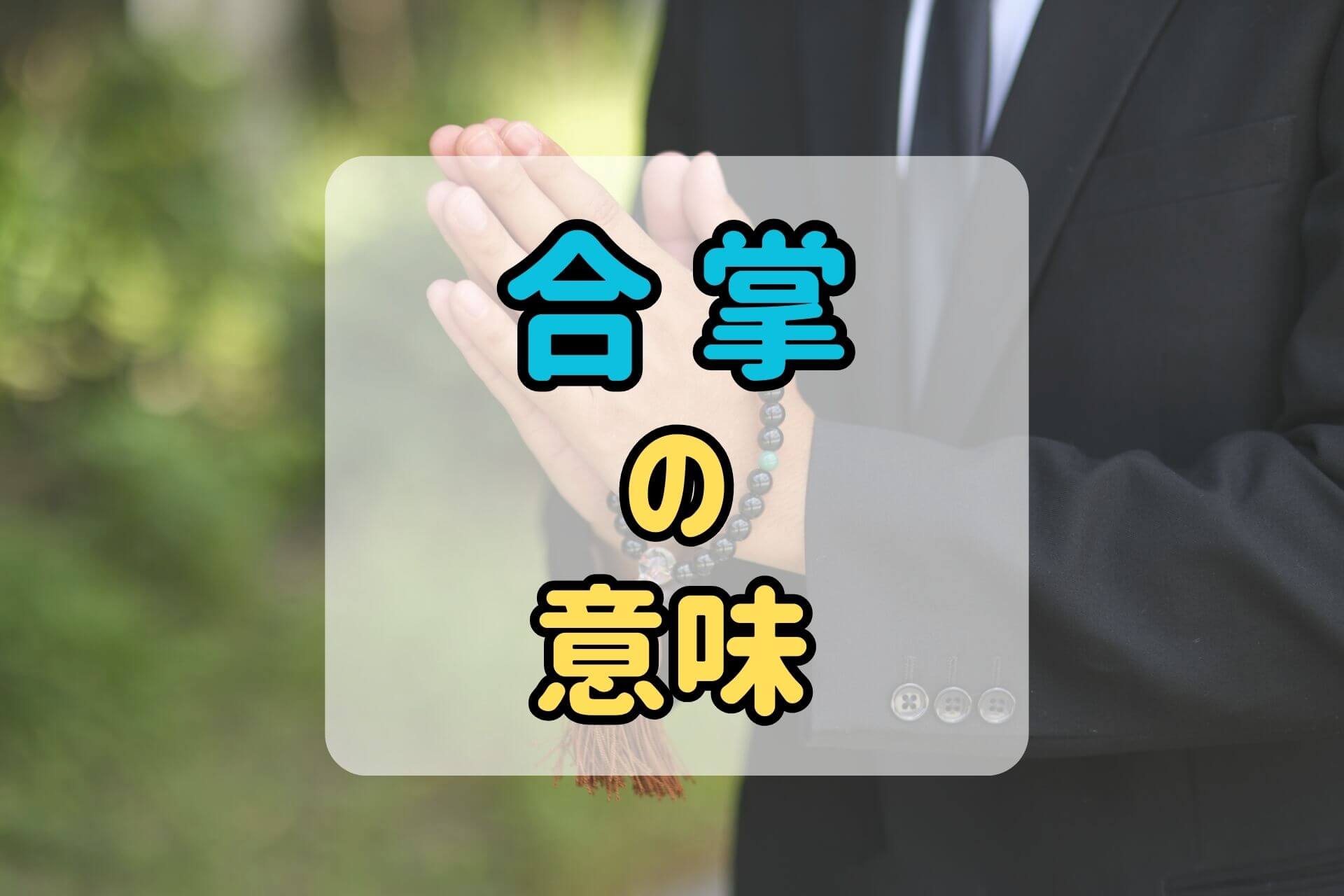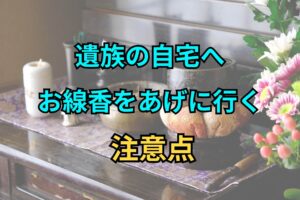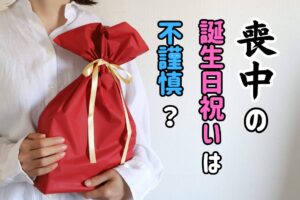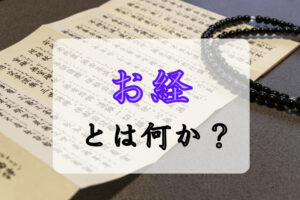- 合掌にはどんな意味があるの?
- 合掌は、なぜ両手を合わせるんだろう?
- 合掌をするときの作法を知りたい。
仏事に欠かせない作法といえば『合掌』です。
お葬式や法事では当たり前のようにやっている合掌ですが、多くの人はその意味を知らないまま何となく手を合わせています。
合掌にはとても大事な意味があり、それを知ってこそ《本物の合掌》になります。
この記事では、
- 合掌の意味
- 合掌の作法
について詳しく紹介しています。
この記事を読んでいただいた後の合掌は、以前の合掌とは全くの別物になりますので、ぜひチェックしてみてください。
この記事を書いている僕『未熟僧(みじゅくそう)』は、お坊さん歴25年以上。仏事の疑問を解消するいろんな情報を発信しています。
お寺で手を合わせるときは、手を叩かない
お寺や神社へ参拝したときには必ず手を合わせますよね。
じつは、お寺と神社では手を合わせるときの作法が違います。
僕のいるお寺では、たまに本堂の前で「パンッパンッ」と手をたたく(打つ)音が聞こえます。
べつにそれが大間違いとかタブーというわけではないですが、お寺の場合はそっと手を合わせるだけの『合掌』をしてください。
神社にお参りをしたときは、頭を2回下げてから手を2回たたき、そのまま手を合わせて拝んだら、最後にもう1回頭を下げます。これは、いわゆる神社における『二礼二拍手一礼』の作法です。
神社で手をたたくのは、神様にこちらを向いてもらうため、またはこちらへ来てもらうため、という意味があるそうです。
しかし、仏様はわざわざ私たちからアクションを起こさなくても、いつも見守ってくれており、正しい方向へと導いてくださいます。
それに対して、私たちは「仏様いつもありがとうございます」と、そっと手を合わせて【御礼の気持ち】を表しているんです。
合掌の意味
お葬式、法事、お墓参り、お仏壇参りのときは必ず合掌をしますが、合掌の意味を知っている人は少ないです。
せっかく合掌をするなら、その意味を知った《本物の合掌》をしませんか?
敬意・感謝・平和を表す
合掌には、敬意・感謝・平和を表す意味があります。
仏教発祥の地であるインドでは、目の前にいる相手に対して敬意や感謝の気持ちを表すために合掌をします。
また、相手に自分の両手を見せることで、
- あなたを攻撃するつもりはありません
- あなたとの友好的な関係を望んでいます
という平和を表します。
つまり、合掌というのは、仏様(ご先祖様)や故人に対して、私たちの『敬意・感謝・平和』の気持ちを表現するための作法なのです。
仏様と私たちが一体になることを表す
合掌をするときは、その名のとおり【両方の手のひら(掌)】を合わせますよね。
両手を合わせることにより『仏様と私たちが一体となる』ことを表します。
これはインドの考え方が元になっています。
右手は清浄、左手は不浄
インドには、
- 右手は清らかな手(=清浄)
- 左手は清らかではない手(=不浄)
という考え方があります。
たとえば、インドの人は食べ物を直接手でつかんで食事をしますが、そのときは【右手】を使います。
これは、食べ物は『ありがたい恵み』なので清浄の手(=右手)でいただく、というわけです。
そして、排便をするときには、清らかな右手でお尻を触るわけにはいかないので、不浄の手(=左手)でお尻を洗います。
このように、インドでは両手を清浄と不浄で使い分けているのです。
右手は仏様、左手は私たち
次に、インドの考え方をふまえて、両手の意味を《仏教的な視点》で見ると、
- 清浄な右手=仏様
- 不浄な左手=私たち
となります。
合掌という『両手を合わせる形』にすることで清浄と不浄が1つになり、それは仏様と私たちが【一体】になることを意味するわけです。
仏様と私たちが一体になると、その瞬間から仏様のチカラによって私たちの全身が清められます。
つまり、仏様や故人を前にして合掌をするのは、
敬意を表すべき対象(仏様や故人)を目の前にするときは、私たちも全身を清めるのが礼儀である。
と考えているからなのです。
ちなみに、
『右ほとけ、左は我と合わす手の、内ぞゆかしき、南無のひと声』
という、合掌について詠んだ句があります。
この句でも、『両手を合わせて仏様と一体になり、仏様に対して日頃の敬意と感謝をこめて「南無」とお唱えしましょう』と合掌の大切さを教えています。
食事の作法と合掌
手を合わせるのは、仏様や故人の前だけではありません。
私たちは食事をするときにも「いただきます。」と言って手を合わせます。これは、目の前にある食べ物が【ありがたい貴重な恵み】であり【感謝をするべき対象】だからです。
私たちの食材となる、肉、魚、野菜などの自然の恵みにはすべて【命】があります。私たちは、その【命】を頂くことで生きていられるわけです。
だから、食事の前に必ず手を合わせて「(ありがたい自然の命を)いただきます。」と言うんですよね。
また、自然の命を頂くまでには、命を捕獲または収穫する人たちがいて、それをまた切り分けたり、加工、運搬、販売、購入、調理するといったように多くの人が携わっています。
これらの人たちもまた感謝をするべき対象です。
このように、目の前に並んでいる食べ物すべてが『感謝をするべき対象』なので、それらを頂く前に手を合わせて自分の全身を清めるのです。
そして、食べ終わった後は頂いた命に感謝をして「ごちそうさまでした。」と再び手を合わせます。
手を合わせるとき(合掌)の作法
仏事では必ず合掌をします。
合掌は両手を合わせるだけの単純な動きですが、そこにはちょっとした作法があります。
合掌の具体的な作法
合掌の作法には、
- 立ったまま合掌する(立拝)
- 座って合掌する(座拝)
の2つがあります。
立ったまま合掌をする場合
まずは、立ったまま合掌(立拝)をするときの作法を紹介します。
立ったまま合掌をする場面は、葬儀式場でのお葬式、お墓参り、屋外にいる仏様にお参りするときなどでしょう。
作法の手順としては、
- 対象の目の前に着いたら、両脚と背筋を伸ばし、かかと同士をつけて、まっすぐに立つ。
- 両方の手のひらをしっかり合わせ、指をまっすぐに伸ばす。このとき、すべての指の間隔を開けないようにする。
- 合わせた両手の中指の先を上に向ける。
- そのまま両腕を【中指の先が喉仏の位置にくる高さ】まで上げて、少しだけ脇をしめる。
- 前方へ45度くらい上半身を倒し、そのまま姿勢をキープ。
- しばらくしたら、体を起こす。
- 両手を離す。
というカンジです。
完全にこの通りにできなくてもいいので、今後の仏事で手を合わせるときに少し意識してみてください。
座って合掌する場合
続いて、座って合掌(座拝)をするときの作法です。
座って合掌をする場面は、自宅でのお葬式や法事、お寺の本堂での法要、仏壇をお参りするときなどでしょう。
作法の手順は、
- 対象の目の前に着いたら、正座をして少し前に進み、背筋を伸ばす。
- 両方の手のひらをしっかり合わせ、指をまっすぐに伸ばす。このときすべての指の間隔を開けないようにする。
- 合わせた両手の中指の先を上に向ける。
- そのまま両腕を【中指の先が喉仏の位置にくる高さ】まで上げて、少しだけ脇をしめる。
- 前方へ45度くらい上半身を倒し、そのまま姿勢をキープ。
- しばらくしたら、体を起こす。
- 両手を離す。
- 少し後ろに下がってから立ち上がる。
というカンジです。
これも完全にこの通りにしなくても問題はないですよ。
特に、足が悪かったり、どうしても正座が苦手な人は無理に正座をする必要はありません。
お坊さんの中には合掌をするときに『手をずらす』人がいるけど?
お葬式や法事のときには、ついお坊さんの動作を見てしまいますよね。
そして、お坊さんの動作を見ていると、お坊さんが【両手を少しずらして合掌をしてる】ことがあります。
一般的には、両手がズレないように合掌をしますので、初めて見た人は違和感を感じることでしょう。
あれは、べつにお坊さんが雑に合掌をしているわけではなく、宗派によって合掌のやり方が少し違うのです。
両手をずらす形の合掌は『金剛合掌(こんごうがっしょう)』といい、真言宗でよく用いられます。
両手をずらし、双方の指で互いをしっかりと挟み合うことで、仏様と私たちの強い一体感を表しているのです。
金剛合掌をするときは、両手をパーにした状態で合わせ、右手だけを少し反時計回りにずらし、あとは両手の全部の指同士がしっかりと挟み合うように手を合わせます。
右手を反時計回りにずらすのは、仏様を表す右手がより自分に近くなってくれるからです。
手を合わせている時間はどのくらい?
あなたは、お墓や仏壇をお参りするときに何秒くらい手を合わせていますか?
僕が今まで見ていると、多くの人はだいたい【5〜10秒】くらいだと思います。
もちろん、手を合わせる時間には個人差がありますので、30秒くらい手を合わせている人もいます。
とりあえず、手を合わせる時間に決まりはありませんが、早くパッと終わらせてしまうのも寂しいので、僕なりの基準をお伝えします。
僕が手を合わせている時間は、左右それぞれの手の温もりが、互いに十分に伝わるまでです。
両手を合わせていると、右手の温もりが左手に、左手の温もりが右手にジワ〜っと互いに伝わります。
このように、両方の手のひらの温もりが互いにしっかりと伝わるまでは手を合わせておくんです。
先ほど、合掌は【仏様と私たちが一体になること】を意味すると言いました。
つまり、僕は、
- 仏様(右手)の慈愛に満ちた温もりが自分(左手)に伝わり、
- 自分(左手)の敬意、感謝、平和の気持ちが仏様(右手)に伝わる。
というイメージで両手を合わせています。
ですから、互いの温もりが十分に伝わり合ったときに【仏様と私たちが一体になること】ができている状態であると考えているわけです。
でも、これはお葬式や法事といった場面ではできません。なぜなら、一人あたりの合掌の時間がかかりすぎてしまうから。
なので、個人的にお寺・お墓・仏壇にお参りするときに、じっくりと温もりを両手に伝え合ってみてください。
まとめ
お寺で合掌をするときは、手を叩かずに、そっと両手を合わせましょう。
合掌には、
- 敬意・感謝・平和を表す
- 仏様と私たちが一体になることを表す
という意味があります。
合掌をするのは、目の前におられる【感謝するべき対象】に対して敬意を表し、自分の体を清めるためです。
本記事を読んでくださったあなたは、もうすでに合掌の意味を知っています。
これからは、合掌の意味を知っている《本物の合掌》をしてくださいね。