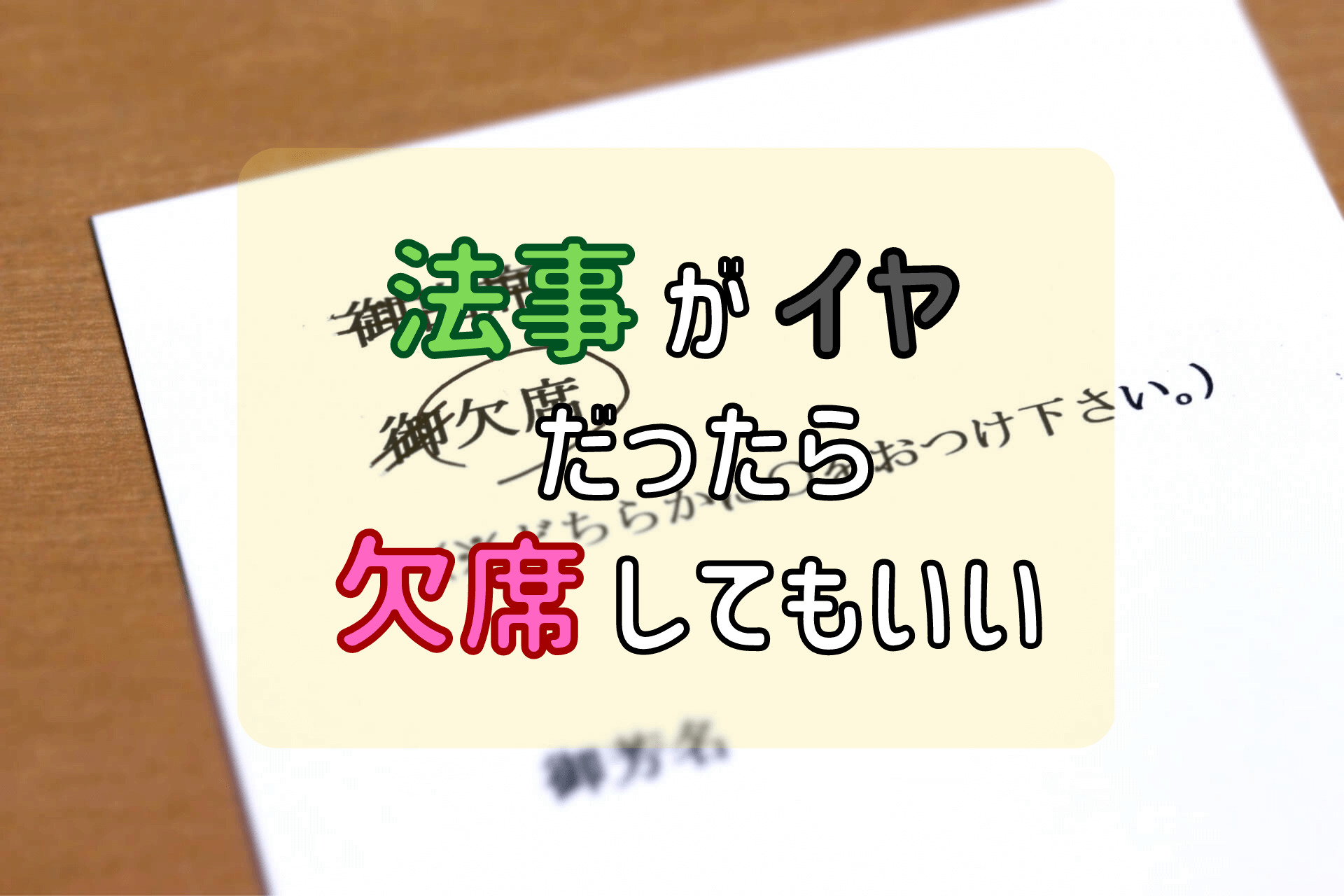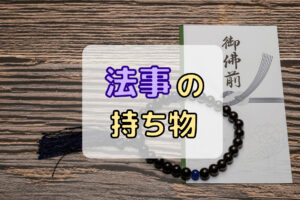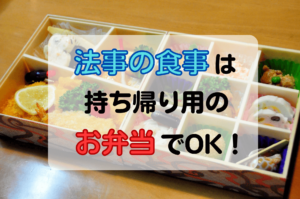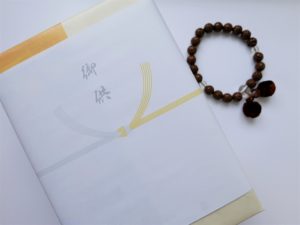- 法事は面倒くさいから、できれば欠席したい。
- 他の人はどんな理由で法事に行きたくないと思っているんだろう?
- 法事を欠席する場合はどんなことに注意すればいいの?
法事は《数年に一度のこと》とはいえ、同じ人(故人)の供養を何度もします。
ですから、何回も法事に参列していると「また法事か、なんだか行くのが面倒だなぁ。」という気持ちになりますよね。
法事に行きたくない理由は人それぞれですが、どうしても気が進まないのであれば法事を欠席してもいいですよ。
この記事では、
- 法事を欠席することに対する考え方
- 多くの人が法事を欠席したくなる理由
- 欠席する時の注意点
について書いています。
最後まで読んでいただき、それから法事に欠席するかどうかを決めてみてください。
 未熟僧
未熟僧人それぞれの【法事】に対するリアルな気持ちを紹介しますね。
この記事を書いている僕『未熟僧(みじゅくそう)』は、お坊さん歴25年以上。仏事の疑問を解消するいろんな情報を発信しています。
法事に行きたくないなら欠席してもいい
法事に出席するのは大変ですよね。
法事のたびに、
- 貴重な休日を使って(もしくは、わざわざ仕事を休んで)
- 慣れない喪服を着て
- 『御仏前』を用意して
- 退屈な法要に参列して
- 親戚の人たちと気を遣いながら会話をして
- ヘトヘトになって帰宅する
これらをしなくてはいけません。
しかも、その家で他にも亡くなっている人がいれば、その人の法事もすることになります。
そうすると、



なんだか毎年のように法事に出席してる。もう法事には行きたくないなぁ・・・。
と思うことでしょう。
だからといって、簡単に法事を欠席することもできず、結局は【気が進まないけど出席する】という流れになります。
『法事に行きたくない』と思う理由は人それぞれで、それは他人からすれば【大したことない理由】のように思えても、当事者にとっては【重大な理由】だったりします。
もしもあなたにとって重大な理由があるなら法事を欠席してもいいですよ。
そもそも、法事は《故人の供養》のためにするものですから、『故人を供養したい』という気持ちのある人だけが参列すればいいのです。



いや、べつに故人を供養したい気持ちが無いわけじゃないんだよ。
そうですよね、おそらく今のあなたは、故人を供養したいのに【重大な理由】があるせいで『法事に行きたくても行けない』という状況なのでしょう。
それなら法事を欠席しても大丈夫ですよ、故人だってあなたの気持ちや状況をちゃんと理解してくださいますから。
ただし、あなたが【故人の遺族】である場合は、よほどの理由がない限り法事に出席してくださいね。
一般的に【遺族】と呼ばれるのは、故人との関係が、
- 配偶者
- 子
- 両親
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
にあたる人です。
これだけ近い関係なのに、大した理由もなく法事に行かないというのは、あなたの『人間性』を疑われてしまいます。



法事への欠席を決める前に、まずは『あなたの立場』をよく考えましょう。
法事を欠席したい理由
法事を欠席したい理由は人それぞれですが、じつはみんな似たようなケースに該当しています。
親戚との関係が悪い
あなたには【会いたくない親戚】がいるんじゃないですか?
じつは、『顔を合わせたくない親戚がいる』という人はとても多く、統計によれば3人に1人は【親戚間の悩み】を抱えているのだそうです。
僕が今まで聞いた《法事に行きたくない理由》の中で最も多かったのは『親戚との関係が悪いから』というものでした。
誰だって《苦手な人》の1人や2人はいますよね。
だから、どうしてもソリが合わない親戚がいても全然おかしくない、というか、それはよくある話なのです。
そして、あなたに【苦手な親戚がいる】ということは、他の親戚にも何となく伝わっています。
それで、他の親戚は、そんなあなたに対して気を遣っているわけですが、あなたはそのことに気付いているでしょうか?



つまり、あなたが嫌な思いをしながら法事に出席していると、他の親戚も嫌な思いをするのです。
ですから、どうしても会いたくない親戚がいるのなら、他の親戚のためにも、思い切って法事は欠席してしまいましょう。
出費が多い
法事に参列するときは、手ぶらで行くわけにはいきませんよね。
必ず施主に『御仏前』を渡します。
あなたと故人との関係性にもよりますが、『御仏前』の相場としては【1万円~3万円】くらいです。
これって結構大きな金額ですよね?
ここへさらに交通費なども追加されますから、法事というのは出費が多いイベントです。
法事に招かれた人の中には、経済的に余裕がなくて『毎月ぎりぎりの生活』をしている人もいるかもしれません。
そのような人は、



亡くなった人よりも、今は自分の生活の方を優先したいよ。
と思うでしょう。
そりゃそうですよ、1万円もあれば他の【生活に必要なもの】がいろいろと買えますからね。
それに、1万円を稼ぐのだって大変ですから、経済的に本当に余裕がないという場合は、まずは自分の生活を優先して法事は欠席してください。
遠いから移動するだけで大変
法事に出席することを前向きに考えているとしても、物理的な問題がそれをジャマする場合もあります。
例えば、法事の行われる場所が自宅からとても遠い場合、法事に出席しようという気が薄れてしまいませんか?
隣の市町村くらいならあまり問題はないと思いますが、もしも、
- 飛行機や新幹線を利用しなくてはいけない
- 何時間も高速道路を走行しなくてはいけない
というような距離だと移動するだけでも大変ですし、それだけ多くの交通費もかかるんですよね。
すると、



移動で疲れるし出費も大きい、そうまでして法事に行かなくちゃいけないの?
という気持ちになってしまいます。
ですから、出席するかどうかは【あなたと故人の関係性】で決めましょう。
あなたと故人の関係性が【数年に1度会う程度】だったのであれば、いっそのこと法事を欠席してください。
しかし、注意することが1つあります。
いくら遠いからといっても毎回欠席するのではなく『3回に1度』くらいは出席した方がいいですよ。
あなたの本音としては、
できるだけ法事には行きたくない。でも施主や他の親戚から「あの人はいつも来ない」と言われるのは避けたい。
ですよね?
だったら、あくまでも『供養したい気持ちはあるけど、遠くてなかなか毎回は行けないんですよ』という体裁でいなければダメです。



なので、数回に1度は頑張って法事に出席しましょう。
法事をすることに意味を感じない
以前、ある信者さんに面と向かって普通に、
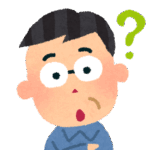
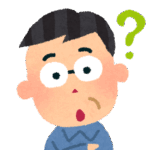
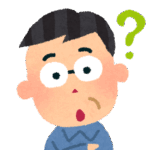
法事って、そんなに何回もやる必要はないと思うんですが・・・。
と言われたことがあります。
これは、要するに「法事なんか1回やれば十分でしょ?」ということです。
そうですよね、いくつか【法事に出たくない理由】を紹介してきましたが、根本的な理由はおそらく『法事そのものに意味を感じない』ということでしょう。
何のために法事をするのか、なぜ何回も供養をするのか、という法事をする意味や必要性を感じないから欠席したくなるんですよね。
じつは、法事は故人のためだけに行うものではなく、参列者のためでもあるのです。
法事をする意味について詳しく知りたい人は、別記事の『法事をする必要性と意味。法事の注意点も合わせて解説します。』を読んでみてください。



法事をする意味に納得がいかなければ欠席してもかまいませんよ。
法事を欠席する時の注意点
法事を欠席すると決めたら、できるだけ早めに施主に欠席の旨を伝えましょう。
欠席の旨を伝えるときにはいくつか注意点があるので紹介します。
法事を欠席する理由とお詫びの気持ちを伝える
送られてきた『法事の案内』に返信ハガキが付いている場合は、返信ハガキの《欠席》に印をつけて返送します。
しかし、ただ印を付けて返送するだけではいけません。
欠席に印を付けたら、その近くの空きスペースへ欠席理由を書いて『お詫び』をしておく方がいいです。



欠席理由とお詫びの文は簡潔に書くようにしましょう。
法事を『やむを得ない事情』で欠席することもありますが、ほとんどの欠席理由は《ただの言い訳》なんですよね。
ですから、欠席理由とお詫びは短くスパッと書く方がいいです。
例えば、
当日はどうしても都合がつかず、誠に申し訳ございませんが欠席をさせて頂きます。
みたいな文言を書くだけでOK。
欠席の理由をダラダラと書くのは逆効果ですし、しかもそれはマナー違反とされています。
次に、お詫びの文を書いたら返信ハガキをすぐに送り返すようにしてください。
ハガキの返送が遅いと、「なんだ、返事が遅いくせに結局は欠席するのか!」と施主に悪い印象を与えてしまいます。



何でもそうですが、マイナスのことは《先に》そして《早めに》伝えるのが鉄則です。
そういう意味では、返信ハガキを送る前に、施主に欠席の旨を電話で伝えておくといいですよ。
施主の家が近いなら【御仏前】はなるべく直接手渡す。
法事への欠席を電話や返信ハガキで施主に伝えたら、次は【御仏前】を渡さなければなりません。
もしも、あなたの自宅から施主の家が近いなら、法要の日までに施主の家へ出向いて直接【御仏前】を手渡すことが望ましいです。
御仏前を手渡すときは、現金をそのまま渡すのではなく、ちゃんと『不祝儀袋』に入れるようにしてください。
そして、そのときに法事を欠席することのお詫びをしておきましょう。
ちなみに、【御仏前】を渡しに行く際には『手土産』をお忘れなく。
法事への欠席を詫びるのですから、まさか手ぶらで行くわけにはいきません。



手土産は【値段が安すぎず、高すぎず、日持ちする物】を選ぶようにしましょう。
施主の家が遠い場合は【現金書留】で御仏前を郵送する
施主の家が自宅から遠いということも当然あります。
そのような場合は、御仏前を【現金書留】で郵送するようにしましょう。
たぶん御仏前の袋を現金書留の封筒に入れるとパンパンになるので、御仏前の袋はできるだけサイズが小さなものを買うようにしてください。
便箋でお詫びの文を添えておく
現金書留で御仏前を郵送する場合は、便箋でお詫びの気持ちを伝えておくようにしましょう。
お詫びの文章は、返信ハガキと同じで【簡潔】に書くようにしてください。
例えば、
この度は、◯◯様の△△回忌法要にお招きをいただき、大変恐縮に存じます。
心よりお礼を申し上げます。
さて、お招きをいただきました件につきましては、当日やむを得ない事情により、不本意ながら欠席させていただくことをご容赦ください。
当日のお参りが叶いませんこと、誠に残念ではございますが、◯◯様のご冥福をお祈り申し上げます。
心ばかりのものを同封いたしますが、またあらためてお参りをさせていただきたく存じます。
と、こんなカンジでかまいません。
御仏前と一緒に送るなら、お花ではなく菓子折が無難
法事を欠席するときのマナーとして、「供養の気持ちを表すために、御仏前と一緒に【お花=供花】を送りましょう。」と言う人もいます。
たしかに、「せめてお花くらいは送っておきたい。」という気持ちになりますし、その方がより一層『故人を供養したい気持ち』が施主に伝わるかもしれません。
しかし、お花を送ったところで、はたして本当に施主は嬉しく思うのでしょうか?
じつは、お花を送ると施主に迷惑をかけることもあるんですよね。
故人が【お花が大好きだった】という場合を除いて、できるだけお花を送るのは控えるべきです。
お花は、仏壇に供えるときも、後で処分をするときにも手間がかかりますが、だからといって【供えずに捨てる】なんていうこともできませんよね。
それで、
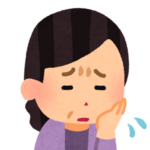
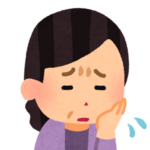
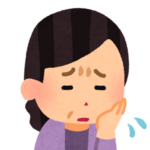
せっかく送ってもらったお花だし、仕方ないから1度お供えしておこうかな・・・。
みたいな扱いになってしまいます。
お花を送ると、結果的に相手へ余計な負担をかけてしまうことが多いのです。
ですから、法事を欠席する場合、施主には御仏前と便箋を送るだけで十分。
どうしても何かを一緒に送りたいのなら、ちょっとした菓子折がいいと思います。それ以上は、施主にとって『ありがた迷惑』となる可能性があるので控えてください。
じつは、参列者の少ない方が施主は助かる?
ここで、あなたに1つ良いお知らせがあります。
あなたは、法事を欠席したいと思う一方で、



法事を欠席するなんて言ったら、施主の気分を害してしまうかな?
と心配になりますよね。
でも、それは安心して大丈夫ですよ。だって、施主は『あなたが欠席すること』をさほど気にしていませんから。
じつは、参列者の少ない方が施主は助かるのです。
たしかに、施主も最初は「えっ、欠席するの?」と残念がるかもしれませんが、それはほんの一瞬だけ、あるいは残念なフリをしているだけということもあります。
最近では、お葬式も法事も『規模の縮小化』がどんどん進んでいますよね。
それはつまり、喪主や施主が【あえて参列者を限定している】ということなんです。
その理由は簡単で、大勢の人が来るとすべてにおいて【面倒くさい】からです。
喪主や施主は、建前としては「できるだけ多くの人に来てもらって故人の供養をしたい。」と言いますが、本心はまったく違います。
本当は、



限られた人だけが来てくれたらいいよ、それ以上はむしろ面倒くさいし。
と思っています。
そのため、あなたが欠席しても、施主は「そっか、まぁそれなら仕方ないか。」と意外と気にしないかもしれません。
ということで、あなたがどうしても法事を欠席したい理由があって、すべきことをすれば法事には行かなくてもかまいません。
【関連記事】:法事は身内だけでやりたい!親戚を呼ばないで法事をするときの注意点
まとめ:自分の立場をよく考えて、それでも法事に行きたくないなら欠席してOK。
法事に参列するのが面倒になることは誰にでもあります。
また、人それぞれに『法事に行きたくない理由』があります。
だから、どうしても法事に行きたくないなら欠席してもいいんです。
ただし、あなたが故人の【遺族】である場合は話が別ですから、法事に行くかどうかは《あなたの立場》をよく考えてください。
よく考えた上で、それでも行きたくないなら、やるべきことをやった上で欠席をしてください。
そして、できれば次回こそは法事に出席してもらいたいなと思います。
※法事に出席するべき立場の人はコチラの記事を読んでみてください。