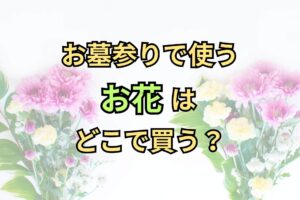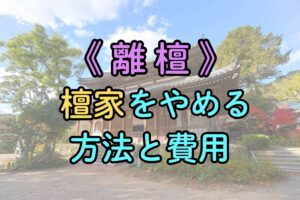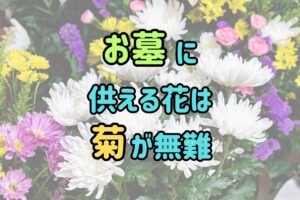- 多くの人が「お墓を継ぎたくない」と思う理由
- お墓の継承者の決め方
- お墓を継がずにすむ方法
お墓というのは、親から子へと大事に受け継いでいくものです。
ご先祖様たちが大切に守ってきたお墓を、子孫である私たちが簡単に終わらせるわけにはいきません。
・・・というのは少し前までの考え方。
どうしてもお墓を継ぎたくなければ無理に継がなくてもいいですよ。
お墓を守るのはとても素晴らしいことですが、それであなたの人生を犠牲にする必要はありません。
お墓を継ぐことに抵抗がある方は最後まで読んでみてください。
この記事を書いている僕『未熟僧(みじゅくそう)』は、お坊さん歴25年以上。仏事の疑問を解消するいろんな情報を発信しています。
多くの人が「お墓を継ぎたくない」と思う理由
最近では【お墓を継ぎたくない】という人がものすごく増えました。
昔は『家督制度(かとくせいど)』といって、その家の長男が財産を継承し管理していくという慣習がありました。
現在ではそのような制度自体は廃止されていますが、それでも【継承に関する考え方】は根強く残っています。
そのため、今でも『お墓は基本的に長男が継ぐもの』という認識が一般的です。
しかし、長男の人からすれば、

そんな時代遅れなことを言われても困る。面倒なことばかりで何もメリットがないし、お墓なんて継ぎたくないよ・・・。
という気持ちになるんですよね。
この【誰がお墓を継ぐのか】という問題に多くの人が頭を悩ませています。
では、なぜ多くの人がそれほど【お墓を継ぐ】ことを嫌がるのでしょうか?
維持費が必要
お墓というのは、墓石を建てたらそれで終わり、というわけにはいきません。
お墓を建てたら、お墓を使い続けるための【維持費】が必要で、これはお寺や霊園には必ずあるものです。
維持費の金額はお寺や霊園によって違いますが、1年間あたり【4千円~2万円】くらいの範囲ではないかと思います。
このように、お墓を継ぐことは『継続的に費用がかかる』という大きなデメリットがあるわけです。
だから、多くの人はお墓を継承するのを嫌がるんですよね。
定期的に掃除などの管理をする必要がある
お墓を継ぐと『定期的に清掃などの管理をする必要がある』という点も継承者がいなくなる理由の1つです。
お墓は家と同じで、ちゃんと管理をしてあげないと劣化が早まるんですよね。
とはいえ、墓石に使われる石は非常に硬いので、劣化が早まるといっても数年でどうこうなるわけではありません。
また、いつも【墓地が雑草だらけ】というのも見た目が悪いだけでなく、隣の墓地にも迷惑をかけてしまいます。
それに、墓石に汚れがついたままにしておくと、やがて変色したり、場合によっては部分的に劣化が進んでしまいます。だから、定期的にちゃんと墓石の汚れなどを拭きとってあげないといけません。
さらに、春から秋にかけて【雑草】がグイグイと生えてきますが、これを放っておくと隣の墓地の人からすぐにクレームがきます。
雑草に関するトラブルは多いので、「ちょっとくらい除草をサボっても大丈夫だろう。」なんて思っていたら、すぐにお寺や霊園から電話がかかってくるでしょう。
そうなると、【お墓の管理】をするために何度もお墓へ行く必要があります。
お墓まで行って【ただお墓を掃除して帰る】というわけにはいきません。ちゃんとお墓参りをしなくちゃいけません。
お墓参りをするときには線香やお花も供えるので、それでまた出費をすることになります。
このように、お墓を継承すると維持費がかかるだけでなく、定期的な清掃作業などの【管理】と【お墓参り】をする必要があります。
お金の話だけではなく、清掃作業やお墓参りまでしなくてはいけないのですから、お墓を継ぐことを嫌がるのは仕方ないのかもしれません。
お寺の墓地だと定期的な供養をする必要がある
お墓はだいたい、
- お寺
- 霊園
- 地域の集合墓地
のどこかにあります。
この中でも、あなたの家のお墓が『お寺』にある場合はとても厄介です。
お墓がお寺にあるということは、あなたの家はそのお寺の【檀家(だんか)】になっているのです。
つまり、あなたは【そのお寺の宗派の信者】となっていなければいけないんですよ。
さらに、檀家というのは、お寺の行事へ積極的に参加することを求められて、当然ながらそれなりの費用も納めるわけです。
そして、そのお寺や宗派の規則にしたがって『供養』をしなければならない立場となります。
年回忌供養やお盆供養はもちろん、お彼岸や命日の供養などもお寺から要求されるかもしれません。
お寺にあるお墓を継承するということは、お墓を維持するだけではなく『定期的な供養をする必要がある』ということも覚悟しましょう。
維持費を支払い、清掃作業やお墓参りをするだけではなく、さらには定期的な供養までしなくてはいけないんです。
だから、お寺にお墓がある場合は、お墓を継ぎたがらない人が特に多いんですよね。
【関連記事】:【檀家をやめたい】菩提寺を離檀する方法と費用の相場
誰がお墓を継ぐべきなのか
お墓というのは誰が継ぐべきものなんでしょう?
先ほども言いましたが、お墓を継ぐのは一般的に【長男】です。
しかし、家督制度が廃止された現在では、お墓を継ぐのが必ずしも長男である必要はありません。
お墓を継ぐのに適した人であれば、誰でもお墓を継ぐことはできます。
お墓の継承者の基準は民法第897条にある
お墓や仏壇というのは、『祭祀財産(さいしざいさん)』といいます。
この祭祀財産を継承することで、お墓や仏壇の継承者となります。
ちなみに、この祭祀財産は原則として1人だけが継承するもので、お墓はAさん、仏壇はBさん、というように分けて継承はしません。
そして、祭祀財産は、金銭や不動産といったような『相続財産』とは別モノとして扱われ、相続人がきっちりと法律で定められているわけではないんです。
祭祀財産を継承する人を選ぶ基準は『民法第897条』に記載されています。
具体的には、
《民法第897条》
【1項】系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
【2項】前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
となっています。
もう少し分かりやすく言うと、
系譜・仏壇・位牌・墓地・墓石といった【祭祀財産】については『故人の住んでいた地域の慣習』に従って決めた継承者が受け継いでください。
ただし、生前に故人からの指定があったら、指定された人が受け継いでください。
もしも、慣習が明らかでない(【慣習があるのかどうか】【その慣習はどのようなものなのか】ということがわからない)場合は、家庭裁判所が継承者を決めます。
ということです。
基本的には、その地域の『慣習』に沿ってお墓を継ぐ人を決めましょう。
でも、お墓の継承者に関する『慣習』は多くの地域で【長男が継ぐ】となっているので、ほとんどの場合は長男がお墓を継いでいます。
ただし、「お前がお墓を守ってくれ。」と生前に故人から指定をされていた人は、優先的に継承者となります。
もしも、故人の指定もなく慣習も特にないという場合は家庭裁判所が決めてくれる、ということです。
とはいえ、だいたいは家族で話し合って、その中で【お墓を継ぐことができる人】がお墓を継いでいます。
長男がお墓を継ぐのが一般的
長男って何かと大変ですよね。
小さい頃は、弟や妹が生まれると、、
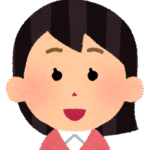
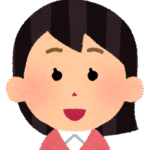
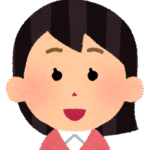
あなたはもうお兄ちゃんなんだからね。
と言われ、大人になってからも、
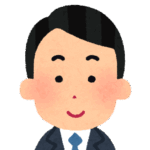
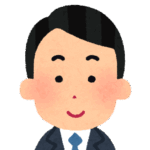
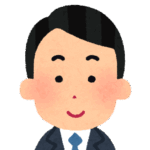
おまえはウチの長男なんだから。
と言われます。
この【長男の責任】みたいなものは、もちろんお墓の継承でも適用されています。
みんな口には出しませんが、



あなたは長男なんだから、家のお墓を守るのも当然あなたの仕事でしょ。
みたいな空気が流れます。
そして、長男である人自身もそれをしぶしぶ受け入れているのが現状でしょう。
なぜ、それほど【長男】ということを強調されて、そして、それに応じた行動を要求されるんでしょうね?べつに長男になることを望んで生まれたわけじゃないんですけどね。はい、そうです、僕も長男です。
昔は『家督制度』という謎な制度があって、長男がいろんな財産を優先的に継承していました。
その代わりに、家をしっかりと守り続けて、絶えさせることなく次の世代にバトンタッチしなければなりませんでした。
要するに、長男に対して「家を継いでいくのは大変だけどよろしくね。その代わりにいろんな財産をあげるからさ♪」というカンジで後を継がせていたんですね。
昔はそれが【当たり前のこと】だったんですが、今はそんな制度は廃止されていますし、財産もしっかりと法定相続されています。
ところが、現在の日本は、十分な財産を継承できないのに、お金のかかるお墓とか仏壇の管理だけはしっかり継承させられるんです。
そりゃあ、長男の人だってお墓の継承を嫌がるに決まってますよね。
長男以外の人でもお墓を継承できる
何度も言いますが、ほとんどの地域では、慣習としてお墓を継ぐのは【長男】です。
しかし、長男の人だって、お墓を継いでも負担が大きいだけでほとんどメリットがないんですから「オレはお墓なんて継ぎたくない!」という気持ちになります。
なのに、もしも生前に「お前がお墓を継いでくれ」という指定を受けていたら、お墓を継がなくてはいけないんです。
祭祀財産の継承というのは特殊で、継承者として指定をされたら【拒否】ができないのです。ムチャクチャだと思いませんか?
でも安心してください、拒否することはできませんが、継承した祭祀財産を自分の判断で【処分】する権利はあるんです。
どうしても祭祀財産を継承したくないのなら、一旦は継承をして、その後に処分してしまえばいいのです。
費用はかかりますが、お墓は『墓じまい』をして、『仏壇』はお焚き上げをしてもらえば、祭祀財産の処分ができます。
でも、実際のところはそう上手くもいかないんですよね。
きっと、長男の人が「オレに権利があるから、祭祀財産はすべて処分する!」なんて言ったら、きっと家族から反対されるでしょう。
そうすると、結局は家族で話し合って、長男以外の【お墓を継ぐことができる人】が継承することになるのです。
そして、それはだいたい、
- 実家で親と同居をしている人
- 実家の1番近くに住んでいる人
になります。
このように、お墓というのは【長男以外の人】でも継承できるものですし、実際にそのようなケースも多くあります。
お寺に決めてもらうことはできない
お墓の継承者を家族で話し合って決めることも多いのですが、当然ながらモメることもあるんですよね。
よほど折り合いがつかなかったのでしょうね、たまに、



話し合っても全然決まらないので、お寺さんが決めてくれませんか?
という人がいるんですが、それはできません。
この記事の内容をお伝えすることはできても、お寺が継承者を決めることはできません。
仮にお寺が継承者を決めてしまって、その後に何らかのトラブルがあったときにお寺は責任を負えないです。
お墓の継承者は、その家の人達が責任をもって決めましょう。
お墓を継がずにすむ方法とは?
僕が今まで見てきて、「どうしてもお墓なんて継ぎたくない」という人はけっこういます。
ここからは【お墓を継がずにすむ方法】について紹介します。
墓じまいをして永代供養にする
「お墓なんて継ぎたくない!」と言っている人に対して僕もいろいろと説得をしてみるのですが、だいたいの人は決意が固いんですよね。
そうなったら、僕としては『墓じまいをして永代供養にする』ことを提案するしかありません。
誰も継承者がいないお墓をそのままにしておいたら『無縁墓』になってしまい、お寺や霊園としてもその後の処理に困ってしまうんです。
しかも、雑草などが生え放題だと近隣の墓地にまで迷惑がかかってしまいます。
そんなことになるくらいなら、ちゃんと【墓じまい】をして、遺骨もすべて【永代供養】にしてもらった方が、その家のご先祖様のためにも良いです。
【墓じまい】というのは、お坊さんに『魂抜き』という供養をしてもらった後に墓石をすべて撤去して、墓地を【お墓を建てる前の状態】に戻すことをいいます。
【永代供養】とは、お墓の中の遺骨をお寺の管理する永代供養墓へ移して、後はお寺側でずっと供養をしていくことをいいます。
費用は、墓じまいと永代供養の両方を合わせると【50万円〜100万円】くらいは必要です。
かなりの負担となってしまいますが、お墓を継承せずに終わらせる、というのはそれだけ大変なことなんですよね。
ただ、永代供養まですべて終わったら、その家にはもう【お墓の継承者の問題】はなくなりますので、そういう意味ではスッキリします。
法的には【まったくの他人】でもお墓は継承できる
お墓の継承者といえば、
- 家族
- 関係の近い親族
が継ぐものだと思いますよね?
じつは、法的にはお墓を継ぐのが家族や親族である必要はないんです。
だから、『まったくの他人』でもあなたの家のお墓を継承できるんですよね。とはいえ、いくら法的に可能でもそんな人を探すのはヤメた方がいいですよ。
これまで説明してきたとおり、お墓の継承者はとにかく大変です。なにしろ負担ばかり大きくてメリットがほぼないんですからね。
それなのに、わざわざ【他人の家のお墓】を継ぐなんて、そんな人はいませんよ。それに、万が一お墓の継承をしてくれたところで、他人の家の仏様を大事に供養してくれる人はごくごく少数です。
法的にはまったくの他人がお墓の継承することが可能ですが、それは『今後のお墓をどうするか?』の選択肢に入れない方がいいでしょう。
まとめ:どうしてもお墓を継ぎたくないなら無理に継ぐ必要はない
お墓を継ぐのはとても大変なことです。
管理料や行事の費用といった維持費が必要ですし、定期的にちゃんと墓地の掃除もしなきゃいけません。
ですから、お墓を継ぐということは、それなりに大きな負担がかかるのです。
どうしても【お墓を継ぎたくない】のであれば、墓じまいをして、永代供養にするのが1番いいです。
もちろん、墓じまいや永代供養にもお金はかかりますが、その後の何十年も負担をし続けるよりはマシですよね。
ずっと不満を抱きながらお墓を守り続けるくらいなら、ご先祖様のためにも、いっそのこと永代供養をした方がいいです。
お墓は誰かが継承してもいいですし、墓じまいをしてもいいでしょう、どちらの選択も尊重されるべきものです。
ただし、それをあなた1人だけで勝手に決めず、ちゃんと家族や関係の近い親戚とよく話し合ってから決めてくださいね。
※こちらの記事もご参考にどうぞ。