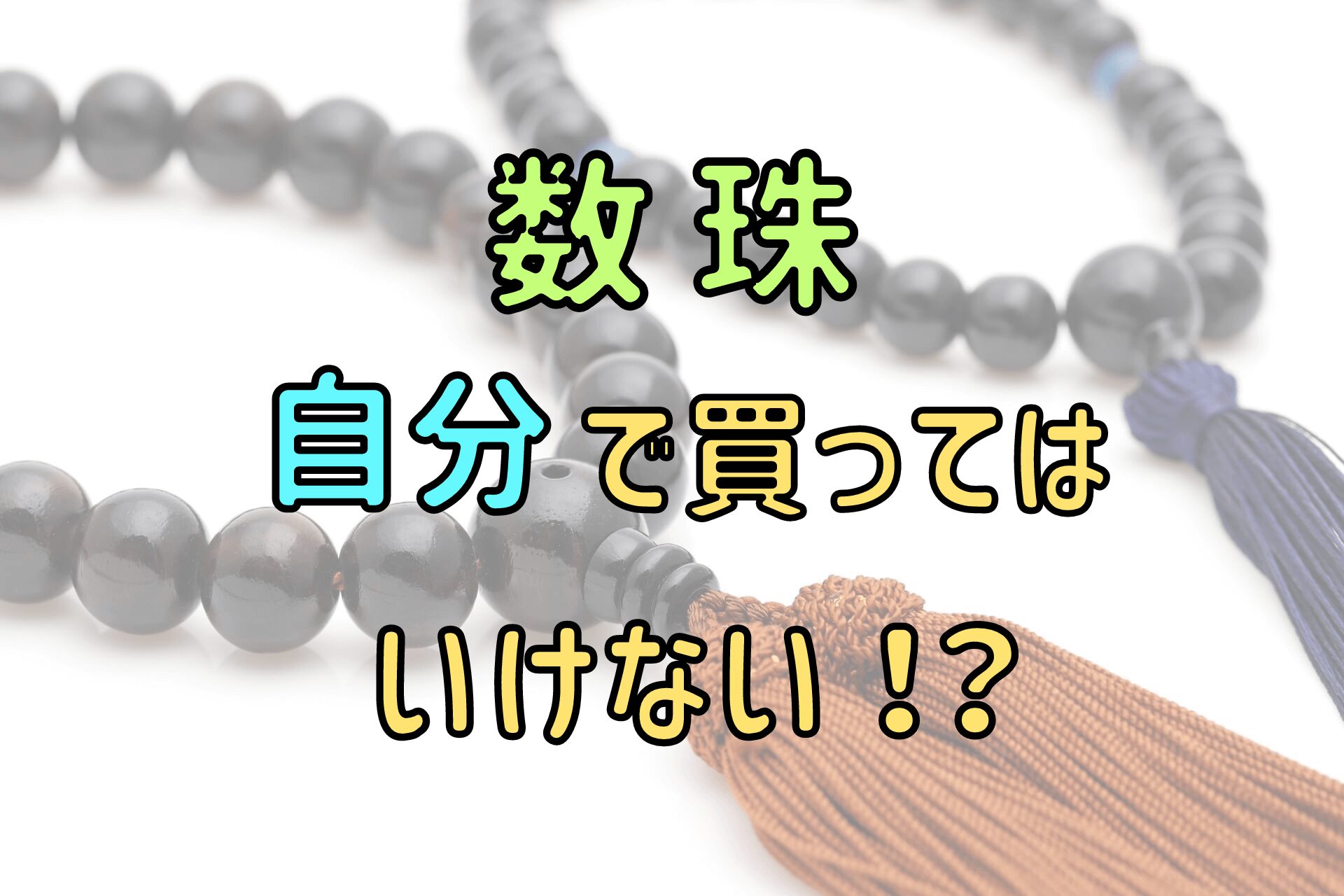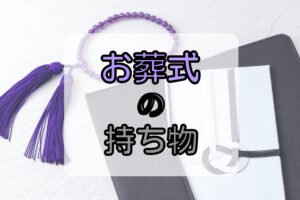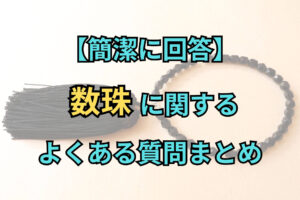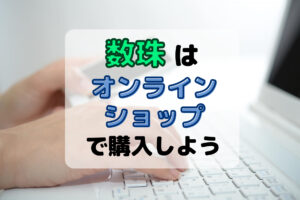ときどき「数珠を自分で買ってはいけない。」と言う人がいますよね。
それ、じつは間違いで、むしろ数珠は自分で買うべきなんです。
「数珠を自分で買ってはいけない」と言われるのは、
- 数珠を自分で買うと縁起が悪いから
- 数珠は自分で買うものではないという地域の習慣があるから
という理由です。
しかし、『縁起が悪い』というのは迷信であり、『地域の習慣』は限定的なものなので大多数の人には関係ありません。
数珠には【仏様のチカラ】が宿り、数珠の持ち主を清めてくれます。だから、数珠は自分で選んで買うことが大事です。
この記事では、「数珠を自分で買ってはいけない」と言われる理由と、その真偽について解説しています。
 未熟僧
未熟僧安心して数珠を買えるようになりますので最後まで読んでみてください。
この記事を書いている僕『未熟僧(みじゅくそう)』は、お坊さん歴25年以上。仏事の疑問を解消するいろんな情報を発信しています。
数珠を自分で買ってはいけないの?
一部では「数珠を自分で買ってはいけない。」と言われていますが、数珠は自分で買っても問題ありません。
数珠には【仏様のチカラ】が宿り、数珠の持ち主を清めるとされているので、むしろ数珠は自分で買うべきです。
お葬式や法事で焼香をするときには数珠を持ちますが、あれは、焼香の前に数珠を持つことで【仏様のチカラ】によって自分の体を清めているんです。
ちなみに、焼香のときに数珠を借りている人を見かけますが、じつは数珠を借りるのはよくないことなので注意してください。
数珠には、持ち主の《仏様や故人に対する感謝と供養の気持ち》がたくさん詰まっており、だからこそ数珠に【仏様のチカラ】が宿るのです。
それなのに、他の人が数珠を借りてしまうと、数珠の持ち主が受け取るはずの【仏様のチカラ】を、借りた人が横取りすることになってしまいます。
あなたにも『ご縁のある数珠』がありますので1度探してみてください、たくさんの数珠の中から《気になる数珠》が出てくるはずですから。



気になる数珠があなたにとって『ご縁のある数珠』ですよ。
数珠を購入するときには、あなた専用の数珠を、ちゃんとあなたの目で見て選んで、そしてあなた自身が買うようにしましょう。
なぜ「数珠を自分で買ってはいけない」と言われるのか
数珠はちゃんと自分で買うべきですが、なぜ「数珠を自分で買ってはいけない。」と言う人がいるのでしょう?
その理由は、
- 数珠を買うと誰かの不幸を暗示するようで縁起が悪い
- 最初から【数珠は人から貰うもの】という考え方になっている
- その地域のルール
ということが挙げられます。
数珠を買うと誰かの不幸を暗示するようで縁起が悪い
数珠を買うことは誰かの不幸を暗示するようで縁起が悪いと言われています。
しかし、そんなのは迷信です。
例えば、『数珠を使う場面』といえば、多くの人は【お葬式】を連想します。
そのため、数珠を買うことを『お葬式に向けた準備』のように解釈する人もいたんですよね。
そして、それがさらに飛躍して「自分で数珠を買うと《身近な人》の不幸を招く。」と言われるようになりました。
でも、そんなことはないので安心してください。迷信に惑わされずに、数珠はちゃんと自分で買いましょう。
当たり前ですが、お葬式の知らせは急にやってきます。なので、いざというときにちゃんと数珠を手にして冥福を祈ることができるように準備をしておくべきです。



もちろん『数珠を買うこと』と『不幸があること』には何の因果関係もないですよ。
そもそも、数珠を使う場面はお葬式や法事だけでなく、
- 寺院への初詣
- 仏式の結婚式
- 仏式の七五三
- 仏式の地鎮祭
- 墓石の新規建立
など『お祝いの仏事』のときにも数珠を使用します。
【縁起が悪い】という発想になるのは、数珠を《お葬式》で使うことばかり考えているからです。
本来なら数珠は日常的に使うものなので、ちゃんと自分で選んで買いましょう。
最初から【数珠は人から貰うもの】という考え方になっている
数珠は、嫁入り道具の1つとして贈ることもあります。
嫁入りする娘のために新しい数珠を買って贈ったり、あるいは親が使っていた数珠をキレイに直してから贈るのです。
嫁入り道具として数珠を贈るのは、
- 娘の幸せを願う『御守』の代わり
- ちゃんとした数珠を持たせて、娘に恥をかかせないようにする
という意味があります。
そのような《嫁入りする娘に数珠を贈る》という習慣がある地域に住む人たちには、最初から【数珠は人から貰うもの】という認識が根付いているため『数珠を自分で買ってはいけない』という考え方になります。
しかし、何度も言いますが、本来なら数珠は自分で買うものであり、人から貰うというのは特殊なケースなんです。
とはいえ、嫁入り道具に数珠を贈ることはとても素敵な習慣だと思いますので、その数珠は大事に使ってほしいと思います。
その地域のルール
仏事というのは、地域によって【やり方】や【考え方】が違います。そのため、地域のルールで『自分で数珠を買うことを良しとしない』というところもあります。
そのような地域では、先ほど解説した【縁起が悪い】などの理由で、自然に『数珠を自分で買う=良くないこと』みたいな考え方が根強く残っているのでしょう。
しかし、それはあくまで地域の限定的なルールにすぎません。
地域のルールに従うことは大事ですが、基本的に【数珠は自分で買うもの】ということは忘れないでください。
数珠の購入についてよくある質問
数珠は自分で購入してください。
しかし、数珠を買うにあたりいろんな疑問が出てくることでしょう。
ここからは、数珠を購入するときの【よくある質問】をいくつか紹介します。
数珠は他の家族の『お下がり』を使ってはダメですか?
他の家族や故人が使っていた数珠など、誰かの『お下がり』の数珠を使っても大丈夫です。
原則として数珠は自分で買うべきですが、【自分で買ったものしか使ってはいけない】というわけではありません。
他の家族が以前に使用していた数珠があるなら、それを引き継いで使うのは問題ありません。
また、亡くなった家族が使っていた数珠があれば、それを処分せずに【形見】として大切に保管しておいてもいいですし、他の家族が引き継いで使っても大丈夫です。
使われなくなった数珠を引き継いで使うのは、《前に使っていた人》と《引き継いだ人》の両者の思いが込められた大事な数珠になります。
もしも修理が必要な状態であれば、房を交換したり、ヒモを締め直すなどリメイクして使いましょう。
数珠はどこで買えばいいですか?
数珠を購入できる場所には、
- オンラインショップ
- 念珠店
- 仏具店
- お寺(規模の大きな寺)
- デパート(百貨店)
- 紳士服専門店
- 大型ショッピングモール
- 葬儀式場や霊園
- 雑貨店やホームセンター
- 普通の服飾店
- 大手ディスカウントショップ
- コンビニ
- 100円均一ショップ
などがあります。
数珠の購入場所としておすすめなのは、種類の多さ、値段、品質、購入の手間などを総合的に考えると『オンラインショップ』です。
オンラインショップなら数珠の種類がとても豊富で、スマホやパソコンを使っていつでも購入できるので非常に便利。
しかも、大手のオンラインショップならだいたい購入日の翌日~3日間程度で届くので、急いで買いたい人は利用してみてください。
数珠を買うときは、どんな数珠を選べばいいですか?
数珠の形には大きく分けて、
- 本式念珠:お坊さんが使うような数珠
- 略式念珠:一般の人が使うような数珠
の2つがあります。
数珠を買うときには、とりあえず『略式念珠』を選んでください。
『略式念珠』なら宗派を問わず使用でき、さらに取り扱いがラクで価格も安いので、略式念珠を1つ持っておけば問題ありません。
数珠の色については『赤色』以外なら何色でもいいので、あなた好みの色を選びましょう。
購入する数珠の価格は『1,500円以上』を目安にすれば、比較的買い求めやすくて品質も高い数珠が買えます。
数珠にはたくさんの種類がありますので、もしも「種類が多すぎて選べない!」という人は別記事の『【初めて数珠を買う人向け】数珠の選び方と購入時の注意点』を読んでみてください。
まとめ:数珠は自分で買いましょう。
一部で『数珠を自分で買ってはいけない』と言われている理由は、
- 誰かの不幸を暗示するみたいで縁起が悪い
- 最初から【数珠は人から貰うもの】という考え方になっている
- その地域のルール
です。
しかし、これらは単なる《迷信》や《地域の限定的なルール》にすぎません。
数珠には【仏様のチカラ】が宿ると言われているので自分が使う数珠は自分で買うべきです。
数珠を買うときは、価格が【1,500円以上】の『略式念珠』を選べば、使い勝手がよくて高品質な数珠が購入できます。
自分で使う数珠は、自分で選んで自分がお金を出して買うからこそ、愛着がわいて大事に使えます。
あなたの周りの人が何と言おうと数珠は自分で購入しましょう。