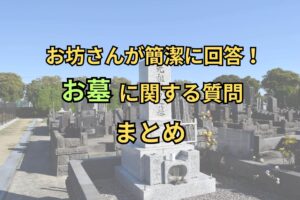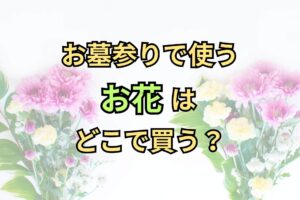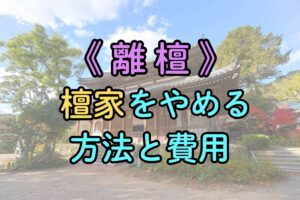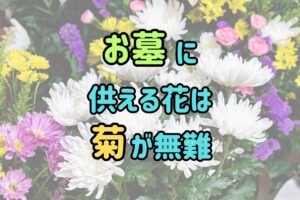- 子供がおらず、お墓を継ぐ人がいない。
- 子供が娘だけで、嫁いだ娘にお墓を継がせるのは気が引ける。
- 自分の代で『墓じまい』をしようと思っている。
近年では、多くの家で『お墓を継ぐ人がいない』という問題を抱えています。
せっかく建てたお墓なので、できれば何とかして残しておきたいですよね。
しかし、お墓を継ぐ人が本当にいなければ『墓じまい』をしなくてはいけません。
そして、『墓じまい』をした後には【遺骨をどうするか】という問題も残ります。
お墓の問題は後になればなるほど面倒になってくるので、なるべく早めに解決しておきましょう。
この記事では、
- 墓じまいの方法
- 永代供養の方法
- 改葬の方法
について解説しています。
墓じまいに関する一連の手順が分かりますので最後まで読んでみてください。
 未熟僧
未熟僧お墓の問題は、あれこれ考えるよりも、すぐに行動した方が早く解決できますよ。
この記事を書いている僕『未熟僧(みじゅくそう)』は、お坊さん歴25年以上。仏事の疑問を解消するいろんな情報を発信しています。
お墓を継ぐ人がいない!
お墓は代々受け継がれていくものです。
しかし、やむを得ない事情によって『お墓を継ぐ人がいない』ということもありますよね。
では、お墓を継ぐ人がいない場合はどうすればよいのでしょう。
放置すると、いずれお墓は完全に無くなる
お墓を継ぐ人が誰もおらず、さらにお墓が長期間放置されていた場合、墓地の管理者(寺院や霊園)はそのお墓を『無縁墓』として扱います。
そして無縁墓は最終的に管理者によって、
- お墓を建てた墓地使用者の『墓地使用権』が取り消される
- 墓石が撤去され、墓地は更地に戻される
- 遺骨
- 遺骨は【永代供養墓】に移され他の人のお骨と一緒に納骨される
といった措置がとられます。



要するに、完全にお墓が無くなるということです。
そして、更地に戻された墓地は、すぐに他の人が使用できるようになります。
とはいえ、無縁墓となってから数か月程度でお墓が無くなることはありません。
ほとんどの寺院や霊園では、管理費などが数年間支払われず、なおかつ墓地使用者と連絡が取れない場合にそのような対応をします。
また、管理者と墓地使用者とで『墓地や遺骨の対処』について事前に話し合いをし、ちゃんと手続きをしておけば墓地使用者の希望通りに対応してもらえます。
お墓を継ぐ人がいなければ【墓じまい】をする
お墓を継ぐ人が誰もいなければ、そのお墓は【墓じまい】をしましょう。
お墓がある限り、ずっと維持管理の労力や金銭的負担が必要となります。
僕がいる寺では、2010年頃から、



ウチにはお墓を継いでくれる人がいないんですが、どうすればいいでしょうか?
という相談が急増しています。
お墓を継ぐ人がいなくなってしまうのは、
- 少子高齢化や核家族化など社会的な変化
- 仏事(宗教)に対する関心の低下
- 人口が都市に集中している
ということが主な原因です。
昔のように家族の人数が多ければ、誰か1人くらいはお墓を継承してくれる人がいました。
しかし、今の若い世代の人たちはお墓に対してほとんど関心がなく、お墓を維持することを負担に感じてしまいます。
そのため、若い世代の人たちは『お墓を継承すること』に対してネガティブな考えを持っているのです。
しかも、少子化による人口減少と同時に、人の都市部への集中により、地方では『お墓を継ぐ人』がどんどん減って、それだけ【墓じまい】をする家が増えています。
代々受け継がれてきたお墓を自分の代で無くしてしまうことは、先人たちに申し訳なくて非常に心苦しいことでしょう。
しかし、現実的に考えると、お墓を継ぐ人がいないのであれば、早めに『墓じまい』をした方がいいですよ。
『墓じまい』の流れ
ここからは、実際に『墓じまい』をするときの流れを紹介します。
お墓を継いでくれる人が本当にいないのか再確認する
『墓じまい』というのは最終手段です。
お墓を継ぐ人が1人でもいれば、そのままお墓を使うことができるので、お墓を継いでくれる人が本当に誰もいないのか改めて確認をしてみてください。
とはいえ、どのような人がお墓の継承者となれるのでしょう?
お墓の継承者の選び方については『民法第897条』に定められています。
条文には、
《民法第897条》
- 【1項】系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
- 【2項】前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
と書かれています。
もう少し分かりやすくすると、
系譜・仏壇・位牌・墓地・墓石といった【祭祀財産】については『故人の住んでいた地域の慣習』に従って決めた継承者が受け継いでください。
ただし、生前に故人から継承者の指定があった場合は、指定された人が受け継いでください。
もしも、【慣習の有無が不明】とか【慣習の内容が不明】といったように、慣習が明らかでない場合は家庭裁判所が継承者を決めます。
ということです。
このように継承者の選び方は決まっていますが、現実的には『地域のやり方』や『故人の遺志』をふまえ、家族や親戚で話し合って決めています。
すると、多くの場合は【その家の長男】がお墓を継ぐことになります。
これは、明治期に始まった『家督相続』の影響により【お墓は長男が引き継ぐもの】という意識が定着しているからです。
でも、お墓は『長男以外の人』でもお墓を継承できます。もっと言うと、『被相続人の指定』があれば、お墓の継承は血縁関係者に限らず誰でもできるんですよね。
ちなみに、系譜・仏壇・位牌・墓地・墓石といったものは『祭祀(さいし)財産』と呼ばれ、他の財産とは別に相続されるもので、相続するのは一人だけなんです。
例えば、兄弟姉妹や親戚で、
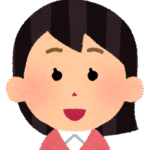
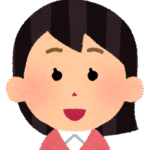
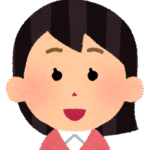
私が仏壇と位牌を守るから、お兄ちゃんはお墓の方を守ってね。
みたいに、何人かで分けて相続することができない財産となります。
だから、たった1人でいいんです、本当にお墓を継承する人が誰もいないのか、念のためもう一度確認をしてみてください。
『墓じまい』の方法と費用
どうしてもお墓を継ぐ人がいなければ『墓じまい』をする必要があります。
『墓じまい』とは、
- 閉眼供養(魂抜き)をする
- 墓石撤去工事をする
- 墓地返還の手続きをする
ということです。
お墓の閉眼供養(魂抜き)をする
墓じまいをするには、まずお墓の『閉眼(へいげん)供養』をしなければなりません。
閉眼供養とは、墓石を【お墓としての役目を終わらせる】ために執り行うものなので、必ずお坊さんに依頼をしてください。
そして、お坊さんに閉眼供養をしてもらうには『お布施』が必要です。
閉眼供養のお布施は、お寺や霊園によって金額が違いますが、だいたい《3万円〜5万円》くらいが相場でしょう。



僕のいる寺では閉眼供養料として3万円を目安に納めていただいています。
また、閉眼供養が終わるとお墓から遺骨を取り出しますが、この作業は石材店へ依頼をしてください。
ごく稀に、



最後くらい、自分でお骨を取り出してあげたい。
と言う人がいますが、それはヤメた方がいいですよ。
まず、遺骨を取り出すには、お墓の【蓋石】を動かさなければいけませんが、これがかなり重たいのです。たぶん、あなたが想像しているよりも重たいですよ。
墓石の取扱いを知らない人が蓋石を動かすとケガをする可能性があります。
次に、遺骨を取り出すときにも注意が必要です。
遺骨を取り出すときには、骨壺の中に水が溜まっていたりしますので、これもまた結構重たいのです。
手を滑らせて骨壺を落としたら大変なので、遺骨の取り出しに関するすべての作業は石材店などの専門業者に任せるようにしてください。
墓石撤去工事をする
閉眼供養が終わり、遺骨をすべて取り出したら、あとは専門業者が墓石の解体と処分、墓地を更地に戻します。
専門業者へ支払うこれらの費用は、使われている石材の【数】【量】【素材】【重さ】によって変わります。
そして、このような費用の相場は地域によっても違いますが、だいたい《1㎡あたり、13万円〜20万円》くらいです。
また、墓じまいの依頼をする専門業者ですが、お寺や霊園に【指定石材店】がある場合はそこへ依頼し、もしもなければ他の業者へ依頼をしましょう。
墓地返還の手続きをする
墓じまいには墓石の撤去だけではなく『墓地返還の手続き』が必要です。
墓石が無くなっても、まだ墓地使用権が残っており、その状態だと墓じまいが完了していません。
お寺や霊園にある墓地返還用の書類を提出し、正式に墓地を返還することで墓じまいが完了します。
墓地返還の手続きに関する費用については、お寺や霊園ごとで違いますので事前に確認しておきましょう。



僕がいる寺では、墓地返還手続きの費用はかかりません。
取り出したお骨は永代供養をするか他の場所へ納骨する
お墓から取り出した遺骨は、他の墓所へ納骨するか、どこかで保管をしなければなりません。
永代供養をする
墓じまいをした後には『永代供養』をするケースが多いです。
永代供養とは、寺院や霊園などで遺骨をずっと供養してもらうことをいいます。
永代供養をすれば、あなたの家のご先祖様達が『無縁仏』にならずに済むんですよね。
最近では、多くの寺院や霊園で『永代供養墓』が設けられています。
永代供養墓には、
- 骨壺から遺骨を出して、他人の遺骨と一緒にして供養(=合祀)
- 骨壺のまま個別に供養
の2つの形式があります。
一般的な永代供養墓は、骨壺から遺骨を出して他人の遺骨と一緒に供養していく形式です。
そうなると、
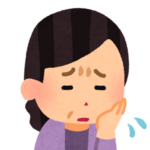
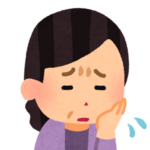
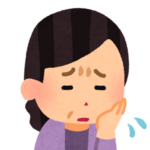
えっ、見ず知らずの人と一緒になっちゃうのかぁ・・・。
とためらってしまう人もいます。
しかし、墓じまいはそういうデメリットを受け入れなければならないんですよね。
たまにチラシなどで『骨壺のまま永代供養をいたします』という宣伝を見かけますが、これは大きな土地や納骨施設がないとできないことです。
そのため、骨壺で個別の永代供養ができるお墓もあるにはありますが、そんなに数が多くはない上に、価格も高くなるでしょう。
また、永代供養の費用については、お寺や霊園によって大きな違いがあり過ぎるので、ここでは目安の金額でさえもお伝えできません。
他の場所へ納骨する
永代供養墓へ納骨することに抵抗がある人は、ひとまず他の場所へ納骨することを考えてみてもよいと思います。
納骨施設などへ納骨する
最近では、とてもキレイな納骨施設で遺骨を個別に預かるところもあります。
その中には、ビル全体が納骨施設となっていて、ボタン1つで各家の遺骨に手を合わせられるところもあります。キレイな納骨施設は、よくテレビCMで流れていたりしますので、一度見学してみるのもいいですね。
また、納骨施設として『納骨堂』を用意しているところもあります。
納骨堂は《専用のロッカー》あるいは《個別に仕切られた棚》などで遺骨を預かるというものです。
しかし、納骨施設や納骨堂というのは、永代供養墓のようにずっと預けられるわけではありません。
一定の契約期間が終われば、結局はその施設に関連するお寺などで永代供養墓へ埋葬されるのです。
ほとんどの納骨施設や納骨堂では、一時的に個別で預かりますが、最終的には永代供養墓へ納骨されることを理解しておきましょう。
樹木葬墓地へ納骨する
最近とても人気なのが『樹木葬』です。
樹木葬とは、緑豊かな自然の中に納骨するタイプのお墓をいいます。
従来のような墓石を使用せずに木の周りなどへお骨を納めるので、
- 費用を安く抑えられる
- 自然思考の人に好まれる
といった特徴があります。
私たちは、自然の中で生まれて、いずれまた自然の中へ帰っていきます。そういう意味では、樹木葬が私たち生き物とって本来の納骨形式なのかもしれません。
ただし、樹木葬にも、
- お骨をそのまま土中へ埋める
- 一定期間が過ぎたらお骨を永代供養墓へ移す
という2つのタイプがあるのでご注意ください。
都市部から離れた場所にある樹木葬墓地であれば、広大な土地があるので【遺骨をそのまま土中へ埋める】ことができます。
一方で、都市部に近い樹木葬墓地の場合は、一定期間は骨壺のまま土中へ納め、最終的には永代供養墓へ遺骨を移すことが多いです。
ですから、樹木葬だからといってずっとその場所に遺骨を納められるとは限りませんので、どのような使用方法なのかを必ず確認しておきましょう。
海洋散骨をする
最近注目され始めてきた方法ですが、遺骨をどこにも納骨せずに『海洋散骨』をするという人もいます。
ただし、勝手に海へ遺骨をまくことはできないので、専門業者に依頼をしなくてはいけません。
また、散骨をする場合には、遺骨を2ミリ以下に『粉骨』するのがルールです。大事な家族の遺骨を砕くというのは気が引けますが、散骨をするには粉骨が必須なんですよね。
しかし、海洋散骨をすれば、その後の遺骨の管理をする必要がないため非常に経済的です。また、海洋散骨なら故人の望む海域へお骨をまくことができるので、家族にとっても満足のいく方法です。
ただし、当たり前ですが、海へ散骨してしまうと遺骨は二度と戻りません。
海洋散骨をするなら、家族や親戚とよく話し合った上で、後々のトラブルがないよう慎重に執り行ってくださいね。
特別祭祀をしてもらう
寺院や霊園によっては『特別祭祀(とくべつさいし)』という供養をしているところもあります。
特別祭祀とは、
- 自分以外には誰もお墓の継承者がいないから、自分が他界した後は、寺院や霊園で契約期間中はお墓の維持管理と供養をしてください。
- 契約期間が過ぎたら、お墓の遺骨は永代供養墓へ移して、墓石も解体してください。
- 墓地の維持管理費用や撤去時の費用、そして供養料は前もって全額お支払いしておきます。
という約束をした供養方法です。
つまり、お墓の後継者がいなくても、先に費用をすべて支払っておくことで、契約期間中はお墓は撤去されずにそのまま残してもらえるのです。
特別祭祀は、
- お墓の継承者がいなくなった後すぐにお墓が無くなってしまうのは寂しい
- しばらくはお墓をそのままにしておきたい
という人が利用しています。
特別祭祀をしているところはまだ少ないですが、もしもあなたの近くに導入しているところがあれば、一度話を聞いてみてはいかがでしょうか?
改葬の流れ
墓じまいをして取り出した遺骨を他の納骨場所へ移動するときには【改葬】の手続きが必要です。
改葬とは、簡単に言うと【お骨の引っ越し】です。
私たちは、引越しをするときには役所へ行って『転出』や『転入』などの手続きをしますが、お骨についても似たような手続きがあります。
改葬手続きの流れ
改葬をするには『墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)』に沿った手続きが必要なので、勝手に遺骨を移動させてはいけません。
改葬の手続きは以下のとおり。
- 移転先の墓地を確保し、移転先の墓地の管理者から『受入証明書』を発行してもらう。
- 現在の墓地の管理者の承諾を得て『埋葬証明書』を発行してもらう。※この段階で現在のお墓から遺骨を出しておくことが多い。
- 現在の墓地がある場所の市区町村役場に行き、『改葬許可申請書』をもらい、必要事項を記入する。
- 現在の墓地の管理者のもとへ『改葬許可申請書』を持って行き、記入欄に署名と捺印をしてもらう。
- もう一度、現在の墓地がある場所の市町村役場に行き、『改葬許可申請書』『受入証明書』『埋葬証明書』を提出する。
- 提出した書類に不備がなければ『改葬許可証』が発行される。
- 発行してもらった『改葬許可証』を、移転先の墓地の管理者に提出し、納骨をする。
改葬の手続きは、あちこちから書類を出してもらう必要があるので意外と面倒なんですよね。
しかし、改葬をすれば、遠く離れた場所ではなく、自宅近くで家族の遺骨を供養できるようになるので頑張りましょう。
改葬をするときの注意点
改葬をするにあたり注意点があります。
あなたの家のお墓が『お寺』にある場合、墓じまいの後に改葬をするということは、お寺との付き合いを解消することになります。
お寺との付き合いを解消することを『離檀(りだん)』といいます。
離檀をする場合、お寺によっては『離檀料』を要求されることがあります。離檀料の金額は、お寺によって大きく異なりますし、僕のいる寺のように『離檀料は不要』という場合もあります。
もしも、何百万円といった法外な金額を請求された場合は、法律の専門家に相談してみましょう。ほとんどの場合、『そんなものを納める必要はない』という結果になりますよ。
法外な金額を納める必要はありませんが、お礼の意味で【1万円~5万円】くらいを納めておくといいでしょう。
まとめ
どうしてもお墓を継ぐ人がいない場合は『墓じまい』をしましょう。
墓じまいをした後は、お骨を『永代供養墓』へ納骨し、寺院や霊園に永代供養をしてもらうと安心です。
あるいは、他の納骨施設や樹木葬など、他の納骨形態を利用してもいいと思います。
いずれにせよ、誰にも供養や管理がされない【無縁墓】を出さないように、墓じまいや改葬をしましょう。
※こちらの記事も読まれています。